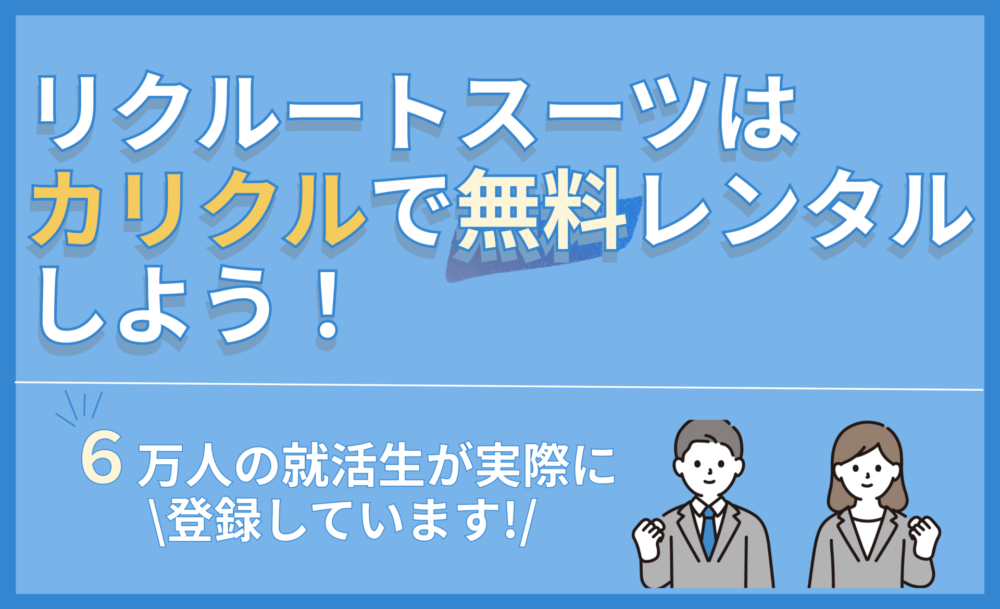ネクタイは、男性の就職活動に欠かせないアイテムのひとつです。ですが、「どの色のネクタイを選ぶべばいいのか」「結び方はどうすべきか」などの悩みを抱えている方もいるでしょう。
そこで本記事では、就活用スーツのネクタイの選び方や結び方について解説します。就職活動を控えている男性はぜひ参考にしてくださいね。
カリクルが就活のスタートをサポート!
- ①リクルートスーツレンタル|無料
- レンタル予約から受け取りまでLINEで完結
- ②面接質問集100選|400社の質問を分析
- LINE登録で面接前に質問を確認!
- ③適職診断|LINEで3分
- 自分に合う仕事が見つかる
- ④AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- 3分でESを自動作成してくれる
就活ではネクタイ選びが大切
就活用スーツに合わせるネクタイの色や柄にはこだわりましょう。就活では見た目の印象も重視されるためです。
見た目の印象を大きく左右するのは就活用スーツですが、「どのようなネクタイを選ぶか」も同じくらい重要となります。
就活中は黒や紺の無地のスーツ選ぶことが多いため、みんなが同じような格好になりがちです。そんな中、ネクタイの色や柄を工夫することで手軽に印象を変えられます。
また、志望企業のイメージや企業理念に合わせて、色や柄を選ぶことも可能です。
就活用スーツにオススメなネクタイの色と印象

就活中のネクタイは、どのような色でも良いわけではありません。就活用スーツにオススメなネクタイの色は以下の4つです。
それぞれの色が与える印象についてくわしく解説します。
①青・紺
青・紺系のネクタイが与える印象は、「フレッシュさ」「爽やかさ」「誠実さ」などです。相手に悪い印象を与えることはないでしょう。
青・紺系カラーは日本人に好まれる色で、特に比較的上の世代の方から印象が良いといわれています。社長や役員との面接でも安心してつけられます。
どのようなスイーツにも合わせやすい点も、青・紺系のネクタイを選ぶメリットです。就活中のネクタイに悩んだら、青・紺系を選んでおくと間違いありません。
②エンジ・赤
赤・エンジ系のネクタイが与える印象は、「エネルギッシュ」「前向き」「情熱的」などです。青・紺系とは対照的に、攻めた印象を与えてくれる色です。
赤・エンジ系のネクタイは、営業職でエネルギッシュさをアピールしたい方や、最終面接など「ここ一番」という時に向いています。
ただし、真っ赤なネクタイは攻撃的な印象を与えるため避けたほうが良いでしょう。
就活中に赤・エンジ系のネクタイを選ぶ場合は、落ち着いたエンジやワインレッドをオススメします。
③黄色
黄色系のネクタイが与える印象は、「協調性」「親近感」「社交性」などです。黄色系カラーには、相手の警戒心をやわらげる効果があります。
黄色系のネクタイは、協調性を重視する企業や面接時のディスカッションに向いています。
注意点としては、カジュアルすぎる印象を与える可能性がある点です。アパレル系企業やクリエイティブな職種であればオススメできる色ですが、それ以外は避けたほうが良いかもしれません。
④グレー
グレー系のネクタイが与える印象は、「穏やか」「知的」「勤勉」などです。穏やかで真面目な印象を与えたいシーンに向いています。
グレー系のネクタイをオススメしたいのは、公務員や金融業界など比較的保守的な企業です。
グレー系は控えめな色なので、印象に残りにくい点はデメリットといえます。企業や職種によっては、「自己主張が弱い」と捉えられる可能性があるため要注意です。
就活用スーツにオススメのネクタイの柄と印象

ネクタイを選ぶ際は、色だけでなく柄にも着目してください。就活用スーツにオススメのネクタイの柄は以下の4つです。
それぞれの柄が与える印象についてもくわしく解説します。
①無地
無地とは、柄が一切入っていないものを指します。柄が入っていないため、どのようなスーツとも合わせやすいのがメリットです。
無地のネクタイが与える印象は、「清潔感」「誠実さ」などです。清潔かつ真面目な印象を与えるため、就活時に向いています。
しかし、柄がない分色選びが難しい点はデメリットと言えるでしょう。無地のネクタイを選ぶ際は、紺色やエンジ色などの定番の色を選ぶと良いでしょう。
②レジメンタルストライプ
レジメンタルストライプとは、斜め右上に向かうストライプ柄です。ビジネスシーンでも定番の柄となっています。
レジメンタルストライプのネクタイが与える印象は、「知的」「落ち着いている」「おしゃれ」などです。
レジメンタルストライプのネクタイは、線の太さや使っている色の数によって印象が大きく異なります。就活時には、太さは細めで色は3色以内のものを選ぶことをオススメします。
外資系企業の面接時には、レジメンタルストライプのネクタイは避けた方が良いでしょう。レジメンタルは元々、所属している隊を表すデザインだったためです。
③チェック
チェック柄とは、格子縞の模様のことで、ギンガムチェック柄(小格子柄)やアーガイルチェック柄(ダイヤ柄)などさまざまな種類があります。
チェック柄のネクタイが与える印象は、「活発」「親しみやすい」「フレッシュさ」などです。無地やレジメンタルストライプと比較すると、カジュアルな印象となります。
大柄なチェック柄はカジュアルな印象になるため、就活に使用するなら細かいチェック柄を選びましょう。また、色数は地色を含めて3色以内に抑えてください。
④ドット
ドットとは水玉模様のことを指し、ネクタイの柄としては定番中の定番です。
ドットのネクタイが与える印象は、「上品」「誠実」「落ち着いている」などです。上品かつ真面目な印象を与えるため、就活時にも向いています。
また、レジメンタルストライプやチェックと比較すると色数が少なく、スーツ初心者でも合わせやすい点も嬉しいポイントです。
大きめのドット柄を選ぶとカジュアルになり過ぎるため、就活時には細かいドット柄を選ぶことをオススメします。
就活用スーツにオススメのネクタイの素材

ネクタイに使われる素材は、シルク・ウール・ニット・リネン・コットンなどさまざまです。その中でも、就活用スーツには、シルクのネクタイを合わせることをオススメします。
シュルクのネクタイは程よい光沢感があり、上品な印象を与えてくれます。シルク以外の素材はカジュアルな印象を与えるため、就活中は避けたほうが無難です。
ポリエステルのネクタイは使い勝手が良いものの、結び目がほどけやすかったり、光沢があり過ぎて安っぽく見えたりとデメリットがあるため、注意しましょう。
就活用スーツで避けるべきネクタイ

就活中につけるとマナー違反となるネクタイがあることをご存じでしょうか。就活用スーツで避けるべきネクタイは以下の3つです。
①派手な色や柄のネクタイ
派手な色や柄のネクタイは、採用担当者に「TPOをわきまえていない」と思われる可能性があります。具体的には、ピンク色や紫色などの派手な色のネクタイは避けたほうが良いでしょう。
ピンク色のネクタイはカジュアルな印象を与えるため、日本のビジネスシーンではあまり好まれません。紫色のネクタイに関しては、神秘的なイメージを与えるため、少し扱いにくい人物だと思われる可能性があります。
柄に関しては、大きすぎる柄や紋章が多く並んでいるような柄は避けたほうが無難です。
②黒・白の無地のネクタイ
黒・白の無地のネクタイは冠婚葬祭に用いられるため、就活中につけるのはNGです。
黒色のネクタイは葬儀用、白色のネクタイは婚礼用と決まっています。就活に限らず、冠婚葬祭以外で黒・白の無地のネクタイをつけるのはマナー違反です。
就活で黒・白の無地のネクタイをつけると、採用担当者に常識がない人物だと判断される可能性が高いでしょう。
③NGではないが使い方に気を付けたいネクタイの色
夏に茶色などの温かみのあるカラー、冬に寒々しい水色など、季節感のない色を選ぶのは避けましょう。
また、先述のピンク色に加え、黄色やゴールド、シルバーのネクタイもカジュアルな印象が強いため、就活の際に着用するのは避けた方が無難です。
ただし、服装が比較的自由なアパレル業界やクリエイティブ業界などであれば絶対にNGというわけではありません。
黄色は明るく活発な印象に、ピンクは穏やかで優しい印象になりますし、どちらも親近感を感じさせる色でもあります。
とはいえ、やはり扱いが難しいカラーではありますので、どうしても着用したい際はメインカラーではなく差し色として使用されている程度のものを選ぶと失敗がなくてよいでしょう。
就活でのネクタイの結び方

ネクタイに慣れていないと、どう結べば良いのか悩んでしまいますよね。就活でのネクタイの結び方について、以下の流れで解説していきます。
ネクタイに関する重要ワード
ネクタイの結び方について解説する前に、ネクタイに関する4つの重要ワードについてチェックしておきましょう。
①ノット
ノットとは、ネクタイの結び目部分です。ネクタイはノットの作り方によって大きく印象が変わります。
ノットにはさまざまな種類がありますが、就活にはシンプルな「プレーンノット」がふさわしいとされています。
②ディンプル
ディンプルとは、ネクタイの結び目の下にあるくぼみです。英語で「えくぼ」という意味があります。
ディンプルを作ると、ネクタイの結び目がより立体的になります。就活においても、ネクタイを結ぶ際はディンプルを作るのがオススメです。
③大剣
ネクタイを真っすぐに伸ばした際に、両端が太い部分と細い部分があります。このうち太い方を「大剣」と呼びます。
大剣は7.5cm~9.0cm幅が一般的です。大剣が狭すぎるネクタイはカジュアルな印象を与えるため、就活では避けた方が良いでしょう。
④小剣
小剣とは、ネクタイの細い部分を指します。小剣は4.0cm幅が一般的です。
通常、小剣は大剣の後ろに隠れるので目立ちません。小剣をあえて左右にずらして見せる着こなしもありますが、就活では避けた方が良いでしょう。
プレーンノットの結び方
就活では、最もシンプルな結び方「プレーンノット」を推奨します。プレーンノットの結び方は以下の5ステップです。
- 大検を小剣の上からクロスさせる
- 大剣を小剣の裏へ通す
- 大剣を裏から喉元へ通す
- 結びのループ状の部分から大剣を通す
- 結び目を締める
はじめに大検を長めに取り小剣の上からクロスさせ、大剣を小剣の裏へ通します。大剣を裏から喉元へ通し、結びのループ状の部分から大剣を通してください。
最後に、緩すぎずきつすぎない程度に結び目を締めます。結び目を締める時にディンプルを作ると、より立体感のある仕上がりになります。
就活用のネクタイのQ&A

ネクタイに慣れていないと、着こなしや扱い方に悩むことがあるかもしれません。最後に、就活用のネクタイに関する以下の5つの質問に回答していきます。
Q1.|就活でネクタイピンはつけてもいい?
就活でネクタイピンをつけても問題ありません。
ネクタイピンの有無が選考の結果に左右することはありませんが、つけ方によっては採用担当者の心象を悪くする場合があります。
就活でネクタイピンをつける場合は、以下の点に注意してください。
- シンプルなデザインを選ぶ
- 色はシルバーが無難
- ネクタイが曲がらないよにする
- 大剣、小剣、シャツを同時に挟む
- 位置に注意する
上着を着用している場合は上着の第1ボタンより若干上に、上着を着用していない場合はシャツの第4ボタンと第5ボタンの間につけましょう。
Q2.|ネクタイがシワにならない保存方法・洗濯方法は?
ネクタイの一般的な保存方法は、「丸める」「吊るす」「平置きする」の3つです。収納スペースの応じて、好きな保存方法を選択してください。
結び目の部分はシワになりやすいため、ネクタイを外したら1日吊り干しして休ませてから収納するのがおすすめです。
収納スペースがない場合は二つ折りでも構いませんが、折り目をつきにくくするために軽めに畳みましょう。
洗濯方法に関しては、ネクタイの裏に書かれている洗濯表示に従ってください。シルク100%やドライクリーニングオンリーのネクタイは自宅では洗濯できないため、クリーニング店にお願いしましょう。
Q3.|面接のネクタイは証明写真と同じでいい?
面接のネクタイは、証明写真と同じでも違うものを着用しても問題ありません。
ネクタイを変えることで、同じスーツを着ていても印象を変えることができます。
証明写真と印象を変えたいのであれば、違うネクタイを着用してみるのもよいでしょう。もちろん、同じ印象を与えたいならあえてネクタイを変える必要はありません。
証明写真と面接、それぞれで与えたい印象に合わせてネクタイを選びましょう。
Q4.|就活用のネクタイは何本必要?
就職活動では、1社あたり少なくとも2回の面接があるため、少なくとも2本、可能であれば3本以上用意しておくと安心です。
また、複数社に応募している場合は、そのぶんネクタイも多めに用意する必要があることもあります。
例えば、1社目で用意したネクタイのカラーが赤色だったとします。しかし、2社目の企業にとって赤がライバル企業を思わせるカラーであった場合には、赤色ではない他のカラーのネクタイを用意する必要があります。
ネクタイは、自分の状況や志望している企業に合わせて適切な本数を用意しましょう。
Q5.|結んだネクタイがスーツの下からはみ出る場合はどうする?
ネクタイは、剣先がベルトのバックルにかかる長さが適切ですので、スーツのボタンの下から剣先がのぞくのは問題ありません。
ただし、長すぎる場合には結び方を変えたりネクタイピンを使用して長さを調節しましょう。
ノットが大きくなる「ダブルノット」「ウィンザーノット」「セミウィンザーノット」で結ぶとネクタイが短くなります。
また、小剣側を長めにして、大剣の後ろで折りたたむようにネクタイピンで固定する方法もあります。
就活中はネクタイにも気を使おう!
就活では見た目も重視されるため、ネクタイにも気を使いましょう。就活用スーツを着用しているとみんな同じ印象になりやすいため、ネクタイを工夫して面接官へ印象付けてみてはいかがでしょうか。
ネクタイの色や柄によって相手に与える印象は変わります。企業のイメージに合わせてネクタイの色や柄を選ぶのもオススメです。
ただし、就活にふさわしくないネクタイを選ぶと採用に影響する可能性もあるため、くれぐれも注意してください。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。