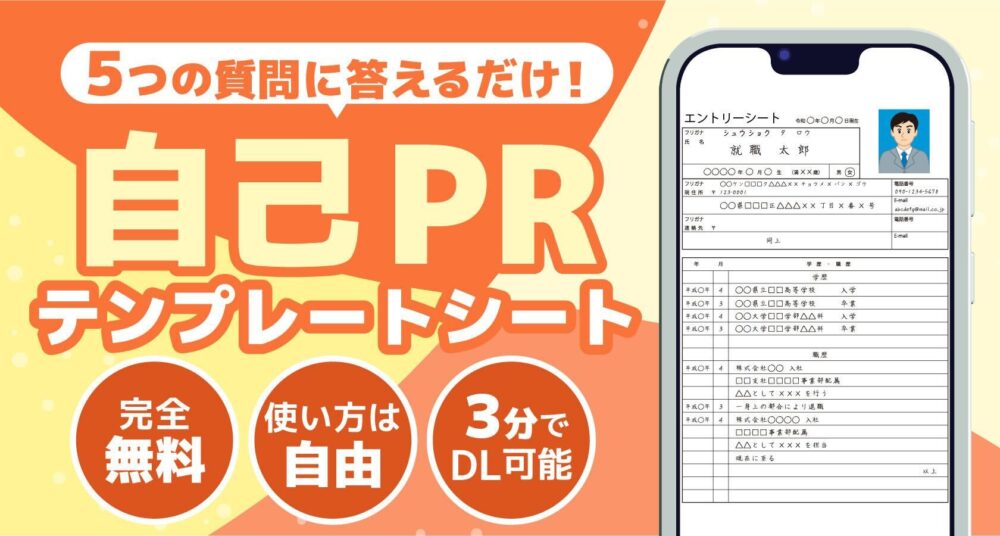自己PRを作成する際、「観察力」を強みとしてアピールしたいと考える人は多いでしょう。
しかし、「どのように表現すれば評価されるのか」「ありきたりな内容にならないか」と不安に感じることもあるはずです。
そこで、本記事では観察力の種類や書き方、注意点まで詳しく紹介します。ぜひ、これからの就活対策の参考にしてみてくださいね。
まずは確認!観察力には3つの種類がある
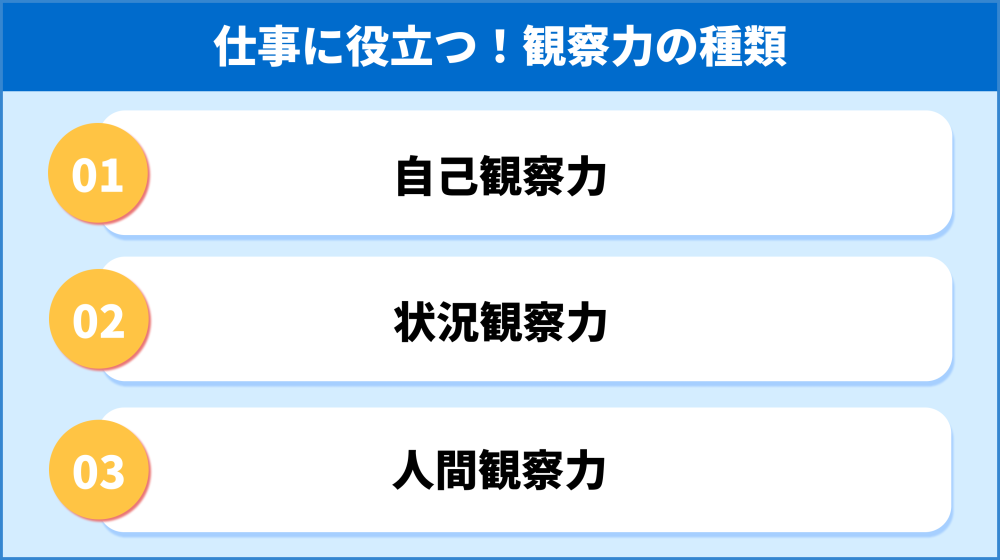
観察力には以下の3種類があります。仕事に役立つと効果的にアピールするためにも、あなたの持つ能力がどれなのか、まず明らかにしましょう。
- 自己観察力
- 状況観察力
- 人間観察力
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方は強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自身を持って臨めるようになりますよ。
①自己観察力
観察力は大きく自分の内側に向くものと外側に向くものに分類され、内側に向くものを自己観察力と呼びます。自己観察力とは、自分自身の状況を客観的に把握する能力のことです。
自己観察力が高い人材は、自分を見極めてセルフコントロールできるため、内省的に物事を考えられます。ストレスの対処が上手で、高い目的達成能力を持っていることも特徴です。
②状況観察力
観察力のうち、外側に向くものを状況観察と呼びます。つまり状況観察力とは、自分の周囲の環境や状況を観察して、情報を的確に捉える力のことで、観察力と言われて一般的にイメージする能力です。
状況観察力があると周りの状況を瞬時に判断できて、イレギュラーな事態にも対応できるでしょう。
仕事では、常に最善の選択をするために状況判断が重要になります。
その根本の能力が状況観察力なので、所属しているチームや組織の状況を観察して、改善につながったエピソードがあればぜひアピールしましょう。
③人間観察力
観察力と聞くと、人間観察力を思い浮かべる人もたくさんいるのではないでしょうか?
人間観察力に優れていると、周りの人を観察して情報を集めて、気持ちを細やかに捉えられるため、トラブルも回避しやすくなります。
しかし、この力は確かに役に立つこともあるのですが、企業への自己PRに使うときには少し注意したい側面も。次の章で詳しく説明しているため、ぜひ確認してみてくださいね。
企業が評価する観察力はどれなのか?
自己PRで観察力をアピールしたいと考えていても、企業が本当に評価する観察力とは何かを理解している人は少ないかもしれません。
観察力にはさまざまな種類があり、自己PRに適しているものと、そうでないものがあります。この章では、企業が評価する観察力と、自己PRでの伝え方について解説します。
- 「状況観察力」と「自己観察力」が評価される
- 「人間観察力」は評価されにくい
① 「状況観察力」と「自己観察力」が評価される
企業が求める観察力には、大きく分けて「状況観察力」と「自己観察力」の2つがあります。どちらも仕事で活かしやすく、成果につながる能力だからです。
状況観察力とは、周囲の動きや環境を適切に把握し、的確に判断できる力のことで、判断力や対応力にも通じる力です。企業では様々な判断をする機会があるため、重宝される力と言っていいでしょう。
自己観察力とは、自分の行動や思考を客観的に振り返り、成長につなげる力です。たとえば、マーケティングや企画職では、過去の施策やデータを分析し、改善策を考える力が不可欠ですよね。
自分を冷静に振り返り、次の行動につなげる力がある人は、自然と企業から評価されることになります。つまり状況観察力や自己観察力は、実務で活かしやすく、自己PRに適したスキルです。
② 「人間観察力」は評価されにくい
一方で、「人間観察力」を強みとして伝える際には注意が必要です。人間観察力とは、他者の行動や心理を細かく読み取る能力のことですが、観察するだけでは仕事の成果に結びつきにくいためです。
たとえば「私は人間観察力があり、人の表情や仕草から気持ちを読み取るのが得意です」と伝えても、業務にどのように役立つのかが明確でないと、評価もされにくいでしょう。
人間観察力をアピールする際には、単に「観察ができる」ことだけでなく、「観察した情報をもとに、適切な行動をとる力がある」と強調してくださいね。
たとえば、「私は人間観察力を活かし、お客様に応じて適切な声かけをすることで、顧客満足度が地域トップになった経験があります」と伝えると、実務に活かせることが分かりますよ。
観察力が強みとして生かせる職種を3つ紹介

観察力は多くの場面で活かしやすい強みですが、特に以下の3つの職種で大いに活躍できます。
自分に適性のある職種がまだ見つかっていない方は、ぜひ参考にしてください。
「自分に合う仕事は何だろう….」
「やりたい仕事なんてな….」
自分のやりたいことや合う仕事が分からず、不安な気持ちのまま就活を進めてしまっている方もいますよね。カリクル就活攻略メディアでは、就活応援のために「適職診断」を用意しました。LINE登録して診断するだけであなたに向いている仕事や適性が分かります。3分で診断結果が出るので、就活に不安がある方は診断してみてくださいね。
①マーケティング
マーケティング職は、観察力が最も活かせる職種の1つです。消費者の行動や市場の動向を多角的な視点で分析する必要があるため、トレンドや心理を読み取る能力が成果に直結します。
より具体的には、数値データだけでなく、消費者の微細な反応や社会的変化を注意深く観察することが重要な職種であるため、観察力がある人はより適性が高いでしょう。
また、競合他社の戦略分析や、新商品の売上が伸びない理由の特定、顧客の潜在的ニーズの発見なども踏まえると、観察力はマーケティング職において極めて重要な能力と言えるでしょう。
鋭い観察力とそこから知見を得られる洞察力が、効果的なマーケティング戦略立案につながります。
②営業
観察力がある人材は営業職にも向いています。営業職ではそれぞれの顧客の反応や感情の機微から、潜在的なニーズや購買意欲を察知し、最適な提案につなげる必要があるためです。
例えば、商談中の顧客の反応を細かく観察し、興味を示すポイントや躊躇するタイミングを的確に把握して提案を挟むことで、営業の成功確率が上がるでしょう。これには観察力が不可欠です。
単なる話術だけでなく、観察力に基づいた戦略的なコミュニケーションが、営業職においては大いに役立ちますよ。
③カウンセラー
カウンセラーは、観察力が特に重要視される専門職の1つです。相談相手の言語的・非言語的コミュニケーションを細部まで観察し、心理的な状況を正確に理解する能力が求められます。
とくに、カウンセラーにかかる人は心が不安定なことも多く、言葉以外にも表情や身体の緊張具合などから、相手の潜在的な不安を読み取って対応する必要があるため、観察力は必須です。
この際、観察力を活用できる人材なら、言葉の奥にある本質的な感情や心理状態を察知し、それに合わせた適切なサポートを行なえるでしょう。
簡単4STEP|観察力を活かした自己PRの書き方
選考で勝ち抜くためには、あなたの強みを魅力的に伝えることが大切です。自己PRを書く際には、以下の4つのステップを心がけましょう。
- まずは結論を伝える
- 具体的なエピソードで観察力の信憑性を高める
- 観察力を発揮して出た成果を伝える
- 仕事への活かし方を明確にする
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①まずは結論を伝える
初めに結論として「自分の強みは観察力である」と伝えてください。このとき、あなたがアピールしたい観察力の種類と、その能力によって何ができるのかを、簡潔に一文で書きましょう。
例えば、「私の強みは自己観察力であり、自分の状況を客観的に捉えることで、適切な選択ができます」と、話の結論をはっきり示すことが重要です。
最初に結論を提示するだけで、聞き手にも印象が残りやすくなります。
採用担当者は、多くの就活生のエントリーシートに目を通しています。そのため抽象的で回りくどい表現は避け、簡潔で分かりやすいかを意識しましょう。
②具体的なエピソードで観察力の信憑性を高める
次に、観察力を発揮した過去のエピソードを具体的に述べましょう。ただ「自分には観察力があります」とだけ伝えても信憑性がないため、具体性のあるエピソードを根拠として伝える必要があります。
あなたの観察力の信憑性を上げるためにも、これまでの経験を振り返って、具体的なエピソードを探してみましょう。
あなたの強みによって問題を解決したり、困難な状況を打破した経験をアピールできると、採用担当者にも好印象を与えられます。
③観察力を発揮して出た成果を伝える
次に、観察力がどのような成果に繋がったのかを明確に伝えましょう。
「このように観察をしました」だけでは、観察力を発揮したとは言えませんよね。観察だけでなく、それによってどんな対策をとり、どんな結果に繋がったかを伝えることで説得力を高められます。
例えば、「アルバイトで観察力を活かし、お客様の動きを見ながら対応を工夫した結果、接客満足度アンケートで高評価を得た」といった形です。
明確な成果でなくても、学びや自分の成長に繋がったことを強調してくださいね。
④どう仕事に活かすかを述べる
最後にあなたの強みが、応募企業の仕事にどのように活かせるのかアピールしてくださいね。
採用担当者は「この強みが実際に入社後の業務で役立つのか?」が気になっているため、入社後の業務への活かし方、いわゆる「強みの再現性」を示す必要があります。
ここで再現性を示せると、働く姿をイメージしやすくなり、良い評価が得られる可能性も高まるでしょう。
もし、仕事への活かし方が見つからないなら、志望企業で観察力が適していないかもしれません。仕事に役立つことを明確にして、志望している職種との関係性を提示する必要があります。
企業は、入社後に自分の強みの活かし方を考えているかを見ています。
強みがどれほどすごいものでも、入社後に活かせなければ意味がありません。内定をゴールにするのではなく、入社後の活躍まで見据えてアピールしましょう。
差別化!観察力を好印象にアピールする2つのコツ
自己PRを書き始めたばかりのときは、「観察力」を強みとして伝えても、企業に本当に評価されるのか不安になるでしょう。
しかし、伝え方次第で観察力は魅力的な強みに変わります。この章では、企業に好印象を与えるための観察力アピールのコツを2つ解説します。
- エピソードに具体的な数字やデータを用いる
- 第三者からの評価も伝える
① エピソードに具体的な数字やデータを用いる
観察力をアピールするときは、具体的な数字やデータを入れると説得力が高まります。
「周りを見る力があります」だけでは、抽象的かつ、強みに信憑性が出ません。数字やデータを合わせて説明することで、専門外の人でも強みを客観的に把握でき、評価がしやすくなりますよ。
例えば、接客業のアルバイト経験がある場合、「お客様の動きを観察し、適切なタイミングで声をかけた結果、売上が10%伸びました」など、具体的な成果を数字で示してください。
数字があることで、自分の観察力が仕事に活かせることを明確に伝えられます。
②第三者からの評価も伝える
観察力を自己PRで伝えるときは、自分だけの視点ではなく第三者からの評価を伝えることが効果的でしょう。
「観察力が強みです」と自分で主張するだけでは客観性がなく、説得力が低くなります。
そこで、「アルバイト先の店長から『よく周囲を観察しているから接客が的確だ』と褒められました」など、第三者からの評価を添えると良いです。
客観的な評価を含めることで、企業も安心してあなたの強みを理解できます。
観察力を自己PRで伝える際の注意点4つ
観察力を伝える際の注意点は以下の4つです。悪い印象を与える自己PRを作成しないためにも、一通りチェックしてくださいね。
- 自分の観察力の種類を明確にする
- 人間観察力のみをアピールしない
- 観察力と洞察力を混同しない
- 完璧主義な印象が強くならないように注意
①自分の観察力の種類を明確にする
自己PRで観察力をアピールする際は、単に「観察力がある」と述べるのではなく、自分の観察力がどんな種類か具体的に分析し、把握しておくことが重要です。
自分の観察力の特徴や、それがどのように発揮されてきたかを客観的に分析することで、より説得力のある自己PRを作成できます。
例えば、「細部まで注意を払う力」「状況の本質を素早く把握する力」「人の微妙な感情の変化を読み取る力」などのように、より的確な表現に言い換えましょう。
自分の観察力の特徴を具体的に言語化し、それを裏付ける経験や事例を準備しておくことが大切です。
②人間観察力のみをアピールしない
人間観察力は、周囲の人の態度や雰囲気から、人の気持ちを細やかに察せられる特徴があり、これが仕事に役立つ場面も確かにあります。
しかし、「人の気持ちを察せられる」だけでは実務に結びつかないため、これだけを強くアピールしても評価に繋がらない可能性が高いでしょう。知らずに主張し続けると、選考落ちに繋がりかねません。
人間観察力をアピールする場合は、自己観察力や状況観察力など、仕事の成果に直結しやすい観察力を合わせて強調するのがおすすめ。
または、人間観察力を活用してどんな行動を取り、それがどんな成果に繋がったか、詳しくアピールすると良いでしょう。
③観察力と洞察力を混同しない
観察力を自己PRで伝える際には、洞察力と混同しないことも重要です。観察力は事実や現象を正確に捉える能力であり、洞察力は観察した情報から本質的な意味や背景を読み解く力を指します。
似ている強みですが、明確に違いがあるため注意が必要です。観察力は特定の現象について「何が」「どう起こったか」を観察する力で、洞察力は「なぜ」「どういう意味があるか」を考察する力を示します。
例えば、「チームメンバーの業務を注意深く観察し、メンバーが迷いやすい部分をマニュアル化して業務の効率化を図った」という経験なら、観察力としてのアピールになります。
④完璧主義な印象が強くならないように注意
観察力は企業も重宝する力ですが「絶対に失敗しないように徹底的に観察する」などのアピールをすると、「完璧主義すぎて柔軟性に欠けるのでは」と警戒される可能性もあります。
幅広い人材が集まる組織では、業務をするにあたって、慎重さと柔軟性のバランスも重要です。
観察力がある人でも、リスクに対して警戒しすぎたり、判断をギリギリまで迷う人は、組織によっては合わないと判断されることも少なくありません。
したがって、観察力を強みに用いる際には、完璧主義だと思われないように気をつけてくださいね。
自己PRで観察力をアピールする例文を5つ紹介
観察力を自己PRでアピールするための例文を、能力別・職種別に全部で5つ紹介します。例文を参考にすれば、どんな構成で書くべきか理解できるでしょう。
実際に自己PRを書き始められるように、カリクルは全力で就活生を応援しています。
まだ自己PRの作成ができていない方は自動生成ツールでサクッと、すでに自己PRができている人は赤ペンESという無料添削サービスで自己PRを添削してもらいましょう!
すべて「完全無料」で利用できますよ。
また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。
無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介
観察力の種類別の自己PR例文2選
観察力はいくつかの種類にわけられますが、より自己PRに適しているのは「自己観察力」と「状況観察力」の2つです。
まずはこれらの観察力を自己PRに活用した例文を紹介していくため、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 自己観察力
- 状況観察力
①自己観察力
自己観察力を自己PRの軸にした例文を添削しました。自己観察力によって、仕事の優先順位を意識して取り組めるようになったと述べた自己PRです。
自己観察力の自己PR
【結論】私の強みは、自身の失敗を成長に活かすために原因を分析する自己観察力です。失敗を成長の糧に変える自己観察力と、その改善を実行に移す行動力です。
添削コメント|「自己観察力」に「改善を実行する行動力」を加えることで、企業が求める即戦力としての印象を強化できます。また、「成長の糧に変える」と表現することで前向きさをアピールします。
【エピソード】私は大学時代にイベント会場で配膳のアルバイトをしていました。仕事量が増えてくると、忙しさからつい簡単な業務から手を付けてしまい、業務が悪循環に陥ってしまうことが何度かありました。業務が増えるにつれて忙しさに負けて簡単な作業から手を付けてしまい、業務の進行が悪循環に陥る場面を経験しました。
添削コメント|エピソードは「何が起こったか」を簡潔かつ鮮明に表現しましょう。「経験しました」とすることで、読者に一貫性を感じさせ、流れを自然にできます。
【エピソード詳細】常に効率的に業務を進めるためには、面倒なことでも優先順位を意識して取り組むべきだと客観的に判断したため、それ以降は自身の行動を改め、仕事の順番を重視して落ち着いて業務を遂行しました。すべきだと気づきました。その後、仕事の順番を重視するためにタスクの洗い出しを徹底し、落ち着いて業務を遂行するよう行動を改めました。
添削コメント|具体的な行動(タスクの洗い出し)を加えることで、努力の過程が伝わりやすくなります。抽象的な表現を避け、成果に結びつく行動を記述するのがポイントです。
【結論】結果的に、ミスなくスムーズに仕事を進められるようになったと思います。結果として、業務の効率化が進み、ミスなく仕事を進められるようになり、上司からも信頼を得られるようになりました。
添削コメント|「上司からの信頼」を加えることで、成果が第三者視点で評価されていることをアピールします。企業は他者からの評価を重要視するため、有効な表現です。
【入社後】この自己観察力を活かして、ミスを客観的に見つめなおして学び続ける人材として、貴社で活躍したいです。と行動力を活かし、常に改善を重ねながら成果を追求する人材として、貴社の業務効率化や成長に貢献したいと考えています。
添削コメント|「業務効率化や成長に貢献」と具体的な貢献内容を明示することで、企業に対する適応性と意欲を効果的に示せます。
【足りなかった部分】自己観察力と行動力のつながりが不明確で、具体的なエピソードや成果が抽象的でした。また、企業での貢献イメージが不足しており、自己PRとして説得力を高める要素が欠けています。
【添削箇所】結論で行動力を強調し、エピソードにタスクの洗い出しを加え具体性を向上させました。成果に第三者評価を追加し、入社後の展望を具体的に表現しています。
【どう良くなったか?】エピソードに具体性が増し、行動力を伴う強みとして説得力が向上しました。成果と入社後の展望が明確化し、企業が求める人物像を強くアピールできています。
| ・具体的なエピソードを明示する ・自己観察力があったことによる成果と学びを強調する ・企業への貢献できる可能性をアピールする |
②状況観察力
状況観察力を自己PRの軸にした例文を添削しました。企業でもこの能力を活かして顧客の潜在的なニーズに合わせて営業できることをアピールしています。
状況観察力の自己PR
【結論】私は状況観察力があり、周りが求めることを的確に把握して行動できます。私の強みは、状況を的確に把握し、周囲のニーズに応じた行動を迅速に取れる状況観察力と行動力です。
添削コメント|「状況観察力」と「行動力」をセットでアピールすることで、単なる特性ではなく行動へ結びつく強みとして説得力を持たせました。
【エピソード】私は東日本大震災をきっかけにボランティアに興味を持ち、大学時代に熊本地震のボランティアに出向きました。大学時代、熊本地震のボランティア活動に参加し、混乱する現場で状況を把握して行動する重要性を学びました。
添削コメント|エピソードの背景に「混乱する現場」という課題を追加し、取り組んだ内容に意義を持たせました。
【エピソード詳細】炊き出しの班では状況を観察しながら、乱れた配膳の列を整備したり、配膳が足りなくなりそうなときには紙皿を取りに行ったりというように周囲を見ながら動いた結果、他のボランティアの人たちから、働きやすかったと言ってもらえました。配膳の列が乱れる中、迅速に整備を行い、配膳物が不足しそうな際には紙皿を補充するなど、全体の状況を見て主体的に動きました。その結果、他のボランティアの方々から「働きやすかった」と感謝の言葉をいただきました。
添削コメント|「迅速に」「主体的に動きました」と行動の質を具体化し、成果を強調することでエピソードに説得力を持たせました。
【結論】このボランティア経験によって、周りの状況を見ながら適切に判断して、臨機応変に対応できる力を身につけたと思っております。周囲の状況を迅速に判断し、臨機応変に対応する力が身につきました。この力はどのような環境でも活用できると自負しています。
添削コメント|「どのような環境でも活用できる」とすることで、企業が求める汎用的なスキルとして魅力をアピールしました。
【入社後】入社後には状況観察力を活かして、営業職としてお客様の様子を観察しながら、潜在的なニーズを見極めた提案を常に心がけたいです。入社後には、状況観察力と行動力を活かし、お客様の潜在的なニーズを把握し、それに応じた提案を迅速かつ的確に行うことで、貴社の顧客満足度向上に貢献したいです。
添削コメント|「顧客満足度向上」と具体的な成果を加えることで、企業への貢献意欲をより明確に示しました。
【足りなかった部分】状況観察力が持つ具体性や行動へのつながりが曖昧で、エピソードから成果までの流れが弱いのが改善点でした。また、企業への具体的な貢献イメージが不足しています。
【添削箇所】結論では行動力を明示し、エピソードでは混乱する現場という課題を加えました。成果に第三者評価を取り入れ、入社後の貢献内容を具体化しています。
【どう良くなったか?】行動力を伴う具体的な強みを伝え、エピソードに説得力を持たせました。入社後の貢献が明確化し、企業に適した人材像を効果的にアピールできています。
| ・具体的なエピソードを提示する ・入社後の具体的な活用例を加える ・観察力と行動力のバランスを強調する |
職種別の自己PR例文
観察力をアピールできる自己PR例文を、ここでは志望する職種別に3つ紹介します。全体像を把握して、自己PR作成に役立ててくださいね。
- 営業
- 看護・介護
- マーケター
①営業(元記事運用)
観察力と営業を結び付けた自己PRを添削しました。観察力を活かして、後輩の悩みを解決できたことをアピールする例文です。
観察力と営業を結び付けた自己PR
【結論】私の強みは、相手の本心を考え抜いて提案できる観察力です。深く汲み取り、最適な解決策を提案できる観察力と問題解決力です。
添削コメント|「観察力」を「本心を汲み取る力」とし、「解決策を提案できる問題解決力」を加えることで、具体性と行動力が強調され、企業が求めるスキルに即した内容に改善しました。
【エピソード】私は、大学時代に所属していた野球部の活動で、周りと打ち解けられずにいる後輩がいることに気付きました。際、周囲と打ち解けられずに孤立している後輩に気付きました。何気ない会話から理由や背景を確認し、些細な心掛けを意識しました。日々の会話を通じて、状況や背景を慎重に観察し、具体的な原因を探ることを意識しました。
添削コメント|「何気ない会話から理由を確認」という曖昧な表現を、「会話を通じて状況や背景を慎重に観察」と具体化し、観察力を活かしたプロセスを明確にしました。
【エピソード詳細】相手の本心を探っていくと、一番の理由は練習についていけてなかったためだと分かりました。練習方法や改善点などを指導しながら日々練習に打ち込んでいくと、次第にチームメイトとの壁がなくなっていく様子を見守ることができました。観察を続けた結果、後輩が練習についていけていないことが孤立の主な原因だと分かりました。その後、練習方法を個別にアドバイスしながら、丁寧にサポートを続けました。次第に後輩がチームに溶け込み、メンバーとの信頼関係を築けるようになる変化を見届けることができました。
添削コメント|「練習方法や改善点を指導」という抽象的な表現を、「個別にアドバイスし、丁寧にサポートを続けた」と具体化することで、行動の過程が明確になり、説得力が増しました。
【結論】先輩として後輩と向き合い、悩みを解決に導くことができて嬉しかったです。この経験を通じて、観察力を活かしながら相手の本心を汲み取り、信頼関係を築くことで、問題解決へと導ける力を身につけました。この力は人間関係の構築やチームの成果向上に役立つと確信しています。
添削コメント|「悩みを解決できて嬉しかった」という感情的な表現から、「信頼関係を築き問題解決に導く力を身につけた」と成果を具体的に示す形に改善しました。
【入社後】この経験から、相手の本心を汲み取ることで、深いニーズにたどり着けると感じました。貴社の営業として、顧客ニーズを考え抜いた提案をして、売上に貢献したいと考えております。や潜在的なニーズを観察力で見抜き、最適な提案を行うことで、貴社の売上拡大と顧客満足度向上に貢献したいと考えております。
添削コメント|「深いニーズにたどり着ける」という抽象的な表現を、「売上拡大と顧客満足度向上」という具体的な成果に置き換え、入社後のビジョンを明確化しました。
【足りなかった部分】「観察力」の具体的な活用方法や成果が曖昧で、行動の過程が分かりにくい部分がありました。また、企業での具体的な貢献イメージが不足しています。
【添削箇所】「観察力」に「問題解決力」を追加し、行動過程を具体化しました。成果には信頼関係の構築や問題解決の力を明示し、入社後の貢献内容を「売上拡大に貢献する」としています。
【どう良くなったか?】観察力を活かした行動や成果が具体化され、説得力が向上しました。入社後の活躍イメージも明確になり、企業が求める能力と一致した内容となっています。
| ・具体的な行動プロセスを描写する ・問題解決の結果を成果として明確化する ・入社後の活用イメージを具体化する |
営業職の志望動機を書くポイントは、こちらの記事でも詳しく解説しています。他の学生と差別化してアピールする方法も載っていますよ。
【新卒・未経験者必見】営業職の志望動機の書き方を例文付きで紹介
②看護・介護
観察力と看護・介護を結び付けた自己PRを添削しました。些細な体調変化にも察知できる観察力がアピールされています。
観察力と看護・介護を結び付けた自己PR
【結論】私の強みは、普段からよく相手を観察し、些細な体調変化にも気が付けることです。相手の些細な変化を見逃さない観察力と、それに基づき迅速に対応できる冷静な判断力です。
添削コメント|「観察力」に「冷静な判断力」を加えることで、問題解決への行動につながる強みを明示しました。企業が求める具体性や実務適応力を強調しています。
【エピソード】その強みを活かして、介護職員実務者研修を修了し、介護職として入居型の施設で働いています。その後の入居型施設での業務において観察力を活かしながら、ご利用者の健康を支える役割を担っています。
添削コメント|「強みを活かして」という漠然とした表現を、具体的な業務内容に置き換え、日常的に強みを発揮していることを示しました。
【エピソード詳細】常にご利用者の表情や様子を観察して、些細な変化を察知できる観察力を利用して、迅速に往診医に知らせたり、冷静な対応を取ったりした結果、大事に至らずに済んだことが、これまでに何度かあります。些細な変化を察知した際には、迅速に往診医に報告し、適切な対応を取ることで、大事に至らない事例を何度も作り出しました。
添削コメント|「何度かあります」という曖昧な表現を、「大事に至らない事例を作り出した」と具体化しました。また、「適切な対応を取る」と対応内容を明示しています。
【結論】ご家族の方々からも感謝の言葉をいただくことが嬉しく、介護職としての仕事にやりがいを感じています。この取り組みにより、ご家族から感謝の言葉をいただく機会が増え、信頼関係を深めることができました。介護職としての責任とやりがいを強く感じています。
添削コメント|「嬉しく」という感情的な表現を削除し、「信頼関係を深める」と成果を明確にしました。プロフェッショナルとしての姿勢を伝えることを意識しています。
【入社後】貴事業所でも介護職として、些細な変化を察知して、病変にも真っ先に気が付くことで、ご利用者の健康維持に貢献したいです。観察力を活かし、些細な変化をいち早く察知することで、ご利用者の健康維持や早期治療につなげ、事業所の信頼向上に貢献したいです。
添削コメント|「病変に真っ先に気が付く」という表現を、「健康維持や早期治療」「事業所の信頼向上」と具体的な貢献内容に置き換え、より説得力を高めました。
【足りなかった部分】観察力と判断力が問題解決にどのように結びついたかが曖昧で、行動や成果の具体性が不足していました。また、入社後の貢献内容が抽象的です。
【添削箇所】「冷静な判断力」を追加し、行動内容を具体化しました。成果として信頼関係を深めた点を明確にし、入社後の貢献を「健康維持や早期治療」「信頼向上」に具体化しています。
【どう良くなったか?】観察力と判断力を活かした具体的な行動と成果を明示することで、説得力が向上しました。入社後の貢献が明確化し、企業への適応力をより強くアピールできています。
| ・具体的な行動を強調する ・迅速な対応とその結果を具体化する ・入社後の貢献内容を企業視点で表現する |
「福祉業界の志望動機を書くポイントをさらに知りたい!」という方は、ぜひこちらの記事も読んでみてくださいね。
福祉業界の志望動機の例文を紹介|ポイントや注意すべき点も解説
③マーケター
観察力とマーケターを結び付けた自己PRを添削しました。観察力を発揮しただけでなく、そこから学びを得たことも示した例文です。
観察力とマーケターを結び付けた自己PR
【結論】わずかな変化にも気づく観察力が、私の強みです。私の強みは、わずかな変化から本質を見抜き、新たな価値を見出す観察力です。
添削コメント|「観察力」を「本質を見抜き、新たな価値を見出す」と具体的かつ応用性の高い表現に変更しました。これにより、企業が求める創造性や分析力を強調できます。
【エピソード】週末にはよくウィンドウショッピングをしていますが、なぜ多くの人がハイブランドのディスプレイに魅了されるのか気になりました。多くの人々がハイブランドのディスプレイに引き寄せられる理由に興味を持ちました。
添削コメント|「気になりました」を「興味を持ちました」と表現することで、主体的かつ意識的な観察の姿勢を強調しました。
【エピソード詳細】そこでハイブランドの店舗のインテリアや配置の特徴を観察してみると、マネキンが季節ごとにポーズを変えて、世界観を引き出しているためだと思いました。ハイブランド店舗のインテリアやディスプレイを観察し、季節ごとのマネキンのポーズや配置がブランドの世界観を巧みに引き出している点に気づきました。
添削コメント|「観察してみると」といった曖昧な表現を「観察し、気づいた」と具体的に表現しました。また、「世界観を引き出している」という結果に説得力を持たせています。
【結論】小さな発見かもしれませんが、私が観察を重視している理由は、日常生活で新しい発見を繰り返すほど、人生は面白くなると感じているためです。この発見を通じて、観察力が物事の本質を捉え、新たな気づきを生み出す力であると実感しました。この力は人々の心を動かす商品やサービスを創出する基盤になると考えています。
添削コメント|「人生は面白くなる」といった個人的な感想を削除し、「本質を捉え、新たな気づきを生み出す力」と表現することで、企業における応用性を強調しました。
【入社後】データや人の心理に対する観察力を活かして、入社後には世間の動向を見ながら、継続的に商品が売れるための仕組みを構築したいと考えております。観察力を活かし、データ分析や消費者心理の理解を深め、世間の動向に応じた商品の魅力を最大化する仕組みを構築し、貴社の事業成長に貢献したいです。
添削コメント|「継続的に商品が売れる」という表現を、「商品の魅力を最大化」「事業成長に貢献」と具体化し、貢献意欲を強調しました。
【足りなかった部分】観察力が具体的にどのように活用され、成果につながったかの説明が不足していました。また、入社後の貢献内容が抽象的で具体性に欠けています。
【添削箇所】「観察力」を「本質を見抜き、新たな価値を見出す力」と再定義し、エピソードの発見内容を具体化しました。入社後の貢献を「商品の魅力最大化」「事業成長」と明確化しています。
【どう良くなったか?】観察力を具体的な発見や成果に結び付けることで説得力が増しました。入社後のビジョンが明確化され、企業への貢献意欲がより具体的に伝わる内容となっています。
| ・観察力を「具体的な発見」に結び付ける ・観察力の成果を「新たな価値」として明示する ・企業での貢献を明確化する |
こちらの記事では、Webマーケティング職の志望動機の書き方を紹介しています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
webマーケティングの志望動機を例文付きで解説!必要な素質も紹介
要注意!自己PRで観察力をアピールする際のNG例を紹介
「観察力」を自己PRの強みとして考えている人は多いですが、伝え方によってはマイナスの印象を与えることがあります。
ここでは、観察力を自己PRに盛り込む際に避けるべきNG例と、その改善方法について解説します。
- 人間観察力のみを強調しすぎた自己PR
- 観察力と洞察力を混同している自己PR
①人間観察力のみを強調しすぎた自己PR
観察力の自己PRでは、「人をよく見ている」ことのみを強調しすぎると逆効果になる場合があります。特に、人間観察が得意なだけでは、企業が求める「仕事に活かせる観察力」とは結びつかないため注意が必要です。
以下の例文は、観察力を強みとして伝えようとしながらも、アピールとして適切でない表現を含んでいるNG例です。
人間観察力のみを強調しすぎた自己PR
私は観察力があり、人のちょっとした変化にもすぐ気づくことができます。
大学の講義では、教授のちょっとした仕草や表情を観察し、その日の気分や講義の進め方を予測していました。その結果、教授の機嫌が良い日は質問がしやすく、成績評価を上げるために適切なタイミングで発言することができました。
また、サークルではメンバーの様子を細かく観察し、誰が悩んでいるのかを察知して声をかけるようにしていました。ある時、元気がない後輩に「何かあった?」と声をかけたところ、驚かれながらも相談に乗ることができ、信頼を得ることができました。
このように、私は人の表情や行動の変化を敏感に察知し、状況を有利に進めることができる観察力を持っています。
この例文の問題点は、「観察力が実践的な業務に活かせない」と判断される可能性がある点です。
特に、教授の機嫌の良さを観察していたというアピールは、一見成果には繋がっているものの、企業での再現性は低いでしょう。観察力が発揮されたとは言い難いエピソードになっています。
観察力のエピソードでは、観察した情報を元に、チームや業務に貢献した具体的な成果を示してくださいね。
②観察力と洞察力を混同している自己PR
観察力をアピールする際に、「人や物事を観察して分析し、行動に活かすこと」と「単に深い洞察を行うこと」を混同してしまうケースがあります。
以下の例文は、観察力ではない力をアピールしているうえ、観察後に行動に活かせていないNG例です。
観察力と洞察力を混同している自己PR
私は観察力があり、細かいことにすぐ気づきます。
大学のカフェでアルバイトをしていた際、常連のお客様の服装や持ち物の変化をよく観察していました。例えば、いつもと違うバッグを持っていたり、少し疲れた表情をしていたりするのを見て、「今日は仕事が忙しかったのかな」と推測していました。
また、授業では友人のノートの取り方や姿勢を観察し、「この人は集中している」「この人は退屈している」と考えるのが得意でした。このように、私は周囲の人の些細な変化を察知する観察力を持っています。
この観察力を活かし、御社でもお客様の気持ちを理解し、円滑なコミュニケーションを図っていきたいと考えています。
この例文の問題点は、観察力と洞察力を混同していることと、「観察して終わってしまっている」ことです。人の変化を見てその背景を予測することは洞察力であり、観察力とは異なる力です。
また、例文では相手の変化に気づいても、それを活かして行動に移す場面がないため、仕事で求められる「ビジネスに役立つ観察力」とは言えません。
観察力を自己PRする際は、「気づいたことをもとに行動し、具体的な成果を生んだ経験」を示すように気をつけましょう。
観察力を強みとして自己PRを作成する際のQ&A
自己PRを書く際、「観察力」を強みに選んでも、本当に企業に評価されるかどうか不安になるでしょう。また、具体的にどう伝えるべきか分からず、悩んでいるかもしれません。
ここでは、観察力を自己PRに活用する際に疑問として浮かびやすい3つのQ&Aをまとめて解説します。
- 自己PRで観察力を伝えるときのコツは?
- 自己PRで観察力を伝えるときの注意点は?
- どんな職種で評価されやすい?
① 自己PRで観察力を伝えるときのコツは?
観察力を発揮したエピソードを伝える際、当時の行動の結果に、具体的な数字や客観的な評価を入れましょう。
自己PRで観察力をアピールするときは、観察力を活かしてどのような行動を取ったか、最終的な成果は何かまで説明する必要があります。ここで数字や評価を入れると、信憑性が高まるのです。
ただ「売上が上がりました」だけでは信憑性に欠けますが「売上が10%上がり、お客様からも『対応が丁寧で嬉しかった』との評価をいただきました」とすれば、誰にでも成果が伝わりますよね。
このように、成果を数字で示した自己PR例文を用いることで、企業にあなたの強みを具体的にイメージさせましょう。
② 自己PRで観察力を伝えるときの注意点は?
自己PRで観察力を伝えるときは、神経質な印象を与えないよう気をつけましょう。
「細部まで完璧に観察します」「失敗しないよう、確信が持てるまで時間をかけて観察します」と書くと、企業に柔軟性がない人だと思われる可能性があります。
細かく観察することはあくまで手段であり、そこから得られた情報を元に素早く判断・行動できることを示してくださいね。
③ どんな職種で評価されやすい?
観察力が特に評価されやすい職種は営業職や接客・サービス業など、人と接する仕事です。
なぜなら、こうした職種では相手が口に出さないニーズまで観察力で察知し、迅速に行動する力が求められるからです。
営業・接客・サービス業では、顧客の悩みを素早く把握したり、逐一反応を見てアプローチを変更したりする必要があります。これらの行動には観察力が欠かせません。
観察力を強みにして好印象な自己PRを作成しよう!
今回は、自己PRで観察力を活用する場合の書き方と注意点を解説しました。
観察力と言っても能力の種類は幅広いので、どんな種類の力で、どう活かせるのか明らかにしましょう。あなたの長所をうまく提示して、高評価を獲得してくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。