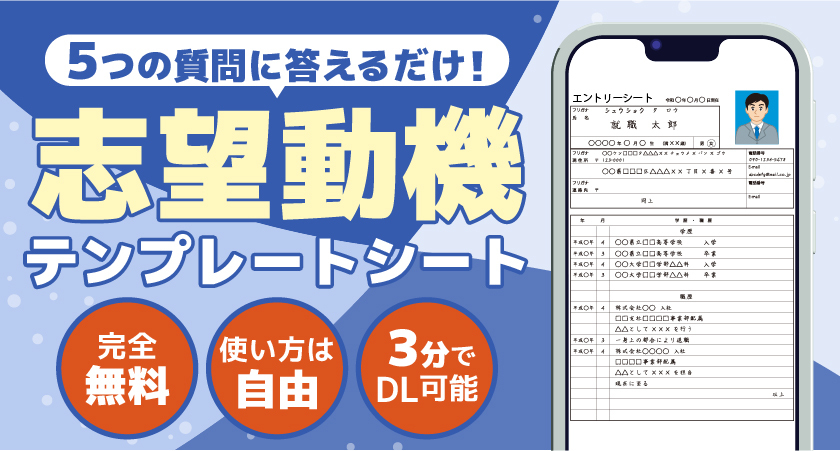就職活動を進めるにあたり、少なくとも「自己PR」と「志望動機」の作文がありますよね。違いが分からなかったり、内容を工夫するために頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
今回は自己PRと志望動機の違いから、参考例文を解説していきます。
志望動機のお助けツール!完全無料
- 1志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を作成できる
- 2ES自動作成ツール
- AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
- 3志望動機の無料添削
- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します
自己PRと志望動機の違いとは?
自己PRは自分の経験、スキル、資質など、自分自身の強みや特徴をアピールするもので、主な目的は企業に自分を採用するメリットや価値を伝えることです。
具体的な経験や実績をもとに、自分がどのような成果を上げられるのか、また、企業やチームにどのような価値をもたらせるのかをアピールします。
一方、志望動機はその企業を選んだ理由や、その企業で働くことに対する意欲、入社後に何を成し遂げたいのかなど、自分の動機や目的を伝えるものです。
主な目的は自分がその企業で働きたい理由や、企業の文化、ビジョンにどれだけ自分が共感しているのか、自分がどのようなキャリアを築きたいのかを示すことと言えるでしょう。
自己PRの作成方法3ステップ

自己PRを作成するにあたり、重要なステップは大きく分けて3つあります。
それぞれのポイントを抑えておくことで、より採用担当の方に響く自己PRを作成できるので、一緒に確認していきましょう。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①自己PRを問われる意図を把握する
採用担当の方は、応募者が自分自身の強みや得意分野をどれだけ理解し、どうアピールすることができるのかを見極めたいと考えて自己PRを課しています。
また、応募者がその企業や職種においてどれだけの価値をもたすのか、具体的にどのような貢献が期待できるのかを示すにあたっても重要です。
採用担当の方は、具体的な実績や経験をもとに、応募者がチームやプロジェクトに適応できるかを判定したいとも考えているので、積極的に順応性をアピールするのも良いでしょう。
②自己分析をして強みを見つける
自己PRの根幹は「自分の強みや特性をいかに採用企業に伝えるか」という点に集約されます。よって、自己分析を実施し、強みや特性を明確に理解するのも非常に重要です。
まず、自己分析で自身の強みや長所、短所を理解することで、他の応募者との差別化を図れます。
多くの人は「コミュニケーション能力がある」や「努力家である」といった一般的な強みを挙げがちですが、自己分析を行うことで、独自性のある、他の人とは違った強みをアピールできるでしょう。
自己分析の仕方が分からない方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。
③強みが活きたエピソードから組み立てる
自己PRの目的は自らの価値を具体的に伝えることなので、「強みが活きたエピソード」を中心に自己PRを組み立てることは極めて重要と言えます。
エピソードを使うことでより具体的な話ができるので採用担当の方にとってイメージしやすく、印象に残りやすいです。
抽象的な強みや長所をただ列挙するよりも、実際のシチュエーションでどのように経験が活かされたのかを示すことで、その強みの実用性や効果を具体的に伝えられるでしょう。
また、エピソードを用いることで自分自身がどのような状況でどのように行動し、それがどのような結果をもたらしたのかというプロセスを明示的に示すことも可能です。
志望動機の作成方法3ステップ

自己PRと同様に、志望動機を作成するにあたってのステップも確認していきましょう。
自己PRと統合性のある内容が求められるので、自分で書いた自己PRも確認しながら執筆することが大切です。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①志望動機を問われる意図を把握する
面接官が志望動機を問う背景にはさまざまな理由がありますが、第1に、「求職者がその企業や業界に対してどれだけの情熱や関心を持っているかを評価するため」が挙げられます。
熱意のある人は業務に取り組む際のモチベーションも高く、企業のために価値を生み出す可能性が高いと判断できることが多いです。
第2に、「求職者が企業のビジョンやカルチャー、価値観に共感し、組織にフィットするかどうかを確認するため」が挙げられます。
企業文化と合致した人材は組織内での適応が早く、転職や退職をせず、長期間に渡って働いてくれる可能性も高いです。
②業界・企業研究をしっかりと行う
志望動機の作成において、業界・企業研究も必要不可欠なステップです。しっかりと行うことで、応募者が真剣にその企業や業界を目指している様子が伝わります。
単に表面的な知識や情報ではなく、深堀りした情報を持っていると、「この人は本当に入社したいのだな」と判断してもらえるでしょう。
全ての志望者が内容の深い志望動機を持っているわけではない中で、詳細な業界・企業知識をアピールすることで、他の応募者との差別化も図れますよ。
企業研究のやり方については、こちらの記事で紹介しています。ぜひ最後まで読んで、企業研究を実践してみてくださいね。
③具体的なエピソードをもとに組み立てる
具体的なエピソードを基にすることも非常に効果的です。まず、抽象的な言葉や一般論ではなく、具体的なエピソードを元に話すことで、自身の経験や考えに根拠があることが伝わり、説得力が増します。
また、なぜその企業が良いのかをエピソードを交えて説明することで、単なる表面的な志望動機ではなく、具体的な経験や体験をもとにした、熱意を持っていることも伝わるでしょう。
「Point(主張)」、「Reason(理由)」、「Example(具体例)」、「Point(再度の主張)」の順番で情報を伝える、PREP法を活用するのもおすすめです。
この法則に従いエピソードを織り交ぜながら志望動機を述べることで、採用担当の方も最初の段階から結論を念頭に置いて読み進められます。
志望動機のテンプレートを無料でプレゼント!
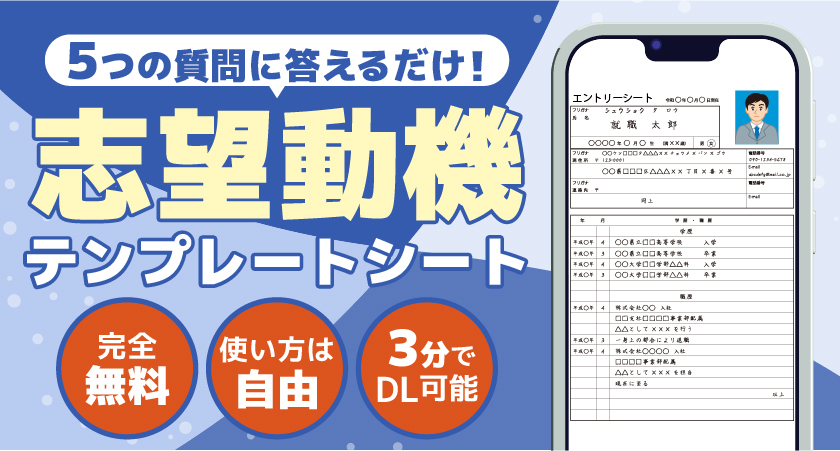
志望動機で言いたい内容が決まっていても、どういう構成や流れで書くのが正しいのか悩みますよね。そもそも志望動機で書く内容が決まらない方も多いはず。
そこでカリクルでは、志望動機を書くためのテンプレートを無料でプレゼントします!
何から始めればいいかわからず就活が不安な方、うまくエントリーシートが書けず一次選考で落ちてしまう方、ぜひこの志望動機のテンプレートを活用してください。
テンプレートには5つの質問があり、回答していくだけで、簡単に志望動機が完成します!テンプレートを使って自分の魅力を最大限引き出した志望動機を作りましょう!
この特典はパソコン・スマホにダウンロードして利用できますよ。さっそく以下のフォームから、特典をチェックしてみてくださいね。
自己PRと志望動機をつなげる方法

ここからは、自己PRと志望動機を繋げる具体的な方法をご紹介します。
以下のコツを押さえることで、両者に一貫性が生まれてより説得力のある内容に仕上がるでしょう。
①同じエピソードを用いてつなげる
自己PRと志望動機をつなげる効果的な方法の1つは、同じエピソードを用いることです。
自己PRで語った経験や成長の過程を、志望動機においても企業への貢献や志望理由と関連付けて説明します。
例えば、大学でのプロジェクト経験を自己PRで語った場合、同じエピソードを志望動機でも活用しその経験が企業の理念や事業とどのようにつながるかを説明する、といった具合です。
②共通する自分の境遇を用いてつなげる
共通する自分の境遇を用いることも一貫性を持たせる上で効果的です。
自身の成長過程や人生経験を具体的に示し、その経験が志望企業への関心にどうつながったかを説明します。
例えば、家族の介護経験から福祉業界への志望理由を説明したり、幼少期の困難な経験が現在の仕事への意欲につながっていることを伝えたりすることで、自己PRと志望動機に一貫性を持たせられます。
③同じ活躍した経験を用いてつなげる
同じ活躍した経験を用いる方法も効果的です。大学でのプロジェクトなど、自分が成功を収めた経験を自己PRで語り、その経験で培った能力や学びを志望動機に活用します。
例えば、大学のゼミでプロジェクトリーダーを務め、チームをまとめて成功に導いた経験を自己PRで説明し、そのリーダーシップとチームワークのスキルを志望企業でどのように活かせるかを志望動機で語ります。
活躍に基づくことから入社後のイメージがしやすく、より説得力のあるアピールができる点でもメリットが大きいです。
【自己PR】志望動機の内容とつなげる例文3選

ここからは志望動機の内容とつなげる例文を3つ、実際に見ていきましょう。
全て例文と同じ流れで執筆する必要はありませんが、参考にしつつ執筆してみてください。
実際に自己PRを書き始められるように、カリクルは全力で就活生を応援しています。
まだ自己PRの作成ができていない方は自動生成ツールでサクッと、すでに自己PRができている人は赤ペンESという無料添削サービスで自己PRを添削してもらいましょう!
すべて「完全無料」で利用できますよ。
以下の記事でサービスの詳細を説明しているので、ちょっと添削依頼が気になっている方は読んでみてくださいね。
赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
【例文①】チャレンジ精神豊富
例文①
私は常に新しいことに挑戦することを恐れず、積極的にチャレンジする姿勢を持っています。
現在大学では栄養学の研究を行っており、これまで授業で習わなかった分野での実験を行う機会もあるため多くの失敗がありました。しかし、そのたびに原因を分析し、改善策を模索し、成果を出すことができました。この経験から、失敗は成功への第一歩であり、それを乗り越えることで成長できると、現在まで強く実感しております。
失敗経験から得られる学びは大きいため、積極的にチャレンジしていく姿勢が重要だと考えております。そのため、貴社の「失敗を恐れない」社風にも通ずると感じており、貴社への入社を強く希望しております。
貴社は私のチャレンジ精神をより一層高める場であると感じており、私のスキルを活かしつつ、貴社の企業発展に貢献したいと考えております。
志望動機で「失敗を恐れない社風に魅力を感じた」と伝えた場合、自己PRで「チャレンジ精神豊富」という特性を前面に出すことで、両者の一貫性や繋がりを明確に示せます。
自己PRでの「失敗を恐れずに挑戦する」経験や姿勢について執筆することで、志望動機における「失敗を恐れない社風」に共感する理由を補完しているのもポイントです。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
「エントリーシート(ES)が選考通過するか不安….ESを誰かに添削してほしい….」
そんな就活生の声に答えて、カリクル就活攻略メディアでは無料ES添削サービスである「赤ペンES」をおすすめしています。
第一志望である企業の選考に通過するためにも、まずは就活のプロにES添削を依頼してみましょう!LINE登録3分で満足が行くまで添削依頼ができますよ。
【例文②】主体的な行動力がある
例文②
私は日常の中でも主体的に行動することを心がけています。何事も自分ごととして捉え、後回しにしたり他人事で考えたりしないことが、自身を成長させると思います。
そう考えたきっかけは、飲食店のアルバイトでリーダーを経験した際に、アルバイトへのモチベーションが低かった仲間に積極的にコミュニケーションをとり、仲間のやる気が向上した経験です。やる気の向上は営業の活発化にもつながり、お客様にも良い影響を及ぼすことができました。
それ以降、常に主体的に行動し、周囲を巻き込むことを意識しています。私の常に主体的に行動する姿勢は、必ず貴社にも役立てられると感じ、志望いたしました。
自己PRの「主体的な行動力がある」を強調することで、その良い体験・経験をどのように行動に移し、実際に価値を生み出そうとするかを具体的に示すことができます。
これにより、単なる消費者から、「御社の一員として価値を共創できる」存在であると強調することが可能です。
主体性をアピールするポイントをもっと知りたい!という方は、ぜひこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
【例文③】分析能力が高い
例文③
私は一つの物事を分析する際、様々な情報を収集し、要因を戦略的に分析する能力に自信を持っています。
現在大学の授業で、不動産業界分析のプロジェクトをチームで担当した際、企業の戦略や業務形態を詳細に調査・分析したのですが、当初は分析の方法が全くわからず、周囲にも迷惑をかけました。しかし、周囲のサポートもあり、1から分析方法やリサーチ方法を学び、現在は大学のゼミにおいても卒業論文制作のリサーチを担当しています。
初めはうまくできなくても、分析の方法を学び実戦の現場においての活かし方が理解できました。また、本質的な部分まで分析できるようになり、数字を通してさまざまなことを分析できるようになりました。
貴社は戦略や業務形態のオリジナリティを重要視しており、他社との差別化を行い業界の第一線でご活躍されています。私の分析能力を活かしてその成長をサポートしたいと強く感じています。
分析能力が高いとアピールすることで、会社の戦略や業務形態を更に発展させるための分析と洞察を提供できると示唆しています。
自分のスキルが企業の戦略をより一層推進するための有効なツールであることを明確にでき、採用担当の方により強くアピールできるでしょう。
自己PRで分析能力をアピールするポイントはこちらの記事でも解説しています。
【志望動機】自己PRの内容とつなげる例文3選
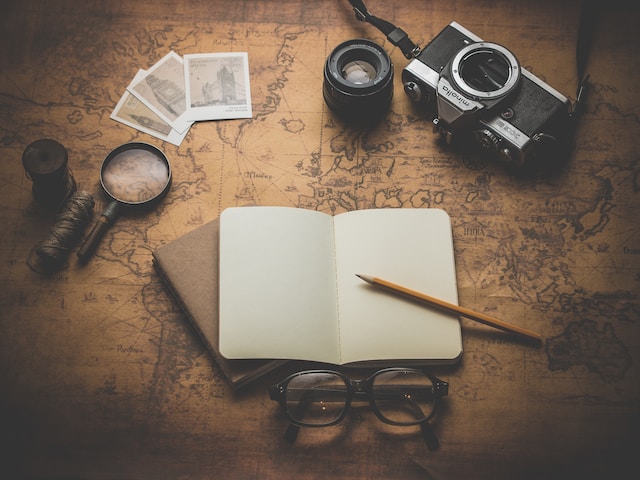
自己PRの書き方について学び、例文なども確認してきたところで、自己PRの内容とつなげる志望動機の例文についても確認していきましょう。
それぞれの要点を抑えることで、より質の高い志望動機を執筆できます。
そもそも志望動機がうまく作れない……と悩む人は、以下の自動生成ツールでサクッと作ってしまいましょう。まずはとっかかりを掴むことが重要ですよ。
逆に、既に志望動機がある人には「赤ペンES」がオススメ!現役の就活のプロが、今回の添削例文よりもさらに詳細な解説付きで、志望動機を無料添削しますよ。
また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。
無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介
【例文①】失敗を恐れない社風へ魅力を感じた
例文①
大学時代、私は新しいクラブの設立に取り組むことになったのですが、クラブの目的は、異なる専攻の学生が共同でプロジェクトを進めることで、多角的な視点を学ぶことでした。
初めは誰もが戸惑っており、多くの失敗を繰り返しましたが、失敗を通じて学び、それを次のアクションに活かすことで、最終的にはクラブは大学でも有数の人気クラブとなったのです。
このクラブ設立の経験から、失敗を恐れずにチャレンジを続けることが成長への近道であると痛感しております。
御社の「失敗を恐れない社風」はこの経験と深く共鳴すると感じており、挑戦を応援する社風の中で、自らのチャレンジ精神を最大限に発揮したいと強く感じました。
新しい取り組みや提案を通じて、会社の更なる成長に貢献していく所存です。
「失敗を恐れない社風へ魅力を感じた」という志望動機は、チャレンジを恐れずに新しいことに取り組むという自己PRの「チャレンジ精神豊富」と関連させています。
経験談を通じて、失敗を経験しながらもそれを乗り越え、結果を出せたというエピソードは、自らのチャレンジ精神を具体的に示すものとして強固になります。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
「エントリーシート(ES)が選考通過するか不安….ESを誰かに添削してほしい….」
そんな就活生の声に答えて、カリクル就活攻略メディアでは無料ES添削サービスである「赤ペンES」をおすすめしています。
第一志望である企業の選考に通過するためにも、まずは就活のプロにES添削を依頼してみましょう!LINE登録3分で満足が行くまで添削依頼ができますよ。
【例文②】商品・サービスで良い経験ができた
例文②
昨年、友人との旅行中に御社の商品に出会いました。当日、私たちは急な雨に見舞われ、旅行の計画が狂ってしまいました。
しかし、友人が御社のAI音声案内デバイスを持っていたことで、雨を避けるルートや室内で楽しめるアクティビティの提案を即座に受けることができ、最高の旅行となったのです。
この経験が私の「主体的な行動力」を強化するきっかけとなりました。その後、私は自らイベントの企画を立ち上げ、突発的なトラブルや変更にも柔軟に対応する能力の強化を目指しています。
私はこのような経験を活かし、主体的に動き、チャレンジすることで、より多くの人々に最高の体験を提供するため、商品やサービスの開発に取り組んでいく所存です。
「商品・サービスで良い経験ができた」という志望動機は、「主体的な行動力」という自己PRと関連しており、印象も良いでしょう。
「御社の商品を通じて得た良い経験が主体的な行動を起こすきっかけとなった」エピソードを通して志望動機を強固にしている点もポイントです。
【例文③】会社の戦略・業務形態へ魅力を感じた
例文③
私は大学時代にマーケティングの研究をしており、多くの企業の戦略や業務形態を分析してきました。
そして、御社の業務形態や中長期的な戦略が非常に独自であり、業界の変化を先取りする形での取り組みに強く魅力を感じています。
御社には学生の、就職を意識する前から注目しており、デジタルトランスフォーメーションを初めて導入した際はその動きを早い段階でキャッチし、どのように成功を収めたのかを研究しました。
私の「分析能力の高さ」を活かして、御社の戦略策定や業務形態の最適化に貢献したいと考えています。
私がこれまでに培ってきた分析のスキルセットを活かして、御社が目指す更なる成長や変革の過程で、新たな視点や改善の提案に役立てる所存です。
「会社の戦略・業務形態へ魅力を感じた」という志望動機は、「分析能力の高さ」という自己PRと密接に関連できています。
会社の魅力を正確に捉える能力をアピールすることで、自己PRが志望動機と綿密に結びついていることも示せており、採用担当の方に響くような例文でしょう。
自己PRと志望動機を作成する際の注意点

自己PRと志望動機を作成する際に、共通して注意すべきポイントがいくつか存在します。
両者を繋げて一貫性のある内容にするだけでなく、以下の点も気にすることで、より魅力的で伝わりやすい内容に仕上がるでしょう。
①企業が求める人材像にマッチするよう作成する
自己PRと志望動機を作成する際は、企業が求める人材像を徹底的に理解し、そのニーズに合わせて内容をカスタマイズすることが重要です。
先行突破のためには企業研究を通じて、求められるスキルや能力、企業の理念や文化を深く理解し、自分の強みとどのように合致するかを明確に示す必要があります。
例えば、チャレンジ精神を重視する企業であれば、新しい課題に挑戦した経験を自己PRと志望動機に戦略的に盛り込むことで、企業のニーズに応える人材であることをアピールできます。
②アピールしたいポイントを絞る
両者を通じて、アピールしたいポイントを1つに絞ることも重要です。複数の強みを詰め込もうとすると、焦点がぼやけてしまい、伝えたい内容が曖昧になってしまいます。
最も自分の特徴を端的に表現できる強みを選び、その強みがどのように培われ、志望企業でどのように活かせるかを明確に示しましょう。
「リーダーシップ」や「問題解決能力」など、1つの強みに焦点を当てそのスキルの具体的な成果と企業での貢献可能性を論理的に説明すると効果的です。
③数字を用いて具体的に伝える
内容を説明する際は数字を用いることで具体性と説得力が高まります。単なる抽象的な表現ではなく、定量的な成果を示すことで、自分の能力を明確にアピールできるためです。
プロジェクトでの成果や貢献は可能な限り数値化して伝えましょう。
例えば、「チームの売上を20%向上」「顧客満足度を15ポイント改善」「業務効率を30%改善」といった具体的な数字を用いることで、自分の実績と企業への貢献可能性を明確に示せます。
④可能な限り簡潔にまとめる
自己PRと志望動機を作成する際は、可能な限り簡潔にまとめることも重要です。冗長な表現を避け、要点を明確に伝えることで、面接官に強い印象を与えることができます。
具体的には、結論を先に簡潔に述べ、その後に具体的なエピソードや数字を用いて裏付けることで、説得力のある内容に仕上げることができます。
長々とした説明は避け、簡潔かつ力強い文章で自分の強みと志望理由を伝えることに注力しましょう。
自己PRと志望動機をつなげて一貫性のある回答をしよう
今回は自己PRと志望動機の違いや関連性を持たせることの重要性について解説しました。
しっかりと対策し、質の高い自己PRと志望動機を繋げることでより高い評価を受けられるので、本記事を参考に対策してくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。