【例文10選】「趣味」を自己PRのエピソードとして活用する方法|注意点も紹介
「自己PRで趣味を話していいのかな?」
就活の面接やエントリーシートで趣味を聞かれると、「雑談のきっかけかな?」と思う人も多いかもしれません。
しかし、実は趣味を通してあなたの人柄や強みを知ろうとしているケースが少なくありません。
例えば、読書が好きなら「探究心」や「集中力」、スポーツが趣味なら「継続力」や「協調性」といったように、趣味は自己PRにつながるのです。
本記事では、自己PRで趣味を効果的に伝える方法やメリット・デメリット、具体的な例文集までをわかりやすく解説します。自分の趣味を就活で強みに変えたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
企業が自己PRで趣味を質問する理由
就活の面接で趣味について聞かれると、雑談の一部と受け取ってしまう人も少なくありません。ですが企業がこの質問をする背景には、採用に関わる重要な意図があります。
ここではその理由を理解し、回答の質を高めるヒントを得てください。
- 人柄や価値観を知るため
- 仕事との適性を判断するため
- 継続力や熱中度を確認するため
- 面接の場を和ませるため
①人柄や価値観を知るため
企業が趣味を聞く大きな目的の1つは、応募者の人柄や価値観を知ることです。履歴書やエントリーシートでは伝わりにくい部分も、趣味を通してその人の考え方や行動パターンが見えてきます。
例えばアウトドア好きは活動的で社交的な印象を与えやすく、読書好きは落ち着きや分析力を感じさせるでしょう。面接官はこうした情報を参考に、自社の社風や配属先の雰囲気に合うかを判断します。
答える際は趣味の名前だけでなく、その魅力や取り組み方、どのような気持ちで続けているかまで具体的に話してください。
さらに、その趣味から得られた価値観や姿勢を、大学生活や他の活動にもどう活かしているかを説明すると説得力が増します。
背景やエピソードを交えて語れば、応募者の人物像がより鮮明になり、記憶に残る自己PRになるでしょう。
②仕事との適性を判断するため
趣味は余暇の過ごし方にとどまらず、仕事との相性を測る重要な材料にもなります。
例えばチームスポーツで培った協調性やリーダーシップ、個人競技や創作活動で身につけた集中力や自己管理能力などは、職種や業務内容と直結する強みです。
企業はこれらをヒントに、職場のチーム構成やプロジェクトの進め方とのマッチ度を判断します。面接では、趣味と業務内容を関連付ける意識が必要でしょう。
直接つながらない趣味でも、そこで得た経験や工夫、成果を業務にどう応用できるかを示せば高評価が期待できます。
例えば登山を趣味にしている場合、「計画立案」「体力管理」「リスクへの備え」といった要素を業務姿勢に重ねられるはずです。趣味の魅力だけでなく、そこから導かれる適性を意識的に表現してください。
③継続力や熱中度を確認するため
企業は趣味を通して、応募者がどの程度の期間、熱意を持って物事に取り組めるかを見極めます。継続的な努力や地道な積み重ねの経験は、業務においても不可欠な資質です。
数年間続けている音楽やスポーツ、資格取得に向けた学習などは、忍耐力や計画性を証明する要素になります。
一方で、短期間でやめてしまう活動ばかりだと、責任感や粘り強さに不安を持たれる可能性があるでしょう。
面接では、続ける中で直面した課題や、それを乗り越えるために工夫したこと、成長を実感できた瞬間を具体的に伝えてください。
単なる楽しみではなく、努力と成長の証として趣味を提示できれば、大きなアピールポイントになるはずです。
④面接の場を和ませるため
面接は緊張感が高まり、普段の自分を出しづらくなる場です。そこで企業は、趣味という話しやすいテーマで場を和ませ、自然な受け答えを引き出そうとします。
リラックスした状態では、表情や話し方、姿勢などが自然に表れ、人物像をより正確に把握しやすくなります。この場面で大切なのは、趣味の話に明るさや熱意を込めることです。
そうすることで、面接官に安心感や好印象を与えられるでしょう。反対に、答えが短く淡々としていると、かえって距離を感じさせてしまいます。
趣味にまつわる面白い体験や、そこから得た気づきを交えて話せば、会話が弾みやすくなります。
日常的に趣味について人に説明する練習をしておくと、本番でも自然に話せるようになり、面接全体の雰囲気をより良くできます。
自己PRで趣味をアピールするメリット

自己PRに趣味を盛り込むことは、単なる話題提供ではなく、面接官に人柄や強みを自然に印象づける有効な方法です。
限られた時間で個性を伝える場面では、趣味という身近なテーマが共感や興味を引きやすいでしょう。ここでは、趣味をアピールする具体的なメリットを4つに分けて解説します。
- 強みと人柄を同時に伝えられる
- 印象に残りやすい
- 会話のきっかけを作りやすい
- 他の応募者との差別化ができる
①強みと人柄を同時に伝えられる
面接で趣味を話す大きな利点は、スキルと人柄を一度に示せることです。例えば、登山が趣味なら「計画性」や「忍耐力」、さらに自然を大切にする価値観まで伝わります。
資格や実績では表せない部分を、具体的なエピソードを通して知ってもらえるのが魅力でしょう。自己PRでは「結論→理由→具体例→まとめ」の流れで話すと理解されやすくなります。
たとえば「私は計画性を大切にしています。その背景には登山という趣味があります。出発前には天候や装備を調べ、仲間との役割分担を行います。
この経験から計画を立てて物事を進める力が身につきました」という構成です。
さらに「登山では急な天候の変化に対応するため、柔軟な判断も必要でした」と付け加えれば、臨機応変な対応力も同時に伝えられます。このように、趣味は複数の強みを自然に盛り込むきっかけになります。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方は強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自身を持って臨めるようになりますよ。
②印象に残りやすい
趣味は自己紹介の中でも記憶に残りやすい要素です。面接官は多くの応募者と会うため、履歴書や志望動機だけでは差がつきにくい場面もあります。
そこで、独自性のある趣味や具体的なエピソードを交えると、面接後に名前と一緒に思い出してもらえる可能性が高まります。
例えば「趣味は和太鼓演奏です」と言えば、音や動きのイメージが浮かび、単なる「音楽が好き」よりも印象が強まります。
さらに「地域の祭りで演奏経験があり、仲間と一体感を味わうのが好きです」と加えれば、人柄や協調性も印象づけられます。
ただし奇抜さを狙いすぎると誤解を招くおそれがあるため、企業や職種の雰囲気に合った内容を選んでください。趣味は覚えてもらうためのラベルであり、同時に信頼感や安心感を与える材料にもなります。
③会話のきっかけを作りやすい
趣味は面接で自然な会話を生みやすい話題です。緊張しやすい就活生でも、得意分野の話になると表情や声が柔らかくなります。
例えば「カメラが趣味です」と答えると、「どんな被写体を撮りますか?」や「最近撮った中でお気に入りはありますか?」といった質問が返ってくることがあります。
こうしたやり取りは一方的な質疑応答から双方向の会話に変わり、雰囲気が和らぎます。また、趣味に関する話は感情が伴いやすいため、相手に熱意や生き生きとした印象を与えることができます。
さらに「写真展に出品した経験があり、他の参加者との交流から刺激を受けました」といった具体的なエピソードを交えると、学びや人間関係の広がりまで示せます。
趣味は緊張をほぐしながら、自分の魅力を引き出す有効なきっかけになるでしょう。
④他の応募者との差別化ができる
自己PRに趣味を加えることで、他の応募者との差別化が可能です。学歴や経験が似ている人が多い中で、趣味にまつわるエピソードは独自性を生みます。
これは、選考の中であなたを特別な存在として記憶に残す手助けになります。
例えば「マラソンが趣味」と伝えるだけでは弱いですが、「3年間で10回以上大会に出場し、自己ベストを更新してきました」と話せば、継続力や努力する姿勢が伝わります。
さらに「練習を通じて自己管理能力や目標達成への計画性を磨きました」と付け加えれば、職場での活躍が想像しやすくなるでしょう。
差別化には、珍しさだけではなく、趣味を通して得た具体的な成果や成長を語ることが重要です。これにより、同じ趣味を持つ人とも異なる印象を与えられます。
自己PRで趣味を伝える際のデメリット

就活で趣味を自己PRに盛り込むことは、一見すると人柄を伝える有効な手段に思えます。しかし、伝え方を誤ると評価を下げる原因にもなります。
趣味は価値観や性格を示す材料になる反面、業務で求められるスキルや成果とのつながりが弱く見える場合があるためです。
ここでは、自己PRで趣味を話すときに注意すべき3つのデメリットを詳しく解説します。理解しておけば、面接官の意図を踏まえて自分の強みを効果的に伝えられるでしょう。
- 好きなことだから頑張れたと思われる可能性がある
- スキルや成果が伝わりにくい場合がある
- 業務内容と直接関係がないと評価されるリスクがある
①好きなことだから頑張れたと思われる可能性がある
趣味を自己PRで語るとき、多くの就活生が「好きだから頑張れた」という印象で終わってしまいがちです。面接官は、あなたが業務の中でどのように努力し、結果を出せるかに注目しています。
そのため、好きなことだから続けられたという理由だけでは、ビジネス環境で同じ成果を再現できるのか疑問を持たれる可能性があります。
この印象を払拭するには、趣味を通じて身につけた具体的な能力や行動パターンを示すことが不可欠です。
単なる情熱ではなく、業務にも応用できるスキルとして結びつけることが、面接官の評価を高める鍵です。
②スキルや成果が伝わりにくい場合がある
趣味を自己PRに使う場合、客観的な評価が難しく、印象がぼやけてしまうことがあります。面接官は具体的な成果や数字など、判断材料となる情報を求めています。
例えば「旅行が好き」とだけ伝えても、その中で発揮した計画力や情報収集力、予期せぬトラブルへの柔軟な対応などを説明しなければ、単なる娯楽にしか聞こえません。
この問題を避けるには、成果や変化が明確なエピソードを用意することが重要です。資格取得、コンテストでの入賞、長期プロジェクトの達成など、事実として裏付けられる内容を盛り込みましょう。
さらに、その経験を業務場面に置き換えて話すことで、即戦力としての可能性を感じてもらえます。
例えば、登山が趣味であれば、綿密な事前計画や予測不能な事態への対応力をプロジェクト管理に生かせると説明できます。
こうした具体的な成果の提示により、面接官はあなたの能力を正確にイメージできるようになるでしょう。
③業務内容と直接関係がないと評価されるリスクがある
趣味を自己PRに取り入れる際、応募職種や企業の業務内容と結びつきが弱いと「なぜこの話をしているのか」と疑問を持たれる可能性があります。
職務に直結しない場合でも、関連性を見いだし、効果的に橋渡しをする工夫が必要です。例えば料理が趣味の場合でも、レシピ開発を通じた創造力や改善力を企画職や商品開発職のスキルと関連づけられます。
写真撮影であれば、被写体の魅力を最大限に引き出す構図や光の調整力をマーケティングやデザイン業務に応用できるでしょう。
こうして、趣味が単なる余暇活動ではなく、業務遂行に役立つ能力の一部として位置づけられます。また、企業研究を行い、業務との接点を事前に見つけておくと、説得力が格段に高まります。
面接官は常に「会社にどう貢献できるか」という視点で見ているため、趣味のエピソードもその観点から整理して話すことが評価向上のポイントです。
自己PRで趣味をアピールする3つのコツ

自己PRに趣味を盛り込むと、面接官に人柄や価値観を伝えられます。しかし、好きなことを述べるだけでは効果が弱まります。大事なのは、趣味と自分の強みをどう結びつけ、納得感を与えるかです。
ここでは、就活生が意識すべき3つのコツを紹介します。押さえておけば、趣味があなたの魅力をより引き立てるでしょう。
- 自分の強みに直結する趣味を選ぶ
- 趣味の背景や取り組み方を具体的に説明する
- 趣味で得た力を仕事に活かす方法を示す
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①自分の強みに直結する趣味を選ぶ
自己PRで趣味を効果的に伝えるには、自分の強みと結びつく趣味を選ぶことが欠かせません。例えば、協調性を示したいならチームスポーツ、集中力を強調するなら読書やプログラミングなどが適しています。
趣味と強みが一致すれば、面接官は「この特性は職場でも役立つだろう」と自然に想像できます。反対に、単なる娯楽としての趣味は評価につながりにくいでしょう。
選定の際は、「この趣味から何を学び、どんな力を伸ばしてきたか」を掘り下げることが重要です。さらに、自分の強みを裏付けるエピソードや成果を具体的に示すことで説得力が増します。
たとえば部活動での役割やコンテスト入賞など、数字や成果を絡めれば印象が鮮明になります。自分らしさを活かせる趣味を選び、経験と実績を交えて語ることが、面接での好印象につながるでしょう。
②趣味の背景や取り組み方を具体的に説明する
趣味を自己PRに使う際、「〇〇が趣味です」とだけ伝える人は少なくありませんが、それでは熱意や独自性が十分に伝わりません。
大切なのは、始めたきっかけや続けている理由、日々の取り組み方を詳しく述べることです。
例えば「読書が趣味です」よりも、「毎日30分以上の読書を5年間続け、要約ノートを作って知識を整理する習慣を身につけました」とすれば、継続力や自己管理能力が伝わります。
さらに、どのような分野の本を選び、そこから何を学んだのかまで触れると、人物像がより立体的になります。背景や工夫を話すことで、単なる娯楽ではなく、努力や成長のプロセスを示せます。
加えて、その習慣が自分に与えた影響や考え方の変化も盛り込めば、面接官の印象に深く残る自己PRになるでしょう。
③趣味で得た力を仕事に活かす方法を示す
趣味を自己PRに取り入れる最終的な目的は、それが仕事にどう結びつくかを明確にすることです。
例えば写真撮影が趣味なら、「被写体の魅力を引き出すために構図や光を工夫し、その過程で磨かれた観察力や創造性をマーケティング業務での顧客分析や企画立案に活かせます」と具体的に伝えられます。
このように、趣味で培ったスキルと職務内容を橋渡しする説明が必要です。面接官は「この人は趣味を通じて実践的な力を身につけている」と感じやすくなります。
さらに、仕事でその力をどう応用するか、未来の行動イメージまで描けると説得力は格段に高まります。
たとえば「旅行で得た計画力を、営業活動での訪問スケジュール管理に活かしたい」といった具体例は効果的です。
趣味を単なる楽しみで終わらせず、成果と応用例を結びつけて語ることが成功の鍵となるでしょう。
自己PRで趣味をテーマにする際の注意点

就活で自己PRに趣味を使うときは、伝え方によって印象が大きく変わります。趣味は人柄や価値観を示す良い材料ですが、選び方や話し方を誤れば評価が下がることもあります。
ここでは、企業が重視するポイントを踏まえた注意点を4つ紹介します。
- 企業にマイナス印象を与える趣味は避ける
- 説明を簡潔にまとめる
- 事実に基づいて話す
- 「趣味はない」とは答えない
①企業にマイナス印象を与える趣味は避ける
採用担当者は趣味を通じて応募者の価値観や生活習慣を見ています。過度にギャンブル性が高いものや危険な行為、反社会的な活動などは避けましょう。
企業は長期的に安心して働ける人材を求めているため、リスクを感じさせる趣味は懸念の対象になりやすいです。
例えば「オンラインカジノ」や「過激なSNS配信」は、印象を悪くするだけでなく、企業のコンプライアンス意識とも合わない可能性があります。
また、あまりに内向的すぎる趣味や、協調性が見えない趣味も注意が必要です。たとえ個人的には健全でも、説明が不足すれば誤解を招く恐れがあります。
もし趣味が誤解されやすい場合は、取り組む理由や得られた学びを具体的に伝え、相手が安心できる背景を添えると良いでしょう。
安全性や社会的評価の高い趣味を選ぶことで、自己PR全体の印象も安定します。
②説明を簡潔にまとめる
趣味の話は、詳細に語りすぎると焦点がぼやけます。自己PRは限られた時間で自分の魅力を伝える場なので、趣味の概要とそこから得た強みを短くまとめることが大切です。
例えば「週末にマラソンを続けており、自己管理能力と継続力が身につきました」というように、一文で趣味と強みをつなげると効果的でしょう。
背景やエピソードは必要な部分だけにとどめ、聞き手の興味を引くきっかけにしてください。さらに、説明の流れを「趣味の概要→きっかけ→学んだこと」という順に整理すると、自然で理解しやすくなります。
面接官は限られた時間で多くの応募者と会うため、端的な表現は高く評価されます。聞き手が頭の中で映像としてイメージできるような説明にすると、印象に残りやすいでしょう。
③事実に基づいて話す
趣味を盛って話したくなることはありますが、事実とかけ離れた内容は面接時に矛盾を生み、信頼を損ねます。面接官は深掘り質問で真実性を確認するため、具体的な経験や成果をもとに話しましょう。
例えば「料理が趣味」と言うなら、頻度や得意料理、挑戦したエピソードなど事実に裏付けられた情報を交えると説得力が増します。
また、実際のエピソードには自分の行動や感情を盛り込み、話に臨場感を与えることが大切です。数字や期間を交えると信ぴょう性も高まります。
さらに、事実を伝える姿勢は「誠実さ」という評価にも直結します。企業はスキルだけでなく人間性も重視しているため、誠実な回答は信頼関係の構築につながります。
事実に基づいた自己PRは、面接全体の一貫性を保ち、安心感を与える要素にもなるでしょう。
④「趣味はない」とは答えない
面接で「趣味はありません」と答えると、会話が広がらず自己開示に消極的な印象を与えてしまいます。特別な趣味がなくても、日常で行っていることや興味のある活動を工夫して伝えてください。
例えば「最近は読書アプリでビジネス書を週に1冊読んでいます」や「友人と週末にカフェ巡りをしています」など、身近な行動でも構いません。
その活動を通して得た学びや性格面の強みを結び付けることが重要です。また、まだ趣味と呼べるほどの経験がなくても「興味を持って取り組み始めたこと」を前向きに紹介すれば、成長意欲を示せます。
趣味は特技レベルである必要はなく、人柄を知ってもらうきっかけになります。何もないと答えるより、小さな習慣をポジティブに表現したほうが印象は格段に良くなるでしょう。
趣味別|自己PRで示せる強み

就活の自己PRで趣味を話すときは、その趣味から得られる強みを具体的に示すことが重要です。趣味は単なる余暇活動ではなく、性格や価値観、行動特性を映す要素といえるでしょう。
企業はその情報から、仕事への適性や職場での立ち回り方を想像します。ここでは趣味の種類ごとに、アピールできる代表的な強みを整理します。
- 家で過ごす系の趣味:集中力や創造力
- 外で活動する系の趣味:情報収集力や発見力
- 身体を動かす系の趣味:忍耐力や課題解決力
- 仲間と楽しむ系の趣味:協調性や計画力
- 自己成長を促す趣味:学習意欲や探究心
①家で過ごす系の趣味:集中力や創造力
家で過ごす趣味は、一見インドアな印象ですが、集中力や創造力を示す好材料になります。読書や絵画、プログラミングなどは、長時間1つの対象に向き合える姿勢をアピールできるでしょう。
企業はこの特性を、地道な作業や分析業務を着実にこなす力として評価します。さらに、集中力は精度や正確性が求められる場面で大きな強みとなります。
また、創作活動であれば独自の発想やアイデアの組み立て方を具体的に話すことで、提案型の仕事にも適性があると伝えられます。
創造力は、課題に対する新しい解決方法を生み出す力にもつながるため、単なる趣味の枠を超えて評価されやすいでしょう。
ただし、自分の世界にこもる印象にならないよう、学んだことを人や仕事にどう活かすかも一緒に説明してください。作品や成果物、改善の工夫など具体例を交えると、聞き手に鮮明な印象を与えられます。
②外で活動する系の趣味:情報収集力や発見力
外で活動する趣味は、行動力と好奇心を裏づけるエピソードが豊富です。旅行やカフェ巡り、街歩きなどは、新しい場所や人との出会いを通して情報収集力や発見力を磨けます。
この特性は、顧客ニーズの変化を素早く捉えたり、新しい市場を見つけ出す場面で役立つでしょう。
自己PRでは、単に行動範囲が広いことを述べるのではなく、現場で得た情報や体験をどう分析し、活用したかまで触れることが重要です。
例えば旅行で得た文化的な知識をプレゼンに反映させた経験や、イベント情報を集めて企画の質を高めた事例などが有効です。
柔軟な発想や迅速な判断力は、変化が激しい環境での適応力として企業から高く評価されます。行動のきっかけや選択理由も添えることで、主体性や戦略的な行動力が強く伝わるでしょう。
③身体を動かす系の趣味:忍耐力や課題解決力
身体を動かす趣味は、体力や健康面のメリットに加えて、精神的な粘り強さや課題解決力を示せます。
ランニングや登山、スポーツ競技などは、明確な目標を立てて継続的に努力する姿勢を自然に表現できるでしょう。これは、困難な状況でも最後までやり遂げる人材としての評価につながります。
また、スポーツには改善のための振り返りが欠かせません。練習や試合で得た反省点を分析し、次回に活かす行動はPDCAサイクルを体現しているといえます。
チーム競技であれば、仲間との連携や役割分担の経験も補足することで、協調性や状況判断力も同時にアピールできます。
さらに、課題を乗り越えるために考えた工夫や方法論を盛り込めば、問題解決型の人材として印象づけられるでしょう。
④仲間と楽しむ系の趣味:協調性や計画力
仲間と一緒に行う趣味は、協調性や計画力を裏づける具体的な事例が多くあります。
バンド活動やボードゲーム、サークルイベントの企画運営などは、他者との関係づくりや役割分担を自然に経験できる場です。
企業は、この特性をチームで成果を出すための調整力やコミュニケーション力として評価します。
自己PRでは、仲間と意見をすり合わせながら進めたプロジェクトや、スケジュール管理で成果を上げた経験などを盛り込むと効果的です。
特に、計画段階から課題を想定し、それに備える取り組みを行った事例は、実務でも役立つ力として高く評価されるでしょう。
また、衝突や意見の違いを解消した経験を交えることで、柔軟性や冷静な判断力も同時に伝えられます。
⑤自己成長を促す趣味:学習意欲や探究心
自己成長につながる趣味は、学習意欲や探究心を示すうえで非常に有効です。語学学習や資格取得、専門分野の研究などは、自分で課題を設定し、継続して取り組む姿勢を裏づけます。
こうした姿勢は、新しい技術や知識が求められる現場で特に重宝されるでしょう。自己PRでは、学びのきっかけと成果、その知識やスキルをどのように実務や生活に活かしているかを明確にしてください。
例えば、資格勉強で培った計画性や効率的な学習法をプロジェクト管理に応用した事例などは説得力があります。
さらに、難易度の高い課題に挑戦した経緯やモチベーション維持の工夫を加えることで、粘り強さや自主性も同時にアピールできます。
単なる勉強好きではなく、成果を出すための行動力を持つ人材だと印象づけましょう。
自己PR用の趣味が見つからないときの対処法
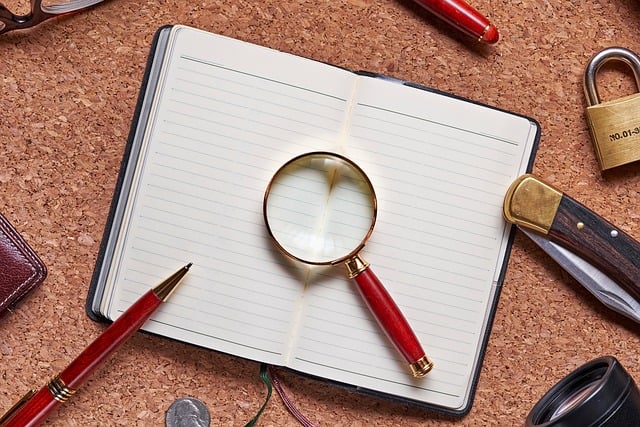
就活の自己PRで趣味を聞かれたときに答えられないと、会話のきっかけを逃してしまうでしょう。しかし、趣味は特別な活動でなくても問題ありません。
日常を見直せば、自分らしさを表す趣味は必ず見つかります。ここでは、趣味が思い浮かばないときの具体的な見つけ方を紹介します。
- 休日の過ごし方を振り返る
- 最近楽しかった出来事を思い出す
- 家族や友人に聞いてみる
- 自分史やモチベーショングラフを作成する
①休日の過ごし方を振り返る
趣味探しの出発点は、自分の休日をどう過ごしているかを丁寧に振り返ることです。企業は趣味を通して、あなたの価値観やストレス解消法、日常の優先順位を知りたいと考えます。
そのため、特別なスキルや珍しい活動でなくても、日々の過ごし方から十分にアピールできます。たとえば、散歩やカフェ巡り、映画鑑賞、読書なども立派な趣味です。
重要なのは、その活動から得られる気づきや、続けている理由を説明できることです。さらに、休日の行動を振り返るときは、1日だけでなく数週間単位で見直すと、自分の行動の傾向がより明確になります。
スマホのメモやカレンダーを確認すれば、無意識に繰り返している習慣や好きなことが浮かび上がるでしょう。それを趣味として整理すれば、自然で説得力のある自己PRにつながります。
②最近楽しかった出来事を思い出す
直近で楽しいと感じた出来事を思い出すことは、自分の興味や情熱の方向性を知る有効な方法です。楽しかった理由を掘り下げると、自己PRで使える行動特性や強みがはっきりします。
例えば、友人とスポーツ観戦をして盛り上がったなら、チームワークや熱中力をアピールできるでしょう。初めて訪れたカフェで感動したなら、新しいことに挑戦する柔軟性や好奇心を示せます。
ここで大切なのは、出来事そのものよりも、その背景や感情の変化を言葉にすることです。また、複数の出来事を思い返し、その共通点を探すと、自分の興味分野や価値観の軸が見えてきます。
こうして整理した体験は、単なる「趣味」の枠を超えて、自分を語るストーリーとして魅力的に伝えられるはずです。
③家族や友人に聞いてみる
自分では気づいていない趣味や強みは、身近な人の意見で明らかになることが多いです。家族や友人は、あなたの日常の行動や会話の中から、無意識に続けている活動や特徴を見抜いています。
例えば、「いつも写真を撮っているね」と言われたら、それは立派な趣味の候補になります。第三者の視点は、自分の思い込みを取り払い、意外な自己PRの材料を発見するきっかけになります。
また、人に聞くことで、自分がなぜそれをしているのかを改めて考える機会にもつながります。もし意見が複数寄せられた場合、その共通点を見つけると、あなたの強みや興味がよりはっきりするでしょう。
普段の会話や行動に隠れている習慣も、評価の視点を得ることで自信を持って話せるようになります。
④自分史やモチベーショングラフを作成する
長期的な視点で自分の人生を振り返ると、趣味の原点や一貫して関心を持ってきた分野が見えてきます。
自分史やモチベーショングラフを作ることで、過去に夢中になったことや感動した瞬間を整理でき、そこから趣味のヒントを得られます。この作業は趣味探しに役立つだけでなく、自己PRや志望動機の一貫性を高める効果もあります。
例えば、小学生の頃から工作が好きで、美術の課題に積極的だった経験があるなら、創造力や計画力の強みとして語れます。
さらに、過去の出来事を並べていくと、ある特定の分野や行動パターンが繰り返し出てくることがあります。それを趣味や興味として再定義し、過去から現在へと続くストーリーとして企業に伝えれば、印象に残る自己紹介になるでしょう。
趣味を活かした自己PR例文集

趣味を自己PRに活かすと、あなたの人柄や強みが具体的に伝わりやすくなります。
ここでは、さまざまな趣味を題材にした自己PR例文を紹介します。興味や経験に近いものを参考にし、自分らしいアピールポイントを見つけてみましょう。
実際に自己PRを書き始められるように、カリクルは全力で就活生を応援しています。
まだ自己PRの作成ができていない方は自動生成ツールでサクッと、すでに自己PRができている人は赤ペンESという無料添削サービスで自己PRを添削してもらいましょう!
すべて「完全無料」で利用できますよ。
また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。
無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介
①登山
登山を趣味としている人は、体力や忍耐力、計画性を自己PRでアピールしやすいです。大学生であれば、仲間との登山や部活動での経験を交えて話すと、より人柄が伝わります。
| 私は大学1年生の頃から友人と登山を続けています。最初は体力的にも不安でしたが、事前にルートや天気を調べ、必要な装備を整えることで無事に登頂できた達成感を何度も味わいました。 特に、3年生の夏に挑戦した富士山登山では、悪天候に備えて複数の計画を立て、仲間と連携しながら安全に行動しました。 この経験を通じて、困難な状況でも冷静に判断し、粘り強く取り組む姿勢を身につけました。今後もこの姿勢を活かし、与えられた課題に最後まで取り組んでいきたいと考えています。 |
登山の例文では「計画性」「チームワーク」「忍耐力」を具体的なエピソードで示すことが大切です。数字や具体的な行動を入れると、信頼性と説得力が高まります。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
②ランニング
ランニングは、継続力や自己管理能力をアピールできる趣味です。日々の練習や大会への参加経験を盛り込むと、努力の積み重ねが伝わります。
| 私は大学入学を機にランニングを始め、週に3回のペースで継続しています。最初は数キロで息が上がっていましたが、練習を重ねるうちに10キロを無理なく走れるようになりました。 昨年は友人とハーフマラソンに挑戦し、計画的な練習と体調管理の大切さを学びました。走る時間を確保するために生活リズムを整えた結果、学業面でも集中力が高まりました。 今後もこの継続力と自己管理の姿勢を活かし、与えられた課題に粘り強く取り組みたいと考えています。 |
ランニングでは「継続力」「自己管理能力」を数字や期間とともに示すと説得力が増します。大会や目標達成の経験を入れると効果的です。
③読書
読書は、知識の幅や思考力を示せる趣味です。ジャンルや読書量を具体的に述べることで、自分らしい学びの姿勢が伝わります。
| 私は小説やビジネス書など幅広いジャンルの本を読むことを習慣にしています。大学入学後は年間50冊を目標にし、通学時間や空き時間を読書に充てています。 特に、行動心理学の本からは、人との接し方やプレゼンでの工夫を学び、ゼミの発表にも活かせました。 読書を通じて得た知識は、自分の考えを深めるだけでなく、多様な視点を持つきっかけになっています。これからも学びを行動に結びつけ、成長し続けたいと考えています。 |
読書の例文では「冊数」「ジャンル」「得られた学び」を明示しましょう。学びを実践に結びつけた経験を入れると印象が強まります。
④旅行
旅行は行動力や柔軟性、計画力を示せる趣味です。訪れた場所や経験した出来事を具体的に挙げると臨場感が増します。
| 私は大学生活の中で国内外への旅行を積極的に行ってきました。友人と計画した北海道旅行では、移動や宿泊、観光ルートを自分たちで調整し、限られた時間で効率的に回ることができました。 現地での急な天候変化にも柔軟に対応し、全員が満足できる旅になりました。旅行を通じて、事前準備の重要性と予期せぬ事態への冷静な対応力を身につけました。 この経験は、今後のチーム活動や仕事にも活かせると考えています。 |
旅行の例文では「計画力」と「柔軟性」を具体的な出来事で示すことがポイントです。場所や出来事を入れると印象が鮮明になります。
⑤映画鑑賞
映画鑑賞は感受性や発想力、分析力を示せる趣味です。作品選びの理由や感想を交えると人柄が伝わります。
| 私は週末に映画を鑑賞することを習慣にしています。ジャンルを問わず観ますが、特に社会問題をテーマにした作品から多くの気づきを得ています。 昨年観たドキュメンタリー映画では、異文化や価値観の違いについて深く考えさせられ、その内容をゼミのディスカッションで共有しました。 映画を通じて得た多様な視点は、自分の考えを広げるきっかけとなり、柔軟な発想や他者理解につながっています。 |
映画鑑賞では「テーマ」「感想」「得られた視点」を具体的に書くと良いです。感想を行動や発言に結びつけると説得力が高まります。
⑥料理
料理は計画性や工夫する力、集中力を示せる趣味です。調理のきっかけやエピソードを交えると親しみやすさが出ます。
| 私は一人暮らしを始めた大学1年生の頃から料理を続けています。最初は簡単なレシピから始めましたが、食材や調味料の組み合わせを工夫し、徐々にレパートリーを増やしました。 友人を招いて手料理を振る舞った際には、「美味しい」と言ってもらえたことが自信につながりました。料理を通じて、計画的に準備し、丁寧に作業を進める姿勢を身につけることができました。 |
料理の例文では「きっかけ」「工夫」「結果」を具体的に示しましょう。人との交流エピソードを入れると温かみが増します。
⑦絵画
絵画は創造力や集中力を示せる趣味です。作品作りの過程や発表経験を入れると印象が強まります。
| 私は幼い頃から絵を描くことが好きで、大学でも趣味として続けています。特に水彩画に魅力を感じ、休日に風景画を描くことが多いです。 昨年は学園祭の展示に参加し、多くの人に作品を見てもらえたことが励みになりました。絵を描く過程で集中力や観察力が磨かれ、物事をじっくりと見極める姿勢を身につけました。 |
絵画では「制作の過程」や「発表経験」を入れると説得力が増します。ジャンルや技法を明示すると個性が際立ちます。
⑧タイピング
タイピングは効率性や努力の積み重ねを示せる趣味です。練習の工夫や成果を具体的に入れるとわかりやすいです。
| 私は大学のレポート作成をきっかけにタイピング練習を始めました。毎日15分間の練習を続けた結果、1分間に100文字以上入力できるようになりました。 授業中のメモや課題提出もスムーズになり、時間の有効活用につながっています。小さな努力を継続することで、確かな成果が得られることを実感しました。 |
タイピングの例文では「練習方法」「成果」を数字で示すと説得力が増します。学業や日常での活用例を入れると効果的です。
⑨早起き
早起きは自己管理能力や規律性を示せる趣味・習慣です。生活改善や成果につながった経験を書くと好印象です。
| 私は大学2年生の春から早起きを習慣にしています。毎朝6時に起き、1日の計画を立ててから授業や課題に取り組むようにしました。 その結果、時間に余裕が生まれ、課題提出の遅れがなくなりました。朝の時間を有効に使うことで、勉強だけでなく趣味の時間も確保でき、生活全体が充実しました。 |
早起きでは「時間」「習慣化の経緯」「得られた成果」を具体的に書きましょう。生活全体への効果を入れると印象が良くなります。
⑩音楽鑑賞
音楽鑑賞は感受性やリラックス方法を示せる趣味です。好きなジャンルや活用場面を交えると個性が出ます。
| 私は日々の生活の中で音楽鑑賞を楽しんでいます。特にジャズやクラシックを聴くと、心が落ち着き集中力が高まります。試験前には静かな曲を選び、落ち着いて勉強できる環境を作っています。 音楽を通じて気持ちを切り替える習慣は、日常のストレスを軽減し、前向きな姿勢を保つ助けになっています。 |
音楽鑑賞では「ジャンル」「活用場面」「効果」を明確に書くと良いです。感情や行動の変化を具体的に示すと説得力が増します。
趣味を自己PRに活かす鍵を握ろう!
自己PRで趣味をテーマにすることは、人柄や価値観を伝え、企業との適性を示す有効な手段です。特に、強みと人柄を同時にアピールでき、会話のきっかけにもなります。
一方で、業務と関係が薄い場合や成果が伝わりにくいリスクもあるため、趣味選びと説明方法が重要です。具体的には、自分の強みに直結する趣味を選び、その背景や取り組み方を明確に伝えましょう。
さらに、趣味で得た力を仕事にどう活かせるかを示すことで説得力が増します。企業にマイナス印象を与える内容は避け、事実に基づく簡潔な説明を心がけることが成功のポイントです。
趣味が見つからない場合も、日常を振り返ることで新たなアピール材料を発見できます。戦略的に趣味を活用することで、印象深い自己PRを実現できます。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。










