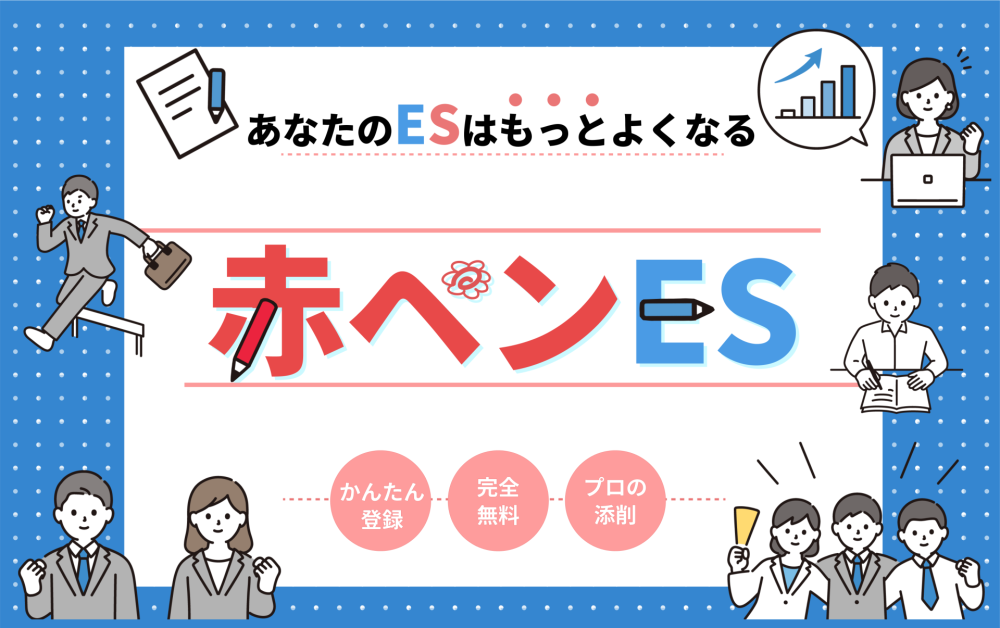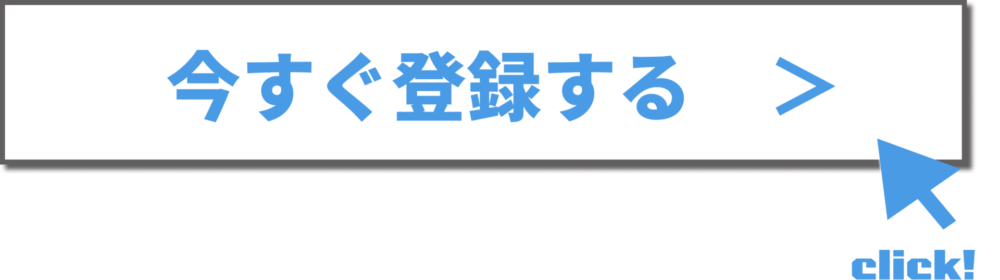エントリーシートの語尾はですます・であるどっちがいい?注意点も紹介
エントリーシートは、就活生の経歴や資格といった基本情報の他に、文章を通してその人の性格や内面を知る目的があります。正しく綺麗な言葉を使うようにしたいですが、そもそも語尾は「ですます調」と「である調」のどちらが良いのでしょうか。
今回はエントリーシートのですます調とである調それぞれのメリット、また注意点を紹介していきます。
全て無料!ES作成に役立つツール
★ES自動作成ツール
AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
★志望動機テンプレシート
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機をカンタンに作成できる
★自己PR作成ツール
最短3分で、受かる自己PRを作成できる
エントリーシートの口調は「ですます」と「である」どちらでもいい
エントリーシートは「ですます調」と「である調」のどちらでも問題ありません。基本的に企業側から指定されることは無いので、どちらを選ぶかは就活生の自由です。
ただいずれにしても、エントリーシート全体で語尾は統一しなければいけません。1つのエントリーシート内で文章によって語尾が違うと、でたらめで適当な印象を与えてしまいます。
ただあくまでエントリーシートはその人の経歴や実力、人間性を見る資料です。語尾の使い方よりも、あくまで内容が優れているか、または正しい日本語が使えているかが大事です。
エントリーシートで「ですます」を使うメリット3選
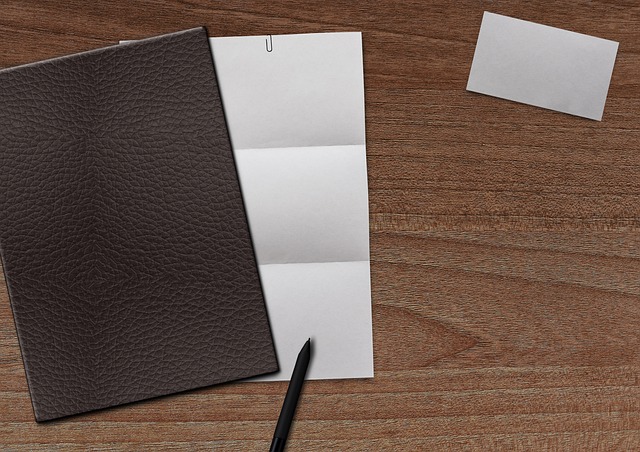
どちらでも良いとはいいつつも、やはり就活生の大半が「ですます調」を使っているはずです。敬語にするだけで、読みやすく丁寧な文章になりますよね。
「ですます調」だと具体的にどういったメリットがあるのか、紹介していきます。
- 敬語で丁寧な印象を与えられる
- 読みやすくて伝わりやすい
- 読む人が不快に
①敬語で丁寧な印象を与えられる
ですます調を使うと、文章は敬語の形になりますよね。自然と柔らかく落ち着いた言葉遣いになるので、丁寧な文章になります。また敬語を使うことで低姿勢な物言いになるため、礼儀が正しい印象を与えられるでしょう。
この時点ではまだ対面で話したことが無い分、採用担当者は言葉を通して相手の性格を読み取ろうとします。企業側に良い印象を抱いてもらうためには、ですます調を使うと効果的です。
②読みやすく伝わりやすい
ですます調の文章は、日本人が最も読み慣れている文末と言っても良いでしょう。したがって、ですます調で統一された文章は非常に読みやすく、スムーズに内容が頭に入っていくでしょう。
せっかく良い内容のエントリーシートも、読みづらいとそれだけでマイナスポイントになってしまいます。分かりやすい文章を作れるというのは、社会人としてとても魅力的です。
③読む人が不快になりにくい
敬語というのは相手を敬う言葉なので、ですます調になっているだけで読み手への敬意を表せます。
もちろん、である調だと敬意が無いわけではありません。ただ威圧的な口調だと捉えられ、不快にさせてしまう可能性があるのも確かです。
それに対してですます調は低姿勢で丁寧な文末のため、読んでいて相手が不快に思うことはほとんど無いでしょう。第一印象が決まる大事なエントリーシート、なるべく読み手が気持ちの良いものにしたいですね。
エントリーシートで「ですます」を使うデメリット3選

エントリーシートでは、丁寧で良い印象を与えられるからと、就活生のほとんどがですます調を使用しています。しかし、そんなですます調にもデメリットはあります。どういった弱点があるのかを知り、自身のエントリーシートにですます調は合っているか確認してみましょう。
- 文字数が多くなる
- 語尾に変化が無くなる
- 間違えた敬語を使ってしまう可能性が高い
①文字数が多くなる
ですます調は敬語で丁寧に文章を締めくくるので、どうしても文字数が多くなってしまいます。エントリーシートは、どれだけ自分の魅力を伝えられるかが重要です。
ですます調にして文字数が多くなってしまうことで、伝えられないことが増えてしまうともったいないでしょう。
逆に言えば、ですます調にすることで文字数を稼げるとも考えられます。したがって「内容は十分だけど文字数が足りない」という人には、ですます調がおすすめです。
②語尾に変化がなくなる
ですます調の語尾は「です」「ます」になるのがほとんどなので、同じ語尾が連続して使われがちです。
同じ語尾が続くと、読んでいてリズムが悪かったり、飽きやすい文章になってしまいます。単調なリズムが続くので、あまり良い文章とは言えません。また「です」が続いていると、あまり賢くない印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。
語尾の種類が多いである調とは違い、ですます調で文章ごとに語尾を変えるのはそう簡単ではありません。
③間違えた敬語を使ってしまう可能性が高い
ですます調は丁寧で綺麗なイメージがありますが、その分間違えてしまうとかなり印象が悪いです。
敬語というのはかなり言葉の種類が多く、立場や単語の組み合わせによって使い方が変わってきます。自分では正しいと思って使っている敬語も、実は恥ずかしい間違いをしているかもしれません。
社会人として正しい言葉を使えるかどうかはとても重要です。下記にある「気を付けたい敬語一覧」を確認して、正しい敬語を使いましょう。
気を付けたい敬語一覧
敬語は詳しく分類すると多くの種類があり、立場や形式によって使い分ける必要があります。
エントリーシートを書く際に特に間違えやすいのが、尊敬語と謙譲語の区別です。尊敬語は目上の人に使う言葉で、自分が主語の時に使うものではありません。尊敬語を使って自分のことを話すと、自らを敬っている形になります。自分が主語の話をする時は、尊敬語ではなく謙譲語を使用しましょう。
下記の間違いやすい尊敬語と謙譲語リストを、是非1度チェックしてみてください。
| 常体 | 尊敬語 | 謙譲語 |
| 言う | おっしゃる | 申し上げる |
| 行く | いらっしゃる | お伺いする |
| 聞く | お聞きになる | うかがう |
| 読む | お読みになる | 拝読する |
| 会う | お会いになる | お目にかかる |
| する | なさる | いたす |
| いる | いらっしゃる | おる |
| 見る | ご覧になる | 拝見する |
| 受け取る | お受け取りになる | いただく |
エントリーシートで「である」を使うメリット3選

ですます調とは違った雰囲気を持つ、である調には敬語ではないからこそいくつかのメリットがあります。エントリーシートで使用するには少し勇気が要るかもしれませんが、まずはどんな特徴があるのか理解してみましょう。
- 文字数が少なく済み内容のある文章を書ける
- 説得力のある文章をかける
- 誤った敬語を使うことが無い
①文字数が少なく済み内容のある文章を書ける
どうしても文字数が多くなってしまうですます調と違い、である調は1文を短くまとめられます。
例えば「目指しています」「目指す」のように、1つの言葉で4文字も減らすことができますよね。その分文字数に余裕ができるので、伝えたい情報をより多く記載できます。制限された文字数の中で、他の就活生と比べて、内容が充実した読み応えのあるエントリーシートを目指しましょう。
特にエントリーシートの内容がいつも文字数ギリギリだという人は、である調が適しています。
②説得力のある文章を書ける
である調は自分の意見や考えを断定する口調なので、説得力のある文章にできます。言い切る形にすることで、自分の考えに自信を持っている印象を与えられるでしょう。自分の考えや希望を自信を持って伝えられるのは、それだけで就活生として加点ポイントですよね。
また経験談を交えてアピールすることで、より説得力がある内容にできます。意見や自己PRを裏付ける経験と、それを強調するである調の組み合わせで、完成度の高いエントリーシートにしましょう。
③誤った敬語を使うことがない
ですます調と違って、である調で敬語表現を間違えることはありません。
敬語は状況によってルールが変わるので、気を付けなければいけない点が多いですよね。ですます調では、特に動詞などの敬語をミスすることがあります。それに対してである調は敬語ではないため、基本的に語尾だけ気を付けていれば問題ありません。
就活生として、正しい日本語が使えているかどうかは大切です。しかし敬語に気を付けるがあまり、エントリーシートの内容が疎かになってしまうのも避けたいですよね。敬語の使い分けが苦手な人は、是非である調を使ってみましょう。
エントリーシートで「である」を使うデメリット2選

説得力を持つエントリーシートを作成できるである調ですが、使用することでいくつかのデメリットもあります。どういったリスクがあるのか事前に知っておくことで、である調を上手に使っていきましょう。
- 上から目線の口調になってしまう
- 堅い印象を与えてしまう
①上から目線の口調になってしまう
相手を敬い下手に出る敬語と違い、である調は少々強気に聞こえてきます。特に問題提起をする時などは、かなり上から目線に聞こえてしまうでしょう。本人にそのつもりがなくても、読んでいて「偉そうだな」と思われてしまう可能性もあります。
言い切ることから説得力のあるである調ですが、上手く使わないと少し違和感を与えることもある口調です。上から目線にならないよう内容に工夫をしてみたり、なるべく柔らかい口調になるように言葉を言い換えてみましょう。
テーマごとに語尾を使い分けるのもOK
読んでいて不快感の無い文章にするために、テーマごとに語尾を使い分けると効果的です。
例えば、自分に関する話をしている時はである調を使い、社会問題や会社の話をしている時はですます調にするというようにテーマで語尾を変えることで、である調でありながら失礼の無い文章にすることができます。
同じテーマの中で語尾が混在してしまうのは、必ず避けましょう。まとまりが無くて、文章として完成度が低いように思われてしまいます。
②堅い印象を与えてしまう
である調の特徴は、意見を断定するような、言い切る形になることです。説得力があり力強い文章というメリットにもなりますが、逆に言えば柔らかい印象を与えられないというデメリットでもあります。相手に委ねるような口調ではないので、真面目で堅い印象を与えてしまうでしょう。
誰かにエントリーシートの添削を頼む機会があれば、堅くないかどうかも見てもらうと良いですね。もし修正したい場合は、言葉選びや内容で工夫できる点が無いか確認してみましょう。
エントリーシートで「である」と「ですます」を使い分けるコツ
エントリーシートの文末表現は「ですます調」と「である調」のどちらも使用可能ですが、与える印象は少し異なります。
企業の特性や自分のアピールポイントに合わせて効果的に使い分けることで、より説得力のある文章を作成することができるでしょう。
- 文字数制限が厳しい場合は「である」を使う
- 応募する企業に合わせて与えたい印象で書き分ける
- 迷ったら丁寧な「ですます」を使う
①文字数制限が厳しい場合は「である」を使う
エントリーシートでは、文字数制限が厳しい場合に「である調」を選択すると効果的です。
「である調」は「ですます調」と比べて文字数を大幅に節約できるため、限られた字数でより多くの情報を盛り込むことが可能です。
例えば、「思います」(4文字)を「思う」(2文字)に変えるだけでも2文字の節約になり、文章全体では10文字単位での差が生まれ、その分アピールポイントや具体例を追加することができます。
一般的な目安として、200文字以内の制限がある場合は「である調」の使用を検討しましょう。
②応募する企業に合わせて与えたい印象で書き分ける
応募する企業の特性や求める人材像によって、「ですます調」と「である調」を使い分けることで、より効果的な自己アピールが可能です。
伝統的な業界や大手企業では、丁寧で誠実な印象を与える「ですます調」が適しています。
特に金融、商社、メーカーなどの保守的な企業では、「ですます調」を使うことで、礼儀正しさや協調性をアピールできるでしょう。
一方、IT業界やベンチャー企業、クリエイティブ職では、「である調」を選択することで、自信や主体性、論理的思考力を印象付けることができます。
③迷ったら丁寧な「ですます」を使う
エントリーシートの文体選びでどうしても迷った場合は、最終的には「ですます調」を選択するのが無難です。
丁寧で柔らかい印象を与えることができ、読み手に悪い印象を与えるリスクも低いためです。
特に就活初期の段階では、企業との関係性を築く第一歩となるため、敬意を示せる「ですます調」が適切です。
なお、どちらの文体を選んだ場合でも、最も重要なのは文末表現を統一することで、文体が混在すると、まとまりのない粗雑な印象を与えてしまう可能性があります。
エントリーシートを書くときの3つの注意点

これまでですます調とである調それぞれのメリットを比較しましたが、エントリーシートを書くうえで注意したい点は語尾の種類だけではありません。優れたエントリーシートにするために、注意点は事前によく理解しておきましょう。
- テーマごとの文章の中での語尾は統一する
- 最も見られているのはエントリーシートの内容
- 空白や「特になし」で未回答のまま提出しない
①テーマごとの文章の中での語尾は統一する
ですます調とである調は、それぞれにメリットがあるので、どちらかを選ぶのは難しいでしょう。
その時はテーマごとに語尾を変えてみて、それぞれの良さを活かすのも効果的です。しかし1つのテーマの中では、必ず語尾を統一するようにしましょう。
テーマ内で語尾が統一されていないと、それだけで文章としてマイナスになります。
もし可能なら、エントリーシート全体で語尾が統一されている方が望ましいです。どうしても気になる場合だけ、テーマごとに変えてみるようにしましょう。
②最も見られているのはエントリーシートの内容
語尾や正しい日本語を遣えているかは大事ですが、大前提としてエントリーシートで最も大事なのはその内容です。
言葉に気を付けてばかりで、内容が不十分になってはいけません。
言葉のミスしやすい部分や基本的なルールだけ押さえたら、あとは内容を充実させるように努めましょう。
③空白や「特になし」で未回答のまま提出しない
エントリーシートの各設問には、企業が応募者に求める情報量が反映されており、規定字数の少なくとも8~9割は埋めることが重要です。
空白が多いと「志望度が低い」「熱意に欠ける」と判断され、マイナスの印象を与えかねません。
また、自由記述欄を空欄にしたり「特になし」と記入したりすることは避けましょう。これも企業に対して消極的な姿勢を示すことになります。
読みやすい文字の大きさを心掛け、具体的なエピソードや経験を交えながら、適切な文字数で記入欄を埋めることが大切です。
エントリーシートの文末・文体についてよくある質問
最後に、エントリーシートの文末・文体について、就活生からよく寄せられる質問に解答していきます。
ここで疑問を解消して、エントリーシートを自信をもって書けるようになっておきましょう。
- エントリーシートの言葉遣いが原因で落ちることはある?
- エントリーシートには体言止めを使ってもいい?
①エントリーシートの言葉遣いが原因で落ちることはある?
エントリーシートの言葉遣いが選考結果に影響する可能性もあります。
誤字脱字や話し言葉の使用、読みづらい文章構成は、仕事でのミスの多さや基本的なビジネスマナーの欠如を示唆するため、書類選考で不合格になる可能性が高まります。
特に応募者が多い企業では、言葉遣いの観点から人数を絞ることもあるため、適切な文章表現を心がけることが重要です。
②エントリーシートには体言止めを使ってもいい?
エントリーシートでの体言止めは、適度に用いることで文章に変化をつけ、単調さを避けられます。
あくまで、重要なポイントを強調したい場合や、文章にリズムを持たせたい時に効果的なので、多様は避けましょう。
エントリーシートの語尾は迷ったら「ですます」がおすすめ
エントリーシートの語尾は、どうしても迷ってしまう場合はですます調を使用するのがおすすめです。敬語の間違いにさえ気を付けていれば、少なくとも悪い印象を持たれることが無いからです。
ですます調とである調それぞれの特徴をよく理解して、エントリーシートに取り組んでいきましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。