インターン(インターンシップ)とは、企業に所属する前に学生が実際の仕事を体験する制度です。ただしその期間はさまざまで、企業ごとに異なる期間を設け、実施されています。
本記事では、インターンの期間の違いや特徴、またそれぞれのメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。
業界や企業、職種への理解や自己分析を深められるよう、またインターンの期間をより有意義にすごすため、これらをぜひ参考にしてくださいね。
インターンに受かるお助けツール集
- 1リクルートスーツレンタル|無料
- ぴったりのスーツでインターンに参加
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 好印象な志望動機を作成できる
- 3AI強み診断|自己分析
- アピールポイントがすぐ見つかる!
インターンの期間は種類によって違う

インターンは1日で終了するものから、1年以上継続するものまであります。インターンに参加する場合には事前に目的を考慮し、内容をチェックしてから期間を選択するとよいでしょう。
ただしインターンの経験は就職を希望する企業へのアピールとなり、その後の志望動機や自己PRを作成する際にも役立ちます。このため、インターンの参加期間をあらかじめ逆算し、就職活動の準備をはじめている学生も少なくありません。
インターンの3つの種類
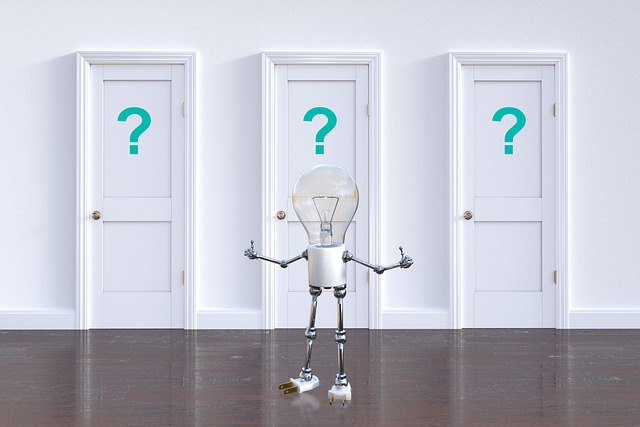
インターンの期間には幅があり、厳密には決まっていませんが、おおまかに次の3種類に分類されるのが一般的です。
- 1Dayインターン
- 短期インターン
- 長期インターン
詳しくみていきましょう。
①1Dayインターン
もっとも短いインターンは1Dayインターンといい、半日~1日限りで終了します。このため、実際の業務よりも、インターンを実施する企業の紹介や業務内容の説明、短時間のグループワーク、社員や社長によるセミナーなどが中心です。
また、企業側は自社に興味をもってもらい、志望意欲を高める目的で実施する傾向があります。
②短期インターン
短期インターンとされるのは通常、数日~1ヶ月程度の期間で実施されるインターンです。
夏季や冬季など学校の休暇期間にあわせて実施され、1Dayインターン同様実際の業務にかかわることはあまりありません。
しかし、グループワークによる課題解決や、その結果をプレゼンテーションで発表するなど比較的実践的です。
また短期インターンにおける成績が優秀な場合、本選考の際に面接が免除になる優遇措置が受けられることもあります。
③長期インターン
最低でも1ヶ月から3ヶ月以上にわたり職業体験をおこない、実際に企業の一員として業務に従事するインターンは長期インターンと呼ばれます。
実際の業務を体験できるのはもちろん、ビジネススキルやマナーなども学べるほか、一般的には給与も発生するのが特徴です。
参加することで長期にわたって企業に対してアピールができるので、短期インターンよりもさらに選考が有利になる場合があります。
【期間別】企業がインターンを実施する意図
上で解説したように、インターンには大きく分けて3つの期間が設定されていますが、それぞれの期間によって企業側の意図が異なります。
企業の意図がわかれば、どんな点を意識してインターンに参加すべきなのかも見えやすいので、ぜひチェックしてください。
ここではそれぞれの期間ごとに、企業側の意図を探っていきましょう。
①1Dayインターンの場合
1Dayインターンは、短期間で企業理解を深めてもらおうと企画されるプログラムです。
1日間のインターンを通じて、自社の業界や事業内容、職場の雰囲気を学生に知ってもらうのが目的で、採用活動の前段階として自社の魅力を伝え、学生に興味をもってもらうのが主な意図といえます。
また学生にとっても、限られた時間の中で効率よく複数の企業を比較検討できるメリットがあり、気軽に参加しやすい点が特徴です。
②短期インターンの場合
短期インターンの場合、プレゼンテーションやグループワークを通じて自社の業務内容や仕事の進め方、企業文化をより深く理解してもらい、企業の雰囲気を肌で感じてもらうのが主な意図です。
短期間であっても、学生がごく簡単なプロジェクトや課題に取り組む場合もあり、業務に対する適性や意欲を見極める目的もあります。
さらに、優秀な学生に早期から自社の魅力を伝えることで、採用活動の際に自社を志望してもらいやすくする効果も狙っているでしょう。
③長期インターンの場合
長期インターンは数か月以上の期間をかけて実施され、企業には学生に実務経験を深く積んでもらう意図があります。
企業にとって、長期インターンは学生の業務遂行力や問題解決力、組織との相性を見極める良い機会です。そのため、将来的にそのまま採用につなげる場合も多く、採用活動として位置づけている企業もあります。
また、長期インターンのほとんどが報酬が発生する「有給インターン」なので、予算をかけている分企業の熱量も高めです。
学生にとっても、実務経験が就職活動時の大きなアピール材料となるため、双方にとって価値のあるインターン期間といえるでしょう。
実施時期別のそれぞれのインターンの特徴

インターンは、期間だけでなく実施時期もさまざまです。特に短期インターンの場合、夏季や冬季など学校の休暇期間にあわせて実施されることが多く、時期によって特徴も異なります。
時期の種類はおおよそ以下の通りです。
- 夏季(3年生の夏)
- 秋季(3年生の秋)
- 冬季(3年生の冬)
- 春季(4年生の春)
- 通年募集
①夏季(3年生の夏)
比較的長い夏季休暇に行われるため、内容が充実したインターンです。学生の興味を惹くよう企業もコストをかけ、避暑地などで行われることもあります。
募集件数も多く、企業側としては優秀な学生とより多く接触することが目的です。
②秋季(3年生の秋)
大学では講義をおこなっている時期なので、多くは平日開催で夏季より短めです。基本的には募集件数も夏季よりは少なめとなっています。
金融関連の外資系企業やコンサルティング企業、一部ITベンチャーでは参加が本選考の条件になっている場合もあります。
③冬季(3年生の冬)
冬季のインターンは1~3日が中心で、解禁日である3月1日よりも前に開催される、説明会としての性格が強いものです。また、募集件数も多く、企業としては夏季や秋季のインターンで接触した学生に対し本試験への動機付けを強化する目的もあります。
④春季(4年生の春)
3月以降に行われるインターンです。こちらも1~3日が中心となっていて、内容自体も冬季と同様です。
業界研究の不十分な学生にも参加しやすく、グループワークなどが中心で、説明会と選考会も兼ねていることがあります。
通年募集
通年募集のインターンはほとんどが長期インターンです。
時期も決まっておらず、平日昼間から夕方にかけて最低でも5時間以上、かつ週3日以上にわたって開催されます。
一方で募集は随時で、学業をはじめサークル活動やイベント参加などとの両立にも配慮されています。
また就職活動を行う3〜4年生だけでなく、就職活動を意識する1〜2年生の受け入れもおこなわれるのが特徴です。
長期インターンを行う理想の期間は?

長期インターンの場合、期間は最低でも3カ月以上、可能であれば1年以上が理想です。
これは教育期間や習熟期間を考慮した場合、企業側も一定の期間が必要だからです。
特に実際の業務に従事する長期インターンでは、期間が短いと責任ある業務を任せることができません。
その結果インターンの期間中に与えられる業務が、雑務やルーティンワークに終始してしまうこともあります。
ただし、あまり長期にわたると学生側のハードルが高くなって参加を躊躇してしまいます。傾向としては6カ月程度が一般的ですね。
インターン種類別のメリット・デメリットを解説

ではインターンに参加するにあたり、その種類によってどのようなメリット、あるいはデメリットがあるのでしょうか。これらを知っておくことで、より有意義なインターンの期間を過ごすことができます。
1Dayインターンの場合
1日限りの1Dayインターンは参加のしやすさが最大のメリットです。忙しい就職活動中でも、半日のものなら午前、あるいは午後にはアルバイトなど別の予定を入れることもできます。
また、複数の興味ある業界や企業のインターンに参加することも可能です。
一方でデメリットは期間の短さから実際の業務への理解が深まりにくいことです。
内容も短時間のグループワークやセミナーが中心となるため、社員と個別で話すことや、仕事の流れ、あるいは職場の雰囲気を知るのは難しくなります。
こうしたデメリットを考慮して、企業側も1Dayインターンは学生の業務への理解度よりも、自社の認知度を上げることを目的に開催しています。
短期インターンの場合
短期インターンは学校の休暇期間にあわせて実施されることから、1Dayインターン同様参加のしやすさがメリットとなります。
スケジュールの調整もしやすく、学校の授業のある時期を避けて参加することが可能です。
また、期間もそれほど長くないことから、複数の業界や企業のインターンに参加でき、それぞれの違いや相性の把握にも役立ちます。
しかしながら、その内容はグループワークやプレゼンテーションなど、実践的な業務とは異なるため、企業に対する理解を深めたり、実際に働く際のイメージをつかむのは難しいかもしれません。
長期インターンの場合
長期インターンなら、その企業で所属している社員に近い仕事を任されるため、実際の業務を学生のうちに体験することができ、専門的なスキルも学べます。
また名刺交換の方法や、企業とのメールのやりとりといった、ビジネスマナーも身に着けられるでしょう。
こうした経験は入社後のアドバンテージとなり、社会人としてのスタートに役立ちます。
ただし、長期インターンの場合には平日の日中、社員と同様に企業で業務に従事するため、学業や単位取得への影響が否定できません。
そこで、企業によってはリモートワークを可能にしたり、働く時間帯や曜日に配慮していることもあります。
長期インターンではこうした実施状況もうまく利用し、学業がおろそかにならないよう注意するとよいでしょう。
適切なインターン期間を設定するポイント3選
適切なインターン期間を設定するためには、意識すべきポイントがあります。
上でも解説したように、一口にインターンと言っても募集形態によってさまざまな期間が用意されており、漠然と考えているだけでは自分にあった期間が見えてきません。
ここでは自分にあった適切なインターン期間を設定するポイントとして、以下の3点を解説します。
①参加の目的をはっきりさせる
インターン期間を適切に設定するためには、参加の目的をはっきりさせなければいけません。
インターンには「特定のスキルを身につけたい」「業界の理解を深めたいなど」とさまざまな目的がありますが、それぞれの目的に応じて必要な期間も異なります。
たとえば、業界の基礎知識を得るための短期インターンであれば1週間から数週間で十分な場合もありますが、スキルを習得し、実務に自信をつけたい場合には、3か月以上の長期インターンがおすすめです。
目的が曖昧なまま参加すると期待していた成果を得られず、貴重な時間を費やす結果になりかねないため、目的を明確にしてから自分にあった期間を探りましょう。
②可能な限り早いうちから準備を進める
適切なインターン期間を設定するためには、可能な限り早いうちから準備を進めてください。
多くの学生が参加を希望する人気の企業は、インターン枠が早く埋まってしまう場合も多く、準備が遅れたために希望とは違う企業のインターンに参加するケースも珍しくありません。
そのため、業界研究や企業のインターン募集状況を早めに調査し、スケジュールや期間を早いうちから確認しておきましょう。
学生は講義やサークル活動、部活など何かと時間が取られがちなので、「まだ時間があるから」とインターンの準備を後回しにすると、あっという間に時間がなくなってしまいます。
③先々の予定を洗い出しておく
適切なインターン期間を設定するためには、先々の予定をあらかじめ洗い出しておかなければいけません。
学生生活には、授業や試験、サークル活動、就職活動など多くの予定が重なるため、インターン期間を計画する際に他の予定と重ならないよう、早めの調整が求められます。
特に、試験期間や卒業研究、ゼミの発表など、学業に大きく影響を及ぼすスケジュールには注意が必要です。
学生生活が圧迫されないためにも、就職活動が本格化する時期を意識してインターンを組み込んで、就活と学業を両立させる姿勢を意識してください。
インターンに参加する期間は募集形態による!

ここまでのように、インターンは募集形態によって期間が異なり、実施時期も異なります。
このため、メリットやデメリットも知ったうえでより自分の目的にあった種類やスケジュールを選ぶことが大切です。
これによりインターンは就職活動を進めるうえでの有効な手段となり、自らの成長につなげることも期待できます。
ぜひインターンシップを有効に活用し、就職活動の成功につなげてくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









