「大学院生の就職活動事情はどうなんだろう?」そのようにお悩みではありませんか?
たしかに大学院生になると研究や学会発表などのスケジュールが詰まっていることもあり、いつから就職活動を始めれば間に合うのか把握しておきたいですよね。
そこで本記事では、大学院生の就職活動事情や、研究職以外にもおすすめの職業について解説しているので、ぜひ参考にして就職活動に役立ててください。
企業分析をサポート!便利ツール集
- 1適性診断|企業研究
- ゲットした情報を見やすく管理!
- 2志望動機テンプレシート|楽々作成
- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!
- 3志望動機添削|プロが無料添削
- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!
大学院生の就職活動事情について

大学院生の就職活動は、学部生と同じ就職活動の方法もできますが、大学院に所属していないと選択できない方法を使って就職活動を進められます。
また、理系院生だと企業募集が学部生よりも増えるので有利に働くことが多いです。
文系院生は教員や公務員の就職に有利になることが多く、学部生にはない就職活動を活用して就職の幅を広げていきましょう。
大学院生の就職活動は修士1年の6月から始める
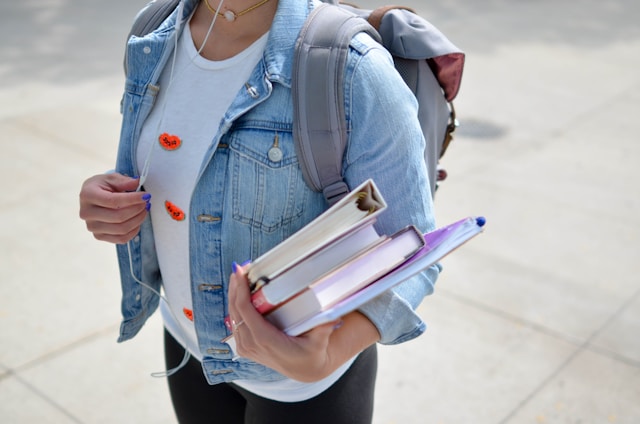
大学院修士課程の就職活動は、1年の夏(6月~7月)からスタートするのが理想的です。
ただし、この時期は前期研究発表との兼ね合いもあるので、研究と就職活動のスケジュールを逆算して調整しておく必要があります。
学業優先とはいえ、就職活動も両立して、早めに取り掛かることが大切です。
大学院生が就職活動に失敗する理由4選

ここからは専攻や所属する研究室によっても異なりますが、大学院生が就職活動に失敗する主な理由を4つ解説します。
研究も大切ですが、自分の将来のためにも就職活動の準備も考えながら行動しましょう。
①研究と就活のバランスが取れない
大学院生は毎日が研究漬けになるので、ついつい時間を忘れてしまいがちになる人が多いです。
しかし、大学院生はもともと学部生の頃から計画的に院生試験の勉強や物事を逆算して考える力が備わっているはずなので時間が作れないことはありません。
研究と就職活動に充てる時間を決めて行動しておくことで、本格的に忙しくなる時期も慌てずに行動できます。
②就活を後回しに考えていることが多い
大学院生は研究ばかりに没頭し過ぎて、就職活動のことを深く考えていないことが多いです。
志望する企業に就職するには、早めに企業研究や自己分析をして、計画を立てて行動しなければなりません。
特に、大企業や有名企業、他の大学院生や学部生にも人気の高い企業は就職倍率も高く、いくら専門知識をもっていても求める人材のミスマッチとなれば不採用となるケースもあり得ます。
就職活動のことを後回しにせず、しっかり準備しておくことが大切です。
③実績が少なくアピールポイントが弱い
企業が大学院生に求めることは、即戦力となる高い専門スキルです。
そのため大学院生ならではの強みをアピールしていかないと就職活動で失敗する原因となってしまうでしょう。就職活動では他の就活生との差別化が結果を大きく左右します。
大学院生の間に得た、学会発表の実績や、ティーチングアシスタント経験、研究で使用している解析ソフトなどの事例をフルに伝えて差別化を図るようにしてください。
④教授の企業とのコネクションが弱い
所属する研究室の教授と企業のコネクションが弱いと、就職活動で不利になる可能性があります。
ほとんどの研究室では、教授や助教が、研究成果を出すことを前提に文部科学省の所轄である日本学術振興会から研究費用(科研費)をもらい研究を進めていくのが一般的です。
中には、企業がスポンサーとなって金銭的支援をしてくれることもありますが、ごく一部の研究者にしかありません。
大学教授といえども企業とのコネクションがない人もいるので、インターンシップの参加や、キャリアセンターでOB・OG訪問をして自主的に就職志望の企業とコネクションを作っておくと良いでしょう。
大学院生が就職活動に失敗しない4つの必勝法
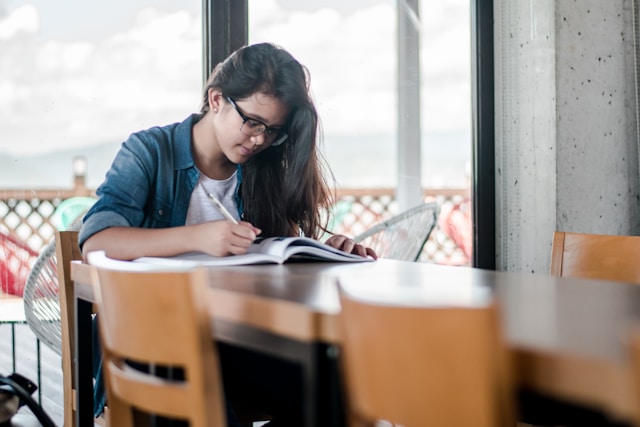
ここからは、大学院生が就職活動に失敗しない必勝法を4つ解説します。
研究内容を何も知らない人に伝えることが意外に難しいというのは、常日頃から何となくわかっているかもしれません。
就職活動を成功させるには、改めて誰が聞いても理解できるよう簡潔に研究内容や自己アピールを考えおくと良いでしょう。
①就職活動のスケジュールを確認する
大学での研究発表や、学会発表の参加発表の締め切りなどと重なるので、すぐに取り掛かれないかもしれませんが、最低限志望する企業のサマーインターン参加締め切り日は確認しておきましょう。
前述した通り、就職活動を始める時期の理想は、大学院修士1年の夏(6月~7月)です。
研究と就職活動のスケジュールを把握しておくこととで、締め切り期日を逆算して準備できます。
準備不足や、メンタル面でも慌てないようにするためには事前にきちんと自己管理しておくことが大切です。
②現在の研究内容を簡潔に説明できるようにしておく
次に誰に対しても研究内容をわかりやすく簡潔に説明できるよう準備しておきましょう。
大前提として初めて研究内容を聞く人が一回で理解するのは不可能です。
大学院生であればわかっている人も多いと思いますが、改めて自分の研究内容を要約し、専門用語をできる限り分かりやすい言葉で述べられるよう考えておかないといけません。
このような下準備は、就職活動だけに限らず、同じ学会に所属する人でも専攻が若干異なるので、自分の研究説明にも役立つはずですよ。
③大学院ならではの高いスキルをアピールする
大学院ならではの高いスキルとは、修士課程であれば2年間かけて同じ研究テーマを探究してきた成果と研究発表や学会などの場数や、学会発表の表彰実績があると高く評価されるはずです。
また、難易度の高い質疑応答にも受け答えするだけの能力もあると企業側からの期待値も大きいでしょう。
大学院生は、研究を通じて蓄積された情報や、課題発見、実験数値などを細かく取って分析を繰り返す忍耐力など、自分の研究成果すべてを論文にまとめて認定されなければ卒業できません。
しっかり研究に取り組んできた成果は、どの業界や職業にも応用できる能力として就職においても職務遂行能力としての強いアピール力となるでしょう。
④将来のキャリアビジョンをしっかり持つ
自分の理想の将来や目標を立てて実現するためには、具体的に1年後、5年後、10年後と、将来どのようになっていたいかキャリアビジョンの計画を立てるのもおすすめです。
大学院生は、より専門性の高い研究に取り組むため、その専門分野を活かした仕事に就きたいと思う人が多いでしょう。
ただ文系・理系での違いや、専攻違いによって、志望する就職先が少ない場合や、応募先があっても難易度が高く限られた人しか内定をもらえない場合もあります。
そのため、「〇年後は新たなプロジェクトに参加して成果を出す」「〇年後にはチームリーダーとして〇〇の開発に携わる」など、年数ごとの理想の状況を描いてみましょう。
そうすることで、たとえ自分が志望する企業に手が届かなかったとしても、理想の自分を将来設計できるはずなので、ぜひ自己分析の際に合わせて考えるようにしてみてください。
大学院卒の就職活動のメリットについて
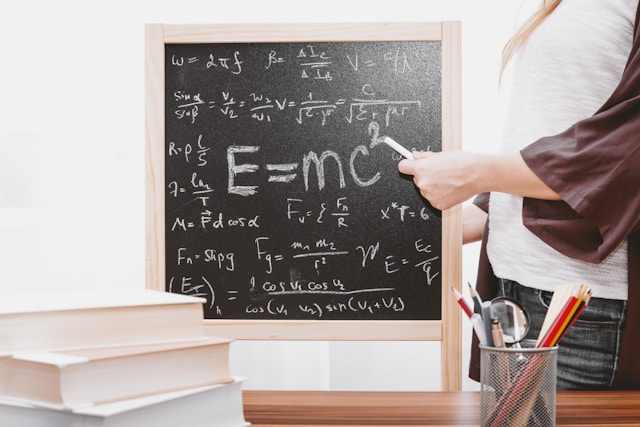
ここからは、大学院卒で就職活動するメリットについて解説します。
自分の研究分野を探究しつつ、学部生よりも大学院生の就職活動のメリットもあるので、ぜひ参考にしてください。
給与(初任給)が高い
厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給」によると、男女ともに大学院修士課程修了の初任給の平均額は23万8900円で、大学卒は21万2000円でした。
大学院卒の方が給与が高くなる傾向にあるので、やはり大学院へ進学しておいた方が得策と考える人もいるでしょう。
この結果が示すように、大学院卒の給与(初任給)は、大学卒よりも約2万円以上高いことがわかります。
とは言え、大学を卒業して2年間先に就職して経験や貯蓄などをしていることを考えると、大学院卒の初任給が高いといっても、そこまで大差がないことも十分あり得ます。
大学の推薦制度を受けられる
学校推薦とは、成績が優秀な学生が推薦権を得られる推薦制度のことです。
同じく、教授推薦というのも、特定の企業のコネクションを利用した推薦制度になります。
後付け推薦は、選考後に企業へ推薦状を提出することで、内定取り消しのリスクを防げる推薦制度のことです。
いずれも推薦されるのにふさわしい成績や研究成果が必要となります。
推薦制度は企業からの信頼性も非常に高いため、大学院生であればぜひ獲得したい推薦枠ですので、ライバルも多いですが勝ち取れるように努力するべきです。
研究分野を活かした企業を受けられる
主に実験中心の分野では、専門機械を使用したり、解析ソフトを使用したり、知識以外にも高度なスキルを身につけなければなりません。
そのため、研究職として企業に入職後すぐに実験手順や解析ソフトを使いこなせるので、即戦力として働くことが可能です。
これらの強みを活かした企業を志望する大学院生も少なくありませんが、大変狭き門であることは覚えておくと良いでしょう。
大学院卒で取得できる資格を活かせる
専攻(研究科)にもよりますが、所定単位数を取得し、大学院を卒業すると同時に取得できる資格があります。
代表的なものは「教員免許状」(教育学研究科)です。(引用元:文部科学省「教員免許状に関するQ&A」)
| 大学卒 | 一種免許状 |
| 大学院卒 | 専修免許状 |
この他にも、臨床心理士(心理学研究科)、司法試験(法学研究科)は大学院卒者に受験資格が与えられます。
この場合、目的意識がはっきりしているので、大学院で学び、資格を取得して就職したいと考える人はぜひ大学院進学はおすすめです。
大学院卒は研究以外にも高く評価されている
企業から一般的な大学院卒は、専門知識以外にも思考力が高いと評価されています。
- 論理的思考力
- プレゼンスキル
- コミュニケーション能力
- 忍耐力
- 挫折経験
- (学会などでの)人脈
研究や学会の発表で培われた経験が、仕事でも活かされると考えられ、人格形成を買って大学院卒を積極的に採用をしたいと考える企業も多いはずです。
大学院卒の就職活動のデメリットについて
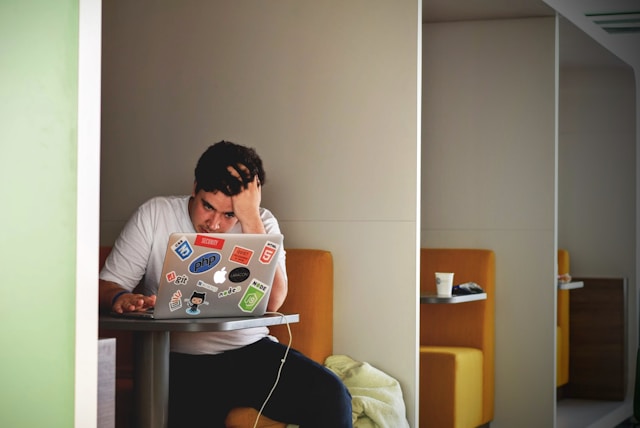
反対に、大学院卒の就職活動のデメリットについても解説します。
これまで学生であったことや、同年齢の社会人と比較されるなど、やはり一緒に仕事を進める上でのやりにくさあるようです。
社会人経験の後れをとってしまう
大学院生が就職で不利となってしまうケースは、学部生よりも社会人経験が遅れてしまうことです。
大学院卒を採用する企業に入社したのであれば問題ありませんが、仮に学部生が応募できる企業を志望した場合は新卒で入社したら同年齢の先輩がいるということを覚えておくと負担が少ないでしょう。
また、大学院卒を採用する企業に入社したとしても、稀に同期が自分よりもポジションが上ということもあるのでプレッシャーに感じてしまうかもしれません。
「自分だけが」ということが重荷に感じ辛くなることもありますが、何度も研究成果が出なくても自分を信じてやり抜いてきた力を信じて努力していくポジティブな気持ちをもつことが大切です。
専攻分野によっては学部卒の就活と変わらない
大学院に進学したからといって、強みとなる専門スキルがないと学部卒とさほどレベルが変わらないと捉えられ、大学院卒の効力が就職であまり役に立たずに終わるかもしれません。
有名大学の大学院を除けば、大学院試験の難易度はさほど高くないため、企業は必ずしも「大学院卒は学部卒よりも優秀」と捉えている訳でないことを覚えておく必要があります。
だからこそ、「大学院で何を学びたくて入学したのか」「大学院でどのような研究してきたのか」を明確に答えが述べられるようにしておかないと就職は厳しいものと思ってください。
大学院卒のアピール効果を使って就職で有利に働きかけるためには、研究で成果を上げ、学会発表などの実績を作っておくことが重要です。
大学院卒でも研究職に就ける保証はない
一般的に大学院生の目標として、専門性を活かた研究職(研究者)に就くことを目指しますが、それも一握りの人しかなれません。
そのため、「大学院に進学しても、卒業後の進路は自分の希望通りにいくとは限らない」という点は十分に理解しておきましょう。
どうしても研究職に就きたいと考えている人は、迷うことなく大学院進学をおすすめしますが、もしも給与や大学の推薦制度のメリットばかりに目がいってしまうのであればもう一度考え直すべきです。
その分だけ早めに現場で社会人経験を積むことで得られることがあるので将来のキャリアビジョンやライフイベントのことも考えて進学か就職かを選択してください。
研究職以外に大学院卒におすすめの職業

最後に、研究職以外にも大学院生におすすめの職業を5つ紹介します。
実務経験こそないものの、大学院の学びを活かせる職業はたくさんあるので、自分にあった業界・職業を見つけておくのもおすすめです。
開発職
メーカー勤務のエンジニアの開発職は、主に工業製品や産業機器の設計・製造・生産管理などに携わっています。
テクノロジーを駆使する開発職になるので、理系の専門知識はもちろん、チームワークも重要です。
大学院での研究との違いは、企業の利益のために成果を残さなければいけないため、ある程度の結果を出して報告しないといけない点となります。
開発職は、自分が作ったものが世間で実際に使われているという点にやりがいを感じられる職業でしょう。
システムエンジニア
システムエンジニアの仕事は、ビックデータやAIを活用したネットワークシステムの構築やセキュリティ管理システムを作る仕事です。
プログラムを組むためには、数学的な思考力が求められ、技術や理論にも理解のある理系大学院卒に向いています。
また、システムエンジニアは知力だけでなく、なぜプログラムが誤作動を起こしているか冷静な判断が必要となるため、問題解決能力にも長けていないと難しい仕事といえるでしょう。
金融関連
金融関連の専門職であるアクチュアリーは、確率や統計などの数理的手法を用いて、年金分野、保険分野、官公庁などのコンサルティング業務をします。
アクチュアリーの仕事は、解析ソフトから出されたデータを分析して結果を導く数学的思考力が必要とされているのが特徴です。
大学院で数式を用いて事実の妥当性があるかどうか結論を出す手法を学んだことがあれば、その能力を活かせる職業になるのでライバルも多いですがチャレンジする価値はあるはずですよ。
商社営業職
IT業界、計測機器メーカー、医療機器メーカーなどを取り扱う商社の営業職に大学院卒が有利となる場合があります。
その理由は、一般の商社に比べると、専門商品を扱うため顧客も専門性が高い場合が多く、対等に話をするには知識をインプットするだけでなくアウトプットするスキルもないといけないからです。
こうしたお互いにスキルの高い話をするときにこそ、大学院生の間にさまざまな場数を踏んできた経験が活かされてくるはずでしょう。
公務員
公務員は、国家公務員と地方公務員があり、「行政職」「専門職」「技術職」などがあります。
文系のみならず、理系の大学院卒の就職先としても人気が高いです。
さまざまな職種があるので、自分の学んできたことを1番活かせるところを受験すると良いでしょう。
研究も就職活動も気合いを入れて切り抜けよう!

本記事では、大学院生の就職活動事情や、就職活動の必勝法を解説しました。
研究で学びを深め、同時に企業の就職活動も行うため、大学院生は時間に追われる毎日が続くでしょう。
とは言え、自分の研究の延長に仕事を見つけて、その経験を活かした企業の内定をその手で掴みにいってくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。

このメディアの監修者
rina
#福岡県出身 #大学生 #24卒 #ビジネス領域専攻 #韓国語勉強中 #韓国ドラマ #コスメ #旅行好き









