公務員試験には、数学の知識が問われる科目もあります。しかし、どのような対策をすればよいのかわからず、悩んでしまう人もいるでしょう。
本記事では、求められるレベルや数的処理で問われる分野、適した対策法を解説します。科目ごとの特徴も紹介しているので、ぜひご覧ください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
数的処理とはどんな科目?
そもそも数的処理とはどんな科目なのでしょうか?日常でよく聞く言葉ではないため、イメージが掴めていない方も多いと思います。
数的処理は、公務員試験で必須とされる分野の一つで、数理的な思考力や論理的な判断力を問われる科目です。公務員としての事務処理能力を測る科目なのですね。
「判断推理」「数的推理」「資料解釈」「空間把握」の問題で構成され、数値や図形、データを基に解答を導き出す力が求められます。
公務員試験のおいて数的処理の科目は問題数が多く、限られた時間内で的確に解くスキルが必要。平均して1問3〜4分で解かなければならず、問題を見たらすぐに解答法を思いつかなければなりません。
日常的な数学知識に加え、効率的な解法やテクニックを身につけましょう。
まず確認!公務員試験で数学が必要な2科目
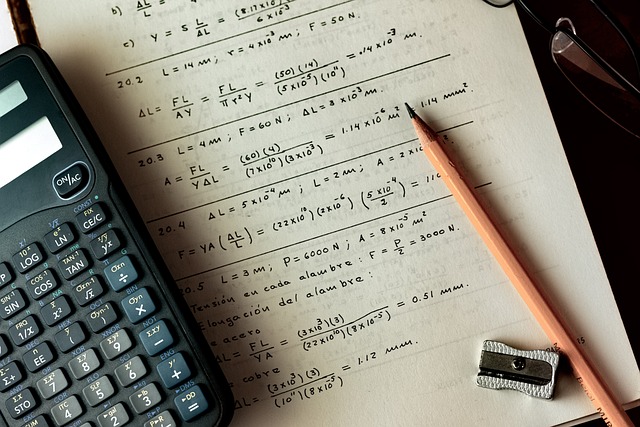
公務員試験で数学の知識が必要になる科目について理解を深めれば、適切な対策を練りやすくなります。
数学の勉強が必要な科目は以下の2つです。
- 数的処理
- 自然科学
①数的処理
数的処理は、基礎能力試験とも呼ばれる、公務員試験の教養択一試験において、知能分野として出題される科目です。
数的推理・判断推理・資料解釈・空間把握の合計4分野から出題されます。それぞれ、以下のような問題が出題されるのが特徴です。
- 数的推理:仕事算・流水算・鶴亀算など
- 判断推理:論理的思考や読解力が試される問題
- 資料解釈:棒グラフや分布図などの資料から計算する問題
空間把握問題は判断推理に含まれる場合もあり、立体・展開図・図形を転がした状態の把握などに関する問題が出題されます。
②自然科学
自然科学は公務員試験の教養択一試験において知識分野として出題される科目です。生物・物理・化学・数学・地学の知識が問われる科目となっています。
正しいものを選ぶ形式・計算で答えを導く形式・図表のうち正しいものを探す形式で問題が出題されるのも特徴です。
国家公務員試験の場合は重要度は低めですが、地方上級の全国型の試験では優先度が高くなります。
公務員試験の数学のレベル
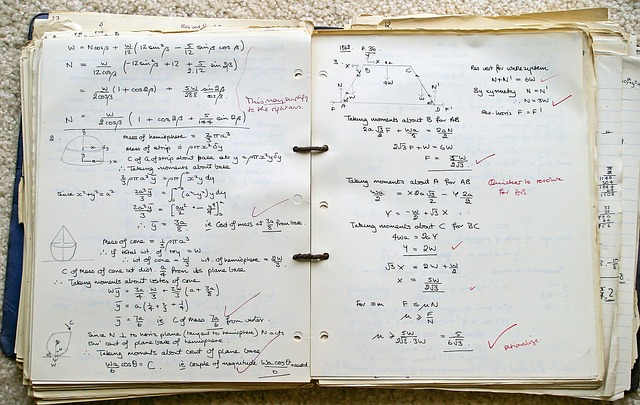
公務員試験の数学のレベルは、難易度が高めのものであっても高校程度に収まっています。
微分や積分といった専門的な問題はあまり出題されないため、最低でも中学数学レベルが解ければ得点率を高めやすいのが特徴です。
また、ほかの科目とは違い、解法の仕組みが理解できていれば正しい答えをスムーズに導きやすくなるといった特色もあります。
ただ、出題数は多い傾向があるため、対策をしっかりと行っておくことが重要です。解答方法を見て暗記するだけでなく、何度も解き直すことで安定した得点を叩き出しやすくなります。
公務員試験の数学「数的処理」の重要性

数学の科目の種類のうち、「数的処理」は出題数が「自然科学」と比べて多く、毎年必ず出題されるため、重点的に対策をする必要があります。
どの職種でも受験は必須となる分、正しい答えを素早く導いて回答できる状態を目指すことが大切です。
そのためには、出題傾向を掴んだ上で適した解き方の練習を積むことが重要になります。問題を繰り返し解くことで正答率が高められ、対策に時間をかけた成果が目に見えて表れやすいのもポイントです。
得点に結びつく勉強をしたい場合は、数的処理対策を重視して時間を割きましょう。
公務員試験の数学「数的処理」の4分野
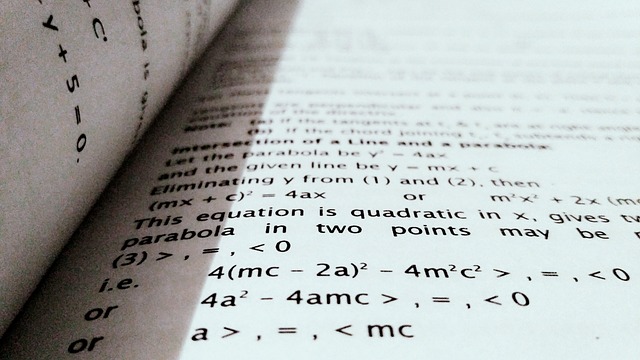
数的処理の分野についてより詳しい知識を持っていれば、自分にとっての苦手分野を手早く分析して適した対策をとれるのが利点です。
ここでは、以下の4分野の出題傾向や特徴を説明します。
- 数的推理
- 判断推理
- 空間把握
- 資料解釈
①数的推理
数的推理は問題文に沿って計算する問題で、4分野の中では最も数学的な考えが必要な分野となっています。
より具体的には、倍数・比と割合・確率・速さ・図形の長さ・二次関数・面積・濃度・最大や最小といった設問が出題されるのが特徴です。
中でも確率や図形問題は出題されやすい傾向があるため、しっかりと対策する必要があります。解き方を身につけていれば正しい回答を導きやすいのがポイントです。
②判断推理
判断推理は論理的にパズルを解いていくような問題が出題される分野です。問題に示されている条件を正しく捉えて、条件を全て満たす選択肢を選ぶことが求められます。
より具体的には、人物の対応・順番・位置、リーグ戦やトーナメント戦に関する設問や、嘘つきがいる問題などが出題されるのがポイントです。
ただ頭の中で条件を組み合わせて考えるのではなく、表の作成を行って手を動かすことで、スムーズに選択肢を絞り込めます。
③空間把握
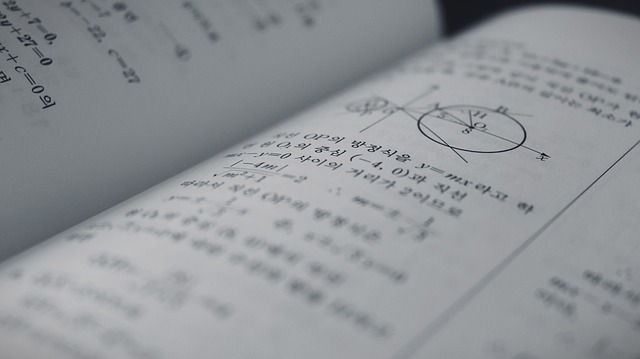
空間把握は図形問題の1つで、計量以外の内容が出てくる分野となっています。
正多面体・立体の切断・投影図・軌跡・一筆書き・円の回転数・折り紙といった、空間認識能力を発揮しないと解けない問題が出るのが特徴です。
解き方の流れを理解して知識を付ける、実際に展開図から立体を組み立てる、三角・四角・円を描いて回転させた軌跡を描いてみる、などの対策で苦手意識が解消されやすくなります。
④資料解釈
資料解釈は提示された統計資料から情報を読み取り、正しい選択肢を選ぶことが求められる分野です。
資料の数値を計算するケースが多く、増加率・減少率・総量・実数・指数・構成比などがグラフ化されて出題されます。
一定の値を超えているかどうか、大小はどうなっているかなど、細かい計算をしなくても判断基準がわかりやすい問題が多いです。
そのため解き方のコツを掴めば素早く正しい回答を選びやすくなります。
数的処理はいつから勉強するべき?何から勉強するべき?
数的処理の勉強は、できるだけ早めに始めることが望ましいと言えます。
少なくとも試験の6か月前から取り組み、基礎から段階的に学習を進めていくのが理想です。
公務員試験では数的処理の出題割合が高く得点源にしやすい科目ですが、問題数が多いため短期間で詰め込んで学習するのは難しいでしょう。
初めの段階では難しい問題に挑むよりも、基本的な解き方を確実に身につけることを意識すると良いですね。
基本を固めたら、過去問や模擬試験に取り組み、時間内に正確に解けるよう練習を重ねましょう。特に頻出分野を重点的に復習することで、効率よく得点力を上げられますよ。
公務員試験の数学の対策法3選

対策法をチェックすれば、より効率よく成果につながる勉強を積み重ねられます。意識すべき対策法は、以下の3つです。
- 出題・解法パターンを把握する
- 過去問を解く
- 時間配分を意識する
①出題・解法パターンを把握する
出題される内容や解法パターンを把握すれば、本番でも緊張せずに実力を発揮しやすくなります。
問題と解法をセットで覚えることで、問題を見て解法がすぐ思い出せる状態に近づけられるのがメリットです。
ただ解法を丸暗記するのではなく、実際に問題演習をして手を動かしながら内容を把握していくことも重要になります。
理解を深めれば、出題された問題の解き方を着実に身につけて、スムーズに解き進めやすくなるのがメリットです。
②過去問を解く
過去問を解けば、覚えた出題傾向や解法パターンをアウトプットできるのがメリットです。
問題を見て解法パターンを瞬時に判断できる力を身につけるためには、過去問を繰り返し解いて問題の具体例をインプットしながら実践的にアウトプットしていくことが大切です。
過去問を通して本番の問題形式に慣れておけば、実際の試験問題に取り組む際にも冷静さを保って正しい回答を導きやすくなります。
③時間配分を意識する
問題の解き方や出題傾向が掴めて来たら、時間配分を意識した実践的な対策をしましょう。
タイマーなどを使って、1つの問題を解くまでの時間を計ることで、時間を消費してしまっている場面がないかチェック可能です。
問題ごとにかかっている時間がわかったら、苦手分野の問題を解く量を増やしましょう。短時間で正解できるようになれば、より多くの問題に余裕を持って対応しやすくなります。
本番形式に慣れて時間の使い方の目安を把握しておくと、実力を発揮しやすくなるのも利点です。
公務員試験の数学についてのよくある質問
公務員試験で出題される数学(数的処理)は、多くの受験者が対策に悩む分野の一つです。
計算力や論理的思考を必要とするため、「どの程度の難易度なのか」「どの分野を重点的に学べば良いか」等の疑問がよく寄せられます。
ここでは、公務員試験の数学に関するよくある4つの質問に対する答えを紹介します。数的処理の具体的な勉強方法を知って、効率的に学習を進めてみてくださいね。
①数的推理は苦手だったら捨てるべき?
数的推理が苦手でも、捨ててしまうのは得策ではありません。
公務員試験での数的推理は頻出であり、全体の得点にも影響するため基本的な問題は解けるようにしておくのが重要です。
捨てる前にまずは簡単な問題から取り組み、解法のパターンを習得しましょう。
実は数的推理は解法のコツを掴むと効率よく得点できる部分も多いので、全問解く必要はありません。
難しい問題にこだわるよりも、基礎的な問題を確実に得点源とするよう心がけてくださいね。
②公務員試験の数的処理の得点は全体の何割くらい?
公務員試験では、数的処理が全体の3~4割程度を占めることが一般的。
特に地方上級や国家一般職の試験では数的処理の重要性が高く、多くの得点がこの科目にかかっています。これらの役職を志望する方は、しっかりとした対策が必要です。
限られた試験時間内で効率よく解答できるよう、スピード感を意識したトレーニングを心掛けましょう。
こちらの章でも紹介しましたが、数的処理は他の分野と異なり、解法のパターンや計算力が問われるため、短期間で習得するのは難しい部分もあります。
受験日から逆算して勉強計画を立て、対策に時間をかけて取り組み、数的処理科目を確実な得点源としてくださいね。
③公務員試験で数的処理は何問出題される?
公務員試験での数的処理の出題数は試験の種別によりますが、一般的に1分野15~20問程度です。
国家一般職や地方上級等の試験では数的処理の問題数が多く、数的処理が重要な得点源となります。
これらの競争率の高い役職の試験では数的処理の得点が合否に大きく影響するため、徹底した対策が必要です。
数的処理の問題は基本的な計算問題だけでなく、論理的な推理や複雑なパターンの認識が必要な問題も含まれるため、幅広い分野を網羅した学習が重要。
繰り返しの演習を通じて問題を解く際のコツや解答の順番を身につけ、徐々に得点率を伸ばしていってくださいね。
④公務員試験に合格するには1日何時間勉強すればいい?
公務員試験に合格するためには、1日5~6時間を目安に勉強時間を確保するのが理想的です。
試験の内容や個人の学力によって違いますが、特に数的処理や専門科目は一朝一夕で習得できるものではないため、継続的に学習する必要があります。
1日の勉強時間を確保するのが難しい場合でも、週に30時間ほどの勉強時間を確保するよう意識するとよいでしょう。
また、長期的に計画を立て、勉強時間だけでなく適度な休息を取り入れることで、集中力と学習効果も高まりますよ。
こちらの記事では、就活や試験に疲れたときに効く、リラックスできる音楽を紹介しています。
適度な休憩時間を取り入れて、より勉強時間中の密度を高めていってくださいね。
公務員試験の数学は対策を立てて取り組もう
公務員試験の数学問題は対策を立てて準備をしましょう。
数学問題は数的処理と自然科学の科目で出題され、数的処理は数多く出題される分、対策の有無が得点に影響しやすいのが特徴です。
問題ごとの解法パターンを把握して過去問を解き、時間配分も考えて対応力を高めましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。










