「インターンの申し込みって、いつから始めればいいの?」
就活準備を進める中で、多くの学生が気になるのがインターンシップの申込時期です。
夏や冬のインターンは人気が高く、募集開始からすぐに定員が埋まってしまうこともあるため、早めの情報収集と準備が欠かせません。
そこで本記事では、インターンの申し込み時期を夏・冬別に整理し、種類やスケジュール、申し込みから参加までの流れや注意点を詳しく解説します。
これからインターンを検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
インターンに受かるお助けツール集
- 1リクルートスーツレンタル|無料
- ぴったりのスーツでインターンに参加
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 好印象な志望動機を作成できる
- 3AI強み診断|自己分析
- アピールポイントがすぐ見つかる!
インターンの申し込みはいつから始めるべき?
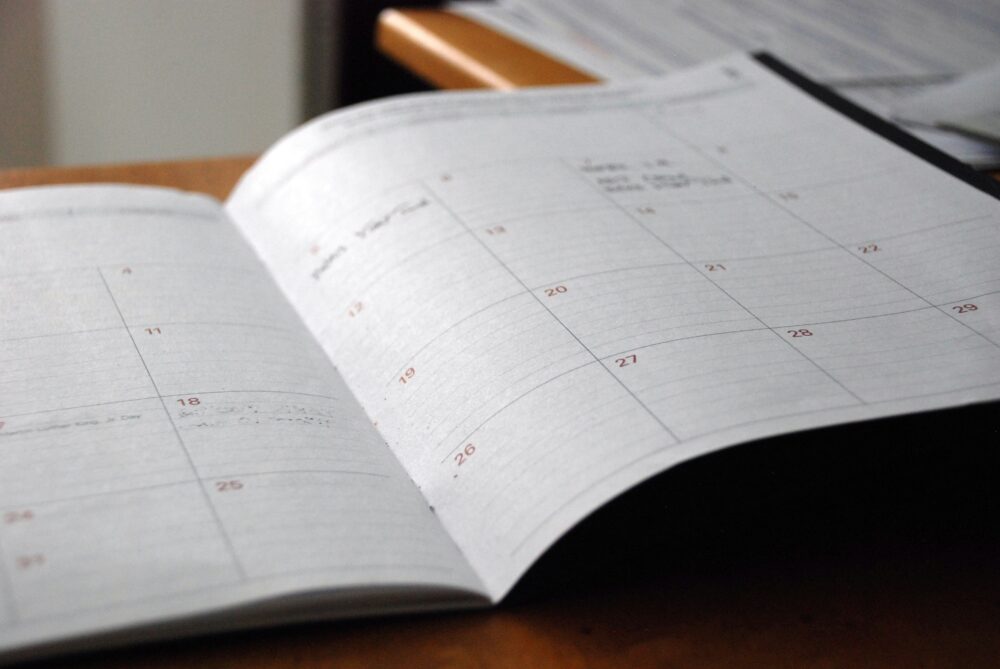
インターンシップの参加時期に悩む学生は多いでしょう。学年や業界によって適切なタイミングが異なるため、自分に合ったスケジュールを把握しておくことが大切です。
ここでは、学年ごとにインターンの申し込み時期やポイントをわかりやすく解説します。
- 大学1・2年生
- 大学3年生/大学院1年生
- 大学4年生/大学院2年生
- 薬学生5年生
①大学1・2年生
大学1・2年生のうちからインターンに参加することは、将来のキャリアを早めに考えるきっかけになります。
「まだ就活には早い」と思われがちですが、実際には多くの企業が低学年向けのインターンや仕事体験イベントを実施しています。
これらのプログラムは、企業の雰囲気や業界の特徴に触れることができ、社会に出る前の準備として非常に有益です。
とくに短期インターンは、学業やアルバイトとの両立がしやすく、初めてのインターンとしても参加しやすい形式です。
参加者は自己PRや志望動機を深く問われることも少ないため、気軽に応募しやすい点も魅力でしょう。
インターンという言葉にとらわれすぎず、企業セミナーや座談会にも目を向けてみるとよいでしょう。
②大学3年生/大学院1年生
大学3年生や大学院1年生は、インターン参加の主戦場ともいえる時期です。多くの企業が本格的なプログラムを展開し、学生も就活の一環として真剣に参加するようになります。
この時期に実施されるインターンは、業務体験の内容がより実践的で、実際のプロジェクトに参加できるものも増えてきます。
中にはインターン参加者限定で特別選考枠を設けている企業もあるため、結果的に早期内定を得るチャンスにもつながるでしょう。
申し込み時期に関しては、夏に開催されるインターン(サマーインターン)は6月ごろから募集が始まり、人気企業ではすぐに締め切られてしまいます。早めの準備が欠かせません。
自己分析や業界研究もこの時期に一度しっかりと行うことで、その後の就活において大きなアドバンテージになります。また、応募に必要なエントリーシートやWebテストの対策も求められることが多くなります。
気になる企業がある場合は、直前ではなく、数か月前から計画的に準備を始めておくことが成功のカギとなるでしょう。
③大学4年生/大学院2年生
大学4年生や大学院2年生になると、すでに本選考が進んでいる学生も多いため、一般的なインターンの募集は限られてきます。
ただし、企業のなかにはこの時期に「就業体験型インターン」や「内定者向けインターン」といった形で、実際の仕事に近い業務に触れさせるプログラムを実施するケースがあります。
これらのインターンは、企業と学生のマッチ度を最終確認するための機会であり、業務内容への適性や社風との相性などを見極める材料となります。
企業側にとっても、早期内定者との関係を強化する狙いがあるため、参加することでより良い評価につながることもあるでしょう。
進路に迷っている学生にとっても、まだチャレンジできる場が残されているという点で、最後の実地体験の機会となるかもしれません。
少しでも不安や迷いがあるなら、エントリーして現場を自分の目で確かめてみるのも一つの手段です。
④薬学生5年生
薬学生にとっての5年次は、長期実務実習が大きな比重を占めるため、インターンの参加機会が制限される傾向があります。
しかし、その一方で薬学部向けに特化したインターンが数多く用意されており、タイミングを見極めれば十分に参加可能です。
とくに製薬会社や調剤薬局、病院などは、薬学生の実習スケジュールを考慮し、夏や秋に短期インターンを実施しています。
こうしたプログラムでは、職場環境を実際に体験できるほか、企業ごとの研究スタイルや働き方の違いを比較することができます。自分のキャリアビジョンに合った職場を見極める貴重な手がかりとなるでしょう。
学会発表や卒論などで多忙になる時期と重なることもあるため、スケジュール管理には一層の工夫が必要です。
日程が合わない場合には、企業説明会やOB訪問など他の手段で情報収集を補うことも視野に入れておくと安心です。
インターンシップの種類
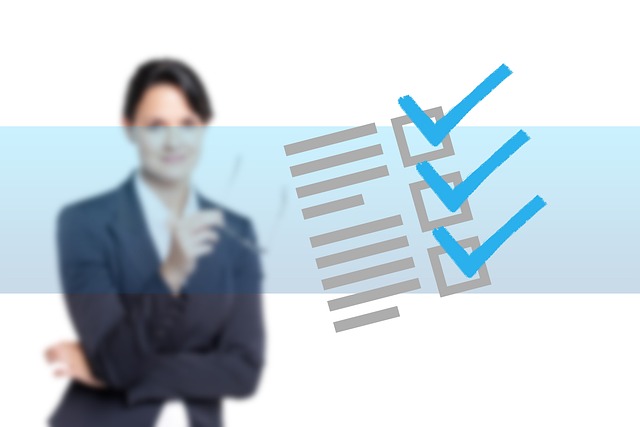
インターンシップにはさまざまな種類があり、それぞれ目的や参加時期、内容が異なります。就活生にとっては、自分に合った形式を見極めることがとても大切です。
ここでは、代表的なインターンの種類と、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。
- 短期インターンシップ
- 長期インターンシップ
- 1dayインターン
- 複数日インターン
- 有給インターン
- 無給インターン
- 体験型インターン
- 実務型インターン
- プロジェクト型インターン
①短期インターンシップ
短期インターンは、1日から数日間の比較的短い期間で行われるプログラムです。主に大学の長期休暇中に集中して実施されることが多く、参加のハードルが低いことが特徴です。
企業の紹介やグループディスカッション、簡易な職業体験などがプログラムに含まれており、実際の業務に触れる前のステップとして最適です。
短期間だからといって軽視してしまうのはもったいないでしょう。複数社を効率よく比較することができるため、業界研究を進めるうえでも大きな意味を持ちます。
また、就活本番でのエントリーシートや面接に役立つ情報を得る場としても活用できます。一方で、参加者が多くなる傾向にあり、企業との距離感がやや遠く感じられることもあります。
しっかりと質問を準備したり、終了後に気づきをまとめたりすることで、短い時間でも学びを深められるはずです。
②長期インターンシップ
長期インターンは、数か月から1年以上にわたって実際に企業で働くスタイルのインターンです。週に数日出社する形式やフルリモートで業務を行う形式など、勤務形態は企業によってさまざまです。
社員と同様のタスクを担当することもあり、責任感を持って働く姿勢が求められます。実務経験を積めるという点では、就活において大きなアドバンテージになります。
実際のビジネスシーンに身を置くことで、課題解決能力や報連相の習慣など、学校では得られない社会人基礎力が身につきます。
また、社内の人間関係を築ける機会もあり、本選考前から自分を知ってもらえる可能性もあります。ただし、業務量や責任の重さに加えて、大学の授業や試験との両立が課題になる場合もあります。
自己管理ができるかどうかがカギとなるため、応募前にはスケジュールをしっかり確認することが重要です。長期で関わるからこそ得られる信頼や達成感は、今後のキャリア形成にも役立つでしょう。
③1dayインターン
1dayインターンは、1日で完結する短時間のプログラムで、就活の初期段階におすすめです。企業説明、ワークショップ、現場社員との座談会など、内容は凝縮されていますが、基本的に情報提供が中心です。
事前知識が少なくても参加しやすく、気になる企業や業界に触れるきっかけとして役立ちます。
その場で企業の雰囲気を感じたり、社員の考え方に触れたりすることで、ネットやパンフレットでは得られない情報を得ることができます。
また、就活本番に向けた練習の場としても有効で、グループワークの進め方や自分の立ち回り方を客観的に見直す材料にもなるでしょう。
デメリットとしては、参加人数が多く、1人あたりの発言や質問の時間が限られる点が挙げられます。また、実務に触れる機会は少ないため、企業での働き方を具体的にイメージするには不十分な場合もあります。
そのため、1dayインターンを複数社経験した上で、興味のある企業には中長期のインターンでより深く関わる流れが理想的です。
④複数日インターン
複数日インターンは、2〜5日程度にわたって行われるプログラムで、1dayよりも内容が濃くなる傾向があります。
複数の部署の業務を横断的に体験したり、企業の実際のデータを使ったケーススタディに取り組んだりする機会が用意されていることもあります。
企業によっては、参加者に対してフィードバックを丁寧に行い、ポテンシャルの高い学生を早期選考へ案内する流れをとっていることもあるため、評価の対象になる可能性も意識しておく必要があります。
準備を怠ると、印象を下げるリスクもあるため注意が必要です。また、グループでの協働作業が中心となることも多く、コミュニケーション力や協調性が問われる場面が増えるでしょう。
限られた時間内に成果を出すためには、積極性と柔軟性が求められます。単なる職場見学ではなく、自分の強みを発揮する場として、しっかり準備を整えて臨むことが大切です。
⑤有給インターン
有給インターンは、企業から報酬を受け取りながら実際の業務に従事するインターンシップです。
仕事内容はアルバイトのような単純作業にとどまらず、プロジェクトへの参加や顧客対応など責任のある業務を任されることも多く、実践的なスキルが習得できます。
報酬が発生する分、企業からの期待も大きくなり、結果や成果が重視される傾向があります。そのため、単に「学ぶ姿勢」だけでなく、自ら成果を出そうとする主体的な姿勢が求められます。
報酬を目的に参加するのではなく、「お金をもらいながら成長できるか」を軸に検討することが重要です。
また、有給であるがゆえに企業側の選考も厳しくなる傾向があるため、エントリーの際には志望動機や自己PRをしっかりと準備しておきましょう。
⑥無給インターン
無給インターンは、報酬が支払われない代わりに、比較的自由度が高く、学びの機会として参加しやすい形式です。
特に短期間や体験重視のインターンで多く見られ、就活のスタート地点として利用されることが多いです。
企業側も学生の育成を目的にプログラムを設計している場合が多く、学びや気づきが得られるような内容が中心になります。
職業観を養ったり、業界の全体像をつかんだりするには最適です。報酬がない分、気軽に参加できる反面、交通費や食事代などが自己負担になるケースもあるため、事前に条件をよく確認する必要があります。
学びを目的とする無給インターンは、参加者の意識次第で得られる経験値が大きく変わります。貴重な時間を活かすためにも、自分なりの目標を持って取り組むことが重要です。
⑦体験型インターン
体験型インターンは、実際の業務を模擬的に体験できるよう設計されたプログラムです。営業ロールプレイや企画立案、模擬商談など、疑似的な業務を通して企業の仕事や業界の特色に触れることができます。
この形式は、仕事の進め方や職場の雰囲気を実感するのに役立ちます。実際に働いているような感覚を得られるため、業務のイメージが湧きやすく、自分に合っているかどうかの判断材料にもなるでしょう。
特にまだ志望業界が定まっていない段階では、複数の業界を体験することで視野を広げる手助けになります。一方で、模擬体験であるため、実務に関わる深さやリアリティには限界があります。
インターン中に出される課題も、やや演出が入った内容であることが多く、実際の仕事とは異なる部分がある点にも注意が必要です。
ただし、就活初期の学生にとっては、自分の適性や課題を発見するきっかけになります。
体験型インターンに参加したら、振り返りを行い、気づいたことや学んだことを言語化しておくと、面接時にも有効に活用できるでしょう。
⑧実務型インターン
実務型インターンでは、企業の現場で実際の業務を行います。社員と同じプロセスで業務を進めるため、社会人としての基本スキルや、ビジネスの進め方を身をもって学べるのが特徴です。
多くは長期インターンとして募集され、実際に成果を求められる場面もあります。業務内容は企業や職種によって異なりますが、営業、マーケティング、開発、デザイン、事務など多岐にわたります。
自分の興味関心や将来の進路に合わせて、適した業務を選べるのも魅力の一つでしょう。ただし、実務である以上、成果や結果に対するプレッシャーがかかる場面もあります。
未経験の業務で戸惑うこともあるかもしれませんが、積極的に質問したり、自主的に学んだりする姿勢があれば、着実に力がついていきます。
また、実際に働いている社員の姿を間近で見られるため、企業の文化や仕事への姿勢に触れる貴重な機会にもなります。
本気でその企業を目指したいと考えるなら、実務型インターンでの経験は大きな武器になるでしょう。
⑨プロジェクト型インターン
プロジェクト型インターンは、一定の期間でチーム単位の課題解決に取り組む形式のインターンです。企業が抱える実際の課題に対し、学生が企画や提案を行うなど、ビジネスの現場に近い体験が得られます。
課題の内容は、新商品のアイデア提案やマーケティング戦略の立案、社内制度の改善など多岐にわたり、自分たちのアイデアが企業に採用される可能性もあります。
自ら考え、チームで協力しながら成果を出すという経験は、就活だけでなく社会人生活においても貴重な財産となるはずです。
この形式では、論理的思考力、プレゼンテーション力、リーダーシップなど、複合的なスキルが求められます。
結果として企業から高評価を得て、選考に有利に働くケースも十分にあるのです。
インターン参加に向けたスケジュール例【夏・冬別】

就職活動のスタートダッシュを切るうえで、インターンシップへの参加は非常に重要なステップです。特に夏と冬では実施時期や企業の目的が異なるため、それぞれに合わせた準備が必要になります。
ここでは、夏と冬のインターンに分けて、参加までの具体的なスケジュールと注意点を詳しく紹介します。
- 夏インターンの準備スケジュール
- 冬インターンの準備スケジュール
①夏インターンの準備スケジュール
夏インターンは、6月から8月にかけて開催されることが一般的です。早い企業では3月ごろから募集を始めるため、春学期の開始と同時に動き出す意識が求められます。
特に難関企業や大手の人気インターンでは、募集期間が短かったり、選考倍率が高かったりするため、スピーディーな準備が欠かせません。
まずは春休みの間に自己分析と価値観の整理を進め、業界や職種についても幅広く情報を集めましょう。
志望する業界の傾向や、過去のインターン内容なども調べておくと、ES(エントリーシート)作成や面接対策が格段に進めやすくなります。
少し先を見越して早めに行動しておくことが、希望するインターン参加への第一歩になるでしょう。
②冬インターンの準備スケジュール
冬インターンは12月から2月にかけて実施されますが、エントリーのピークは9月〜10月に訪れます。時期的に就活意識の差が出やすく、準備を怠るとチャンスを逃す恐れがあります。
夏インターンに参加できなかった人や、志望業界を絞りきれていない人にとっては、軌道修正や深掘りの機会として非常に有効です。
まず、夏インターン後に得た気づきや反省をもとに、自分の関心分野や適性を見直しましょう。もし参加企業の業種が合わなかった場合は、方向転換の材料としても活用できます。
冬インターンの選考は、夏よりも比較的ライトなものが多く、1日完結型やワークショップ形式も増えますが、それでも最低限のESや志望理由は必要になります。
さらに、冬のインターンを通じて得た経験や企業との接点が、本選考のときに評価されることもあります。年明けからの選考を有利に進めるうえでも、冬のタイミングを逃さず活用しておきたいところです。
インターンに申し込みから参加までのステップ

インターンシップは、就職活動の第一歩ともいえる大切な経験です。しかし、「いつ申し込めばいいのか」「何から始めるべきか」と悩む就活生は少なくありません。
ここでは、申し込みから参加までの流れを段階ごとにわかりやすく解説します。
- 参加目的を明確にする
- 情報を収集して比較検討する
- エントリーして書類を提出する
- 選考試験と面接に備える
- 最終確認をして準備を整える
①参加目的を明確にする
インターンに申し込む前に、まず自分が何を得たいのか、その目的を明確にすることが欠かせません。
目的がはっきりしていないと、数あるインターンの中から本当に必要な経験ができる企業を選ぶことが難しくなってしまいます。
たとえば、業界の雰囲気を知りたいのか、実務経験を積みたいのか、それとも内定直結を狙いたいのかによって、選ぶインターンの種類や応募時期も変わってくるでしょう。
目的を明らかにすることで、自分に合ったプログラムを選びやすくなります。また、その目的はエントリーシートや面接時にも大きな意味を持ちます。
応募理由に一貫性があると、面接官の印象も良くなります。目的を事前に整理しておけば、自分の言葉で語れるようになり、面接でも自信を持って話せるはずです。
なんとなく参加するのではなく、自分がどの段階にいて何を身につけたいのかを明確にしたうえで行動に移すことが、インターンを最大限に活かす鍵になるでしょう。
②情報を収集して比較検討する
目的が定まったら、次はインターンの情報収集に取りかかりましょう。ナビサイトや企業の公式サイト、大学のキャリアセンター、SNSなど、情報源は多岐にわたります。
特定の媒体に偏らず、複数の方法で探すことで、見落としを防ぐことができます。とくに注目したいのは、実施時期、開催形式(対面かオンラインか)、報酬の有無、インターンの期間や内容などです。
企業によって条件が大きく異なるため、複数社を比較することは欠かせません。また、同じ企業でも年によって内容が変わる場合があるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
さらに、口コミサイトや過去の参加者の体験談などを参考にすると、パンフレットや募集要項だけではわからないリアルな情報を得られることがあります。こうした情報は、選考対策にも役立ちます。
早期募集が多い人気企業では、夏前からインターンの案内が出ることもあります。出遅れないよう、定期的に情報をチェックして、スケジュールに余裕を持って行動することが重要です。
③エントリーして書類を提出する
参加したいインターンが見つかったら、次は実際にエントリーして必要な書類を提出する段階に進みます。多くの場合、Webフォームの入力に加え、エントリーシート(ES)や履歴書の提出が求められます。
企業ごとにフォーマットや必要事項が異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。エントリーシートでは、なぜその企業なのか、自分はどのような価値を提供できるのかといった視点が問われます。
志望動機や学生時代に力を入れたことなど、よくある設問に対しては、単なる出来事の羅列ではなく、自分の考えや学びを含めたエピソードにすることが大切です。
また、複数の企業に応募する場合は、内容をコピーペーストするのではなく、それぞれの企業に合わせて文章を調整する必要があります。汎用的な表現ばかりにならないよう気をつけましょう。
書類提出には締切がありますが、直前に慌てて作ると内容が浅くなったり、誤字脱字が増えたりするリスクがあります。余裕を持って準備を進め、完成後は必ず見直しをしてください。
提出前に第三者に添削してもらうのもおすすめです。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、ES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
④選考試験と面接に備える
書類を提出すると、多くの企業では選考試験や面接が実施されます。とくに人気のインターンでは応募者数が多いため、しっかりとした対策が必要になります。
選考内容は企業によって異なりますが、SPIやWebテスト、性格診断、グループディスカッション、個人面接などが一般的です。
SPIなどの筆記試験は短時間で多くの問題を解く必要があるため、事前に問題形式を知っておくことが重要です。市販の問題集や無料の模試サイトなどを活用して、繰り返し練習しておくと安心でしょう。
面接対策としては、自分の話したいことを整理したうえで、想定質問に対して答える練習をすることが効果的です。
事業内容や理念、最近の取り組みなどを把握しておけば、受け答えに深みが出ますし、質問にも対応しやすくなります。緊張しやすい人は、模擬面接を何度か受けて場慣れしておくのも有効です。
選考に不安を感じる人も多いですが、事前準備を重ねておけば、自信を持って臨めるでしょう。
⑤最終確認をして準備を整える
インターンの参加が決まったら、当日までにやるべきことをひとつずつ確認していきましょう。集合時間や場所、持ち物、服装の指定など、事前に案内された内容をしっかり確認しておく必要があります。
うっかりミスを防ぐためにも、リスト化してチェックすると安心です。初日の印象はその後の評価にも影響するため、服装や言葉遣い、姿勢など、基本的なマナーにも注意を払いたいところです。
とくに対面型の場合、清潔感のある服装や時間厳守といった社会人としての基本が問われる場面が多くなります。
一方でオンライン開催のインターンでは、通信環境やZoomなどのツールの操作確認も忘れないようにしましょう。音声やカメラが正常に作動するか、背景が整っているかなど、事前にテストしておくと安心です。
また、インターン開始前に不安な点や不明点があれば、企業に遠慮せず問い合わせることも大切です。事前に解消しておけば、当日は落ち着いて参加できます。
準備を万全に整えることで、貴重な経験を最大限に活かせるでしょう。
インターンの探し方

インターンに参加するには、早めの情報収集と自分に合った探し方を知ることが大切です。やり方を誤ると、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。
ここでは、代表的なインターンの探し方を紹介します。
- 就活情報サイトを活用する
- 企業公式サイトやSNSをチェックする
- 大学のキャリアセンターや教授に相談する
- 合同説明会やイベントに参加する
- OB・OGや先輩に紹介してもらう
①就活情報サイトを活用する
インターンを探す際、もっとも手軽で多くの学生が利用するのが就活情報サイトです。
リクナビやマイナビ、あさがくナビなどの大手サイトでは、業界や地域、インターンの実施時期、日数、報酬の有無など、細かな条件で検索ができます。
特に短期インターンでは、募集期間が短かったり、応募開始からすぐに締め切られたりすることもあるため、サイトの「お気に入り登録」や「通知機能」を活用しておくと安心です。
また、エントリーやES提出までサイト上で完結できる場合も多く、手間を減らせる点もメリットです。ただし、選択肢が多すぎて逆に迷ってしまうケースもあります。
そのため、事前に自己分析をして「どんな経験を積みたいのか」「興味のある業界はどこか」を明確にしておくと、効率よく選べるようになります。
インターンの情報は時期によって大きく変わるので、定期的にサイトをチェックする習慣をつけておくことが成功の鍵となるでしょう。
②企業公式サイトやSNSをチェックする
企業の公式サイトやSNSは、インターン情報を直接得る手段として非常に効果的です。多くの企業では、採用ページにてインターンの概要やスケジュール、選考フロー、過去の参加者の声などを掲載しています。
中にはエントリーフォームが設けられており、その場で応募が完了することもあります。
SNSではX(旧Twitter)やInstagram、LinkedInなどで最新の情報を発信している企業もあり、採用担当者が直接投稿しているケースも見られます。
そこでは、インターンの裏話や日常の様子など、公式サイトには載っていない情報が手に入ることもあるでしょう。これにより、企業文化や社員の雰囲気をより具体的にイメージしやすくなります。
受け身の姿勢では情報は入ってきません。積極的にチェックしにいくことで、誰よりも早くチャンスをつかめる可能性が広がります。
③大学のキャリアセンターや教授に相談する
大学にあるキャリアセンターや指導教授は、就活を進めるうえでの強力な味方です。
とくにキャリアセンターでは、企業から直接送られてくるインターン募集情報が保管されている場合があり、それらは公には出回っていないこともあります。
利用することで、競争率の低い案件に出会える可能性もあるでしょう。また、キャリアセンターではエントリーシートの添削や面接練習など、実践的な支援も受けられます。
あまり利用されていない分、競争が激化していないという利点もあります。ためらわずにまずは一度足を運び、どんな選択肢があるのかを聞いてみてください。
④合同説明会やイベントに参加する
合同説明会や業界別イベントに参加することは、インターン探しの方法として非常に効果的です。1回の参加で複数の企業と直接話すことができ、比較検討がしやすくなります。
特に志望業界がまだ決まっていない段階では、さまざまな企業を知る貴重な機会になるでしょう。
会場では採用担当者と直接会話できるため、リアルな情報や、WEBでは得られない裏話なども聞けることがあります。
企業側も参加者の中からインターン候補を探していることが多く、熱意のある学生にはその場で特別な案内をしてくれる場合もあります。
地方に住んでいて会場に行きにくい場合は、オンライン開催のイベントも数多くあるため、積極的に参加を検討してみてください。
⑤OB・OGや先輩に紹介してもらう
OB・OGや先輩からの紹介は、信頼性の高いインターン情報を得る方法のひとつです。
実際にその企業で働いた経験がある人から直接話を聞けるため、仕事内容や雰囲気、選考時の注意点など、実践的な情報を入手しやすくなります。
紹介された側の学生も信頼を得やすく、安心して参加しやすくなります。一方で、自分から話しかけることに抵抗を感じる人も多いかもしれません。
その場合は、大学が提供しているOB・OG訪問システムを活用するとよいでしょう。メールや専用フォームを通じて連絡を取る仕組みが整っており、比較的ハードルが低くなっています。
また、SNSを通じて先輩や卒業生にアプローチする方法もあります。LinkedInなどのビジネス向けSNSでは、同じ大学出身者を見つけてつながることが可能です。
紹介を受けることで得られる情報には、公式ルートにはないリアルな声が詰まっています。勇気を出して一歩踏み出すことで、他の学生が得られないチャンスに巡り合えるかもしれません。
インターンに参加するメリットとは?就活への影響も解説

インターンシップに参加することで、就職活動の準備が一気に進みます。業界や企業の理解が深まるだけでなく、自分の適性や強みを実感できる貴重な経験になるでしょう。
さらに、就活を有利に進めるきっかけにもなります。ここでは、就活生にとってインターンに参加することで得られる主なメリットを紹介します。
- 業界・職種・企業理解を深める
- 志望動機と自己PRを強化する
- 早期選考や内定の機会を得る
- 就活仲間や社会人とのつながりをつくる
- 本選考に向けた準備を進める
①業界・職種・企業理解を深める
インターンに参加する大きな魅力は、業界や職種、企業の実情を自分の目で確かめられることです。
企業のウェブサイトやパンフレット、会社説明会だけでは見えてこない実際の雰囲気や業務内容を、肌で感じ取ることができます。
とくに、将来の進路に悩んでいる段階で複数の業界を比較したいときは、インターンを活用することで自分の視野を広げやすくなります。
たとえば、同じ「営業職」でも、業界や企業によって求められるスキルや働き方には大きな違いがあるものです。そうした違いに気づけるのは、現場に触れてこそ得られる実感でしょう。
また、現場の社員とのやりとりを通じて、自分に合う社風や価値観にも目を向けることができます。「なんとなく興味がある」から「この会社で働きたい」へと、就職観が変わっていくケースも少なくありません。
迷っている時期にこそ、一度参加しておくことで進路選びの判断材料が得られます。
「企業分析がうまくできない…しっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる企業分析シートをを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、シートの構成に従って作成するだけで企業分析がスムーズに行えるので、苦手意識やめんどくささがある方におすすめですよ。
②志望動機と自己PRを強化する
就活で重要視される志望動機と自己PRは、多くの学生が悩むポイントです。企業研究や自己分析だけでは、どうしても抽象的な内容になってしまうこともあるでしょう。
インターンに参加すれば、実際の業務や職場の雰囲気、先輩社員の働き方を目の当たりにすることができ、そこから得られた気づきや経験を通して、自分だけのエピソードが生まれます。
たとえば、「現場で見た課題にどう向き合ったか」「自分の強みをどのように活かせたか」といった具体的な話ができるようになるのです。
こうした実体験に基づいた内容は、面接官にも伝わりやすく、ありきたりな表現になりにくいという強みがあります。
また、インターン先での成功体験や失敗経験を冷静に振り返ることで、自分の成長につながる要素にも気づけるでしょう。
自分の言葉で自信を持って話せるエピソードを持っている学生は、選考においても評価されやすくなります。インターンは、そうした武器を身につける場として非常に有効です。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
③早期選考や内定の機会を得る
インターンに参加することは、企業との関係構築につながり、通常の選考フローとは異なる「特別ルート」への入り口となる場合があります。
実際、多くの企業がサマーインターンや長期インターンの参加者に対し、早期の説明会や選考会の案内を送っており、それは一般には公開されていない非公開ルートであることも少なくありません。
企業側にとっても、インターンを通して学生の性格や働き方、チームでの立ち回りを事前に知ることができるため、採用リスクを抑えられるというメリットがあります。
こうしたチャンスをつかむには、ただ参加するだけでなく、積極的に発言したり、課題に前向きに取り組んだりする姿勢が求められます。
早期内定が得られれば、就活全体にゆとりが生まれますし、他社選考にも冷静に臨むことができます。結果的に、本命企業の選考にも集中しやすくなるのです。
④就活仲間や社会人とのつながりをつくる
インターンでは、同じ時期に参加している学生との交流を通じて、自然と就活仲間が生まれます。
大学や学部の異なる学生と話すことで、自分の考え方を客観視できる機会にもなり、刺激を受けることが多くなるでしょう。
また、グループワークやディスカッションを通じて共に過ごす中で、自然と連絡先を交換したり、情報交換したりする関係になることもあります。
選考時期が近づいてきた際に、お互いの進捗や悩みを共有できる存在がいることは、大きな支えになるはずです。
信頼関係が築ければ、面接対策や企業選びの相談に乗ってくれるケースもあるでしょう。このような人とのつながりは、就活だけでなく社会人になってからも続くことがあり、人生全体の財産になっていきます。
⑤本選考に向けた準備を進める
インターンに参加することは、本番の就職活動に向けた練習として最適です。なぜなら、企業での実務体験を通して、自然と就活で求められる力が養われていくからです。
たとえば、報連相(報告・連絡・相談)や、時間管理、タスクの優先順位づけなど、働くうえで必要な基礎スキルは、実際に現場に入ってみないと身につきにくいものです。
さらに、プレゼンやグループディスカッションといった実践型プログラムを経験することで、本選考でも自信を持って対応できるようになります。
また、フィードバックを受ける機会が多いのもインターンの特徴です。
社員から直接アドバイスをもらえるため、自分の改善点や伸ばすべき強みを具体的に知ることができ、就活準備を効率的に進められるでしょう。
早い段階でこうした経験を積んでおけば、本選考が始まったときにも焦らず対応でき、内定獲得の確率も高まります。単なる経験で終わらせず、成長の場として活かすことが大切です。
インターン申し込み時の注意点

インターンシップは就職活動のスタートラインともいえる大切な経験です。しかし、初めて申し込むときは「何をどのタイミングで準備すればいいのか」と不安になる方も多いでしょう。
ここでは、インターンに申し込む際に特に注意すべきポイントを5つに分けてわかりやすく解説します。準備不足や見落としを防ぐためにも、順番に確認していきましょう。
- スケジュールと申し込み時期を管理する
- 自己分析と目的設定を行う
- エントリーシートや履歴書を正確に作成する
- 事前課題や連絡事項を確認する
- 申し込み数とキャンセル対応を適切に行う
①スケジュールと申し込み時期を管理する
インターンに申し込むときは、企業によってスケジュールが異なるため、事前の情報収集と日程の管理が非常に重要です。
特にサマーインターンは春頃から募集が始まるため、大学3年生はできるだけ早めに動き始めるのが理想です。
出遅れてしまうと、人気の企業はすでに定員に達していることもあり、せっかく興味を持っていた企業に参加できないケースもあります。
申し込み時期を見逃さないためにも、就活専用のスケジュールアプリやカレンダーを使って、企業ごとの締切や説明会の日程を管理しましょう。
エクセルなどで簡単な表を作って、応募先を可視化しておくのもおすすめです。また、学業やアルバイトとの調整も忘れてはいけません。
計画的に行動することで、慌てることなく準備を整え、自信を持ってインターンに臨めるはずです。
②自己分析と目的設定を行う
インターンに参加する前には、なぜその企業を選ぶのか、どんな経験を得たいのかを自分の中で明確にしておくことが大切です。
自己分析を通して、自分の価値観や強み、興味のある業界や職種を把握しておくと、企業選びが格段にしやすくなります。
自己理解が浅いまま申し込んでしまうと、実際に参加しても得られる学びが少なく、時間だけが過ぎてしまうことになりかねません。目的を設定することで、インターン中の行動にも意味が生まれます。
たとえば「営業の現場を体験したい」「自分のコミュニケーション力を試したい」といった目標があれば、自然とその達成に向けて積極的に動けるようになります。
こうした姿勢は、企業の担当者にも好印象を与えるでしょう。また、目的意識があると、エントリーシートの内容も一貫性が出て説得力が増します。
自己分析には時間がかかりますが、今後の就活全体の軸を作るうえでも必要不可欠なステップです。焦らず丁寧に取り組んでください。
「自己分析がうまくできない…しっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる自己分析シートをを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、シートの構成に従って作成するだけで自己分析がスムーズに行えるので、自己分析に苦手意識がある方におすすめですよ。
③エントリーシートや履歴書を正確に作成する
エントリーシートや履歴書は、インターン選考で最初に見られる大切な書類です。
企業にとっては、限られた情報から応募者の人物像を判断するための材料になるため、内容と形式の両方がしっかりしていることが求められます。
誤字脱字や記入漏れがあると、それだけで印象が悪くなってしまうため、提出前には必ず何度も見直してください。特に注意したいのは、企業ごとに異なる指定フォーマットや記入ルールです。
自己PRや志望動機の文字数指定、ファイル形式、写真の有無など細かな違いがあるので、丁寧に確認して準備しましょう。
書類はあなたを映す鏡のようなものです。丁寧に仕上げれば、その誠実さはきっと相手にも伝わるはずです。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、ES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
④事前課題や連絡事項を確認する
インターンの申し込みが通ったあと、多くの企業からは事前課題や説明事項が送られてきます。
これらの対応を軽視してしまうと、インターン当日に準備不足で戸惑うことになったり、企業からの印象を悪くしてしまったりする可能性もあります。
事前の案内には重要な情報が詰まっているため、しっかりと確認してください。たとえば、事前課題の提出には期限が設けられていたり、形式に指定があったりする場合があります。
また、当日の持ち物や服装の指示が書かれていることも多いため、1つでも見落とすと不備の原因になります。
特にオンラインで行われる場合、参加URLや使用するツールの設定方法、通信環境の確認など、慣れていないと戸惑う内容も含まれています。
きちんと準備を整えて臨むことで、当日も落ち着いて行動でき、インターン全体を通して良い成果を得られるはずです。
⑤申し込み数とキャンセル対応を適切に行う
多くのインターンに参加すれば、それだけ経験が積めると考える人は多いかもしれません。しかし、無計画に申し込みすぎると、スケジュールが重なって参加できなくなってしまうおそれがあります。
キャンセルの連絡が遅れたり、無断で欠席したりすれば、企業からの信頼を失う原因にもなるため注意が必要です。申し込みの前に、自分の予定を必ず確認してください。
どうしても辞退しなければならなくなった場合には、できるだけ早めに丁寧な連絡を入れ、謝意と事情をきちんと伝えましょう。
キャンセル対応がきちんとしていれば、たとえ参加できなかったとしても、誠意ある印象を残すことができます。
企業側も事情を理解してくれることが多く、今後の選考や説明会での対応にもプラスになる可能性があります。
応募は「数」ではなく「質」が大事です。自分にとって本当に価値のある経験を得られるインターンを選び、責任ある行動を心がけてください。
インターン参加時期に関するよくある質問

インターンシップは、就職活動を見据えた重要な経験のひとつです。しかし、参加時期や応募の目安は学生によって異なり、情報を正しく理解しておくことが欠かせません。
ここでは、参加を検討するうえで多くの学生が疑問を抱きやすいテーマについて、順を追って解説します。
- 大学3年生からの参加は遅くないか?
- 参加しなくても就職は可能か?
- 看護学生・薬学生・公務員志望者の申し込み時期はいつか?
- 何社くらいエントリーするべきか?
- 26卒のインターン申し込みはいつからか?
①大学3年生からの参加は遅くないか?
大学3年生の夏以降からインターンに参加するのは、まったく遅くありません。
たしかに、1年生や2年生のうちから短期インターンに参加する学生も一部いますが、本格的に増えてくるのは3年生になってからです。
企業側も3年生を対象としたプログラムを多く用意しているため、今からでも十分にチャンスがあります。
業界が決まっていない段階でも、インターンを通じて興味のある分野や自分に合った仕事を見つけられることもあるでしょう。
重要なのは、「遅い」と感じて行動を止めてしまわないことです。今の段階から情報を集め、自分に合ったインターンに応募してみてください。
②参加しなくても就職は可能か?
インターンに参加しなくても、就職活動で内定を得ることは十分に可能です。実際、参加経験のないまま内定を取る学生も珍しくありません。
ただし、インターンに参加しておくと、業界研究や自己分析が深まるため、選考時に話せる経験が増えるなど、就活の準備がしやすくなるのも事実です。
また、一部の企業では、インターン参加者限定の特別ルートを設けている場合もあります。
参加しないからといって不利になるわけではありませんが、選択肢を広げる意味ではインターンに取り組むメリットは大きいといえるでしょう。
③看護学生・薬学生・公務員志望者の申し込み時期はいつか?
看護学生や薬学生、公務員志望者の場合は、民間企業と異なるタイミングでインターンや見学会が開催されることが多いです。
たとえば看護学生は、大学の実習スケジュールが詰まっているため、病院見学や学内の説明会を通じて就職活動を進めるのが一般的です。
薬学生も6年制で学ぶため、主に5年生ごろに病院や企業のインターンに参加する傾向があります。
公務員志望の場合は、夏を中心に行われる官公庁の職場体験や説明会がメインとなります。いずれも通常の就活とは少し異なるため、早めに情報を確認しておくことが大切です。
④何社くらいエントリーするべきか?
エントリーする企業数に明確な正解はありませんが、一般的には5〜10社程度が目安とされています。業界研究のために広く応募する場合もあれば、志望業界に絞って集中する方法もあるでしょう。
ただし、企業によっては書類選考や面接があるため、むやみに数を増やすと準備が雑になってしまうおそれがあります。数をこなすことよりも、1社ごとの応募理由や準備の質を大切にしてください。
自分の目的やスケジュールに応じて、無理のない範囲でエントリー数を調整することがポイントです。
⑤26卒のインターン申し込みはいつからか?
26卒の学生向けインターンの申し込みは、大学3年生の春から夏にかけて本格化します。大手企業では6月〜8月ごろにエントリーを受け付け、プログラムは8月〜9月に実施されることが多いです。
一方、外資系やベンチャー企業などは2月〜5月の間に募集を開始するケースもあります。また、年間を通じて常時募集している企業もあるため、定期的な情報チェックが欠かせません。
「夏からが本番」と決めつけず、早めの行動が有利な結果につながるでしょう。
最適なインターン申し込み時期と対策ポイントを押さえよう

インターンの申し込みは時期によって狙い目が異なります。結論から言えば、目的や学年、インターンの種類によってベストな申し込みタイミングは変わります。
だからこそ、早めに準備を始め、自分に合ったインターンに申し込むことが重要です。
まず、大学1・2年生は体験を重視したインターンで業界理解を深める時期、大学3年生や大学院1年生は就職活動を見据えた本格的なインターンに挑戦すべきです。
さらに、エントリーから参加までのステップや注意点を押さえておけば、申し込み後のトラブルも防げます。
インターンの申し込み時期を見極め、自分の成長につながる経験を計画的に積むことが、就職活動での成功に直結するのです。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









