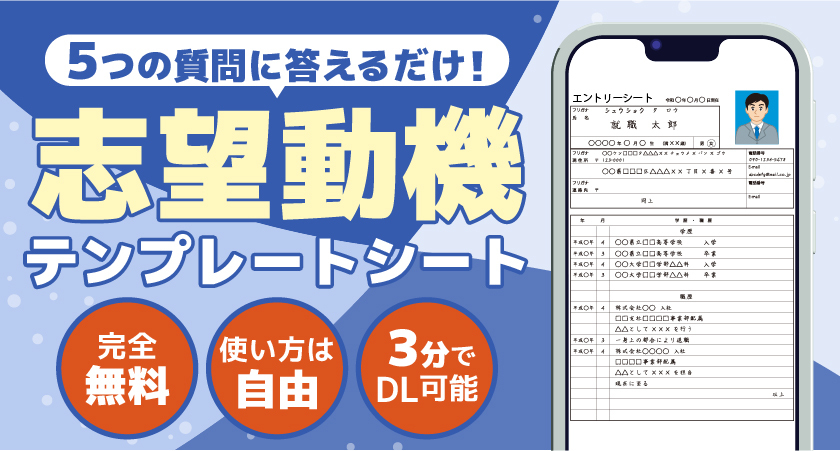設備管理の仕事に就きたいと考えているものの、志望動機の書き方がわからない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、設備管理会社への志望動機の書き方や例文、仕事の詳細に関しても紹介していきます。
ぜひ参考にして、希望の就職先への就職を果たしてください。
志望動機のお助けツール!完全無料
- 1志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を作成できる
- 2ES自動作成ツール
- AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
- 3志望動機の無料添削
- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します
設備管理とは?仕事内容を理解して志望動機に活かそう
設備管理は建物や施設における機器やシステムの維持・管理に重点を置く業務であり、その効率と安全性を高めるのが設備管理の役割です。
エアコン、昇降機、電気システムなど、建物で使用される多種多様な設備のメンテナンス、修理や点検なども業務内容に含まれます。
設備のパフォーマンスを保ちつつ、可能な限り長持ちされるため、定期的な検査や緊急対応が不可欠です。
利用者とコミュニケーションを取ることはもちろん、他の従業員と協力して進める仕事が多いので、コミュニケーション能力が求められる仕事でもあると言えるでしょう。
【企業視点】設備管理の志望動機で評価するポイント
設備管理の志望動機では、企業側がどんなポイントを評価するのかを理解しておくことが重要です。
ここでは、企業が注目する主な評価ポイントを解説し、魅力的な志望動機を作成するためのヒントを紹介します。
①仕事内容・大変さを理解した上で志望しているか
設備管理の志望動機では、仕事内容やその大変さを十分に理解していることを示すことが重要です。
設備管理は、施設や機器の安定稼働を支える責任の重い仕事であり、突発的なトラブルへの対応や定期的な点検業務が求められます。
そのため、具体的なエピソードを交えながら、こうした業務の重要性を理解していることをアピールすると良いでしょう。
例えば、現場の負担を軽減し設備の信頼性向上に貢献したい、と仕事への意欲を伝えるのも良いですね。
②長期的に働く意欲や主体性がありそうか
設備管理の志望動機では、長期的に働く意欲や主体性があることをアピールするのが重要です。
設備管理の仕事は専門的な知識や経験が求められ、継続的なスキル向上が必要となります。
そのため、「長期的に成長しながら会社に貢献したい」姿勢や、資格取得など主体的に取り組む意欲を具体的に伝えると良いでしょう。
チームや現場との連携を大切にしながら自ら積極的に行動する意志を示すことで、企業に安心感を与えられます。
③入社後に活躍できる適正がありあそうか
設備管理の志望動機では、入社後に活躍できる適性を具体的にアピールするのも大切です。
例えば、問題解決能力や現場でのコミュニケーション力、計画性や注意深さといったスキルを挙げると効果的でしょう。
また、過去の経験や学びを通じて得た技術的な知識や、資格取得の意欲を伝えることで、実務への即戦力性をアピールできます。
設備管理の仕事で活かせる資格4選

ここからは、設備管理の仕事で活かせる資格を4選紹介していきます。
それぞれのポイントを抑え、設備管理としての就活を有利に進めていきましょう。
①機械保全技能士
機械保全技能士は機械の保全に関する国会資格であり、名称独占資格です。
例えば工場を例に取ってみると、配電設備やガスの設備をはじめとした、点検が必要な部分が多くあります。機械保全技能士を持っていると、これら全体の設備の点検ができるようになります。
技能保全検定に合格すると機械保全技能士を名乗れるようになり、名刺などにも記載可能。企業によっては資格手当などが支給されますし、就活の際に保有していると企業から引っ張りだこでしょう。
ただし、3級は実務経験が問われませんが、2級は2年以上、1級は7年以上の実務経験が必要なので、新卒で就職を目指す人はひとまず、3級の取得を目指すことをおすすめします。
②第二種電気工事士
第二種電気工事士は電気工事を行う際に必要な資格であり、一般住宅や店舗など、「小規模施設」に分類される施設の電気工事に携われます。
屋内の配線や照明の工事はもちろん、コンセントの設置・交換、エアコン設置工事も可能です。ただし、600V以下で受電する設備に限るので注意しましょう。
また、第二種電気工事士を取得しておくと現場代理人、つまり現場監督のような役割をこなせます。
「居ないと工事ができない」という立場なので、需要が高いです。第二種電気工事士を取得している人が1人居るだけで業務の幅が広がるので、企業から人気の高い資格です。
③ボイラー技士
ボイラー技士の資格は、設備管理の分野で非常に有用です。
ボイラーの操作や保守点検を行う業務に必要不可欠であり、特にビル管理や工場設備の運用において需要が高い資格。
また、この資格を取得すると、安全な運転方法や法令に基づいた管理知識を身につけられるため、現場での即戦力として評価されるでしょう。
志望動機には、資格を取得した背景や、ボイラー管理を通じて設備の安定稼働に貢献したい意欲を盛り込むと効果的です。
④危険物取扱者(乙4)
危険物取扱者の資格は、設備管理において重要なスキルを証明するものです。
特に、危険物を取り扱う設備の管理や保守を行う現場で活かされます。
この資格を持つことで、安全基準を遵守しつつ、施設や作業環境を最適に保つ能力をアピール可能です。
また、消防法に基づいた危険物の知識を活用し、リスク管理や事故防止に貢献できる点も評価されるでしょう。
設備管理の志望動機のポイント3選

設備管理の志望動機の書き方についても、一緒に確認していきましょう。
近年人気の高い職業の1つなので、ポイントを抑え、他の志望者に差をつけられる、魅力のある志望動機を作成してください。
①なぜ設備管理を志望するのか明確にする
まず、何よりも大切なのは「なぜ設備管理の仕事を目指しているのか」を明確にすることです。
志望動機が曖昧だと、採用担当の方に「この人は本当に弊社でなければならないと思っているのだろうか?」と疑問視されてしまいます。
最初になぜ設備管理の仕事を目指しているのか、どのような点に魅力を感じたのかについて述べるようにしましょう。
企業への強い志望を表現することは確かに重要ですが、職業自体への憧れを具体的に解説するのも重要です。
②なぜその企業で働きたいのかを明確にする
続いては、なぜその企業で働きたいのかを明確にする必要があります。
設備管理の求人を出している企業は数多くあり、その中でなぜその企業を選んだのかを詳しく解説しましょう。
企業のホームページなどを見ればビジョンや理念について詳しく掲載されているので、参考にすると良いです。
企業は可能な限り志望度の高い人材を求めています。同じスペックならば「どこでも良いから働きたい」という人より、「ここでこそ働きたい」と考えている人が欲しいことでしょう。
③設備管理として活かせる自身の強みをアピールする
設備管理として活かせる自分の強みをアピールするのも非常に重要なポイントです。
当然ながら、自身の強みをアピールすることでより採用担当の方はあなたが実際に働いている姿をイメージできますし、活躍してくれる想像ができます。
それだけでなく、自身の強みをアピールするということで、働く意志が強いということもアピール可能です。
入社後の姿を具体的にイメージしているということは、「内定を出せば就職してくれる可能性が高い」とみなされ、採用担当の方も内定を出しやすいでしょう。
設備管理の志望動機の書き方3ステップ

ここからは、設備管理の志望動機を作成するにあたってのステップについて解説していきます。
それぞれのステップを抑え、採用担当の方に良い印象を与えられる志望動機を作成しましょう。
①結論ファーストで設備管理の志望理由を書く
まず最も大切なこととして結論ファースト、つまり最初に結論を書くことが挙げられます。
特に大企業の採用担当の方は大量の志望動機、自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を読み、特にありきたりで冗長な文章を読むことに疲れている場合も。
そこで少しでも集中を促し、内容を把握してもらうためにも、先に結論を書くようにしましょう。結論ファーストはビジネスの現場で高く評価される伝え方でもあるので、練習しておいて損はありません。
②志望理由の根拠となるエピソードを書く
志望理由の根拠となるエピソードを書くのも、魅力的な志望動機を作成するにあたって重要なポイントと言えます。
志望動機を作成するにあたり、どうしても企業に感じた魅力や、活かせるスキルの話だけでは説得力に欠けることが多いです。そこで、具体的なエピソードを盛り込みましょう。
その企業のサービスを自分や家族が体験した話でも良いですし、業界の魅力を感じたエピソードでも。具体的かつ、採用担当の方に響きそうなエピソードを探しましょう。
また、エピソードは文字数の調節がしやすいので、複数の企業を受けるにあたり、志望動機の指定文字数が大きく異なっていても調節しやすい点も魅力です。
③入社後に設備管理としてどのように活躍したいかを書く
入社後に設備管理として、どのように活躍したいかの展望を書くのも非常に重要です。入社後の展望を話すことで、採用担当の方も実際にあなたが働いているイメージができるでしょう。
実際に働いている姿、活躍している姿をイメージしてもらえるのはもちろんのこと、強い志望動機を持って応募していることが伝わりやすいのも理由の1つ。
実際に入社後の姿をイメージしているということは、入社する意志が強いということです。「滑り止め」程度の動機ではなく、内定が獲得し、入社する意志が強いことの証明にもなります。
【志望先別】設備管理の志望動機の例文2選

ここからは設備管理の志望動機の例文を、「商業施設」「工場」に勤めたいと考えている場合に分けて紹介していきます。
それぞれ、自分が志望する職場に近い方を中心に参考にしてみてください。
例文①: 商業施設
例文①
私は、商業施設の設備管理として貴社に貢献したいと強く志望します。
商業施設は多くの人々の生活と密接に関わっており、人々の快適な生活や安全に直結するからです。
私自身も、ある時、ショッピングモールでエスカレーターが突如停止し、多くの来場者に影響が出ている瞬間を目の当たりにしました。
それ以降、私はこの分野における専門的なスキルを持ち、設備のトラブルを迅速かつ的確に解決したいと感じています。
貴社が運営する商業施設は、その規模と高いサービス品質から常に多くの人々で賑わっており、設備管理の責任は重大です。
私は貴社において設備のメンテナンスと管理を通じて、安全で快適な環境を提供し続ける役割を果たし、訪れる全ての方々に安心感と信頼を提供したいと考えています。私の情熱と経験をもって、貴社の設備管理業務に寄与する所存です。
まず志望動機を示し、採用担当の方が主題を理解しやすいよう工夫がされています。
その後体験談や、どのように貢献するのかを話すことで入社後のイメージも伝えており、強く企業を志望していることが窺える構成です。
例文②: 工場
例文②
私の志望理由は、貴社の工場で設備管理を行い、生産効率の最適化と安全確保に寄与したいからです。
インターンシップにで工場で働き、その思いは一層強くなりました。
ある日、機械の故障により一部ラインが停止し、多大な生産遅延が発生したことがあります。
後に設備管理不足が原因であったことが分かり、生産現場の裏側で支える設備管理の重要性を痛感し、私はこの道を志しました。
貴社の工場はその先進的な技術と製品で多くの業界に影響を与えています。
私は、その生産の現場で、機械のメンテナンス、安全な運用の確保を通して、工場の更なる効率化と安全性の向上に貢献する所存です。
私の技術と知識、そして設備管理に対する情熱を貴社のもとで発揮し、一緒に新たな価値を創り上げていけることを強く願い、志望いたしました。
まず志望動機を明確にし、なぜ設備管理として働きたいのかを分かりやすく伝えています。
その後インターンシップでの経験を述べ、どのように設備管理として、そして業界活躍していくのかを述べているのもポイントです。
設備管理の志望動機で気をつけたい注意点
設備管理の志望動機を作成する際には、注意すべきポイントがいくつかあります。
本章では、企業に好印象を与える志望動機を作るために避けるべき内容や気をつけたい点を解説します。
①仕事を軽くみていると思われないようにする
設備管理の志望動機を書く際には、仕事を軽く見ていると思われないよう注意が必要です。
設備管理は、施設や機械の安全性と効率を保つための重要な役割を担っています。
そのため、単に「簡単そう」「楽に見える」といった印象を与える内容では、熱意や適性が伝わりません。
志望動機では、設備管理の責任感や専門知識の必要性を理解し、自分がどう貢献したいかを具体的に示しましょう。
②その企業でなくても当てはまる理由にしない
設備管理の志望動機では、「どの企業でも当てはまる理由」にしないことが大切です。
たとえば、「設備管理に興味がある」「技術を活かしたい」などの抽象的な内容だけでは、応募先企業への特別な思いが伝わりません。
その企業の設備や取り組み、特徴的な技術に共感した理由を具体的に挙げ、自分のスキルや目標と結び付けてください。
企業独自のポイントに触れることで、志望動機に深みを持たせることができます。
③自分がどう活躍・貢献したいかを言語化しておく
設備管理の志望動機を作成する際は、自分がどう活躍し、企業に貢献したいかを具体的に言語化しておくことが重要です。
たとえば、「安全で効率的な運用を支える」「省エネルギー対策を推進する」などの目標を明確に示しましょう。
また、過去の経験やスキルを基に、どう設備管理の業務に活かせるかを伝えることで、志望動機に説得力が増します。
自分の強みと企業のニーズを結びつけた内容にすると、意欲がより伝わるアピールが可能です。
設備管理の志望動機では自分の言葉で志望理由を伝えよう
今回は、設備管理の仕事を目指す人向けに志望動機の書き方や構成、例文を紹介してきました。
設備管理は責任が重い仕事ですが、同時にやりがいのある仕事でもあります。
ぜひ本記事を参考に、採用担当の方に響く志望動機を作成してください。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。