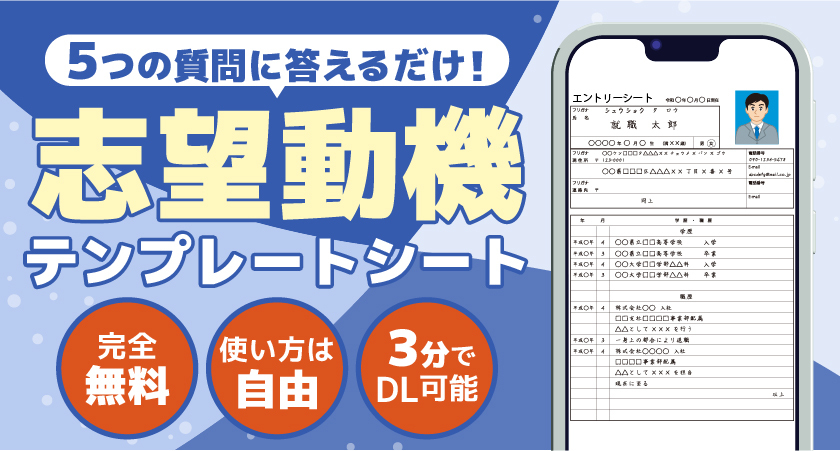臨床工学技士とは、医療機器の操作を担当する職種です。
しかし、どんな志望動機を練ればアピール力を高められるのかわからず、困ってしまう方もいるでしょう。
本記事では、臨床工学技士の概要や志望動機を作る際のポイント・書き方・例文・注意点について解説します。
志望動機のお助けツール!完全無料
- 1志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を作成できる
- 2ES自動作成ツール
- AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
- 3志望動機の無料添削
- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します
臨床工学技士とは?業務理解を深めて志望動機に繋げよう
臨床工学技士とは、生命維持装置などの医療機器を操作する専門職です。国家資格として認定されていて、医療機器の安全性や有効性を担保する役割を担当します。
現代の医療においては特にチームにとって欠かせない存在となっているのがポイントです。
複数の医療スタッフと協力し、患者の治療に携わるほか、安全に機器が動作するようにメンテナンスを行います。
心臓の手術や血液の浄化などをサポートするのも特徴です。
臨床工学技士の志望動機のポイント3選

臨床工学技士の志望動機を作る際には、ポイントを押さえておくとより印象に残りやすくなるのが利点です。ここでは、3つのコツについて紹介します。
①なぜ臨床工学技士として働きたいかを明確にする
なぜ臨床工学技士として働きたいのか、理由を明確にすることが大切です。
入院した家族の治療に尽力してくれた姿を見た、などの仕事に携わりたいと感じたきっかけを説明しましょう。
職種への理解が十分であることを伝えられるだけでなく、オリジナリティのある文章に近づけられます。
また、具体的なエピソードを添えて理由を補強するのも重要です。実際に仕事に就いた時、どのように貢献していきたいのか将来像を説明することも大切になります。
②なぜその施設で働きたいのかを明確にする
なぜその施設を働く場所として選んだのか、理由をはっきりと伝えることも重要です。
ただ自身が望む職種で働きたい想いだけを紹介してしまうと、どの施設でもよいと感じているのではないか、と捉えられるリスクがあります。
そのため、施設ならではの特色や魅力を感じた部分について言及しましょう。
施設の強みをしっかりと分析するには、複数の施設を比較してそれぞれのポリシーや力を入れている点などをリスト化することがおすすめです。
③臨床工学技士として自身の強みを伝える

仕事で自分の強みをどう活かせるのか、具体的な行動を交えて説明することも大切です。
集中力がある・責任感がある・粘り強く取り組めるなどの強みを伝えるだけでなく、どんな作業に活かせるのか一歩踏み込んで紹介することで、説得力のある文章を目指せます。
実際に携わることになる集中治療室での業務や管理業務などの内容にも触れて強みを紹介すれば、自身が活躍している姿を採用担当者に印象付けやすくなるのがポイントです。
臨床工学技士の志望動機の書き方3選

臨床工学技士の書き方の流れを把握すれば、より自然な流れの文章で内容を相手に伝えやすくなるのがメリットです。ここでは、書き方を3段階に分けて解説します。
①結論ファーストで志望理由を伝える
結論ファーストで志望理由を紹介すれば、問われていることに対して的確に回答を示せます。
コミュニケーション能力があることを強調できるほか、一番紹介したい内容を相手に伝えられるのがメリットです。
反対に結論を曖昧にしてしまうと、ほかの就活生の回答よりも完成度が低いと判断されてしまうため、注意しましょう。
また、結論は一文で簡潔に伝えることも重要です。長々と書かないことでストレートに回答が伝わりやすくなります。
②志望理由の根拠となるエピソードを伝える
次に理由の根拠になるエピソードを伝えれば、理由に説得力を持たせられます。
実際に自身が経験した出来事を述べることで、なぜこの仕事で貢献したいと感じているのか独自性のある回答ができるのがメリットです。
また志したきっかけの中で自身に起こった変化について紹介すれば、現在自分が抱えている仕事に尽力したいという熱意が本物であることを強調できます。
使命感を持って業務に臨む必要がある職種への適性があることを印象付けられるのがポイントです。
③臨床工学技士としての活躍の展望を伝える

最後には自身であれば臨床工学技士としてどのように活躍できるのか、展望を述べましょう。
自身が将来どのように貢献できるのか紹介すれば、施設側に自身を採用するメリットを想起させられます。
展望について説明する際には、自身がどんな姿勢や行動を心がけて、どんな業務に尽力していくつもりなのか具体的に述べることが重要です。
また、自身の強みの活かし方も同時に伝えることで、個性を印象付けられます。職種に求められる役割も踏まえて、将来どう活躍できるのかを説明しましょう。
【志望理由別】臨床工学技士の志望動機の例文3選

例文を確認すれば、どんな表現で熱意を書けばよいのか、具体的な伝え方をイメージしやすくなるのが利点です。ここでは、3つの例文を紹介します。
例文①: 患者に寄り添った治療を心がけているため
例文①
患者様の要望に寄り添った治療を心がけている貴院で、臨床工学技士として患者様の健康に貢献したいと感じ、志望いたしました。
私の祖父は透析を必要としていて、病院でリラックスしながら透析の時間を過ごせるよう工夫してくださったことで、治療を継続しやすくなったと話していました。
私は祖父の姿から、臨床工学技士として患者様がより快適に過ごせるよう工夫することで、心身への負担を軽減できることを学びました。
貴院は患者様の要望に合わせて適した治療法の選択肢を提供することを理念として掲げております。
私は貴院で臨床工学技士として業務を丁寧に遂行し、学会への参加などにも励んで貢献できるように努めてまいります。
上記の例文では家族が治療を受けている姿を通して、患者様に寄り添うことの大切さを学んだと紹介しています。
施設が掲げる理念に共感した上で、貢献できるよう努力する姿を想起させているのが特徴です。
例文②: より多くの命を救うため
例文②
新薬の開発事業を行い、患者様に新たな選択肢を提供している貴社で、患者様が望む新薬開発に尽力したいと感じ、志望いたしました。
私には、臨床工学技士として血液浄化治療に携わった経験があります。前職の業務に携わりながら、より多くの命を救って患者様の快適性を追求していくには、新薬の開発が必要であることを実感いたしました。
貴社は高度な専門性を活かした医薬品開発に注力しており、より早く新薬を提供するために新たな治験システムを導入しております。
私は貴社で循環器治療に携わった際に会得した知識や経験を活かし、患者様が求めている新薬の開発に貢献できるよう、尽力してまいります。
上記の例文では、新薬開発事業を展開している会社の強みについて言及して、自身の熱意を強調しています。
また、職種を通してどんな知識を得たのか伝え、会社に貢献できるスキルを所持していることを伝えているのもポイントです。
例文③: 患者との密接なコミュニケーションに惹かれたため
例文③
患者様の精神面でのケアにも力を入れ、密接なコミュニケーションを心がけている貴院で、臨床工学技士として患者様のサポートに尽力したいと感じ、志望いたしました。
私は病院での研修を通して、患者様とどう接するかどうかによって患者様が抱える不安やお悩みを軽減できることを学びました。そして、患者様にわかりやすく説明を行い真剣に向き合う姿勢を身につけました。
貴院は治療で入院されている患者様に精神科の医師によるケアも導入していて、患者様のQOL向上に尽力しております。
私は貴院で、臨床工学技士として医療スタッフの方と連携しながら、患者様がご不安なく過ごせるように接して環境を整えながら治療に貢献してまいります。
上記の例文では、病院の強みと自身が経験を通して実感した事柄を結び付けることで、熱意があることを印象付けています。
病院が行っている施策についても触れて、自分はどのように携わりたいのか紹介しているのも特徴です。
臨床工学技士の志望動機作成時の注意点2つ

文章を作成する際の注意点をチェックすれば、悪印象に陥らないよう対策した文章に仕上げられます。注意するべき箇所は、以下の2つです。
①他の施設にも当てはまる志望動機にならないよう意識する
他の施設にも当てはまるような抽象的な理由は挙げないことが重要です。施設ならではの特徴にしっかりと言及できていない文章は、熱意が足りていない印象に陥ってしまいます。
施設の設備が充実していることや、患者への接し方に共感したことなどを挙げて、自身がどのような魅力を感じたのか説明することを心がけましょう。
文章を作る前に他の施設もチェックして、述べようとしている特色が被っていないか確認することもおすすめです。
②志望動機に待遇を挙げるのは避ける
待遇について述べるのは、自身の利益しか考えていない印象になるため避けましょう。
勤める場所を探す際には待遇面もチェックすることも多いですが、施設に提出する文章の中で言及してしまうと不誠実な印象になるリスクがあります。
福利厚生などが整っている点に魅力を感じていても、文章の中では自身を採用することで施設側がどんなメリットが得られるのかに重点を置いて説明することを意識しましょう。
臨床工学技士の志望動機ではその施設で働きたい理由が重要
臨床工学技士の志望動機を述べる際は、なぜ該当施設で働きたいと感じたのか紹介することが重要です。
自身の強みや志したきっかけ、将来どのように活躍したいのかを具体的に述べて、印象に残る文章を提出しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。