年収を計算する際に、給与やボーナスはどのように扱うのでしょうか?例えば、手取りは少なくてもボーナスが多くて、ボーナスを含む年収が多い人もいるかもしれません。
そこで、本記事では年収やボーナスの定義から、年収やボーナスに関係する用語まで詳しく解説します。気になっている人はぜひ参考にしてくださいね。
企業分析をサポート!便利ツール集
- 1適性診断|企業研究
- ゲットした情報を見やすく管理!
- 2志望動機テンプレシート|楽々作成
- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!
- 3志望動機添削|プロが無料添削
- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!
年収にボーナスは含む!

年収は法律用語ではないため、人によって考え方が違う場合もあります。
ただし、一般的に広まっている認識は以下の2点です。この機会に年収の計算方法を確認しておきましょう。
①年収は1年間の間に会社から支払われる総支給額のこと
年収とは、1年間で企業から受け取る総支給額のことです。したがって、毎月支払われる基本給を12倍した額のことではありません。
基本給に月々固定で支給される手当てを加算したものが月給ですが、年収を12で割ったものは月収なので、月給や基本給とは意味が少し違います。
年収は健康保険料や厚生年金保険料のほか、所得税や住民税が控除されていない状態の支給額です。すなわち、税金や社会保険が引かれる前の金額を指しています。
会社員の場合に年収は、企業から年末に配布される源泉徴収票によって確認できるでしょう。
②企業のことを調べて出てくる年収にはボーナスは含む
年収と記載されていれば、基本給、手当、ボーナスを全て含んだ一年間に受け取る額のことだと考えていいでしょう。
企業の賃金を比べる場合には、文言に気をつける必要があります。
「毎月の支払いは少ないけどボーナスが多い」とか、「ボーナスはないけど手取りが多い」のように、会社ごとに大きく違うためです。
企業の募集要項には月収を記載している場合も多く、月収が判明すれば月収×12で年収も算出できるため、企業を比較するときの目安になるでしょう。
知っておきたいボーナスのこと4つ

年収には、ボーナスや賞与も含まれます。ボーナスの平均的な割合も押さえておきましょう。次に、ボーナスに関する、よくある4つの疑問を解消します。
①ボーナスとは?
ボーナスは毎月の基本給とは別に支給される給与のことで、「賞与」「夏季手当」「年末手当」「期末手当」とも呼ばれます。
ボーナスの支払い回数や支払い時期には、とくに規定はありません。
ボーナスの額は企業の業績や規模によっても大きく違いますが、一般的に大企業はボーナスが多く、中小企業では少ない傾向があるでしょう。
ボーナスの目安は、毎月の給料を基準にすると、大企業は3〜4ヶ月分、中小企業は1〜2ヶ月分と言われています。
②ボーナスの支払いは義務ではない
労働基準法では、ボーナスは企業側に支払い義務がないため、全ての企業で支給されるわけではありません。
中にはボーナスが年収に含まれていない企業もあり、支給されるとしても支給の有無や金額はその年の業績で変動する可能性があります。
ボーナスを当てにしすぎると、突然支給がなくなった場合に、生活に困るかもしれません。
企業のボーナスの有無や支給の基準は、思い込みで判断せずに、会社の採用ホームページや求人情報をチェックしておきましょう。
③ボーナスが支払われる時期は夏と冬の2回
企業によっても違いますが、ボーナスは夏(6月下旬~7月上旬)と冬(12月)の2回が基本です。中には3回以上支払う会社もある一方で、一度も支給しない会社もあります。
ボーナスがない会社よりボーナスの回数が多い方が、年収も高いと思うかもしれませんが、一概にそうとは言えません。
ボーナスがない会社の中には、月々の給与が多い場合もあるためです。
ボーナスは変動しやすいですが、一度定めた給料を変えるのは難しいので、ボーナスがなくても月々の給与が多い方が、収入が安定していると言えます。
④新卒もボーナスをもらえる
ほとんどの企業では新入社員に対して、夏のボーナスが支払われているようです。
ただし、入社したばかりのため、夏の時点で新入社員が携わる仕事は限られており、支給額は寸志として少量になります。
会社の業績が順調であれば、冬のボーナスの平均額は1~2ヶ月分と言われており、新卒の月給平均から計算すると、20万円~40万円程度になると予想できるでしょう。
もちろん、夏や冬のボーナスの平均額は、企業の規模や業種によって差があります。
ボーナスの計算方法

ボーナスの計算方法は企業によって異なりますが、「基本給×◯ヶ月分」としている会社が一般的です。
例えば、基本給が20万円で、基本給の2ヶ月分を支給する場合には、ボーナスは20万円×2ヶ月=40万円となります。
ただし、業績や個人実績による査定で変動する可能性があるでしょう。手取り金額を出すためには、上記から税金が引かれるため、正確に税金の計算も必要です。
業界によってもボーナスの額は違うため、自分が属する業界の平均値をチェックしてみましょう。
年収にボーナスを含むかどうか調べる方法3つ

就職や転職をする場合に、ボーナスの金額は誰でも気になります。しかし、就活でボーナスのことをチェックする際に、調べ方によっては注意が必要です。
そこで、ボーナスに関して調べる3つの方法を紹介します。
①口コミサイトで調べる
求人サイトや口コミサイトの情報をチェックしてみましょう。企業で働いている社員のほか、元社員や就活生が、企業に関する意見を口コミサイトに投稿しています。
口コミサイトでは、年収やボーナスだけでなく、人間関係や風通しの良さのような、あらゆる情報を調べられるでしょう。
ただし、いずれも個人がインターネット上に投稿している情報であり、信頼度はあまり高くありません。
投稿する人間の性質上、悪い口コミの方が良い口コミより信頼性が高いと言われていますが、いずれも参考程度にしましょう。
②OBOG訪問で調べる
OB訪問とは、会社や仕事に関する質問をするため、企業で実際に働いている先輩を訪ねることです。
仕事の実情や本音を聞けるため、求人情報やOB・OGを通して、年収やボーナスに関する正確な情報が得られる場合もあります。
ただし、真っ先に「ボーナスは何ヶ月分貰えますか?」のような質問をしたり、年収やボーナスの金額を聞かないように気をつけましょう。
OB・OG訪問ではマナーをしっかり理解して、適切な質問を準備する必要があります。
③面接の自然な流れで聞くのはOK
面接でも質問できますが、聞き方を間違えると悪い印象になるため、慎重に聞く必要があります。まず仕事内容の質問から始めて、自然な形で年収やボーナスの話に繋げるのが理想的です。
例えば、逆質問で唐突にボーナスのことを聞くのも避けましょう。言い方にも注意が必要で、「ボーナス」や「賞与」のような単語を使ってストレートに聞くことも好ましくありません。
具体的には、「参考までにお聞きしたいのですが、年収の目安はどれくらいになりますか?」と聞くと、年収から逆算して考えて、自分でボーナスの有無や金額を計算できるでしょう。
直接的に質問するのではなく、ボーナスを含んだ年収の目安を聞くとスマートです。聞き方を工夫すると、相手が説明するときに、自然とボーナスについても話してもらえる場合もあります。
ボーナスがない会社もある
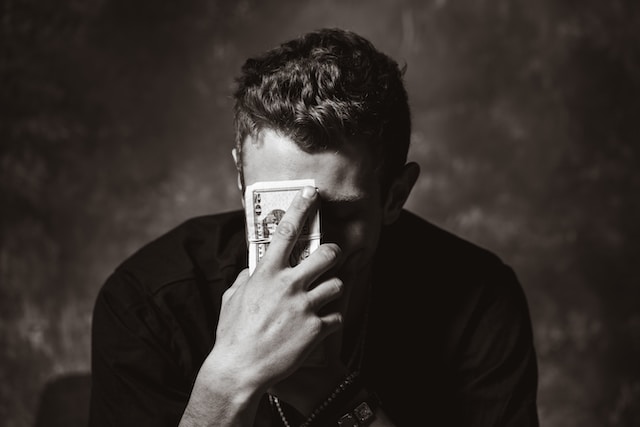
ボーナスが出ない企業は、夏・冬ともにおよそ3割と言われています。ボーナスが出ない場合が多い企業を2種類紹介します。
①ベンチャー企業
ベンチャー企業はボーナスが出ない代わりに、「インセンティブ制度」を導入している場合も少なくありません。
インセンティブ制度とは、業績利益に貢献した社員に対して、給与以外の成果報酬を与える制度のことです。
実績を上げれば報酬が支給される仕組みで、社歴や年齢に関係なく評価されるので、社員としてもやりがいを感じるでしょう。
また、ベンチャー企業は月給が高い傾向にあるため、年収単位では大手企業と変わらない可能性もあります。
②中小企業
一般的に、大企業はボーナスが多く、中小企業では少ない傾向が見られるでしょう。金額的には、大企業は40〜50万円程度、中小企業は10〜20万円程度とされています。
ボーナスの平均支給額は企業の規模のほか、業種でも異なるでしょう。とくに業績が悪化している場合には、ボーナスの支給がない可能性もあるため、注意が必要です。
その一方で、何かビジネスが当たった際に、多額のボーナスが還元される場合もあるでしょう。
年収とボーナスの関係をしっかりと理解しよう

今回は年収やボーナスの定義から、調べ方や計算方法まで紹介しました。
ボーナスがないものの手取りが多い企業もあるため、ボーナスがなくても年収が低いとは限りません。
インセンティブ制度のように、企業独自の方針や判断も違うので、報酬にはあらゆる付与の方法があります。
ボーナスに固執しすぎず、自分にとってどのような給与の形が良いのか考えてみましょう。本記事を参考にして、自分に合った企業を選択してくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









