「職業別の年収を知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
職業別の年収を深掘りするには、日本の平均年収や男女別の平均年収を知ることが大切です。
本記事では、日本の平均年収や業種別平均年収を元に、年収の高い職業について紹介します。
将来のためにどの職業が自分に向いているか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
企業分析をサポート!便利ツール集
- 1適性診断|企業研究
- ゲットした情報を見やすく管理!
- 2志望動機テンプレシート|楽々作成
- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!
- 3志望動機添削|プロが無料添削
- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!
日本の平均年収

日本の平均年収は、令和5年賃金構造基本統計調査によると、318万3,000円です。令和元年(2019年)から令和3年(2021年)の3年間は307万円から大きく変化はありませんでした。
しかし、令和4年(2022年)は311万円8,000円と4万円ほど増額し、令和5年はさらに増額しています。平均年収が変化した理由の1つは、最低賃金が増額されたためです。
また、日本の平均年収は性別や年齢・業種でも異なりますよ。以下では、男女年齢別の平均年収と業種別平均年収について紹介します。
男女年齢別の平均年収
令和5年賃金構造基本統計調査によると、男性の平均年収は350万9,000円、女性の平均年収は262万2,000円です。
| 年 | 全体の平均年収 | 男性の平均年収 | 女性の平均年収 |
| 令和元年(2019) | 307万7,000円 | 338万円 | 251万円 |
| 令和2年(2020) | 307万7,000円 | 338万8,000円 | 251万8,000円 |
| 令和3年(2021) | 307万4,000円 | 337万2,000円 | 253万6,000円 |
| 令和4年(2022) | 311万8,000円 | 342万円 | 258万9,000円 |
| 令和5年(2023) | 318万3,000円 | 350万9,000円 | 262万2,000円 |
男女の差は約88万円になります。また、平均年収の差は性別だけでなく、年齢でも差があります。以下の表は、令和元年から令和5年までの男女年齢別の平均年収をまとめたものです。
| 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
| ~19歳 | 190万円 | 191万1,000円 | 188万4,000円 |
| 20~24歳 | 224万6,000円 | 229万3,000円 | 219万6,000円 |
| 25~29歳 | 258万3,000円 | 267万8,000円 | 245万8,000円 |
| 30~34歳 | 286万円 | 302万1,000円 | 259万6,000円 |
| 35~39歳 | 314万8,000円 | 337万9,000円 | 270万1,000円 |
| 40~44歳 | 338万8,000円 | 371万8,000円 | 276万8,000円 |
| 45~49歳 | 355万7,000円 | 396万9,000円 | 281万7,000円 |
| 50~54歳 | 371万1,000円 | 417万7,000円 | 285万9,000円 |
| 55~59歳 | 376万4,000円 | 427万4,000円 | 281万7,000円 |
| 60~64歳 | 305万9,000円 | 334万2,000円 | 246万6,000円 |
| 65~69歳 | 269万8,000円 | 293万3,000円 | 217万1,000円 |
上記のように、男女とも年齢に応じて平均年収が高まる傾向にありますが、非正規雇用の多い女性は大きな差はないことがわかります。
反対に男性は年齢に応じて管理職に昇進するなどの関係で、50代以降は年収400万円を超えているようです。
業種別平均年収
平均年収は、業種によっても異なります。以下の表は、令和5年賃金構造基本統計調査の「産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」を元にした業種別の平均年収です。
| 産業 | 平均年収 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 366万7,000円 |
| 建築業 | 349万4,000円 |
| 製造業 | 306万円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 410万2,000円 |
| 情報通信業 | 381万2,000円 |
| 運輸業、郵便業 | 294万3,000円 |
| 卸売業、小売業 | 319万6,000円 |
| 金融業、保険業 | 393万4,000円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 340万8,000円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 396万6,000円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 259万5,000円 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 278万7,000円 |
| 教育、学習支援業 | 377万2,000円 |
| 医療、福祉 | 298万円 |
| 複合サービス事業 | 302万円 |
業種別の平均年収の中で最も高いのは、電気・ガス・熱供給・水道業の410万2,000円です。この産業は35歳以降から管理職になる影響などで大幅に年収が高くなる傾向にあります。
また、反対に平均年収が低い産業は、宿泊業、飲食サービス業です。他の産業と比較して年齢でも大きな年収差がないため、転職者が多い産業でもあります。
表全体を見ると日本の平均年収より大きく差のある産業はありませんが、年収が増額される年齢は産業によって異なるため、希望年収のある方は表を参考にして、自分に合う産業を見つけてみてください。
【男女共通】職業別の年収ランキングTOP10を解説

職業別の年収ランキングTOP10を、令和5年賃金構造基本統計調査を元に解説します。
上記は年収の高い職業について触れていますが、実際の年収は企業によって異なります。そのため、平均年収は参考程度に確認し、興味ある企業がある方は自身で深掘りしてみてください。
①航空機操縦士
職業別の年収ランキング1位は、航空機操縦士(パイロット)です。厚生労働省によると、航空機操縦士の年収は1779万と日本の平均年収より約1460万円の差があります。
航空機操縦士の年収が高い理由は、「事業用操縦士」または「定期運送用操縦士」のどちらかの国家資格を取る必要があるためです。
この資格は一定の経験が必要であり、取得難易度が高いため、日本では7,040人しか航空機操縦士として働いていません。
また、航空機操縦士は多くの人の命を預かる責任重大な仕事であることや、勤務時間が変動的で外泊もあるなど不規則な生活になりやすいことが高収入の理由です。
②医師
2番目に平均年収の高い職業は、医師です。内科医・外科医ともに、厚生労働省によると平均年収は1436万5,000円となっています。
医師になるには6年生の大学医学部へ入学する必要があり、医師国家試験に合格しても、さらに2年の研修を積まなければ医師として活躍できません。
また、患者の命を預かる責任重大な仕事であるため、平均年収が高いと言えます。
ただし、医師は平均年収が高いことはメリットですが、24時間体制の対応が必要な可能性もあります。特に勤務医は非常に激務なため、開業医として働く方も少なくありません。
③法務従事者
厚生労働省によると、法務従事者の平均年収は1121万7,000円です。法務事業者とは、裁判官・弁護士・検察官など司法に関連する職業を指します。
1番身近な弁護士は司法のプロとして働くために、難易度の高い「司法試験」に合格する必要があるため年収が高い傾向です。
ただし、弁護士は試験に合格してすぐに独立開業できるわけではなく、経験を積むために法律事務所に所属します。経験が無い状態で開業しても依頼がなく、弁護士として活躍できなくなるためです。
そのため、法律事務所に所属している間は勤務年数や経験に応じて平均年収が下がる可能性があります。
④大学教授(高専を含む)
厚生労働省によると、大学教授(大学教員)の平均年収は1074万7,000円です。大学教授は、専門分野の研究・学生への指導・大学の管理など、様々な仕事があります。
専門分野を研究するために様々な知識が必要なため、平均年収が高い傾向にあります。
また、大学教授は大学内での活動だけでなく、書籍の出版やテレビ出演などの副業を行うと年収が高くなるでしょう。
⑤その他の経営・金融・保険専門職業従事者
次に平均年収の高い職業は、ファイナンシャルプランナー・証券アナリストなど、経営・金融・保険専門職業事業者です。
厚生労働省によると平均年収は947万6,000円と、日本の平均年収より約629万円の差があります。
ファイナンシャルプランナーや証券アナリストは金融や保険のプロとして、顧客や企業の資金にアドバイスする仕事です。
ファイナンシャルプランナーは1級から3級まで階級が分かれていて、特に1級は合格率10%程度と非常に難易度の高い資格となっています。そのため、様々な企業からの需要が高く、年収も高い傾向にあります。
⑥歯科医師
歯科医師は内科医や外科医に比べて平均年収は低めですが、厚生労働省によると平均年収は923万4,000円と日本の平均年収より高い傾向にあります。
歯科医師が内科医や外科医より年収が低い理由の1つは、開業医が多いためです。
実際に歯科医師は、66%が開業医として活躍しています。開業医が多いと競争率が高まり、顧客の確保が難しいため、年収が低くなります。
しかし、開業する地域や顧客確保の工夫次第では、内科医や外科医同様の年収を獲得できる可能性もあるでしょう。
⑦管理的職業従事者
管理的職業従事者とは、課長以外の役職を持っている方や工場長、支配人などが該当します。なかでも、厚生労働省によると総務課長の平均年収は885万3,000円です。
ただし、管理的職業従事者といっても、所属する組織によって平均年収は異なります。また、新卒から管理的職業従事者になることはありません。
管理的職業重視者になるには、同じ組織内で長期間勤務することが条件です。
ただし、経験豊富で企業の求める人材であれば転職で管理的職業従事者になれる可能性もあるため、転職活動の参考にしてみてください。
⑧大学准教授
大学准教授の平均年収は862万1,400万円です。大学准教授とは、大学教授の手前の役職であり、教授と同じ研究や学生の指導などを行います。大学准教授から大学教授になるには、主に年功序列で変化することが多いです。
大学教授と大学准教授の年収差は、約212万円と大きな差があります。そのため、大学内で大学教授に慣れる可能性が低い場合は、転職で大学教授を目指す人も少なくありません。
大学教授になるには経験が必要なだけでなく、研究上の業績が必要です。大学准教授から大学教授を目指す方は、勤務を続けるか、求める人物像に自分が当てはまる大学への転職がおすすめですよ。
⑨高等学校教員
教員関連で大学教授・大学准教授に続いて年収が高いのは、高等学校教員です。
厚生労働省によると高等学校教員の平均年収は699万2,000円と、小学校教員や中学校教員より約40万円ほど高い傾向にあります。
高等学校教員は中学校に比べて高いレベルの教育を求められます。また、工業や商業などは専門知識が必要なため、教員のなかで高い年収です。
⑩大学教師・助教
最後に年収の高い職業は、大学教師・助教で平均年収は692万2,400円です。
大学教師・助教とは、教授や准教授に次ぐ職員で、サポートなどを主に行いますよ。
大学へ就職すると大学教師や助教から始まり、研究の業績や経験を積むと大学助教授や教授を目指せるため、多くは大学教師・助教を目指します。
【男性】職業別の年収ランキングTOP

男性の職業別の年収ランキングをTOP10で紹介します。
| ランキング | 職業 | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 航空機操縦士 | 1,594万円 |
| 2位 | 医師 | 1,356万円 |
| 3位 | 大学教授(高専を含む) | 1,080万円 |
| 4位 | 法務従事者 | 952万円 |
| 5位 | 大学准教授(高専を含む) | 870万円 |
| 6位 | 管理的職業従事者 | 865万円 |
| 7位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 812万円 |
| 8位 | 歯科医師 | 788万円 |
| 9位 | 小・中学校教員 | 777万円 |
| 10位 | 公認会計士、税理士 | 742万円 |
男性の職業別の年収ランキング1位は、航空機操縦士です。日本全体の職業別の年収ランキングも航空機操縦士が高収入であるため、男性のランキングでは1位となっています。
次に医師・大学教授がランクインしていて、男性の場合は全体のランキングと大きな差はないでしょう。
どの職業も国家資格と経験が必要なため、高収入を目指す方が簡単に就職できる職業ではありません。そのため、高収入を目指す場合は、高校生から資格取得と経験を積める大学に進むための準備が必要です。
【女性】職業別の年収ランキングTOP

女性の職業別の年収ランキングは以下の通りです。
| ランキング | 職業 | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 医師 | 1,017万円 |
| 2位 | 大学教授(高専を含む) | 966万円 |
| 3位 | 法務従事者 | 956万円 |
| 4位 | 航空機操縦士 | 853万円 |
| 5位 | 歯科医師 | 851万円 |
| 6位 | 大学准教授(高専を含む) | 810万円 |
| 7位 | 管理的職業従事者 | 738万円 |
| 8位 | 小・中学校教員 | 647万円 |
| 9位 | 大学講師・助教(高専を含む) | 614万円 |
| 10位 | 高等学校教員 | 602万円 |
女性の職業別の年収ランキング1位は、医師となっています。全体のランキングで1位だった航空機操縦士は5位で、勤務時間が安定していないことなどが、女性が就職しても高収入にならない理由と考えられるでしょう。
また、航空航空機操縦士は主に男性が多く、女性は全体の1.7%しかいません。
次に大学教授・法務従事者となっていて、高収入の職業は男性と大きな差はありません。しかし、平均年収が男性より低いため、他の職業も女性の働き方が年収に大きく影響しているようです。
年収の高い職業の特徴

以下では、年収の高い職業の特徴を紹介します。
年収の高い職業の多くは、上記の特徴に当てはまることが多くあります。
そのため、年収の高さだけではなく、難易度や責任の重さを考えながら、就職に向けて活動することが大切です。
①希少性が高い
年収の高い職業の多くは、国家資格の難易度が高く、希少性が高いことが理由として挙げられます。
最も年収の高い航空機操縦士は、国家資格「第一種航空身体検査証明書」を取得するだけでなく、国が定めた条件を満たす必要がありますよ。
例えば、航空会社の機長になる場合は「総飛行時間1,500時間以上」を満たさなければいけません。また、身体検査にも合格する必要があるなど、航空機操縦士は全てを合格した人のみがなれる希少性の高い職業です。
その他、医師や法務従事者なども難解な国家資格に合格して経験を積む必要があるため、希少性の高い職業は比較的年収が高いといえるでしょう。
②専門的知識が必要
年収の高い職業は、専門的知識が必要なことが多くあります。航空機操縦士・医師・教員・法務従事者など、通常では学ばない学問などを勉強し、専門知識を得なければ、それらの職業に就職はできません。
そのため、多くは学生の頃から就職を目指すために勉強をします。また、多くは大学で学んだ後に資格取得することが多いため、大学に合格するための勉強も必要です。
専門的知識を持っている証拠として、国家資格が存在します。国家資格を取得してから経験を積むことで、記事内で紹介したランキングの年収を貰えるでしょう。
③経験が必要
年収の高い職業は、資格取得だけでなく、経験も必要です。例えば、航空機操縦士の場合は条件を満たす時間を操縦すること、医師は研修医として病院で勤務することなどがあげられます。
また、弁護士など資格取得後すぐに開業できる職業でも、経験がなければ集客ができず、収入に繋がりません。
そのため、多くの職業は希少性や専門的知識があるだけで高収入なのではなく、患者や顧客からの信頼のために経験を積んだのち、高収入に繋がります。
④責任が重大
年収の高い職業は、責任が重大なものが多くあります。
航空機操縦士や医師などは多くの人の命を、弁護士は人の将来を、ファイナンシャルプランナーは顧客の資金など、様々な人や物に対して責任が関わる職業です。
そのため、資格を取得できたとしても、責任感のない人は年収の高い職業には向いていません。高収入だからといって勉強するだけでなく、どのような責任があるかを確認することが大切です。
年収の高い職業に就くための国家資格一覧

以下では、年収の高い職業に就くための国家資格を一覧で紹介します。
- 定期運送用操縦士
- 医師免許
- 歯科医師
- 薬剤師
- 弁護士
- 社会保険労務士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁理士
- 行政書士
- 一級建築士
- FP技能検定
- その他
年収の高い職業に関係する国家資格は、医療や法律に関わるものが多くあります。また、一般建築士やFP技能検定など、お金に関係する国家資格も年収の高い職業を目指せる資格です。
しかし、上記の国家資格は全て難易度が高く、合格率が10%未満のものも多くあります。そのため、国家資格を取得するために、独学ではなく、大学に進む人が多くいますよ。
職業年収ランキングを参考に将来を考えよう
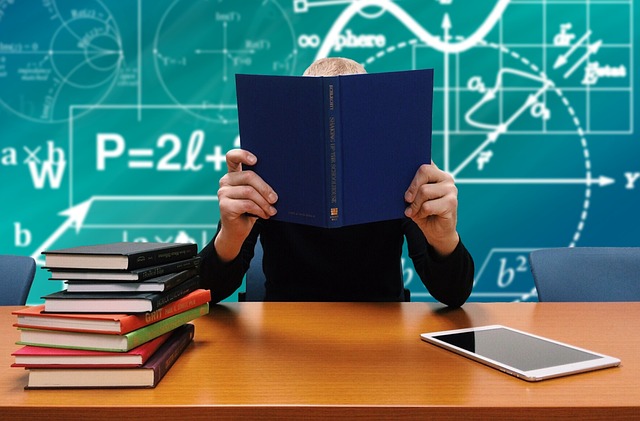
国家資格を取得したり経験を積むことで、航空機操縦士や医師など年収の高い職業を目指すことも可能です。
年収の高い職業は希少性も高いため、将来的に職を失う可能性も低いと言えるでしょう。
しかし高い年収をもらうには、学生の頃から必要な勉強をしたり環境を整える必要があります。
高収入の職業への就職を考えている方は、本記事の職業年収ランキングを参考に、将来を考えてみてくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









