【例文付き】自己PRで「調整力」を効果的にアピールするには?言い換えの具体例も紹介
自己PRで調整力があると伝えたいと考えている就活生も多いのではないでしょうか。調整力は多くの企業から評価される強みですが、効果的にアピールするにはいくつかポイントがあります。
本記事では、自己PRで調整力をアピールする際のポイントや注意点について解説します。
調整力を使った自己PRの例文も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。
「調整力」は就活面接の自己PRで使える効果的な強み!

「調整力」は就活面接で自分を効果的にアピールできる強みです。
実際の業務では、異なる意見や利害が存在するため、調整力は多くの企業が求めるスキルの1つです。
調整力をアピールする際には、単に調整力があると伝えるだけでなく、具体的な経験をもとに主体的に行動したエピソードを含めましょう。
「調整力」が企業から高く評価される5つの理由
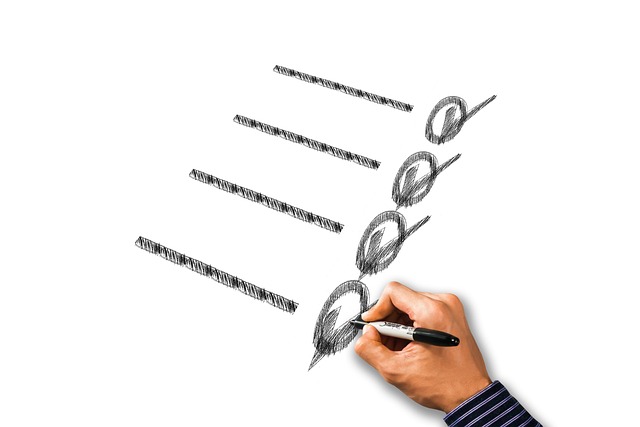
企業が新卒採用で求めるスキルとして、調整力が重要視されています。調整力は、さまざまな人と協力しながら目標達成に導くための能力です。
なぜ企業は調整力を重視するのでしょうか。ここでは、調整力が企業から評価される5つの理由について解説します。
①仕事上の問題を円滑に解決できる力があるから
1つ目の理由は、仕事上のトラブルや課題をスムーズに解決できるからです。
業務において問題が発生すると、関係者が互いに意見を主張し合い、場合によっては対立が生じることもあります。
しかし、調整力がある人は、問題の本質を理解し、関係者全員が納得できる解決策を導き出せますよ。
単に問題を解決するだけでなく、関係者の意見を汲み取り、互いの立場を理解したうえで対話を重ね、全員が納得できる解決策に導くため、企業にとって貴重な存在です。
②同僚やチームでスムーズに仕事ができるから
2つ目は、同僚やチームでスムーズに仕事を進められるからです。
特にプロジェクトを進める際には、複数の部門や職種のメンバーが関わるため、意見や進行方法が異なる場合も多く発生します。
調整力があると、メンバー間の意見をまとめ、全員が理解しやすい形で情報共有ができるため、全員が同じ目標に向かってスムーズに動き出し、円滑に業務が進行します。
また、調整力がある人は事前に問題の予測ができるため、トラブルを未然に防ぐことができ、プロジェクト全体の効率も高まるでしょう。
③顧客や取引先との利害対立を避けられるから
3つ目は、顧客や取引先との対立を避けられるからです。企業活動では顧客や取引先との関係が欠かせませんが、双方の意見が異なり対立が生じる場面も少なくありません。
調整力がある人材は、双方の意見を冷静に聞き取り、妥協点や共通の利益を見出す能力に優れているため、取引先との信頼関係を保ちながら、企業の利益も守れます。
また、双方が満足できる形で問題解決を進められるため、長期的な取引関係を築きやすくなります。
④目的や目標から逆算して動けるから
4つ目は、目的や目標から逆算して動けるからです。調整力がある人材は、単に現状を調整するだけでなく、最終的な目標を常に意識して行動します。
目的から逆算して、どのようなスケジュールやリソース配分が必要かを見極めることで、効率よくプロジェクトを進行できるでしょう。
例えば「次に何が必要か」「どのタスクが優先すべきか」などの判断を素早く行い、無駄な時間やコストを削減できます。
また、目標達成のための全体像を描き、そこに向けた最適な手段を導き出せるため、組織としても利益を最大化しやすくなるでしょう。
⑤リーダーシップを取ることができるから
5つ目は、リーダーシップを発揮できるからです
調整力を持つリーダーは、メンバーそれぞれの強みや特徴を把握し、役割を適切に分担できるため、全体のパフォーマンスを最大化することが可能です。
そのため、特に調整力の高いリーダーは、チーム全体の成果を向上させるうえで欠かせない存在と言えるでしょう。
「調整力」が高く評価される仕事・職業

調整力は、職場における調和を保ちながら業務を推進するために必要なスキルで、特に、部署や立場の異なる人々と協力する場面が多い職業において、調整力が大きな武器になります。
ここでは、調整力が特に評価される4つの仕事・職業を紹介します。
①公務員
公務員は市民や様々な関係者との調整が求められる職業です。日々の業務では、市民の声やニーズを反映させながら行政サービスを提供しなければなりません。
また、他部署や地域団体、他機関との連携が必要となるため、異なる意見や利害を調整する力が欠かせません。
例えば、ある地域のインフラ整備プロジェクトでは、住民の要望と予算の制約を調整する場面が多く、これをうまくまとめる調整力が業務成功の鍵となります。
②企画・開発職
企画・開発職は、部門を超えて多くの関係者と意見を調整しながら、プロジェクトを進行する場面が多い職種です。
特に製品開発や新サービスの立ち上げでは、マーケティング部門、技術部門、販売部門など様々な部署が関与し、それぞれの意見やニーズが異なることが一般的です。
このような状況で、意見の対立を円滑にまとめ、全体としての目標達成を促進する調整力が求められます。
調整力を発揮することで、プロジェクト全体がスムーズに進行し、より良い成果を上げられるでしょう。
③プロジェクトマネージャー
プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの全体管理を行う役割を担い、調整力が特に重要視される職業です。
プロジェクトには多くのメンバーや関係者が関わり、各人の役割や目標が異なるため、意見が食い違うこともあります。
そこで、各メンバーの意見や立場を理解し、妥協点を見つけながら、全体の方向性を調整する力が必要です。
具体的には、スケジュールの調整やリソース配分、問題解決において調整力が発揮されることにより、プロジェクトの円滑な進行が可能となるでしょう。
④営業職
営業職もまた、調整力が求められる職業の1つで、顧客との交渉や他部署との調整が必要な場面が多く、顧客の要望に応じつつ、社内リソースの調整も行います。
例えば、顧客のニーズを適切に汲み取り、製品やサービスの提供条件を調整することで、顧客満足度の向上に繋がります。
また、社内での調整を通じて、効率よくプロジェクトを進める力が必要でしょう。
「調整力」の自己PRのおすすめ構成【3ステップ】
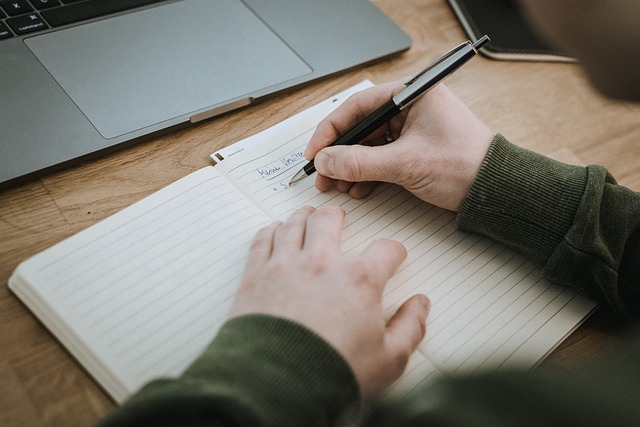
「調整力」をアピールする際は、自分の強みを効果的に伝え、企業に貢献できる姿を描くことが重要です。
ここでは、調整力を効果的にPRするための3つの構成を解説します。
①冒頭で自分のPRポイントを結論から述べる
最初に、自分の強みが調整力であることを端的に伝えましょう。例えば、「私の強みは、異なる意見を調整し、チームの一体感を生み出す調整力です」などと表現してください。
ここで重要なのは、「調整力」とは何かを具体的な言葉で説明し、面接官がイメージしやすくすることです。
自己PRの冒頭で、「異なる意見をまとめ上げる力」や「チームに一体感を生み出す力」を自分の特長として強調することで、面接官に興味を持たせ、話の内容に引き込みましょう。
②具体的なエピソードや経験で説得力をもたせる
続いて、実際のエピソードを通して調整力の実績を示しましょう。
例えば、ゼミ活動での論文発表において、メンバー間の意見対立が生じた際、それぞれの主張を理解し、各々の意見の長所を活かして結論を導いた経験は強いPRになります。
このような経験を通して、単に意見をまとめるのではなく、異なる立場を尊重しながら目標に向かって進んだ過程をしっかりと説明しましょう。
また、エピソードに「結果」を付け加えることで、調整力がもたらした成果を具体的に伝えられ、説得力がさらに高まります。
③入社後どう強みを活用できるかで締めくくる
最後に、調整力を入社後にどのように活かせるかを述べ、貢献意欲をPRしましょう。
例えば、「貴社のプロジェクトでも、異なる意見を調整し、チームが円滑に目標達成できるようサポートします」と具体的に述べることで、企業側にとって有益な人材であるとPRできます。
具体的なビジョンを伝えることで、採用担当者はあなたが入社後にどのように活躍するのかを容易に想像できるでしょう。
「調整力」を自己PRで効果的に伝えるためのポイント

「調整力」は、就職活動の自己PRにおいて使いやすい強みですが、伝え方が次第では上手くPRできません。
ここでは、自己PRで調整力を効果的に伝えるための3つのポイントを解説します。
①求める人物像にマッチしているか確認する
1つ目は、自分の調整力が企業の求める人物像に一致しているか確認することです。
企業に合わせた自己PRを作成するために、仕事内容や企業文化に合った具体的なエピソードを準備しましょう。
自分の調整力を活かせるシーンを想定し、入社後の貢献を明確に伝えることが重要です。
②調整力を発揮したエピソードを入れる
2つ目は、調整力が発揮されたエピソードを盛り込むことです。
具体例として、チーム内での意見の対立をまとめ上げ、目標達成に導いた経験が有効です。
たとえば、グループワークで対立する意見をまとめ、全員が納得できる方向へ調整したエピソードは説得力が増すでしょう。
また、問題が発生した際に率先して行動し、解決策を示した経験があれば、それも良いPRとなります。
③調整力を自分なりの言葉に言い換える
3つ目は調整力を自分なりの言葉に言い換えることです。
「調整力」という言葉自体は抽象的であるため、自分なりの表現に言い換えましょう。
たとえば、「チームを一体化させる能力」や「異なる意見を融合させ、合意形成を図る力」など、具体的な言葉にすることで、より分かりやすく伝えられます。
また、状況に合わせて新しいルールを作り、問題を根本から解決した経験を話すと、調整力をより効果的にPRできます。
「調整力がある」の自己PRに使える具体的な言い換え5選

調整力を自分の言葉に言い換えることが大事と述べましたが、どう言えばいいのかわからない人もいると思います。
ここでは、調整力の言い換え例を5つ紹介します。ぜひ活用してください。
①チーム内の合意形成ができる
1つ目は「チーム内の合意形成ができる」で、複数のメンバーがいる場で、各自の意見をまとめてチーム全体での合意形成できる人におすすめの表現です。
たとえば、学業やサークル活動で、メンバー間の意見が対立したときに、1つの方向性にまとめる役割を担った経験がある人はぜひ使ってください。
「合意形成ができる」と表現することで、単なる意見の取りまとめにとどまらず、全員が納得しやすい意思決定を導き出す力があることをPRできます。
②立場や意見の異なる人の間を取り持てる
2つ目は「立場や意見の異なる人の間を取り持てる」で、異なるバックグラウンドや視点を持つ人たちの間に立ち、双方が理解し合えるようにサポートした経験がある人に適しています。
たとえば、複数の部署が関わるプロジェクトや、学内の多様なメンバーを含むチームで活動した際、対立する意見を調整した経験がある人におすすめです。
「取り持てる」は、意見の異なる相手同士をつなげて理解を深め、協力関係を築ける力をPRするのに効果的な表現でしょう。
③課題解決のためのコミュケーション能力がある
3つ目は「課題解決のためのコミュケーション能力がある」で、困難な状況に直面した際、適切な対話を通じて解決策を導き出す力を持つ人に適しています。
たとえば、サークルでのトラブルやグループ課題での意見対立などを、自ら積極的に解決に導いた経験がある人におすすめの表現です。
単に「調整」するのではなく、問題解決に向けて周囲と協力する姿勢や対話を重視する点が強調され、結果を出すための行動力が伝わりやすくなるでしょう。
④柔軟なリーダーシップが取れる
4つ目は「柔軟なリーダーシップが取れる」で、リーダーシップを発揮する場面で、メンバーの意見を尊重しながら適切な指導を行った経験がある人におすすめです。
たとえば、リーダーとしてプロジェクトを進行した際に、状況に応じて他者の意見を取り入れながら進行役を務めた経験がある場合、この表現が適しています。
「柔軟なリーダーシップが取れる」と表現することで、周囲の状況に応じて指導方法を調整できる力や、チーム全体のパフォーマンスを高めるための工夫ができる点が伝わるでしょう。
⑤組織横断的な調整ができる
5つ目は「組織横断的な調整ができる」で、複数の部署や異なる立場の人々と協力して業務を進めた経験がある人に向いています。
例えば、学内の複数の団体が関わるイベントの運営で、各団体の要望をまとめ、スムーズな運営をサポートした経験がある場合には、この表現がぴったりです。
「組織横断的な調整ができる」と言うことで、他部門と連携して効率的にプロジェクトを進められる力を表し、広い視野と柔軟な対応力をPRできるでしょう。
【経験別】「調整力」の自己PRの例文5選
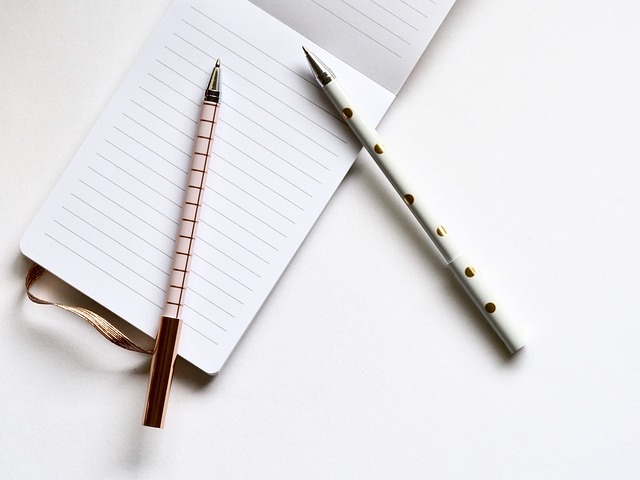
ここまでの内容を踏まえて、調整力を強みとして見せる自己PRの例文を5パターン紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
①部活動の場合の例文
1つ目は、部活動で調整力を発揮した場合の例文です。
| 私の強みは、異なる意見を尊重しながら全員が納得できる最適解を導き出す調整力です。部活動では大会に向けた戦略の調整役を務めていました。 特に、強豪校との試合を控えたミーティングで、メンバー間の意見が割れる場面がありました。守備重視の意見と攻撃重視の意見がぶつかり合う中、双方の主張を理解し、相手チームの分析結果に基づいた戦略を提案しました。 この結果、全員が納得し、練習にも一層力が入るようになりました。入社後は、チーム内で意見が分かれる場面でも、全員の意見を尊重しながら成果を最大化するための調整役として貢献したいと考えています。 |
チーム内の対立を具体的な分析結果をもとに調整し、全員を納得させる力を示しています。
自らが中心となり、対立する意見をまとめ上げ、練習に対する士気を高めた点が評価されるでしょう。
②サークルの場合の例文
2つ目は、サークルで調整力を発揮した場合の例文です。
| 私の強みは、メンバー間の意見を調整しつつ、全員が参加できる柔軟なリーダーシップを発揮する力です。 大学のサークル活動で、イベントの企画をリーダーとして担当しましたが、予算や日程に対するメンバー間の意見がまとまらず、一時進行が止まってしまいました。その際、全員の都合と希望を改めてヒアリングし、要望を反映させながらも現実的な妥協案を提案しました。 結果、全員が納得した上で無事イベントを成功させることができました。入社後も、同僚の意見を尊重しつつ、全員が納得する解決策を導き、プロジェクトを円滑に進めたいと考えています。 |
全員の都合や希望を反映させる形でイベント企画を進めた点がポイントです。
意見の異なるメンバーからの信頼を得て、妥協案を導き出し、成功につなげた「柔軟なリーダーシップ」の発揮が強みとして表れています。
③アルバイトの場合の例文
3つ目は、アルバイトで調整力を発揮した場合の例文です。
| 私の強みは、異なる立場の間で意見を調整し、最適な方法を見つける力です。 アルバイト先のレストランでシフト調整を担当していた際、スタッフの間で出勤時間や仕事内容について意見が食い違うことが多々ありました。そこで私は、各スタッフの都合や希望を聞き取り、それをもとにシフトを組み直し、全員が気持ちよく働ける環境を作りました。 入社後も、周囲との対話を大切にし、全員が働きやすい環境作りに貢献していきたいと考えています。 |
スタッフ間のシフト調整において、個々の意見や都合を取り入れ、全員が働きやすい環境を作った点がポイントです。
細かな配慮をもって柔軟に対応し、結果的に職場全体の満足度向上を実現した調整力が強調されています。
④ボランティアの場合の例文
4つ目は、ボランティアで調整力を発揮した場合の例文です。
| 私の強みは、異なる考え方や文化を理解し、共通の目標に向けて調整する能力です。 海外でのボランティア活動では、異なるバックグラウンドを持つメンバーが集まっていたため、活動方針に対する意見が合わず、進行が難航することもありました。そこで私は、全員が納得できる目標とそれに向けた分担を提案し、再び協力体制を築くことに成功しました。 この経験を活かし、入社後は異なる背景を持つ人たちと協力し、共通のゴールに向かって進めるような環境づくりに貢献したいと考えています。 |
異文化のメンバーが集まる環境で意見を調整し、共通の目標に向けて連携を強化した点がポイントです。
多様な背景を考慮しつつ、メンバーの協力を得て活動を前進させたことが、調整力の高さを具体的に示しています。
⑤長期インターンの場合の例文
5つ目は、長期インターンで調整力を発揮した場合の例文です。
| 私の強みは、異なる部署やチームの間で意見を調整し、プロジェクトを円滑に進める調整力です。 インターン先でのプロジェクトでは、マーケティングと営業の両部署が関わっていましたが、互いの目標が異なるため進行が難航しました。私は、各部署の担当者と積極的に対話し、双方の期待に沿うような計画を立案し、無事にプロジェクトを完遂しました。 入社後も、チーム間の連携を強化し、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。 |
部署間の異なる目標を理解し、調整役としてプロジェクトを完遂させた点がポイントです。
複数の部署をまとめ、対話を通じて双方の期待を満たす計画を策定し、結果的にプロジェクトを成功に導いた力が強みとして表れています。
「調整力」を自己PRの長所に使う場合の3つの注意点とNG例文

調整力は就活で高く評価される強みですが、伝え方を間違えると逆効果になってしまうことがあるため注意が必要です。
ここでは、自己PRに調整力を使う際の3つの注意点をNG例文を紹介します。
①ネガティブなエピソードを使わないようにする
調整力をPRする際、失敗やネガティブな出来事に基づくエピソードを選ぶと、印象が悪くなる可能性があります。
自己PRでは、困難を乗り越えた経験やポジティブな成果を示すエピソードが効果的です。自分が積極的に調整を行い、チームの成長や目標達成に繋がったことを具体的に伝えましょう。
以下、ネガティブなエピソードを使ったNG例です。
| サークルのイベント運営で他のメンバーと意見が対立し、自分が妥協して意見を合わせましたが、最終的にイベントは成功しませんでした。 |
この例は、対立を回避するだけで本質的な調整ができていないため、調整力をPRするエピソードとして不適切です。解決を目指して積極的に行動した部分を強調する方が良いでしょう。
②受動的で主体性がないと思われないようにする
調整力をアピールする際、受動的な印象を与えると、主体性が欠けていると判断されかねません。
調整力を発揮する際も、自らの判断で積極的に行動し、他者を巻き込んで目標に導いたことを伝えることが大切です。
以下、受動的なNG例です。
| 私はいつも周囲の意見を尊重し、自分の意見を言わずに他の人に従うことで、チームが円滑に動くようにしました。 |
受動的な態度が強調され、主体性が欠けている印象を与えかねません。自分の意見や判断をしっかりと持ち、積極的に調整に関与していることを伝える方が良いです。
③ゼロからエピソードを作るのは避ける
実際に経験していないエピソードや偶然うまくいった事例を使うと、信憑性が低くなります。
調整力のPRには、意識的に対応した実際の経験に基づくエピソードを選び、具体的な行動や学びを述べましょう。
以下、偶然上手くいった事例を使ったNG例です。
| アルバイト先でのシフト調整で、たまたま全員の都合が合い、希望通りにシフトを組むことができました。この成功がきっかけで、シフト管理が得意だと思うようになりました。 |
調整力によって問題を解決したわけではなく、偶然の成功に依存しているため適していません。
調整力とは、異なる意見や希望の中で妥協点を見つけ出し、全員が納得できるように調整する能力です。偶然うまくいった状況では、信頼性や説得力に欠けます。
「調整力」の自己PRについてよくある質問

最後に、調整力を使った自己PRに関してよくある3つの質問に回答していきます。参考にしてみてください。
①「調整力」は他の人と被ってしまわない?
調整力に限らず、どんなことをアピールしても他の人と被ることはあります。
他の応募者との差別化を図るためには、自分独自のエピソードを強調しましょう。
例えば、具体的な状況や自分の行動、得た成果について詳細に述べることで、より個性的な自己PRが可能です。
また、「調整力」を単に「意見をまとめる能力」ではなく、「対立する意見を解決する力」や「チームを円滑に進めるスキル」として説明することで、より具体的で印象深い自己PRができます。
②「調整力」をESに書く場合の注意点はある?
ESに調整力を記載する際には、単なる言葉の説明だけでなく、具体的なエピソードを交えることが重要です。
また、受動的な印象を与えないよう、主体的に行動した経験を含めると良いでしょう。
たとえば、「問題が発生したときに、自ら率先して両者の意見を聞き調整した結果、目標を達成した」など、調整力を具体的な行動と成果で表現しましょう。
③「調整力」がある人の特徴は?
調整力がある人の特徴としては、「冷静な判断力」「他者の意見を尊重する姿勢」「全体を見渡せる視野」が挙げられます。
また、調整力の高い人は自分の意見を押し通すのではなく、異なる意見を上手にまとめ、全員が納得する結論を導き出すスキルを持っています。
調整力は、特に多様な意見が交錯する職場で重宝されるため、就活の自己PRにおいて強力なものになるでしょう。
コツを理解して調整力を効果的に自己PRしよう

調整力は、就活の自己PRで多くの企業から評価される強みです。
企業が求めるのは、単に「意見をまとめる力」ではなく、対立する意見を理解し、チーム全体を目標に導く主体的な行動力です。
自己PRで調整力を伝える際は、具体的なエピソードを交え、目標達成に向けた行動や結果を詳しく述べましょう。
また、調整力を自分なりの言葉に言い換えることで、オリジナリティのある自己PRが可能です。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









