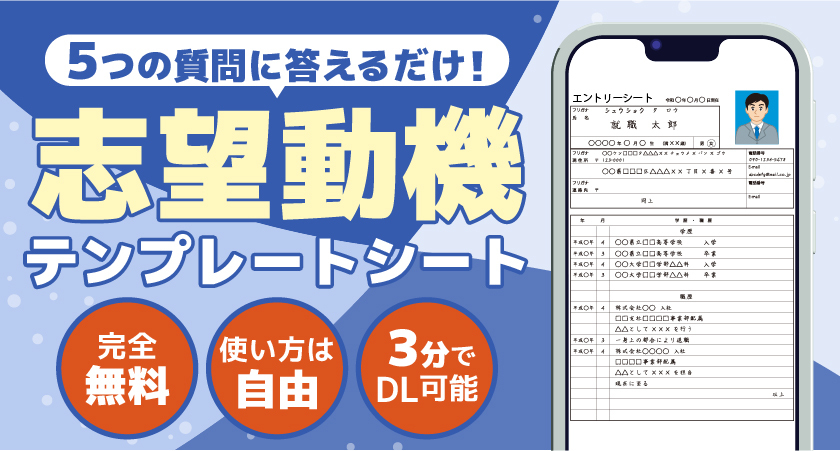毎回応募するたびに企業に合わせて志望動機を書くのは大変ですよね。効率的に就活を進めるためにも、就活サイトから志望動機をコピペしようと思っている人もいるかもしれません。
本記事では、志望動機のコピペの是非について解説します。
志望動機が思いつかない時の対処法も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。
志望動機のお助けツール!完全無料
- 1志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を作成できる
- 2ES自動作成ツール
- AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
- 3志望動機の無料添削
- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します
志望動機のコピペ・丸写しはバレる!その理由とは
エントリーシートや履歴書での志望動機のコピペは、人事担当者に容易に見抜かれます。
なぜなら、人事の人はESや履歴書を見慣れていて、コピペだと違和感を感じるからです。
違和感のある文章はネットで検索にかけ、その際就活サイトもチェックしているため、コピペはすぐバレるのです。
コピペが発覚すると、応募者は信頼を失い、選考で不利になります。そのため、コピペは避けた方が良いでしょう。
志望動機のコピペがNGな理由3つ
コピペは面接官に簡単に見抜かれ、信頼を失う原因になるため、就職活動において、志望動機のコピペは避けるべきです。
ここでは、コピペがNGとされる3つの主な理由を解説します。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①独自性のない文章になる
1つ目は、志望動機をコピペすると、独自性のない文章になってしまうからです。採用担当者は数多くの履歴書を目にしており、コピペされた文章はすぐに見抜かれます。
独自性のない志望動機は、個人の特性や熱意が伝わらず印象に残りません。
自分自身の言葉で書くことで自己の経験や考えを具体的に示すことができ、自分の強い興味や意欲を企業に伝えられるでしょう。
②面接で深掘りされた時に答えられない
2つ目は、面接時に志望動機を深掘りされた際に答えることが難しくなるからです。
自分の言葉で書かれていないため、質問に対して具体的かつ説得力のある回答ができません。
これは、コミュニケーション能力や理解度の不足と見なされ、評価が下がる原因になります。
自分の経験や考えを基にした志望動機を準備することで、面接官の質問にも自信を持って答えられます。
③不誠実な人間だと思われる
3つ目は、あなたが不誠実な人間だと思われてしまうからです。
企業は、自社に対する真剣な興味や熱意を持った人材を求めています。コピペされた志望動機は、熱意や興味が欠如したものであり、企業の信頼を失ってしまいます。
自分自身の言葉で誠実に志望動機を作成し、企業に対する真剣な姿勢をアピールすることが大切です。
どうしても志望動機が思いつかない時の対処法2選

志望動機が書けずに悩んでいる人も多いと思います。そこで、志望動機が思いつかない時の対処法を2つ紹介します。ぜひ実践してみてください。
①自己分析を十分に行う
志望動機を考える上で最も基本的かつ重要なのは、自己分析を行うことです。自己分析をすることで、自分の強みや興味、価値観が明確になり、それが志望動機の土台となります。
例えば、自分が過去に取り組んだプロジェクトや経験から、自分の強みや興味を見つけ出すことができるでしょう。
また、自己分析を通じて、なぜその企業を志望するのか、その企業で何を実現したいのかが明確になります。
自己分析は時間がかかる作業ですが、その分、自分の内面を深く理解でき、説得力のある志望動機を作成することが可能です。
②生成AIで作った文章を参考にする
2つ目の方法は、生成AIを活用することです。例えば、ChatGPTなどのAIを使って、志望動機の草案を作成してもらいましょう。
AIは、与えられた情報を基にして論理的な文章を生成するため、新しい視点や表現を得られます。
ただし、AIが生成した文章はあくまで言い回しを参考にする程度に留め、志望理由などは自分の言葉で書き直すことが重要です。
AIの文章をそのまま使うと、自分らしさが失われたり、面接時に深く話せないリスクがあります。AIを活用する際は、自分の経験や考えを加えて、オリジナルの志望動機を作成しましょう。
ただのコピペにしない!Chatgptに志望動機を書いてもらう流れ
ChatGPTを活用すれば、効率的に志望動機を作成できます。
ここでは、具体的な手順を分かりやすく解説し、活用のポイントを見ていきましょう。
①プロンプトを作成し志望動機の草案を作る
プロンプトを作成して志望動機の草案を作るには、まずChatGPTに伝えるべき情報を整理することが重要です。
たとえば、「志望企業の名前」「その企業のどんな点に惹かれたか」「自身のスキルや経験」「企業で実現したいこと」などを具体的に箇条書きにしてみましょう。
それらをもとに、ChatGPTに「これを踏まえて志望動機を作成してください」と依頼する形でプロンプトを入力します。
曖昧な表現を避け、詳細で具体的な条件を提示するほど、的確で説得力のある志望動機が生成されます。
②志望動機をChatGPTにレビューさせて改善点を確認する
ChatGPTで作成した志望動機を添削する際は、AIに客観的な視点でレビューを依頼することが効果的です。
具体的には、「あなたは優秀な人事担当者です。以下の志望動機を添削してください」と前置きし、作成した文章を入力しましょう。
AIからは、抽象的な表現の具体化、冗長な文章の簡潔化、企業への共感度を高める表現の追加などのアドバイスが得られます。
AIの添削結果をそのまま採用するのではなく、自分の言葉で肉付けし、オリジナリティを加えることがおすすめです。
③指摘された改善点を反映させ、完成度を高める
ChatGPTが生成した志望動機は、そのまま使用せず、必ず自分の視点でブラッシュアップする必要があります。自分の普段使用する言葉遣いに修正し、独自のエピソードや感情を追加することが欠かせません。
また、生成された文章に誤った情報や古い情報がないかを慎重に確認し、自分の意図が正確に反映されているかを吟味します。
さらに、企業や職種に特化した具体的な表現を加えることで、より個性的で説得力のある内容に仕上げることができるでしょう。
志望動機はPREP法を用いてみるのがおすすめ
志望動機に困ったときは、PREP法を活用するのがおすすめです。結論から伝えるこのフレームワークを使えば、論理的で簡潔な志望動機を作成できます。
ここでは、具体的な手順や活用例を解説します。
①Point(結論)
志望動機の「Point(結論)」では、あなたが志望する企業で何をしたいのか、なぜその企業を選んだのかを簡潔に伝えることが欠かせません。
最初の数秒で採用担当者の興味を引くためには、明確で具体的な結論を提示する必要があります。
例えば、「私は貴社の〇〇の事業に共感し、△△の課題を解決したいと考えています」といった形で、自分の熱意と目的を端的に示すことがポイントです。
結論は短く、力強く、そして企業への貢献意欲が伝わるように心がけましょう。
②Reason(理由)
Reason(理由)では、あなたの結論を支える具体的な背景や根拠を示し、この部分をしっかりと書くことで、志望動機に説得力が生まれます。
例えば、「貴社の強みである〇〇に魅力を感じました」や「私のこれまでの経験が、貴社の△△に活かせると考えました」などが挙げられます。
企業が求める人材像や業界の特徴、自分のスキルや経験といった要素を結びつけて説明してみてください。
③Example(具体例)
Example(具体例)の部分では、志望動機に説得力を持たせるための実体験や具体的な事例を盛り込みます。
例えば、「学生時代に広報活動を行い、SNSフォロワーを〇〇人増やした経験があります。このスキルを貴社の□□プロジェクトに活かしたいと考えています」といった形です。
また、「〇〇業界でのアルバイト経験を通じ、□□の重要性を学びました。この経験を基に、貴社の△△分野で貢献したいです」といった実績やエピソードを挙げるのも効果的でしょう。
具体例を入れることで、企業側も「なぜこの人がうちを志望しているのか」を納得しやすくなります。
④Point(結論の再提示)
Point(結論の再提示)では、最初に述べた結論をもう一度簡潔に繰り返し、志望動機を締めくくります。この部分で大切なのは、伝えたいポイントを強調し、相手に印象付けることです。
例えば、「以上の経験やスキルを活かし、貴社の〇〇に貢献したいと強く考えています」といった形で、志望理由や意欲を明確に示しましょう。
結論を繰り返すことで、全体に一貫性を持たせるとともに、採用担当者にあなたの熱意がより伝わりやすくなります。
また、自分自身の思いや考えを具体的に反映させることも重要です。
志望動機は自分の言葉で書くことが重要!
志望動機を書く際は、自分の言葉で表現することが非常に重要です。自分の言葉で書くことで、あなたがその企業や職種に対して真剣に考え、理解していることが伝わります。
また、自分の経験や考えを基にした志望動機は、面接時の質問に対しても一貫性のある回答ができ、信頼性を高めます。
さらに、自分の言葉で書くことで、応募者の個性や独自の視点が際立ち、他の応募者との差別化が可能です。
企業は、自社に対する深い理解と熱意を持った応募者を求めています。自分の言葉で説得力のある志望動機を作成しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。