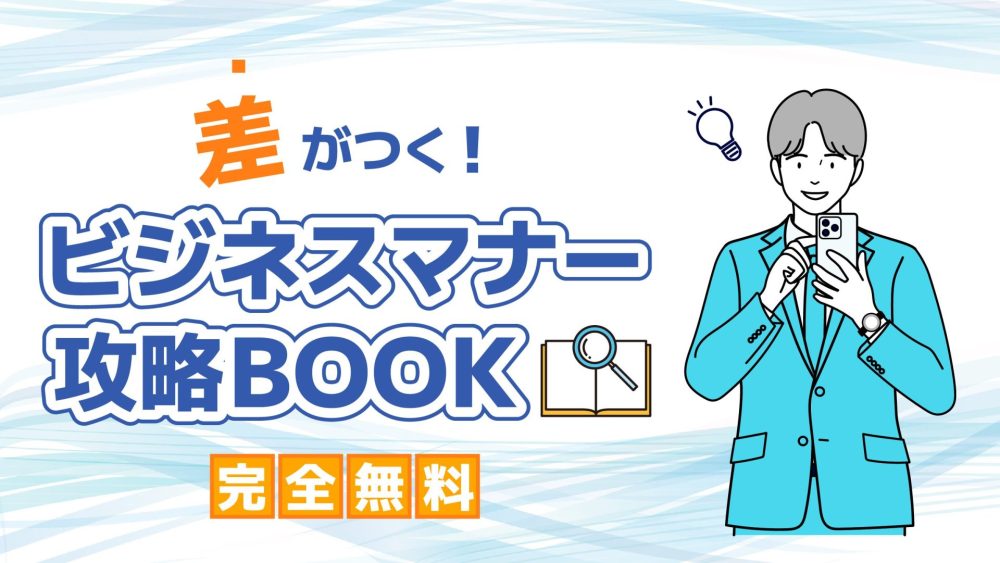就活が活発になってくる冬は寒く、コートが欲しくなりますよね。しかし、どのようなコートを選んだらいいか分からない方は多いのでは?
本記事では、就活におすすめのコートの特徴を紹介しています。ぜひ、参考にしてくださいね。
カリクルが就活のスタートをサポート!
- ①リクルートスーツレンタル|無料
- レンタル予約から受け取りまでLINEで完結
- ②面接質問集100選|400社の質問を分析
- LINE登録で面接前に質問を確認!
- ③適職診断|LINEで3分
- 自分に合う仕事が見つかる
- ④AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- 3分でESを自動作成してくれる
冬は就活でもコートを着るのがおすすめ
コートを着ずに、スーツのみで就職活動を進めるという選択肢もありますが、コートを着用することをおすすめします。
特に、11月から4月頃の寒い時期は体調管理のためにもコートを着ましょう。就職活動は、ただでさえやることが多くスケジュールが詰まっていて体調を崩しやすくなります。
そのため、できる限りの防寒対策は行うようにしてください。体調を崩して、志望している企業のイベントや面接に行けなくなっては、今までの努力が水の泡になってしまいます。
就活で着るコート選びのポイント4つ

就職活動で着るコートは、面接やイベント中は着用しませんよね。その場合でも、どんなコートでも着用して良いわけではありません。
性別に関わらず、コートを選ぶ際に気をつけるべきポイントを紹介します。
- 落ち着いた色をチョイス
- 素材は化学繊維が入ったものがおすすめ
- 丈はジャケットが隠れる程度
- デザイン性よりは寒さ対策を重視する
①落ち着いた色をチョイス
コートの色は、スーツと同じく落ち着いた色を選びましょう。中にスーツを着ていても、派手な色はマナー違反です。
一般的な色は、黒・ネイビー・グレー・ベージュです。黒やネイビーは、落ち着いた印象を与え、ベージュは明るく元気な印象を与えます。
また、色だけでなくデザインも落ち着いたものを選びましょう。色が落ち着いていてもデザインが派手だと、就職活動の際に着用するコートとしては不適切です。
②素材は化学繊維が入ったものがおすすめ
化学繊維が入ったコートは、水をはじく撥水加工がされており、軽いので実用的でおすすめ。素材の例を挙げると、ナイロンやポリエステルなど。
電車の中では、暖房が効いていてコートを脱ぐ機会もあり、コートが軽いと持ち運びが便利です。
そのため、軽い雨が降ってもスーツが濡れる心配はありません。面接では、清潔感が重要なポイントの1つなので、スーツが濡れないように撥水加工のものを選びましょう。
③丈はジャケットが隠れる程度
コートの丈は、スーツのジャケットが隠れる程度の長さのものを選びましょう。
スカートを着用している女性は、膝丈かそれよりも少し上くらいの丈のコートがおすすめです。コートからジャケットやスカートの裾が見えてしまうと、フォーマルな印象になりません。
また、あまり長すぎてしまうコートもカジュアルですし、移動の時に煩わしく感じてしまうのでおすすめしません。
④デザイン性よりは寒さ対策を重視する
就活では見た目の印象も大切ですが、寒い時期の体調管理はより重要なため、コート選びでは、防寒性を第一に考えましょう。
「ライナー」と呼ばれる着脱可能な裏地が付いたタイプを選べば、真冬から春先まで長いシーズン着回しができて便利です。
素材は「コットン」や「ウール」が防寒性に優れており、特にウール素材は暖かさを保ちやすい素材になっています。
また、地域や気候によっては撥水や防風などの機能性も重視しつつ、部分的にストレッチが効いているものを選べば、長時間の移動でも動きやすく快適です。
就活におすすめなコートのタイプ3つ

就活のコートといえば、一般的にはトレンチコートですが、それ以外のタイプでも問題ありません。
こちらもメンズ・レディース関わらず、就職活動において好印象なデザインを紹介します。
- トレンチコート
- ステンカラーコート
- チェスターコート
①トレンチコート
トレンチコートは、最もスタンダードな就職活動におけるコートで、きちんとしたクラシックな印象を与えます。
トレンチコートを着用する際は、ベルトはきちんと締めましょう。また、レディースのトレンチコートにはリボンがついている場合も多くあります。
その場合は、蝶々結びをしてください。トレンチコートの色は、ベージュが最も一般的ですが、ネイビーなど他の色もあります。
トレンチコートは薄手なので、冬はマフラーをするなど防寒対策をして着用するのがおすすめです。
②ステンカラーコート
ステンカラコートは、シンプルなデザインで就職活動に適しています。後ろの襟が高くなっており、モダンな印象を与えますよ。
また、ステンカラーコートは男性が多く着用しているデザイン。ボタンが首まで閉められるので、防寒性は高く、風も通しにくいため、冬でも安心して着られる1着です。
スーツと組み合わせやすく、就職活動でも社会人になっても重宝するコートになります。
③チェスターコート
チェスターコートは、機能性の高いコートです。チェスターコートの中には、洗濯できるものや小さく畳みやすいものも多くあります。
就活では、コートは小さく畳んでバッグの上に置くのがマナーなので、小さく折り畳みやすいものがおすすめです。
また、チェスターコートにはウール製のものも多くあります。ウール製は、冬でも暖かいので冷え性の方におすすめです。
就活でNGなコートの特徴2つ

ここからは、就職活動においてNGなコートの特徴を紹介します。
面接時には脱ぎますが、就職活動に適したコートを選ばないと、企業からの印象も悪くなることも。ぜひ参考にしてくださいね。
- カジュアルなデザイン
- 自然素材100%
①カジュアルなデザイン
就職活動はフォーマルな場なので、カジュアルなデザインはNGです。例えば、ダッフルコート・ダウンジャケット・モッズコート・ファー付きのコートは着用しないように気をつけてください。
また、外から見ると落ち着いた印象のフォーマルなコートであっても、裏地など部分的に派手な場合は着用を避けてください。
就職活動では、ファッションセンスは問われません。いかにお洒落かよりも、ビジネスシーンに適しているかを重要視してコートを選ぶようにしてください。
②自然素材100%
自然素材100%のコートも就職活動の際には、おすすめしません。
ウールやレーヨン100%のコートは、暖かく一般的には高品質だとされますが、重くかさばります。就職活動では、着脱が多いので持ち運びやすい軽いものがおすすめです。
それに対して、コットン100%のコートは軽く涼しいので、春先にぴったりなイメージが持たれます。しかし、シワになりやすい欠点も。シワがあると、就職活動で大事な清潔感があまり感じられません。
要注意!就活でのコートマナー3つ

ここからは、実際に就職活動においてコートを着る際のマナーを紹介します。ビジネスマナーは社会人として大切なので、面接の前に一度確認してくださいね。
- 裏地を表にするたたみ方に注意
- 建物に入るタイミングで脱ぐ
- 面接中はバッグの上にたたんで置く
①裏地を表にするたたみ方に注意
コートを脱いだら、コートのたたみ方にまず注意してください。ほこりなどで汚れている表面をひっくり返してたたむのがマナーです。
順番としては、まず裏地が表になるようにコートを裏返します。そして、両袖を折り込んで縦にたたみ、真ん中あたりでふたつ折りにしてください。
コートをたたんだら、バッグを持っていない方の腕にかけ持ち歩くようにしてください。
②建物に入るタイミングで脱ぐ
コートを脱ぐタイミングは、企業の建物に入る前がマナーです。
面接やイベントの会場から気をつけるのではなく、企業の建物に入った瞬間から見られているという意識を持って緊張感を保つようにしましょう。
コートだけでなく、マフラーや手袋も同じタイミングで取るようにしてください。脱ぐのを忘れてしまう就活生も多くいるので、気をつけてくださいね。
③面接中はバッグの上にたたんで置く
面接の部屋に入室したら、コートはバッグの上に置きましょう。コートを椅子の背もたれにはかけないようにしてください。
コートを椅子の背もたれにかけてしまうと、コートの裾が床についてしまったり、面接中に背もたれから落ちてしまう可能性があります。
このような場合、面接官にだらしない印象を与えてしまうため、背もたれにコートをかけるのは避けてください。
さらに、バッグの上にコートを置く場合も床に落ちないよう、四つ折りにするなどコートをコンパクトにすることを意識してくださいね。
就活で着るコートが購入できる場所4つ

ここまで、就職活動に適したコートの特徴がわかりました。しかし、どこでそのようなコートを購入するのか悩む就活生も多いのでは?
ここからは、就職活動用のコートを購入できる場所を4つ紹介します。
- 百貨店
- スーツ専門店
- 一般ブランド
- 通販
①百貨店
百貨店で売られているコートは、高品質ですが値段も高くなります。そのため、長くコートを着用し続けたいという人におすすめです。
就職活動で着用するコートはスーツに合うもので、ビジネスシーンに適しているので、社会人になっても重宝します。
そのため、百巻店で高品質で長持ちするものを一度購入し、社会人になっても使い続けるという就活生も多くいます。
②スーツ専門店
スーツ専門店の例としては、AOKI・洋服の青山が代表的です。
スーツ専門店で売られているコートは、スーツに合うものなので間違いはないですが、レディースの品揃えが少なめなので注意してください。
百貨店よりも値段は抑えめなので、大学生でも購入しやすい価格帯となっています。
③一般ブランド
一般ブランドの例としては、ユニクロやGUが代表的です。
安価なブランドなので、不安になる人も多いかと思いますが、フォーマルな印象のものであればブランドや価格は関係ありません。
高価かどうかよりも、スーツに合うかどうかや自分のサイズに合っているかを重視してコートを選ぶようにしてください。
④通販
通販は、品揃えもよくすぐ届くので利便性は非常に高くなります。しかし、通販のコートは試着ができないので要注意が必要。
コートは着丈が非常に重要で、ジャケットの裾が見えないようにするなど守るべきマナーがあります。
試着ができないと、実際に着てみて失敗してしまう可能性も非常に高いのであまりおすすめできません。
通販を使うのならば、店舗で試着した上で購入する商品を決めて、通販で購入するというやり方がおすすめです。
冬場の就活でのコートについてよくある質問と回答
ここまでも解説してきましたが、冬場の就活では、コートの選び方や着用マナーに悩む学生が多くいるでしょう。
ここでは最後に、就活生からよく寄せられる質問とその回答を詳しくみていきます。
- 就活スーツに合わせるコートに決まりはある?
- 男女でコートの気をつけるポイントはある?
- 脱いだコートはどのタイミングで着ればいい?
- 就活向けのコートの値段相場はどれぐらい?
①就活スーツに合わせるコートに決まりはある?
就活スーツに合わせるコートは、基本的にビジネスシーンで一般的な種類を選ぶことが望ましく、特別これでなければいけないという決まりはありません。
種類はステンカラーコートやトレンチコートがおすすめで、色は黒、紺、チャコールグレーといったダーク系カラーが無難。女性の場合はベージュも選択肢に入ります。
素材は、防寒性の高いウールや、軽くて扱いやすい綿、撥水性のあるナイロンやポリエステルなどから選びましょう。
なお、ダウンコートやダッフルコートなどカジュアルなものは避けるべきです。また、派手な柄や装飾が入ったものも控えめにし、シンプルで清潔感のあるデザインを選ぶことが重要です。
②男女でコートの気をつけるポイントの違いはある?
男女でコートの選び方には、いくつかの異なるポイントがあります。
男性の場合は、シンプルで落ち着いた印象のチェスターコートやステンカラーコートを選び、黒や紺などのダークカラーを基調とすることが望ましいです。
一方、女性の場合は、トレンチコートが特におすすめで、ベルトを活用してスタイルよく見せることができます。また、女性は体型に合わせた丈選びが重要で、ヒップを覆う程度の長さが理想的です。
男女共通のポイントとして、マフラーや手袋などの小物は、コートと同系色で統一感を出すことが大切です。
③脱いだコートはどのタイミングで着ればいい?
コートを着るタイミングは、面接や企業訪問が終わり建物を完全に出てからにし、室内でコートを着ることは避けましょう。
これは、コートが室内で着用するものではないというマナーに基づいています。
ただし、面接官や企業の方から「寒いので、ここで着てください」と言われた場合は例外で、その際は「ありがとうございます」と礼を述べてから着用しましょう。
最後まで気を抜かず、玄関や出入り口でも周囲の人の邪魔にならないよう注意してください。就活中は常に観察されている可能性があるため、建物を出るまでは気を引き締めて行動することが大切です。
④就活向けのコートの値段相場はどれぐらい?
就活向けのコートの値段相場は1万円~3万円程度です。この価格帯のコートは、品質と機能性のバランスが良く、就活生の予算にも適しています。
なお、コートは就活後も長く使用できるアイテムなので、予算に余裕がある場合は高品質なものを選ぶのも一案です。
また、多くのスーツ専門店では学割キャンペーンを実施しているため、より手頃な価格で購入できる場合もあります。
コートは就活に必要な一式を揃える際の大きな出費の一つとなりますが、スーツ専門店では就活向けの割引セットを用意していることもあるので、そういったお得なプランを活用するのもおすすめです。
就活ではコートにまで気を配り万全な状態で臨もう!
本記事では、就活におけるコートの選び方や実際に着用した際のマナーを紹介しました。
就職活動は、体調管理が1番なのでコートを冬はコートを着るようにしましょう。
面接時にはコートを脱ぎますが、派手な色は選ばず着丈にも気を遣ってコートを選ぶようにしてくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。