「インターンって何年からするものなの…?」
大学2年生になると、周りでインターンをしている人が出てきて、いつから始めるものなのか気になってしまいますよね。
結論、インターンは大学2年生からでも始めるのがおすすめです。この記事では、大学2年生からインターンを始めるメリットやインターンの探し方や注意点を徹底解説。
いつからインターンを始めるか悩んでいる人はこの記事を参考に、周りより1歩早くインターンを始めて経験を積むのがおすすめですよ。
インターンに受かるお助けツール集
- 1リクルートスーツレンタル|無料
- ぴったりのスーツでインターンに参加
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 好印象な志望動機を作成できる
- 3AI強み診断|自己分析
- アピールポイントがすぐ見つかる!
大学2年生もインターンに参加できる

まず結論として、大学2年生からでもインターンには参加できます。就活には早いタイミングではありますが、問題なく企業は採用してくれます。
インターンというとどうしても3年生から始めるものというイメージがありますが、むしろ2年生から始めていた方が良いこともたくさんあるのです。
もし大学2年生からのインターン参加に興味がある場合は、積極的に申し込んでみましょう。
大学2年生からインターンをするメリット6つ

大学2年生からでもインターンができることがわかったところで、早いうちからインターンを始めるメリットを詳しく見ていきましょう。
大学2年生からインターンを始めるのには、主に以下のようなメリットがあります。
- 社会で働く経験ができる
- 企業や仕事への理解が深まる
- 将来やりたいことを見つけるきっかけになる
- 自分の適性を知れる
- スキルが身に付く
- 社会人と関わることができる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①社会で働く経験ができる
インターンでは、通常のアルバイトとは違い、大学卒業後に社会人として働くケースと近い経験ができます。
アルバイトでは経験できなかった業務に携われるので、実際に社会で働くイメージをより具体的に持てるでしょう。
アルバイトではない分、業務に責任も伴いますが、やりがいや成長を感じられるのでおすすめですよ。
②企業や仕事への理解が深まる
インターンでは、正社員が担う業務に携わる機会もあるので、その企業や仕事への理解が深まります。
企業の雰囲気や仕事の内容は、紹介文を見たり話を聞いたりするだけではどうしても実感しづらいものです。
実際の業務に自分で関わることで、企業や仕事への理解が深まり、就職後にも活かせる経験ができますよ。
➂将来やりたいことを見つけるきっかけになる
インターンを通じて社会人が行う業務に触れることで、将来自分がやりたいことを見つけるきっかけにもつながります。
インターンで任された仕事にやりがいを見出せたり、反対にあまり面白くないと感じたりするなかで、自分が将来やりたいことを見つけられるのです。
特に現時点で将来やりたいことが決まっていない人ほど、早めにインターンを始めるのがおすすめですよ。
④自分の適性を知れる
インターンで実際の社会人の業務をする中で、自分がどんな仕事に向いているのかがわかるようになるのも、インターンをおすすめするポイントです。
大学2年生という早い段階から、自分に合う仕事と合わない仕事を知っておくと、余裕を持って就職活動が始められますよ。
⑤スキルが身につく
インターンでは、社会人がする業務をすることから、業務に必要な実践的なスキルを身につけられます。
インターンをやっていない人が研修で身につけるスキルを一足早く備えられれば、就職後即戦力となってステップアップも早くなるのです。
またインターンで既に実用的なスキルを身につけているとなれば、就職活動においても重宝されやすくなりますよ。
⑥社会人と関わることができる
インターンでは、普段大学で関わらない社会人と交流できるのも嬉しいポイント。社会人と交流することで、新しい知見が得られるだけでなく、人脈も広げられます。
新しいことを知り、人脈を獲得することで、自分の将来の選択肢が広がって、より納得のいく進路選択ができるのです。
大学2年生が参加できるインターンの種類
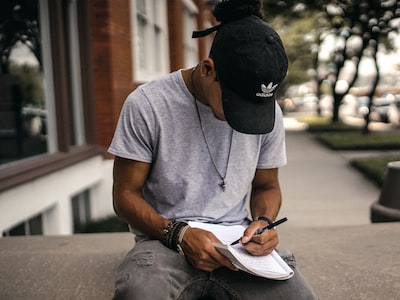
ここまで大学2年生からインターンを始めるメリットについて説明してきました。
それでは実際に参加できるインターンにはどのようなものがあるのでしょうか。大学2年生から参加できるインターンは、大きく分けて以下の2種類があります。
- 長期インターン
- 短期インターン
①長期インターン
まず、大学2年生で参加するのにおすすめなのが、3ヶ月から1年程度を目安に参加する長期インターンです。
長期インターンは長く関わる分、その会社の仕事をじっくり学べて、スキルも身につくのでおすすめできます。
長期インターンは通年募集があるのでいつでも申し込める上に、給料も発生することが多いので、アルバイト中心の生活から切り替えやすいですよ。
②短期インターン
インターンには、長期インターンだけでなく、夏と冬の時期に、1日から数週間程度で参加する短期インターンもあります。
短期インターンでは、短期間でその業界や仕事について理解することが目的です。
スキルは身に付きづらいですが、短期間で色々な業界について知れるので、業界選びで悩んでいる人はいくつか参加してみると参考になりますよ。
インターンの探し方3つ

ここまでインターンについて解説してきましたが、実際に大学2年生からのインターンを探すにはどうすれば良いのでしょうか。
インターンを探したい時は、主に以下の3つの方法がおすすめです。
- 大学のキャリアセンターを利用する
- インターン募集のサイトから探す
- 先生や友人から紹介してもらう
①大学のキャリアセンターを利用する
インターンを探したい時は、まずは大学のキャリアセンターで紹介されているインターンを見てみるのがおすすめです。
大学のキャリアセンターには就活に関する情報が多く集まっているので、自分に合ったインターンが見つかりますよ。OB・OG訪問もしやすいため、ひとまず行ってみるのもありでしょう。
また、職員の人に就活やインターン選びについて相談できるのも嬉しいポイントです。
②インターン募集のサイトから探す
スマホやパソコンで手軽にインターンを探すなら、インターンを紹介しているサイトやアプリを活用してみるのも手です。
インターン募集のサイトでは、自分の求める条件に合わせてインターンを絞り込めるので、簡単に自分にあったインターンを探せますよ。
➂先生や友人から紹介してもらう
自分の先生や友人がインターン経験者であれば、直接紹介してもらうのも確実な方法です。
インターンでは、募集要項に書いてあった内容と実際の業務や待遇が異なるケースが多くあります。
その分実際に働いていた人の声が聞ければ、安心してインターンに応募できるので嬉しいですね。
ただし知り合いからの紹介だけでは、他者との比較を十分にできないままインターン先を決めることになるので、他の方法も併用して十分に比較検討しておきましょう。
大学2年生がインターンに参加する際の注意点3つ

ここまでインターンについて説明してきましたが、最後に、大学2年生からインターンする場合の注意点について解説します。
大学2年生からインターンを始めるか悩んでいる人は、以下の3つのポイントに注意しておきましょう。
- インターンに参加する目的を明確にする
- 学業を疎かにしない
- 責任をもって参加する
それぞれ詳しく見ていきます。
①インターンに参加する目的を明確にする
まず、インターンを始める前にインターンに参加する目的を明確にしておきましょう。
早いうちからインターンを始める学生の多くが、就活のためにとりあえずインターンに参加しておけば良いだろうという浅い考えでインターンをしてしまいます。
しかし、インターンは参加しただけでは何も得られません。真剣にインターンに参加していないことは企業の採用担当者も簡単に見抜いてしまうでしょう。
インターンをする際には、参加前にインターンで自分が達成したい目的を設定し、参加後にその目的を達成できたのか振り返ることが重要になりますよ。
②学業を疎かにしない
インターンに参加する際は、学業を疎かにせずしっかり単位を取ることも忘れないようにしましょう。
インターンに熱中するあまり授業に出席できず、留年してしまったら元も子もありません。
大学生の本分は学業であることを忘れず、授業に支障をきたさない範囲内でインターンに取り組むことが重要です。
➂責任をもって参加する
インターンに参加するときには、自分も社会人の一員なのだという責任を持って参加することも重要です。
アルバイトとは異なり、インターンは正社員と同じ業務や責任ある仕事をもらうことも多くあります。
アルバイトの感覚で適当に仕事をすると、社内だけでなく取引先に迷惑をかけることもあるので、真剣に取り組むことが重要です。
大学2年生からインターンをして就職活動に備えよう

この記事では、大学2年生からのインターンについて解説しました。
大学2年生からのインターンは決して早すぎることはなく、実際の社会の仕事に触れることで、自分の将来の可能性を広げてくれるものです。
早めのインターンを通じて、就職活動を有利に進めましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









