「ESってどうやって書けばいいの?」
就活を始めると必ず直面するのがエントリーシート。自己PRや志望動機、ガクチカなど、何を書けばよいのか迷い、例文を探してしまう人も多いのではないでしょうか。
本記事では、エントリーシートの役割から基本構成、書く際の注意点まで丁寧に解説します。職種別の志望動機例まで網羅しているので、自分のケースに合った参考が必ず見つかるはずですよ。
読み進めれば、自分らしさを盛り込んだ説得力あるESを完成させられるでしょう。
全て無料!ES作成に役立つツール
★ES自動作成ツール
AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
★志望動機テンプレシート
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機をカンタンに作成できる
★自己PR作成ツール
最短3分で、受かる自己PRを作成できる
エントリーシート(ES)とは?就活における役割を解説

エントリーシートとは、就活生が企業に提出する自己紹介文のようなものです。学生時代に力を入れたことや自己PR、志望動機などを通して、自分の強みや価値観を企業に伝える役割があります。
企業側はこれを読み、「この人に会ってみたいか」「自社で活躍できそうか」といった視点で選考しています。つまり、ESはただの情報記入用紙ではなく、自分を売り込むプレゼン資料とも言えるでしょう。
書かれている内容は、面接でさらに深掘りされることも多いため、表面的な内容では通用しません。内容に一貫性がなければ、説得力を欠き、選考で不利になる可能性もあります。
自分の魅力が正しく伝わるよう、読み手の視点に立って書くことが大切です。準備に時間はかかりますが、しっかり対策しておけば、その後の選考も自信を持って進められるようになるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、ES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
企業がエントリーシート(ES)で見ているポイント

エントリーシート(ES)は、企業が学生の第一印象をつかむ重要な書類です。面接の前段階で、学生の能力や性格、志望度などを総合的に判断するために活用されています。
ここでは、企業がESのどこを見ているのかについて具体的に説明します。
- 能力やスキルの把握
- 性格や人柄の理解
- 志望動機や熱意の確認
- 企業との適性・相性の判断
- 論理的思考力・文章力の確認
①能力やスキルの把握
企業はESから、学生が持つ実践的な能力やポテンシャルを見極めようとしています。なぜなら、社会人としての基礎が身についているか、入社後に早期戦力になりうるかどうかが重要だからです。
特に重視されやすいのは、課題解決力、チームでの行動力、リーダーシップ、そして物事をやり遂げる粘り強さです。これらは、どの業界・職種でも求められる共通の能力といえるでしょう。
さらに、自分が得意とする分野と企業の事業内容・求める人物像が一致しているかも大切な視点です。
企業ごとに求めるスキルは異なるため、自己分析に基づき、自分の力をどのようにその企業で活かせるかを考えて表現する必要があります。
自分の経験が企業でどう再現できるのかを想像させることが、通過率向上につながるはずです。
②性格や人柄の理解
企業は、学生の性格や価値観にも大きな関心を寄せています。スキルや経験だけでなく、「どんな人か」「職場に馴染みやすいか」という視点でESを読んでいるのです。
とくに、協調性や誠実さ、努力を継続できる姿勢などは、長く働くうえで欠かせない要素として重視されがちです。
また、ESでは性格を直接的に書くよりも、経験を通じてにじみ出るようにするほうが、読み手に自然に伝わります。
「私は真面目です」と書くよりも、真面目に取り組んだ過程や行動を描写することで、説得力が生まれるのです。企業は「この人と働きたいかどうか」を重視しています。
そのため、自分がどういう人で、どのようなスタンスで物事に向き合ってきたのかを明確に言語化することが重要です。自分の性格と行動が一貫していることが伝われば、印象はさらに良くなるでしょう。
③志望動機や熱意の確認
志望動機はESの中でも特に注目されるポイントであり、企業が「本当にこの会社に入りたいのか」「入社後に長く働いてくれるかどうか」を見極める材料となります。
応募者の志望動機が浅かったり、他の会社でも使い回しできそうな内容だったりすると、魅力的に映りません。
そこで大切なのは、企業独自の魅力をしっかりと理解したうえで、自分の価値観や経験とどのようにリンクするかを言語化することです。
また、自分の経験と志望先企業のビジョンや仕事がどうつながるのかを丁寧に伝えることで、自然な熱意が伝わります。
アルバイトやゼミ活動、ボランティアなど、自分の実体験を踏まえて書くと、言葉に重みが出るでしょう。志望動機においては、相手をよく知ることと、自分の気持ちをしっかり整理することが鍵です。
企業との接点を探り、自分の言葉で語ることが、選考を通過するうえで大きな武器になるはずです。
④企業との適性・相性の判断
企業は、学生と自社との相性が良いかどうかもESから読み取ろうとします。なぜなら、どれだけ優秀でも社風や働き方が合わなければ、入社後のミスマッチや早期退職につながる可能性があるからです。
ESを通じて、「自分の価値観や働くうえで大事にしていること」が企業の文化や仕事のスタイルと合致していることを伝える必要があります。
たとえば、「裁量をもって働きたい」という希望を持つ学生であれば、それを尊重する社風がある企業との相性が良いでしょう。
自分の希望や特性を一方的に主張するのではなく、企業が掲げている理念や社員の働き方を踏まえたうえで、「だからこそこの企業で働きたい」と伝えることで納得感が生まれます。
会社説明会やOB・OG訪問で得た情報を引用するのも効果的です。適性や相性を意識した内容は、単なる自己PRや志望動機以上に、企業にとって重要な判断材料です。
「自分がこの企業で活躍するイメージが持てるかどうか」を明確に伝えることで、他の候補者と差をつけられるでしょう。
⑤論理的思考力・文章力の確認
企業がESで重視しているポイントの一つが、論理的な文章構成と分かりやすい表現ができているかどうかです。社会人としての基礎力には、的確に考えを伝える力が含まれています。
そこで、ESは「何をどう伝えるか」という書き方そのものも評価対象になるのです。
そのため、PREP法(Point→Reason→Example→Point)を意識して書くことが有効です。話の流れが自然で、読み手にも理解されやすくなります。
また、誤字脱字、文末の語尾のばらつき、表記の統一など、基本的な文書スキルも見られています。これらのチェックを怠ると、「丁寧さに欠ける人」という印象を与えてしまうおそれがあります。
構成と表現を工夫し、読み手の目線に立ったわかりやすい文章を意識することで、評価を一段と高めることができるでしょう。
エントリーシート(ES)の書き方|基本構成
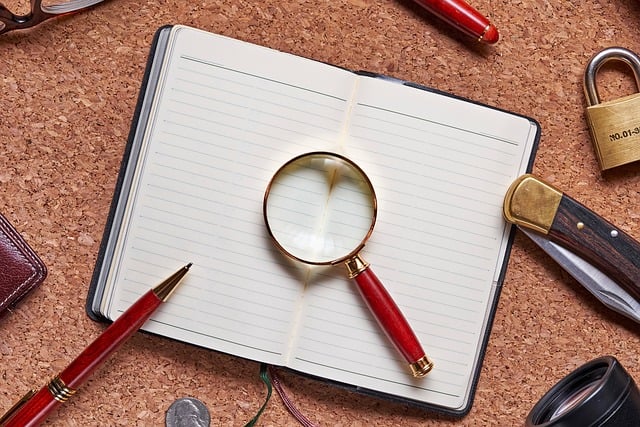
エントリーシート(ES)は、就職活動において最初の関門です。企業が学生を評価する際の重要な判断材料となるため、構成や内容には細心の注意が求められます。
ここでは、ESの基本的な構成と、企業が注目するポイントについて説明します。
- 基本情報の書き方
- 学歴・職歴の書き方
- 志望動機の書き方
- 自己PRの書き方
- 学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)の書き方
- 長所・短所の書き方
- 趣味・特技の書き方
①基本情報の書き方
ESにある基本情報欄では、名前や連絡先、住所などを正確に記入する必要があります。
これらは企業が応募者に連絡するための重要な情報であり、1つでも誤りがあると、連絡が取れず選考が進まなくなる恐れもあります。
特にメールアドレスの入力ミスはよくあるため、必ず提出前に確認してください。また、読みやすく整った文字で記載されているかも、企業側が無意識に評価する要素になります。
誤字脱字がないことはもちろん、項目に過不足なく記入されていることもチェックされるでしょう。
一見すると機械的な項目に見えるかもしれませんが、ここでも「丁寧に書いているか」「提出物に対する意識があるか」が伝わります。
細かいところまで意識する姿勢が、最終的に印象の差となって表れるものです。
②学歴・職歴の書き方
学歴や職歴欄では、一般的に最新のものから記載する「逆時系列」が基本です。しかし、ただ学校名や企業名を書くだけでは評価されません。
応募先企業の業務や求める人物像に関連づけながら、自分の背景を伝える意識が重要です。
たとえば、研究内容やゼミ活動が企業の事業に関係している場合、そのつながりを簡潔に補足することで興味を引くきっかけになります。
また、アルバイトやインターンの記載では、業務内容の説明にとどまらず、どのような課題に取り組み、どんな成長を得たのかを加えると、より深みが出るでしょう。
この欄では、「どこに所属していたか」よりも「そこでどんな姿勢で取り組み、何を得たのか」が問われています。単なる履歴ではなく、自己理解と志望先との接点を意識して書くことが求められます。
③志望動機の書き方
志望動機はESの中でも特に企業が重視する項目です。ここで大切なのは、「企業への共感」「職種への理解」「自分自身との一致点」を明確にすることです。
そのためには、徹底的な企業研究が不可欠となります。公式サイトだけでなく、社員インタビューやIR資料などからも情報を集め、他社との違いや魅力を洗い出しましょう。
企業の理念や文化に共感した点を軸に、自分の経験や価値観と重なる部分を探してください。
たとえば、学生時代の経験で感じたことが、企業のビジョンと一致していると気づいた場合、それをきっかけとして志望した理由を語ると自然な流れになります。
また、単に「成長できそう」「雰囲気が良い」といった曖昧な動機では説得力に欠けます。応募先でなければならない理由を、論理的かつ感情的に伝えることで、より強い動機として評価されやすくなります。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
④自己PRの書き方
自己PRは、あなたの強みを企業に伝える重要な機会です。まず、自分が最も誇れる強みをひとつに絞りましょう。
複数の要素を詰め込むと焦点がぼやけてしまうため、「この特性があるから自分は役に立てる」と明確に言える強みを選ぶことが大切です。
その強みを裏づけるエピソードには、背景・課題・行動・結果の4つの要素を盛り込むと、話に流れが生まれます。
たとえば「粘り強さ」をアピールする場合、途中で諦めずに工夫して乗り越えた経験を、数字や行動で具体的に描写してください。
さらに、企業の求める人物像や業務とその強みがどう結びつくのかを伝えられると、選考担当者の印象に残りやすくなります。
「自分の強みを企業のためにどう活かせるか」をイメージして書くことが、評価される自己PRのコツです。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
⑤学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)の書き方
ガクチカでは、活動の内容以上に、その取り組みに対する姿勢やプロセスが重視されます。企業は、あなたがどんな思考で動き、課題にどう向き合ったのかを知りたがっています。
そのためには、「なぜその活動に注力したのか」という動機から、「どんな工夫をしたのか」「何を乗り越えたのか」といった一連の流れを丁寧に伝える必要があります。
たとえば、サークルの立て直しを担当した場合、「メンバーが集まらない」などの課題にどう対処し、結果として何を得たのかまで述べると、読んだ側にあなたの人物像が伝わります。
成果が目立たない経験でも、問題発見から改善、実行までの過程を描ければ十分に評価されるでしょう。
重要なのは、「どんなことをしたか」ではなく、「どう考え、どう行動し、どう成長したか」です。自分らしいエピソードを選び、具体的なエビデンスを示すことが成功の鍵となります。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずはES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
⑥長所・短所の書き方
長所と短所の記載では、自分の性格や行動の特徴を整理し、応募企業にふさわしいものを選ぶことが大切です。
長所は、企業が求める人物像と合致している点を強調しながら、具体的な場面で発揮された実例を添えて書くと効果的でしょう。一方で、短所については自己分析の深さを見られる項目です。
単に「優柔不断です」といった表現だけでは足りず、それを自覚したうえで、改善のためにどのような行動をしているかを示すことが重要です。
「時間管理が苦手だったが、手帳でタスクを管理するようにした」といったように、具体的な対策を添えると前向きな印象を与えられます。
長所と短所はセットで評価されるため、バランスの取れた記述が求められます。誠実さと成長意欲が読み取れる内容を心がけてください。
⑦趣味・特技の書き方
趣味や特技の欄は、一見すると選考にあまり影響がなさそうに思えるかもしれませんが、実は人柄や価値観、コミュニケーション力を知るための重要なヒントになります。
内容自体に特別なインパクトがなくても、そこにどんな気持ちで取り組んでいるかを伝えることがポイントです。
たとえば、「バスケットボールが趣味」と書くだけではなく、「チームワークの大切さを学んだ」や「日々の練習を通じて継続力が身についた」など、自分の性格やスキルにどう結びついているかまで触れましょう。
また、他の応募者と差別化したい場合は、その趣味を選んだ理由や、その活動を通して成長できたことを具体的に書いてみましょう。
ES全体に一貫性を持たせるためにも、他項目との整合性も意識するとより完成度が高くなります。
エントリーシート(ES)を書く際の注意点

エントリーシート(ES)は、企業との最初の接点であり、第一印象を左右する重要な書類です。内容だけでなく形式にも注意を払うことで、選考通過の可能性を高められるでしょう。
特に基本的な表現や提出の管理など、見落としやすい点にも気を配ることが必要です。ここでは、ESを書く際の注意点について具体的に説明します。
- 求める人物像を確認する
- 話し言葉や口語表現を避ける
- 余白やレイアウトに配慮する
- 誤字脱字や文法ミスを確認する
- 提出期限を管理する
①求める人物像を確認する
ESを書く前に、企業がどのような人材を求めているかをきちんと理解しておくことが大切です。
企業ごとに重視するポイントは異なるため、それを把握せずに自己PRや志望動機を書くと、評価されにくくなってしまうでしょう。
企業の採用ページや説明会で語られる理念や求める人物像を参考にし、自分の経験や強みとどう結びつくのかを整理しておくと安心です。
単に努力した経験を伝えるのではなく、それが企業にとってどう役立つのかを示すことが評価の鍵となります。さらに、応募先の業界全体で共通して求められるスキルや価値観を把握することも効果的です。
自分の資質と照らし合わせて、相性のよさをアピールできれば、説得力が増すでしょう。企業研究が浅いと的外れな内容になってしまうため、書き始める前に十分に情報を集めておくことが欠かせません。
内容の方向性を定める土台として、求める人物像の把握は必須です。
②話し言葉や口語表現を避ける
エントリーシートは、ビジネス文書としての丁寧さが求められます。「〜じゃないですか」や「めっちゃ頑張った」などの話し言葉は避け、適切な文体で表現しましょう。
採用担当者は、文章の書き方からもビジネスマナーや基本的なスキルを見ています。砕けた表現は信頼を損ねる原因となりかねません。
ただし、硬すぎる表現も読みにくくなるため、敬語と簡潔な言葉を組み合わせて、読みやすさを意識することが大切です。
また、文章のテンポやリズムにも気を配りましょう。単調な文が続くと読み手の集中力が落ちやすくなるため、接続詞を活用して論理の流れを整理したり、語尾の表現に変化をつけたりすると効果的です。
言葉づかいは、応募者の「常識力」や「文章センス」が問われる部分でもあります。書き終えたあとに声に出して読んでみると、不自然な言い回しや口語が残っていないか確認しやすくなります。
③余白やレイアウトに配慮する
内容が充実していても、文字が詰まりすぎていたり、読みづらいレイアウトだったりすると、読む側に負担をかけてしまいます。そうした印象が評価に悪影響を与えることもあるでしょう。
改行や段落を使って適度に余白を取り、読みやすさを意識することで、文章の伝わり方が大きく変わってきます。また、文字サイズやフォントも指定通りに整え、見た目に乱れがないよう気を配りましょう。
視覚的に整った書類は、それだけで「丁寧に準備している」という印象を与えることができます。
たとえば、1段落ごとに明確な改行を入れる、余白を均等に取るなど、小さな工夫の積み重ねが読みやすさを左右します。
企業によってはフォーマットが決まっている場合もあるため、指示に従って作成することも忘れないようにしてください。
書類作成はビジネスマナーの一環でもあるため、レイアウトへの配慮を怠らないことが大切です。
④誤字脱字や文法ミスを確認する
どれほど内容がよくても、誤字脱字や文法のミスがあると、それだけで評価が下がることがあります。特に、文章の正確性を重視する企業では、細かな誤りが命取りになることもあるでしょう。
書き終えたあとは必ず見直しを行い、できれば家族や友人など第三者にも確認してもらうのがおすすめです。自分では気づけないミスを指摘してもらえる可能性が高くなります。
また、「てにをは」など助詞の使い方も注意して見直しましょう。主語と述語のねじれ、接続の不自然さなどもミスの一種です。
こうした細かな点に気づくには、一度時間を置いて読み返すと客観的に見やすくなります。
さらに、Wordの校正機能やAI校閲ツールを活用するのも有効です。単なる誤字脱字の確認にとどまらず、読みやすさや文章の流れまで意識してチェックできれば、完成度の高いESに仕上がります。
⑤提出期限を管理する
エントリーシートの提出期限を守ることは、社会人としての基本です。どれだけ内容が優れていても、締切を過ぎてしまえば評価の対象外になることもあります。
複数の企業にエントリーしている場合、期限が重なることも少なくありません。うっかりミスを防ぐためには、スケジュール帳やアプリを活用して、提出予定をきちんと管理する必要があります。
特に締切直前はアクセス集中でシステムに不具合が起こることもあるため、早めの提出を心がけることが大切です。提出ミスを防ぐためにも、期限の2〜3日前を目安に準備を終えておくと安心でしょう。
また、早く提出することで企業側の印象もよくなるケースがあります。「期日を守る姿勢」や「余裕を持って行動する能力」は、働くうえで欠かせない要素とされるため、評価対象にもなり得ます。
提出期限は単なる締切ではなく、自分を評価する重要な基準であると捉えておきましょう。
魅力的なエントリーシート(ES)を書くコツ

エントリーシート(ES)は、就職活動のスタートにおいて最重要といっても過言ではありません。魅力的なESを作成するには、自分の強みや企業理解を深めることが欠かせません。
ここでは、選考を通過するために必要な具体的な工夫を紹介します。
- 自己分析で強みを明確にする
- 企業研究で志望動機に深みを持たせる
- オリジナリティのある表現を工夫する
- テンプレートを活用しつつ個性を出す
- 第三者に添削してもらう
①自己分析で強みを明確にする
エントリーシートを書くには、まず自己分析が必要です。なぜなら、自分の強みや価値観があいまいなままだと、相手に伝わる内容にはならないからです。
たとえば「リーダーシップがあります」と書いても、何をどうしたかがわからなければ印象に残りません。そこで、過去の経験を振り返り、エピソードごとに行動や結果を整理してみましょう。
部活動、アルバイト、ゼミなどから、自分らしい一貫した特徴が見えてくるはずです。さらに、そのエピソードの背景や自分が感じた課題、工夫した点まで掘り下げると、自分だけのストーリーになります。
同じような経験でも、視点や行動の違いが強みとして伝わるのです。こうした深掘りを通じて、自信を持って語れる「根拠のある強み」を見つけてください。
魅力的なESは、表面的な自己アピールではなく、過去の行動に裏打ちされた一貫性のある自己理解がベースになります。
「自己分析がうまくできない…しっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる自己分析シートをを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、シートの構成に従って作成するだけで自己分析がスムーズに行えるので、自己分析に苦手意識がある方におすすめですよ。
②企業研究で志望動機に深みを持たせる
企業の採用担当者が特に注目するのが志望動機です。しかし、「業界に興味がある」「社会貢献したい」など、よくある言い回しでは印象に残りにくいでしょう。
そこで大切なのが、企業研究をしっかり行うことです。企業の理念や事業内容、最近の取り組みなどを調べることで、自分の価値観や目標と重なる部分が見つかります。
具体的なサービスやプロジェクトを挙げて、自分がどう貢献したいかを語ると説得力が高まります。
加えて、なぜ他の企業ではなくその会社なのかという視点も意識してみてください。類似する企業がある中で、その会社を選ぶ理由を語ることが差別化につながります。
事業戦略や社風、働く社員の声なども参考になります。企業に対する深い理解と共感を示すことが、他の応募者との差を生む決め手になります。
結果として、企業側に「一緒に働く姿」が具体的にイメージされやすくなるのです。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
③オリジナリティのある表現を工夫する
数多くのESの中で目を引くには、自分らしさの伝わる表現が効果的です。ただし、わざと変わったことを書く必要はありません。ポイントは、自分の言葉で経験や想いを語ることです。
たとえば、「挑戦を恐れない性格です」とだけ書くよりも、「文化祭で赤字だった予算を立て直し、黒字にできた経験から、予測不能な問題に向き合う力が身につきました」と書く方が伝わりやすいでしょう。
また、他人と同じような経験でも、そのとき自分が何を感じ、どう考えて行動したかを詳しく描くことで、唯一無二のエピソードになります。
表現はシンプルであっても、自分らしさがにじむ言葉を使うことが、読み手の記憶に残るコツです。
さらに、書き方の工夫もポイントです。同じ情報でも、伝え方次第で印象が大きく変わります。比喩や具体的な数字、情景描写などを適度に盛り込むことで、文章に厚みが出て魅力的になります。
④テンプレートを活用しつつ個性を出す
ESの書き方に迷ったら、テンプレートを使うのもよい方法です。特に、結論・理由・具体例・再主張の順に書くPREP法は、論理的に伝える構成として効果的です。
ただし、そのまま当てはめすぎると無難な印象になってしまいます。結論部分に自分らしい言葉を使ったり、具体例で感情や背景を加えたりすることで、文章に深みが出てきます。
テンプレートはあくまで「土台」として活用し、自分自身の視点で書き上げることが大切です。
内容の順序や構成にとらわれすぎず、自分が最も伝えたいポイントを軸にして、柔軟にアレンジする姿勢も必要でしょう。
また、テンプレートを使う際には、読み手が飽きずに読み進められるよう工夫も欠かせません。
たとえば、文体のリズムを変えたり、文末を言い切り型だけにしなかったりするなど、読みやすさを意識すると効果的です。
⑤第三者に添削してもらう
どれだけ内容に自信があっても、見落としや偏りは起こりがちです。そこで有効なのが、第三者に添削してもらうことです。
大学のキャリアセンターや就活経験のある先輩など、客観的な視点を持った人に見てもらいましょう。文章表現のクセや説得力の弱さなど、自分では気づけなかった点を指摘してもらえます。
特に重要なのは、読み手にとってわかりやすく、納得できる構成になっているかをチェックしてもらうことです。言いたいことが伝わっているか、自分では判断しにくいため、他人の視点が有効です。
さらに、フィードバックを受けてブラッシュアップを重ねることで、ESの完成度は大きく向上します。一度で完璧を目指すより、複数回の修正を前提にした方が良い結果につながるでしょう。
他者の意見を取り入れる柔軟性と、自分らしさを失わずに磨き上げる姿勢が、評価されるESを生み出します。
【例文付き】エントリーシート(ES)の自己PRの書き方

エントリーシート(ES)の自己PR欄に、どんな内容を書けば良いのか悩んでいませんか?
ここでは、さまざまな強みごとの例文を紹介し、自分に合った表現方法が見つかるようにサポートします。
- 協調性をアピールする例文
- 主体性をアピールする例文
- 継続力をアピールする例文
- 責任感をアピールする例文
- 柔軟性をアピールする例文
- チャレンジ精神をアピールする例文
- 行動力をアピールする例文
- リーダーシップをアピールする例文
- 論理的思考力をアピールする例文
- 傾聴力をアピールする例文
実際に自己PRを書き始められるように、カリクルは全力で就活生を応援しています。
まだ自己PRの作成ができていない方は自動生成ツールでサクッと、すでに自己PRができている人は赤ペンESという無料添削サービスで自己PRを添削してもらいましょう!
すべて「完全無料」で利用できますよ。
また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。
無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介
①協調性をアピールする例文
今回は、グループでの協力や周囲との連携を通じて成果を出した経験を通じて、「協調性」をアピールする例文を紹介します。
| 大学のゼミで5人チームを組み、地域活性化をテーマにプレゼンを行いました。 メンバーの意見が対立する場面もありましたが、私はまず全員の意見を丁寧に聞き、一人ひとりの考えを整理しながら共通点を探ることに注力しました。 その結果、全員が納得できる方針を導き出すことができ、発表本番では質疑応答も含めて高評価を得られました。 この経験を通して、異なる価値観を持つ人同士が意見を尊重し合いながら一つの目標に向かって進むことの大切さを学びました。 |
周囲の意見を尊重しながら自ら動いた経験を具体的に描くことで、協調性が自然と伝わる構成になっています。「聞く姿勢」や「まとめ役」の行動が含まれていると、より印象が良くなります。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
②主体性をアピールする例文
今回は、自ら課題を見つけ、周囲を巻き込みながら行動した経験を通じて、「主体性」をアピールする例文を紹介します。
| 大学のサークルでイベントの参加者が年々減少していることに課題を感じ、自らアンケートを実施して要因を分析しました。 その結果、宣伝不足と内容のマンネリ化が原因と分かり、新たにSNSを活用した広報施策と、新企画の立案を提案しました。 メンバーの協力も得ながら改善を進めた結果、参加者数を前年の2倍に増やすことができました。この経験を通じて、自ら動くことで組織に良い変化をもたらせると実感しました。 |
主体性を伝えるには、「自分が課題をどう見つけ、どう動いたか」を明確にすることが大切です。行動の理由や成果を数字で示すと説得力が増します。
③継続力をアピールする例文
今回は、困難な状況でも諦めずに取り組み続けた経験を通じて、「継続力」をアピールする例文を紹介します。
| 私は大学入学当初から英語力を高めたいと考え、毎朝30分間の英語ニュースのリスニングを3年間継続しました。 最初は内容をほとんど理解できず挫折しそうになりましたが、辞書を片手に少しずつ慣れていきました。 その結果、TOEICのスコアは初回の450点から最終的には800点を超えるまでに向上しました。この習慣を通して、小さな努力を積み重ねることの大切さを実感しました。 |
継続力は結果とセットで示すと強い印象になります。「どれくらい続けたのか」「どんな成果が出たのか」を具体的に伝えるようにしましょう。
④責任感をアピールする例文
今回は、自分の役割に責任を持ってやり遂げた経験を通じて、「責任感」をアピールする例文を紹介します。
| 学園祭の実行委員として、ステージイベント全体の進行管理を担当しました。 当日は予想外の機材トラブルが発生しましたが、すぐに代替手段を提案し、他のスタッフと連携して無事にスケジュール通りの進行を実現しました。 責任者として最後まで現場を見守り、関係者から「安心して任せられた」と言っていただけたことが自信につながりました。 この経験を通して、自分の役割に責任を持ち、信頼を築く大切さを学びました。 |
責任感を伝える際は、トラブルやピンチの場面でどう対応したかを盛り込むと印象が強まります。周囲の信頼を得た点も評価されやすいポイントです。
⑤柔軟性をアピールする例文
今回は、状況に応じて考え方や行動を変えながら対応した経験を通じて、「柔軟性」をアピールする例文を紹介します。
| アルバイト先の飲食店で、新人スタッフが急遽休んだため、急きょ担当外のホール業務を任されました。 普段はキッチン専門でしたが、臨機応変に対応するため、マニュアルを確認しつつ他のスタッフに助言をもらいながら対応しました。 その結果、大きな混乱もなく営業を終えることができ、店長からも感謝されました。この経験を通じて、状況に応じて役割を柔軟に切り替える力の大切さを実感しました。 |
柔軟性は「想定外の出来事にどう対応したか」で表現しましょう。未経験の業務への対応や他者との協力も、好印象につながるポイントです。
⑥チャレンジ精神をアピールする例文
今回は、新しいことに前向きに取り組んだ経験を通じて、「チャレンジ精神」をアピールする例文を紹介します。
| ゼミ活動で、自分にとって未知のテーマである「地方創生」に関する発表を担当しました。 知識がなかったため、自治体の取り組みを自ら調査し、オンラインで地域の職員の方にインタビューを行いました。 不安もありましたが、積極的に行動することで内容の深い発表ができ、教授からも高い評価を得ました。この経験から、未知のことにも挑戦し、自ら成長の機会を作り出す姿勢の重要性を学びました。 |
チャレンジ精神は「不安や苦手意識がある中で挑んだ」姿を描くことで伝わりやすくなります。挑戦後の変化や成果も具体的に示しましょう。
⑦行動力をアピールする例文
今回は、自ら考えてすぐに行動に移した経験を通じて、「行動力」をアピールする例文を紹介します。
| 大学の授業で、地域の企業と連携して課題解決に取り組むプロジェクトがありました。 私は誰よりも早く企業にアポイントを取り、現場に直接出向いて話を聞きました。 授業の進行より先回りして動いたことで、具体的な課題を早期に把握でき、チーム全体の提案の質を高めることにつながりました。 この経験を通して、すぐに行動することで周囲に良い影響を与えられると実感しました。 |
行動力は「スピード」と「自発性」がカギです。誰よりも早く動いたエピソードや、行動が周囲にどう影響したかを意識的に伝えると効果的です。
⑧リーダーシップをアピールする例文
今回は、周囲をまとめながら目標を達成した経験を通じて、「リーダーシップ」をアピールする例文を紹介します。
| ゼミの研究発表会に向けてリーダーを務めました。メンバーの得意分野を生かせるよう役割分担を工夫し、週1回のミーティングを通じて進捗管理や意見調整を行いました。 時にはメンバーのモチベーションが下がることもありましたが、個別に話を聞いてサポートしました。 その結果、発表は無事成功し、全員から「一体感を持って取り組めた」と言ってもらえました。この経験を通して、人をまとめる力の重要性を学びました。 |
リーダーシップは「メンバーへの配慮」や「課題解決」が見える構成が効果的です。成果だけでなく、過程の中での工夫や苦労も含めると説得力が増します。
⑨論理的思考力をアピールする例文
今回は、情報を整理して筋道立てて物事を考えた経験を通じて、「論理的思考力」をアピールする例文を紹介します。
| 大学のレポート課題で、異なる統計データから結論を導く必要がありました。私はまず各データを表にまとめ、関連性や矛盾点を分析しました。 その上で、根拠を明示したうえで結論を提示し、読み手にも納得してもらえるよう工夫しました。 結果として、担当教授からは「論理構成が明快で説得力がある」と高く評価されました。この経験から、情報を整理し、順序立てて伝えることの大切さを実感しました。 |
論理的思考力は、「情報整理の工夫」や「因果関係の説明」で見せましょう。データ活用や、相手に伝わるよう意識した構成も効果的です。
⑩傾聴力をアピールする例文
今回は、相手の話をしっかり聞くことで信頼を得た経験を通じて、「傾聴力」をアピールする例文を紹介します。
| 大学のキャリアセンターでピアサポート活動をしていた際、就職に悩む後輩の相談に乗る機会がありました。私はアドバイスを急がず、まず相手の気持ちや不安を丁寧に聞くことに徹しました。 次第に後輩も本音を話すようになり、最終的には自分で納得のいく進路を選ぶことができました。後日「話を聞いてもらえて本当に救われた」と言ってもらえたことが印象に残っています。 この経験を通じて、相手の声に耳を傾ける大切さを学びました。 |
傾聴力は「話を聞く姿勢」や「相手の変化」を具体的に描くことがポイントです。自分が支えになれたことを自然に伝えると印象が良くなります。
【例文付き】エントリーシート(ES)のガクチカの書き方

エントリーシートの「ガクチカ」欄で、自身の経験の伝え方で悩む人は決して少なくありません。ここでは、実際の経験を活かした例文を通して、ガクチカの具体的な書き方を丁寧に解説します。
- アルバイト経験を使ったガクチカ例文
- インターン経験を使ったガクチカ例文
- 部活・サークル経験を使ったガクチカ例文
- 留学経験を使ったガクチカ例文
- 研究活動を使ったガクチカ例文
- 趣味・自主活動を使ったガクチカ例文
- ゼミ活動を使ったガクチカ例文
- ボランティア経験を使ったガクチカ例文
- 資格取得の経験を使ったガクチカ例文
- イベント運営経験を使ったガクチカ例文
①アルバイト経験を使ったガクチカ例文
今回は、飲食店でのアルバイトを通して、課題解決力や周囲との連携をアピールした例文を紹介します。忙しい環境での工夫や改善の取り組みがポイントになります。
| 大学2年から居酒屋でホールスタッフとしてアルバイトをしていました。繁忙期には注文ミスや配膳の遅れが頻発しており、クレームも増加していました。 そこで私は、スタッフ全員がスムーズに動けるよう、注文内容や卓番を記載するホワイトボードを設置することを提案しました。 また、新人スタッフには配膳ルートの基本を共有し、効率的な動線を意識するよう働きかけました。 その結果、クレーム数は月に平均5件から1件以下に減少し、お客様から「以前よりスムーズ」との声もいただきました。 忙しい中でも冷静に課題を見つけ、改善策を実行する力を身につけることができました。 |
この例文では、課題に気づき改善提案を自ら行った点が評価につながります。アルバイト先での小さな工夫でも、成果や周囲への影響が明確に伝わるように書きましょう。
「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずはES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。
②インターン経験を使ったガクチカ例文
ここでは、企業での短期インターンを通して学んだ姿勢や成果をアピールする例文を紹介します。実務を体験したからこそ得られた成長を軸に書くのがポイントです。
| 大学3年の夏、IT企業で2週間のインターンに参加しました。初日は緊張からうまく発言できず、グループワークで消極的になってしまいました。 そこで、自分の役割を明確にし、毎日終業後に振り返りをすることで、次第に自信をつけていきました。3日目以降は積極的に意見を出し、最終日にはグループの発表資料作成を任されました。 その結果、発表は高評価を得て、社員の方から「リーダーシップが光っていた」とコメントをいただきました。この経験を通じて、苦手意識を克服し、行動力と主体性の重要性を学びました。 |
この例文では、成長のプロセスがしっかり描かれています。最初からうまくいかない体験を書くことで、変化や努力がより際立つ構成になります。
③部活・サークル経験を使ったガクチカ例文
部活やサークルでの経験は、チームワークや継続力をアピールしやすいテーマです。今回は部内での役割を通じてリーダーシップを発揮した事例を紹介します。
| 大学ではダンスサークルに所属し、2年次には代表を務めました。新型ウイルスの影響で活動が制限される中、モチベーションの低下や練習の減少が課題となっていました。 そこで私は、オンラインでのダンス練習会や週1回の交流ミーティングを企画・運営しました。 最初は参加者が少なかったものの、継続的に工夫を加えることで参加率が向上し、1ヶ月後には全員が毎週参加するようになりました。 代表として、困難な状況下でもメンバーのやる気を引き出し、活動の継続に貢献できました。 |
この例文は、逆境での工夫や粘り強さが伝わる内容です。課題と工夫、その結果までを具体的に書くと説得力が増します。
④留学経験を使ったガクチカ例文
留学経験では、異文化への対応力や自立性を伝えることが重要です。今回は言語の壁を乗り越えた努力と変化を描いた例文を紹介します。
| 大学2年時にアメリカへ半年間の語学留学をしました。最初の1ヶ月は英語がうまく聞き取れず、授業でも発言を避けるようになっていました。 しかし、このままでは何も得られないと思い、毎日1人のクラスメイトに話しかけることを自分に課しました。 最初は会話が続きませんでしたが、続けるうちにリスニング力が向上し、次第に会話も自然になっていきました。 3ヶ月後には現地のディスカッション授業で発表もできるようになり、自信を持てるようになりました。苦手を克服する力と自立心を育めた貴重な経験です。 |
留学経験は「環境の違いへの挑戦」を中心に書くと好印象です。行動の積み重ねと変化を明確に伝えましょう。
⑤研究活動を使ったガクチカ例文
研究活動では、課題解決力や粘り強さをアピールできます。今回は行き詰まりから改善策を導いたエピソードを紹介します。
| 大学3年からゼミで環境問題に関する研究を行っています。私はプラスチック廃棄物に関するアンケート調査を担当しましたが、回収率が予想より低く、十分なデータが得られませんでした。 そこで、対象を学生だけでなく地域住民にも広げ、大学の掲示板やSNSでも告知する方法に切り替えました。 その結果、回収率は従来の2倍となり、必要なデータが集まりました。この経験を通じて、柔軟に戦略を変更することで、課題を乗り越える力を身につけることができました。 |
研究は地道な努力の積み重ねが多いため、失敗と改善のプロセスをセットで書くと説得力が増します。
⑥趣味・自主活動を使ったガクチカ例文
趣味や個人活動も、主体性や継続力を示す題材になります。今回は動画制作を続けて得られた経験を紹介します。
| 高校時代から趣味で始めた動画制作を、大学に入ってからも継続しています。最初は友人向けに旅行の記録をまとめる程度でしたが、SNSに投稿するうちに再生数が増え、多くの人に届くようになりました。 より見やすく編集するために、独学で編集ソフトを学び、週に1本のペースで動画を制作・投稿しました。半年後にはフォロワーが1000人を超え、企業からPR動画の依頼をいただくまでになりました。 この活動を通して、自分で学び、試行錯誤を重ねる力が養われました。 |
自主活動は「なぜそれを始めたか」「どう成長したか」が大切です。数字や成果を入れると信頼性も高まります。
⑦ゼミ活動を使ったガクチカ例文
ゼミ活動では、チームでの議論や発表の経験が強みになります。今回はグループ発表での役割を通じた成長を紹介します。
| 所属ゼミでは月1回のグループ発表があり、私は資料作成と発表の進行役を担当しました。テーマが抽象的で、内容が伝わりにくいという課題があったため、視覚的に理解しやすい資料作りを意識しました。 具体的には、難しい言葉を図や事例に置き換え、要点を箇条書きで整理しました。その結果、教授から「構成が明確で分かりやすかった」と評価され、以後の発表の参考にされることになりました。 情報を整理し、相手に伝える力を身につけた経験です。 |
ゼミでの役割や工夫した点を具体的に書くと、貢献度が明確になります。発表の評価など客観的な事実も加えると効果的です。
⑧ボランティア経験を使ったガクチカ例文
ボランティア活動では、社会貢献意識や行動力を伝えることができます。今回は地域清掃活動に参加した経験を紹介します。
| 大学の地域連携プロジェクトの一環で、月1回の清掃ボランティアに1年間参加しました。 初めはただ作業をこなすだけでしたが、ある日住民の方から「ありがとう」と声をかけられたことで、地域との関わりを意識するようになりました。 その後は、自分から地域のゴミ問題について調べ、他の参加者にも情報共有を行いました。さらに、ゴミ分別の啓発チラシを自主的に作成・配布し、清掃活動の意義を広げることができました。 人の役に立つことの喜びと、自ら動く大切さを実感しました。 |
小さな行動でも、自発的に取り組んだ姿勢や継続性を見せると印象的です。周囲との関わりも描くと深みが増します。
⑨資格取得の経験を使ったガクチカ例文
資格取得は努力や継続力をアピールするのに適したテーマです。今回は学業と両立して勉強を進めた例を紹介します。
| 大学2年のときに、簿記2級の資格取得を目指しました。経済学部に所属していましたが、日々の講義や課題に加えて資格勉強を両立させるのは大変でした。 そこで、毎日30分は必ず勉強する時間を確保し、週末には過去問に集中するなど、計画的に進めました。 途中で模試の点数が伸び悩み、くじけそうになりましたが、苦手な論点を繰り返し復習することで理解を深めました。結果として一発合格でき、自分の努力が形になる経験となりました。 |
資格勉強では「時間の使い方」や「乗り越えた壁」に焦点を当てましょう。地道な努力が伝わる書き方が評価されやすいです。
⑩イベント運営経験を使ったガクチカ例文
イベント運営の経験は、企画力や実行力、チームワークをアピールする題材になります。今回は学園祭の運営を通じた挑戦を紹介します。
| 大学の学園祭で、模擬店エリアのリーダーを務めました。40以上の出店団体との調整や配置決定が必要で、情報の整理と連絡の徹底が課題でした。 私はExcelで管理表を作成し、LINEグループを活用して情報共有を行いました。 最初は連絡の行き違いが多く苦労しましたが、毎週の進捗会議を設けることで問題を早期に発見し、解決できる体制を整えました。 結果として、全団体が予定通り出店でき、多くの来場者に楽しんでもらうことができました。 |
イベント運営は「調整力」や「計画実行力」を示せる絶好のテーマです。大人数をまとめた工夫や仕組みも具体的に書きましょう。
【職種別】エントリーシート(ES)の志望動機例文

エントリーシートを書く際、「自分の志望動機がその職種に合っているのか不安…」と感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、職種ごとに具体的な志望動機の例文を紹介します。
志望する職種の特徴を押さえながら、自分に合った表現を見つけるヒントにしてください。
- 営業職の志望動機例文
- 技術職の志望動機例文
- 事務職の志望動機例文
- エンジニア職の志望動機例文
- コンサルタント職の志望動機例文
- マーケティング職の志望動機例文
- 企画職の志望動機例文
- 人事職の志望動機例文
- 金融業界の志望動機例文
- メーカーの志望動機例文
そもそも志望動機がうまく作れない……と悩む人は、以下の自動生成ツールでサクッと作ってしまいましょう。まずはとっかかりを掴むことが重要ですよ。
逆に、既に志望動機がある人には「赤ペンES」がオススメ!現役の就活のプロが、今回の添削例文よりもさらに詳細な解説付きで、志望動機を無料添削しますよ。
また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。
無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介
①営業職の志望動機例文
営業職を志望する学生がよく書くテーマの一つに、「人と関わることが好き」という内容があります。今回は、その中でも大学生活のエピソードを活かした例文をご紹介します。
| 私は大学時代、飲食店でのアルバイトを通じて接客の楽しさを学びました。お客様に対して丁寧な対応を心がけることで、リピーターになっていただけたことに喜びを感じました。 また、売上目標に向けてスタッフと協力し、販促キャンペーンを考える機会もありました。その経験から、目標に向かって仲間と取り組む達成感と、信頼関係を築く大切さを実感しました。 営業職は、お客様の課題に寄り添いながら信頼を得て、提案を重ねていく仕事だと理解しています。私はこれまでの経験を活かして、相手の立場に立った提案ができる営業として貢献したいと考えています。 |
アルバイト経験と人との関わりを軸に、自分の強みと営業職の適性を結びつけています。同じテーマを書く場合は、エピソードの中で「どんな学びがあったか」を具体的に伝えることがポイントです。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
②技術職の志望動機例文
技術職の志望動機では、「ものづくりへの興味」や「課題解決への関心」を中心に語るケースが多く見られます。今回は、授業や実験の体験をもとにした例文をご紹介します。
| 私は大学の実験授業でロボットの制御プログラムを開発した際、失敗を繰り返しながらも改良を重ねる過程に魅力を感じ、ものづくりに強い関心を持ちました。 特に、原因を一つひとつ検証しながら仮説を立て、少しずつ動作が改善される過程にやりがいを感じました。 この経験から、自分の手で仕組みを作り上げることの達成感と、チームで課題を乗り越える面白さを知りました。 貴社のように技術を通じて社会課題に貢献する企業で、自分の知識を活かして粘り強く取り組み、成長していきたいと考えています。 |
実験の経験を通して、課題解決の姿勢と探究心を表現しています。技術職では「学んだことがどのように仕事に活かせるか」を具体的に書くと説得力が増します。
③事務職の志望動機例文
事務職を目指す場合、「丁寧さ」や「正確性」「サポート志向」といった特性を活かした志望動機が効果的です。今回はゼミ活動を通じた気配りを軸にした例文をご紹介します。
| 私は大学のゼミで議事録や資料作成の担当をしており、メンバーがスムーズに議論できるよう細かい部分まで配慮することにやりがいを感じてきました。 特に、スケジュール管理や提出物の確認など、全体が円滑に進むようサポートすることで感謝される場面が多く、自分の役割に誇りを持つようになりました。 事務職は縁の下の力持ちとして組織を支える重要な役割だと考えています。正確さや気配りを大切にする私の性格を活かし、チームが安心して業務に集中できる環境を整えていきたいです。 |
ゼミでの役割を通じて事務職に必要な要素を表現しています。サポートや気配りの具体的なエピソードを盛り込むと、事務職との親和性が伝わりやすくなります。
④エンジニア職の志望動機例文
エンジニア職を志望する場合、プログラミングや開発への関心をもとにした経験談が効果的です。今回は、アプリ制作をきっかけに志望を深めた例文を紹介します。
| 私は大学で初めて作成したスマートフォン向けの簡単なToDoアプリが思い通りに動いたとき、大きな達成感を覚えました。 バグの修正やUIの改善を繰り返す中で、より使いやすいものを目指す開発の面白さに惹かれました。また、ユーザーの視点を意識して工夫を重ねる過程で、エンジニアとしての視座が広がりました。 貴社が提供するサービスにもユーザー目線の工夫が多く、そこに魅力を感じました。私も常に改善を重ねながら、ユーザーに寄り添う開発を行いたいと考えています。 |
開発経験を通じてエンジニアとしての適性と成長意欲を伝えています。実際に手を動かした経験をもとに、学びと意欲を表現することがポイントです。
⑤コンサルタント職の志望動機例文
コンサルタント職では、課題分析や論理的思考力に加えて「人と関わる力」も重要です。今回は学園祭での実行委員の経験をもとにした例文をご紹介します。
| 私は大学の学園祭で実行委員を務め、予算調整や出店者との交渉を担当しました。 限られた資金の中で最適な案を考えることや、意見の対立を調整する難しさを経験しましたが、同時に課題を整理し、具体的な解決策を導き出す面白さも感じました。 この経験から、複雑な問題に対して冷静に考え、実行に移す力を身につけることができました。 貴社でのコンサルタント職では、こうした経験を活かし、クライアントに信頼される存在を目指して努力していきたいと考えています。 |
問題解決への興味と行動力を結びつけ、コンサルの適性を表現しています。課題→行動→結果の流れを意識して書くと、説得力が増します。
⑥マーケティング職の志望動機例文
マーケティング職の志望動機では、「人の心を動かすこと」や「企画力」に関するエピソードが効果的です。今回は、SNS運用の経験をもとにした例文をご紹介します。
| 私は大学のサークルでSNSを活用した広報を担当し、投稿内容やタイミングを工夫することでフォロワー数を大幅に増やすことができました。 最初は手探りでしたが、過去の投稿データを分析し、写真や文言を変えることで反応が変わることを学びました。この経験から、相手の興味や感情に働きかけるマーケティングの面白さを知りました。 貴社のようにユーザーと向き合いながらサービスを届ける企業で、より多くの人に価値を伝える提案をしていきたいと考えています。 |
SNS運用の成果を通じて、マーケティングへの興味と工夫を具体的に伝えています。数字や結果を交えて書くことで説得力が強まります。
⑦企画職の志望動機例文
企画職では、「アイデアを形にする力」や「人を巻き込む力」に焦点を当てると効果的です。今回はゼミでの企画運営を軸にした例文をご紹介します。
| 私は大学のゼミで合宿の企画運営を担当しました。全員が楽しめるような内容を考え、アンケートを通じて希望を集めたり、予算内で宿泊先や交通手段を比較検討したりと、細かな準備を重ねました。 当日はスムーズに進行でき、参加者からも「楽しかった」と言ってもらえたことが大きな喜びでした。 この経験から、ゼロから形にしていく企画の面白さと責任感を学びました。貴社でもアイデアを現実にする力を磨き、多くの人に喜んでもらえる企画を実現していきたいです。 |
実際に行った企画の工夫と成果を伝えており、企画職への適性が伝わりやすい構成です。相手の立場に立った工夫を加えるとより印象的になります。
⑧人事職の志望動機例文
人事職を志望する場合は、「人の成長に関わりたい」という動機が多く見られます。今回は、アルバイトでの後輩指導の経験を基にした例文をご紹介します。
| 私は飲食店のアルバイトで、新人スタッフの教育を任されたことがあります。 最初は教えることに不安もありましたが、一人ひとりのペースに合わせて丁寧に指導するうちに、後輩が自信を持って働けるようになる姿に大きなやりがいを感じました。 この経験から、人の成長を支えることに強い関心を持つようになりました。貴社の人事職では、社員の採用や育成を通じて組織の成長に貢献したいと考えています。 人を支えることに責任と喜びを持って取り組んでいきたいです。 |
後輩指導の経験を通じて「人の成長への関心」を自然に表現しています。指導したこととその結果を明確に書くと、人事職との親和性が高まります。
⑨金融業界の志望動機例文
金融業界では「信頼される人間性」や「数字に強いこと」への関心があると好印象です。今回は、家計管理を通じて興味を持った例文をご紹介します。
| 私は大学入学と同時に一人暮らしを始め、毎月の支出を家計簿アプリで記録する習慣が身につきました。 無駄遣いを減らしながらも必要な投資を見極めることで、お金の使い方次第で生活の質が大きく変わることを実感しました。 この経験から、金融に関わる知識が人々の生活に直結していることに気づき、興味を持つようになりました。 貴社のように信頼を軸にした金融サービスを提供する企業で、お客様の未来に貢献できる存在を目指していきたいと考えています。 |
身近な体験を通じて金融への関心を自然に伝えています。「金融=難しい」印象を和らげるには、日常とのつながりを強調するのが効果的です。
⑩メーカーの志望動機例文
メーカーへの志望動機では、「ものづくりへの共感」や「社会貢献性」を軸にすることが効果的です。今回は、製品を通じた感動体験をもとにした例文をご紹介します。
| 私は高校生の頃、家庭で使っていた調理家電が壊れた際に、家族で買い替えた製品の使いやすさに感動した経験があります。 それ以来、誰かの生活を便利にする製品を作る仕事に興味を持つようになりました。 大学では製品の設計について学ぶ機会があり、機能性だけでなく使う人への配慮がものづくりにおいて大切だと感じました。 貴社が手がける製品も日常に寄り添った工夫が多く、共感しました。私も生活者目線を大切にしながら、多くの人に価値を届ける製品づくりに携わりたいです。 |
生活の中で得た気づきを起点に、メーカーとの親和性を示しています。製品を「使った経験」を活かすと説得力が増します。
エントリーシート(ES)作成について学び、就活の第一歩を踏み出そう!

就職活動においてエントリーシート(ES)は、自己を企業に伝える最初の重要な手段です。
ESでは能力やスキル、性格、志望動機といった多角的な視点から評価され、内容次第で面接に進めるかどうかが決まります。
基本構成や書き方のポイント、注意点を押さえることはもちろん、魅力的な表現や具体例を盛り込むことで、他の就活生との差別化が図れます。
実際の例文を参考にしながら、自分らしさを的確に伝えることが重要です。ESは単なる応募書類ではなく、自己PRの場であることを意識して取り組みましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









