【就活生必見】面接での自己紹介の解答例を紹介|評価ポイントも解説
面接では、「まず簡単に自己紹介をしてください」と言われる場合がよくあります。しかし、面接官の聞きたい内容とは違うことを、話し始めてしまう就活生はたくさんいるようです。
そこで、本記事では自己紹介で伝えるべき要素や注意したいポイントを解説します。ぜひ、面接対策の参考にしてくださいね。
差別化できる!自己紹介のお役立ち特典
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|志望動機
- 5つの質問に答えて簡単に質高く
- 3自己PR作成ツール|受かる自己PRに
- 3分で好印象な自己PRが作成できる
就活面接における自己紹介と自己PRの違い
自己紹介は自己PRと似ていますが、全く別物です。まず、自己PRとの違いを正しく認識してくださいね。
- 自己紹介はコミュニケーションの掴み
- 自己PRはアピールチャンス
①自己紹介はコミュニケーションの掴み
面接での自己紹介は、就活生が初めて会う面接官とコミュニケーションを図るきっかけになる挨拶です。
したがって、自分に関するプロフィールを簡潔に伝えてください。具体的に伝えるのは、名前・学校情報・趣味・ガクチカのような基本情報と意気込みです。
学校情報には学部・学科・学年が含まれます。面接中にPRをしたい内容に、簡単に触れるのもおすすめですよ。ゼミ・アルバイト・部活動のような、学生時代に力を入れてきた活動があれば、最後に付け加えましょう。
②自己PRはアピールチャンス
その一方で自己PRは、自身の強みや意欲をアピールするものです。すなわち、「あなたを採用すると、どのようなメリットがあるのか」を、面接担当者に説明します。
自己PRでは、「自分の強み」「強みの信頼性を上げるためのエピソード」「強みの仕事への活かし方」を話すのが一般的です。
面接官が応募者の雰囲気を知るために自己紹介を求めたのに、自己PRを始めてしまうと「コミュニケーション能力に問題がある」と思われる可能性があります。
就活面接の自己紹介を求める企業意図

企業側が面接で最初に自己紹介を投げかけるのは、就活生の人柄や特徴を簡単に把握したいからです。
志望動機や自己PRを質問する前に就活生の人柄を確認して、「どのように進めるべきか」「何を深掘りすべきか」を採用担当者は考えます。
それ以外にも質問によって、履歴書やエントリーシートの記載事項に間違いがないかチェックしたり、経歴を改めて確認したり、会話を始めるきっかけにする意図もあるでしょう。
就活面接の自己紹介における企業の評価ポイント
話す内容も重要ですが、それ以外にも注意すべきことがあります。自己紹介で企業担当者に見られているポイントは、主に以下2つです。
- 第一印象
- マナー
①第一印象
自己紹介は面接官に与える第一印象が決まるとても重要な要素であり、もし第一印象が悪いと限られた時間だけではイメージを覆せないかもしれません。
話しているときの表情や視線もしっかり見られており、悪い印象を与えないように気をつけてくださいね。
面接中は誰でも緊張して、声が小さかったり、早口で話したり、ぎこちなくなりやすいので、明るい表情と真っ直ぐな姿勢を保って、面接官の目を見ながらハキハキと話すように心がけましょう。
②マナー
面接で急に敬語を上手に使うのは難しいので、誤った敬語を使ってしまう学生もたくさんいると思います。
就活でよく使用する尊敬語や謙譲語を事前に覚えておき、大学やアルバイトの先輩と普段話すときから、正しい敬語が使えるように練習しておきましょう。
自己紹介では話し方や言葉遣いのような、社会人に必要な基本的なマナーも常に評価されています。髪型や服装のような身だしなみも影響するため、細かな部分にも注意が必要なのです。
就活面接の自己紹介で伝えるべき内容

自己紹介で伝える主な内容は以下の3点です。ただし、企業によっては話す内容を決められていたり、時間の指定があるケースもあります。
- 自身のプロフィール
- 学生時代に力を入れたこと
- 本日の意気込み
①自身のプロフィール
最初に「初めまして。〇〇大学〇〇学部〇〇学科から参りました〇〇と申します。」のように名乗りましょう。
氏名だけでなく、学校名・学部名・学科名を入れて自己紹介して、略さずに正式名称で言うように気をつけてください。
②学生時代に力を入れたこと
続いて、自分自身をアピールするために必要な情報を追加しましょう。
ゼミ・部活動・アルバイトのようなガクチカ以外にも、趣味や特技でも、「あなたらしさ」が伝われば問題ありません。
ただし、自己PRの場ではないので、話しすぎないようにしてくださいね。
③本日の意気込み
最後に、挨拶や意気込みを語るのが一般的です。面接の機会を頂いたことを感謝する気持ちを、「よろしくお願いいたします」と伝えれば問題ありません。
もしくは、意気込みを1~2文で語ってから挨拶で終えると理想的です。
就活面接の自己紹介における回答例2つ
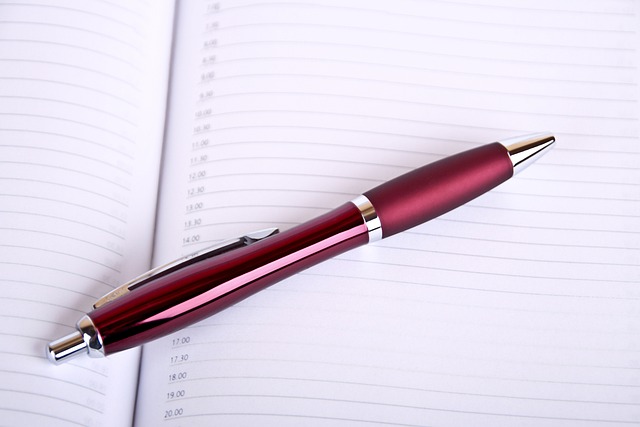
ここで、自己紹介例を2つ紹介します。強調したいポイントを選定しつつ、自分が頑張った内容を紹介してみましょう。
- 例文①: 部活経験をアピールする場合
- 例文②: アルバイト経験をアピールする場合
例文①: 部活経験をアピールする場合
部活動経験のアピールで重要なのは、チームワークです。協調性を重視する企業は多く存在するため、好印象を得られるでしょう。
| 〇〇大学〇〇学部〇〇学科から参りました、〇〇です。 私は中学生のときにサッカーを始め、大学4年間もサッカー部に所属していました。推薦でキャプテンになってからは、チームの目標である大会優勝のために、常に力を注いでおります。サッカーはチームワークが大切なので、大会のために声掛けを全体で行い、同時に大会へのモチベーションも高めた結果、優勝を果たすことができました。 また、私が務めているポジションはミッドフィルダーで、チームのバランスを見ながらゲームメイクを行うポジションです。サッカー部での経験で得たリーダーシップや視野の広さを活かして、御社でも活躍したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 |
例文②: アルバイト経験をアピールする場合
アルバイト経験を自己紹介で語る際には、どのようなことを意識して働いているかをアピールしましょう。目的を持って行動していると評価されやすくなりますよ。
| 〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇と申します。在学中は本屋でのアルバイトに力を入れておりました。 本屋でのアルバイトを始めたきっかけは、子どものころから本を読むのが好きだったためです。アルバイトを初めたときには、お客様がお探しの本がどの本なのか、ほとんど答えられませんでした。そこで、それまで以上に本を読み、常に新刊の情報を確認。現在では断片的なヒントだけでも、作品を絞れるようになりました。私は本屋でのアルバイト経験から、何事も勉強が大切だと考えております。 御社でも学びを活かして仕事に励み、貢献していきたいです。本日は貴重なお時間を取っていただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 |
就活面接の自己紹介で注意すべき3つのポイント

自己紹介での主な注意点は以下の3つです。簡単な基本情報を伝えるだけですが、自分の第一印象を決める大切な挨拶なので、面接早々つまずかないように気をつけましょう。
- 視線や表情・言葉遣い気をつける
- 原稿は丸暗記ではなく要点を抑える
- 大きな声でゆっくりはっきりと話す
①視線や表情・言葉遣い気をつける
表情を明るくして、しっかり相手を見ながら話すように心掛けましょう。下を向いて話すと声が聞き取りづらく、自信がなさそうに感じられるので注意が必要です。
また、大学や仲間内だけで使用している略語は、採用担当者が知らないかもしれません。
全く知らない外部の人が聞いても、分かりやすく正しく伝わるか意識して、言葉遣いを見直してみてくださいね。
②原稿は丸暗記ではなく要点を抑える
内容を丸暗記して話すだけの自己紹介にならないように気をつけてください。丸暗記をすると棒読みになりやすく、自分の人柄が面接官に伝わらないかもしれませんよ。
暗記した内容以外を話を急に振られたら、パニックになってしまう可能性もあります。用意を完璧にしたい気持ちは分かりますが、覚えるのはキーワードや流れだけにしましょう。
③大きな声でゆっくりはっきりと話す
緊張をしていると声が小さくなって、早口になりやすいです。内容が聞き取りにくくならないように、本番では気持ちを落ち着かせてくださいね。
そして、できる限り声を大きくして、ゆっくり話すように心掛けましょう。
友人や家族を相手に事前練習をするか、自己紹介の練習を録音して、自分の話す速度や癖をチェックするのもおすすめです。
就活面接の自己紹介は事前準備が重要
今回は自己紹介で注意したいポイントや例文を紹介しました。
スムーズな自己紹介のためには、事前準備が必要不可欠です。事前に話す内容を考えておき、丸暗記してメリハリのない読み方にならないように注意しましょう。
自己紹介はあなたの今後のイメージを左右する大切な挨拶です。
最初の第一歩で「質問の意図が理解できていない」「言葉遣いが悪い」と印象が悪くならないためにも、本記事で解説したポイントや注意点をしっかり把握して、就活に臨んでくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。











