面接の合否は、通知がくるまでわからないものです。とはいえ「この面接は失敗だったかもしれない」と思う瞬間もありますよね。
不採用を暗示するお祈りフラグが立つような面接にならないためにはどうしたらいいのでしょう。この記事ではお祈りフラグが立つ具体的な兆し、対策などを紹介します。
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
面接のお祈りフラグとは不採用の伏線のこと
「お祈り」とは、不採用通知の末尾にある「今後のご健闘をお祈り申し上げます」という定型句です。このことから「不採用通知=祈られた」という言葉が生まれました。
「フラグが立つ」というのはプログラミング用語で、何かの前触れがあらわれることを意味します。
この2つが合体してできたのが「お祈りフラグが立つ」という造語です。SNSを中心に広がり、面接中に不採用の前触れや伏線のようなものを感じることを意味します。
明日、面接があるけど不安すぎる…
どんな質問が来るか分からず、緊張してしまう…
このように面接に対しての漠然とした不安から、面接に苦手意識を持ってしまったり、面接が怖いと感じてしまうこともありますよね。企業によっても面接の質問や内容が違うので、毎回ドキドキしてしまいます。
そんな就活生の皆さんのために、カリクル就活攻略メディアでは、実際に400社の面接の質問を調査し、100個の質問を厳選しました。LINE登録をすることで【完全無料】で質問集をダウンロードできます。面接質問集をゲットして、不安を解消した状態で面接に臨みましょう!
\LINE登録1分|400社の質問を厳選/
面接でのお祈りフラグの特徴4選

お祈りフラグが立った場合、100%不採用とは限りませんが確率は高くなるとみていいでしょう。
面接中に感じられる具体的なお祈りフラグにはどのような特徴があるのか、ここでは比較的ポピュラーなお祈りフラグを紹介します。
- 面接が予定よりも大幅に早く終わる
- ありきたりな質問しかされない
- 面接官の期待に答えられていない可能性
- 面接官から「就活頑張って」と応援される
①面接が予定よりも大幅に早く終わる
お祈りフラグのサインとして、面接時間が予定時間よりも早めに終わってしまうことが挙げられます。
面接官にとって、面接は任された仕事です。成果がない、つまり求める人材ではない人に対して貴重な時間を割こうとは思っていません。
面接は、限られた時間でお互いのマッチングを模索することです。面接時間が短く終わってしまった場合、面接官は自社と人材とのミスマッチを感じているのかもしれません。
②ありきたりな質問しかされない
面接での定番の質問しかされなかったという場合、お祈りフラグが立っている可能性が高くなります。定番の質問は、学生のことを知る取っ掛かりでしかありません。そこから深堀した質問を行うのが通常です。
しかし、ありきたりな質問で終わってしまった場合、面接官は「深掘りの質問をする必要がない」と判断を下した可能性があります。
定番の質問できちんと答えられていない、深掘りするほど熱意を感じないなど、基本を押さえられずにフラグを立ててしまわないよう、きちんと準備しておきましょう。
③面接官の反応が薄い
面接官の反応は個性があるものですが、あまりにも反応が薄かったり、手ごたえが感じられなかったりした場合は、お祈りフラグの可能性が高くなるでしょう。
たとえば、面接中にメモを熱心に取っていない場合、「不採用」と判断されている可能性があります。
たくさんの学生の面接をする面接官にとって、メモは重要な情報であり、あとから、評価を下すための判断材料となります。面接官がほとんどメモも取らず、サラッと終わってしまった場合は、不採用という確率も高くなるかもしれません。
④面接官から「就活頑張って」と応援される
面接官から「就職頑張って」と応援されるケースもあります。「やさしい面接官だな」と思っても、実はお祈りフラグの前触れといったケースもあるので注意しましょう。
「就活頑張って」を裏読みすると「当社での採用は難しいけれど、ほかの企業での採用されるように頑張って」となるからです。
不合格になった人に対して、少しでも自社のイメージを損ないたくないという心理も働き、不合格者に対してよりやさしい態度としてあらわれるのかもしれません。
面接での合格フラグの特徴4選

面接では、お祈りフラグがある反面、面接突破に期待が持てる合格フラグもあります。どのようなサインや兆候があると、合格の確率がアップするのでしょう。代表的な合格フラグをいくつか紹介しましょう。
- 面接時間が長め
- 深掘りの質問が多い
- 入社後の話をされる
- 他社での選考状況を聞かれる
①面接時間が長め
面接官は多くの学生と面接しなければなりません。そのなかで、興味のある学生に対しては、深く知ろうと考えていろいろな質問を行います。当然、面接時間が長くなります。
採用する可能性のある学生に対しては、選考の判断材料を得るためにも積極的に質問しているケースが多い傾向があります。
②深掘りの質問が多い
面接時の質問内容は、だいたい決まっています。しかし、ひとつの質問から派生した深掘り質問が多くなる場合は、面接官が学生に興味を持っているということです。
興味を持たれず、ありきたりの質問しかされない場合は、お祈りフラグが立ちますが、逆に深掘りされた質問をされた場合は採用フラグの可能性が高くなります。
③入社後の話をされる
入社後の話をされる場合は、合格フラグの可能性が高くなります。なぜなら、面接官は採用を前提に面接を行っていると考えられるからです。
面接官が行う質問や話には、必ず意図するところがあります。入社後の話をされる場合、その人を採用するイメージができているということ。採用の可能性のない学生に対して、入社後の話をわざわざすることはありません。
とくに最終面接では、入社後の希望する部署や仕事内容など深い質疑応答がされた場合、合格する可能性がかなり高くなります。
④他社での選考状況を聞かれる
「採用したい」と考える人物であれば、他社に流れてしまうことを阻止したいもの。面接官が他社での選考状況が気になるのは当然です。
もし他社の方の選考が進んでいる場合、自分のところでも他社に先んじて内定を出す対策を講じなければなりません。
「他社への返事はいつくらいですか」「他社への入社意欲はどれくらいですか」といった選考状況を聞かれた場合、かなりの確率で合格フラグとなります。
面接でお祈りフラグが立ってしまう3つの原因
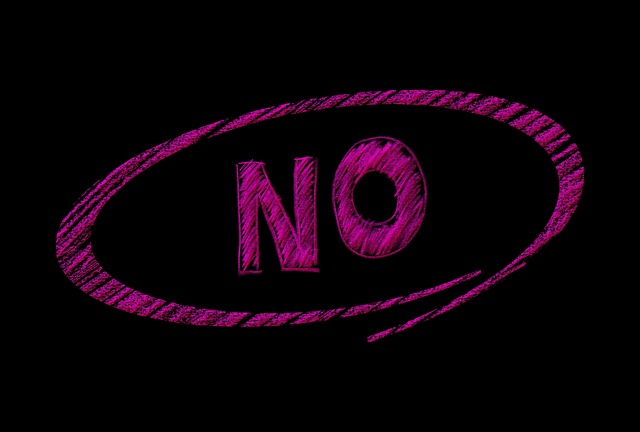
なぜ面接でお祈りフラグ立ってしまうのでしょう。何度面接しても、お祈りフラグが立ち、実際に不採用になってしまう人には、ある共通点があるようです。
面接での自分自身を振り返って原因をチェックしてみましょう。
- 緊張して本来の実力が発揮できていない
- 志望動機や自己PRが不足している
- 面接の反省と改善ができていない
①緊張して本来の実力が発揮できていない
お祈りフラグが立ってしまう人の特徴として、緊張して本来の実力が発揮できていないことが挙げられます。
とくに、最終面接では、上級役員が面接することが多いもの。会社の偉い人がに囲まれている状況では、誰でも緊張を強いられてしまいます。
緊張のあまり頭の中が真っ白になって、適切な返事ができなかったり、上手く話しができなかったりすると、よい結果につながらないことが多くなります。
②志望動機や自己PRが不足している
お祈りフラグが立ってしまう原因として考えられるのが、志望動機や自己PR不足です。自分では十分準備していると思っていても、他の学生はもっと入念に準備しているのかもしれません。
面接官はたくさんの面接を行っています。どれだけ面接に準備してきたのか、真摯に取り組んできたのかを見極めることは簡単なことなのです。
③面接の反省と改善ができていない
一般的に就活では何社も面接を受けます。面接が終わった後、振り返りをせずに漫然と次の面接に臨むのはお祈りフラグが立ってしまう原因となるでしょう。
人は、経験から何かを学ぶものです。反省がなければ次への改善方法も思い浮かばないでしょう。
面接でお祈りフラグを立てないための3つの対処法

面接でお祈りフラグを立てないためには、対処法が必要となります。なぜお祈りフラグばかり立ってしまうのか、自分ではよくわからない方も多いでしょう。
そこで、ここではお祈りフラグを立てないための対処法を3つ紹介します。
- 面接練習を沢山して場慣れする
- 志望動機と自己PRの見直しをする
- 面接後の振り返りを徹底する
①面接練習を沢山して場慣れする
学生時代にディベートなどに慣れている人でも、面接となると少なからず緊張するものです。口下手、上がり症、場慣れしていない人ならなおさらのことです。
実際の面接で緊張しないためには、事前の準備が大切です。友人や家族に協力してもらって、模擬面接を重ねるのもひとつの手段です。何度も練習をすることで、プレッシャーに慣れ、自信も付くことでしょう。
②志望動機と自己PRの見直しをする
志望動機と自己PRは、企業側にとっては就活生の差別化を図る大切な要素です。お祈りフラグが立ってしまわないように、見直しをしてみましょう。
志望動機や自己PRの見直しのため、友人や先輩などに相談してみることもひとつの手段です。
自分に足りないものを補い修正しながらブラッシュアップしていくことで、確実に合格フラグに近づいていけますよ。
③面接後の振り返りを徹底する
面接では、どのような質問にどう答えたのか、答え方に改善すべき点があったのかなど、面接を繰り返すたびにブラッシュアップさせることがお祈りフラグを避けることに役立ちます。
同じ過ちを繰り返さないためにも、面接の反省と改善は必須。面接が終わったら、すぐに今回の受け答えに関して振り返りを行いましょう。
面接途中からお祈りフラグを挽回する2つの方法

面接の途中や面接後に「これはお祈りフラグが立ってしまったかな」と感じることがあります。しかし、そこで諦めてはいけません。挽回のチャンスもあることを忘れないでください。
- 逆質問で入社意欲をアピールする
- お礼メールで感謝と熱意を伝える
①逆質問で入社意欲をアピールする
面接中にお祈りフラグを見つけてしまった場合、大逆転できるチャンスが逆質問です。
逆質問は、自由度が高く、質問者の個性や考え方が大きく反映されます。ここで、まわりとの差別化を図る質問ができれば、面接官の印象を大きく変えることができるかもしれません。
逆質問の内容は、できるだけ多く用意しておき、その中から、一発逆転にふさわしい質問を選びましょう。
②お礼メールで感謝と熱意を伝える
面接の後、お礼メールを送ることが常識となっています。お祈りフラグが立ったと感じても、お礼メールで面接担当者の印象を変えることも可能です。
メールでは、面接のため貴重な時間を作ってくれたことへの感謝の気持ちを伝えましょう。
また、面接時には緊張して思いを伝えきれなかったこと、入社への意欲があることなども付け加えておくと好印象を与えることにつながります。
面接ではお祈りフラグに動揺しないことが重要
この記事では、面接のお祈りフラグのサインや原因、対策などを紹介してきました。しかし、フラグはあくまでも兆候であって、絶対的なものではありません。
自分では合格フラグだと感じたのに、企業からは求められていた人材ではなかった、ということは起こり得ます。その逆のお祈りフラグも同じです。フラグに動揺することなく、全力で面接に臨みましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。











