SPIは適性検査の1つであり、就活では多くの企業が学生の能力や適性を測るために導入しています。
SPIは受検者に結果が通知されないため「高得点が取れたか判断する指標はあるのだろうか」と気になっている人もいるでしょう。
そこで、本記事ではSPI試験の高得点目安の指標から対策方法まで詳しく解説します。ぜひ、最後まで読んでSPIを攻略してくださいね。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
SPIの得点算出方法
まずはSPIの得点算出方法を理解しておきましょう。SPIの得点は難易度毎の正解率に応じて決まり、偏差値で算出されます。
テストセンターで受検したSPIは、受検者の回答状況によって問題が変化し、正解率が高いと徐々に問題の難易度が上がっていく仕組みになっています。
そのため、高難易度の問題に注目することで、ある程度の正解率の予測が可能です。
【4分野別】SPIの高得点指標
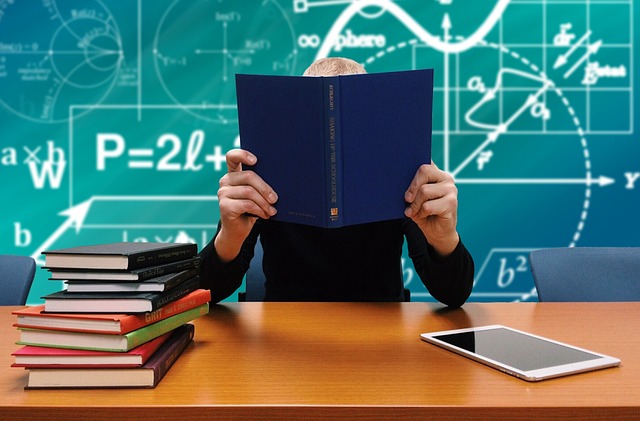
SPIは、出題された問題の内容から高得点が取れているかどうか判断できます。
ここからは、4分野別で高得点の指標について解説します。
- SPI言語
- SPI非言語
- SPI英語
- SPI構造的把握力
①SPI言語
SPI言語の高得点の指標は「長文問題の出題数と形式」「非言語検査の1問目」です。
SPI言語は序盤に語彙問題や文章読解問題、その後長文問題が出題されます。長文問題は時間がかかるため平均出題数は1問です。2〜3問出題された場合は正解率が高いと考えて問題ありません。
特に内容一致問題で複数の選択肢を選ばせる形式や、空欄補充問題で語句抜き出し形式の問題が出題される場合は、問題の難易度が高くなるため高得点の目安となります。
また、SPIはそれまでの回答状況が次の科目にも引き継がれる特徴があります。そのため、SPI非言語の1問目が高難易度の4タブ形式で出題された場合も、SPI言語で高得点を取れていたと予測可能です。
②SPI非言語
SPI非言語の高得点の指標は「推論問題の出題数と形式」「表の読み取り問題のタブ数」です。
SPI非言語では、推論が最も難易度の高い問題です。推論問題が全体の半分以上を占めていれば高得点であると判断して問題ないでしょう。
さらにチェックボックス形式の問題は複数回答を求められるため、推論問題の中でも特に難易度が高くなります。
加えて、表の読み取り問題のタブ数でも正解率の予測が可能です。表の読み取り問題は、タブの数が人によって異なり、前半の正解率が高い人は4タブ問題が出題されます。
③SPI英語
SPI英語の高得点の指標は「長文問題の出題数」です。
SPI英語は、序盤に単語や空欄補充といった基本問題、その後に長文問題が出題されます。長文問題は難易度が高いため、出題数が多ければ高得点が見込めます。
基本的に3問出題されることが多く、見極めがほかの科目に比べて難しくなりますが、長文が4問以上の場合は高確率で高得点だと考えて問題ありません。
④SPI構造的把握力
SPI構造的把握力の高得点の指標はありません。なぜならば、回答状況によって難易度や問題数が変化しないためです。
高得点かどうかの予測はできませんが、設問形式が試験毎に大きく異なることもありません。SPI構造的把握力の問題集でできるだけ多くの問題に触れて、出題パターンを知っておくと高得点を狙いやすくなりますよ。
大企業のSPIのボーダーライン

SPIのボーダーラインを知りたい人も多いと思いますが、合格基準は企業毎に異なるため「何点以上で合格」といった明確な指標はありません。
しかし、一般的には6〜7割以上の正解率で大企業の選考を通過できると言われています。
大企業や有名企業は応募者も多く、ボーダーラインが高めに設定されている可能性もあるため、7割以上の正解率をめざして準備しましょう。
SPIで高得点を取るための3つの対策方法
SPIはいかに素早く正確に回答できるかがポイントです。そのため、高得点を取るためには事前の対策が必須です。
ここからはどのような対策をすべきなのか、3つの対策方法について解説します。
- 志望企業の出題傾向を把握する
- 同じ問題集を2~3周する
- 繰り返し受験して場慣れする
①志望企業の出題傾向を把握する
SPIは言語、非言語、英語、構造的把握力からなる能力検査と性格検査のあわせて5科目で構成されています。どの科目を実施するかは企業によって異なるため、志望企業の出題傾向を確認しましょう。
また受検方式もテストセンター、ペーパーテスト、Webテスト、インハウスCBTの4種類あり、受検方式によって制限時間や回答方法、電卓の使用可否が異なります。
志望企業の試験科目や受験方式を確認し、必要な対策をしましょう。
②同じ問題集を2~3周する
SPI対策で有効なのが、同じ問題集を2〜3周繰り返して解く勉強方法です。SPIはそれほど出題パターンが多くないため、繰り返し練習するうちに解き方のコツを覚えられます。
「複数の問題集を使ってより多くの問題を解いたほうが良いのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、販売されている問題集は網羅的なものが多く、1冊を徹底的に勉強するだけで十分対策可能です。
一方で、多くの問題集を使って対策した場合、数をこなすことに注力してしまい浅くしか勉強できていない事態に陥ることもあるため、注意してくださいね。
③繰り返し受験して場慣れする
繰り返し実践して場の雰囲気や問題の形式に慣れることも重要です。
いきなり志望度の高い企業に挑戦してしまうと、緊張から本来の実力を出せないこともあります。また、完璧に準備したつもりでも、実際の環境で解いてみたら思うようにできないことも。不測の事態を避けるためにも、何社か受けて自信をつけてから受けたほうが安心です。
企業にエントリーしてSPIを受けることに躊躇してしまう人は、無料で受けられる模擬試験に挑戦してみましょう。模擬試験は本番に近い形で問題を解けるため、時間の感覚をつかみやすくなりますよ。
SPI指標関連でよくある質問3選
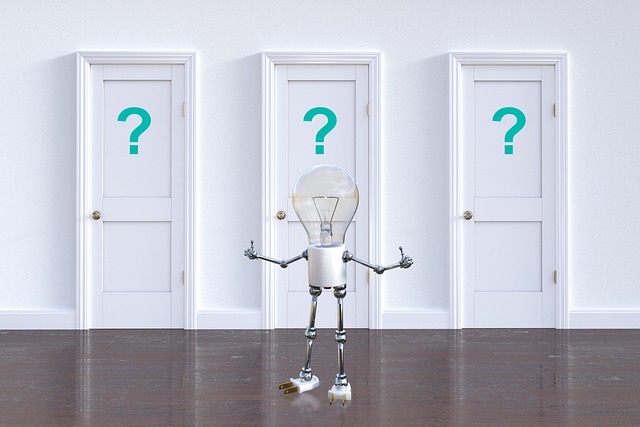
最後によくある質問に回答します。不安や疑問を抱えたままにしないために、以下の内容をチェックしてくださいね。
- SPIの平均点は?
- SPIができなくても選考通過する人はいる?
- SPIのない企業を受けるのはあり?
①SPIの平均点は?
SPIの平均点は、明確に公表されていませんが一般的に6割程度と言われています。少なくとも6割以上の得点を目指して、準備しましょう。
しかし、合格基準は企業によって異なり、8割程度取らないと通過できない企業もあります。高得点を取れれば選考で有利に働く場合もあるので、妥協せずに対策に取り組みましょう。
②SPIができなくても選考通過する人はいる?
SPIができていなくても、選考通過する人はいます。
学歴で基準を設けている場合や、人物重視の採用を実施していて性格検査の結果を重視して判断する場合もあるためです。
③SPIのない企業を受けるのはあり?
SPIが苦手で、できれば避けたい人もいるかもしれませんね。SPIを実施していない企業もあるため、戦略的にSPIのない企業を受けることも1つの手です。
しかし、SPIを実施していないことを条件に絞ってしまうと、視野を狭めてしまう恐れがあるため、注意してくださいね。
SPIの指標を理解して高得点を目指そう!
SPIの結果は受検者に通知されないためわかりません。しかし、高得点の指標を理解していれば正解率を予測できます。
どれくらいできたかどうかを予測して、うまくいかなかったと感じている人は、再度対策を徹底して高得点を目指しましょう。
また、テストセンターで受検したSPIの結果は使い回せるため、今回解説した高得点の目安を判断材料にしてみてくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









