SPIができない原因と合格のための対策法|当日に意識すべきポイントも紹介
「SPIの問題が全然解けない…」
就活を進める中で、多くの学生がぶつかる悩みの1つです。基礎学力を問う試験とはいえ、出題形式に慣れていなかったり、時間配分を誤ったりすると、思うように得点できず不安になりますよね。
本記事では、SPIができないと感じる原因を整理し、言語・非言語分野それぞれの対策法を解説します。
読み終える頃には、苦手を克服し、自信を持ってSPIに臨むための道筋が見えてくるはずです。
できない理由を正しく理解し、効率的な対策で合格をつかみましょう。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
SPIができない原因とは?就活生によくある傾向

SPIが苦手な就活生には、いくつか共通する特徴があります。
原因を正しく理解すれば、今後の対策がより効果的になるはずです。ここでは、SPIに苦戦する人の代表的な傾向について詳しく解説していきます。
- 解法を理解できていない
- 時間配分を間違えている
- 試験形式に対応できていない
- 問題演習が不足している
- 出題傾向を把握できていない
- 本番で焦ってミスしている
①解法を理解できていない
SPIで苦戦する就活生の中には、問題の「意味」や「筋道」をきちんと理解しないまま取り組んでいる人が多く見られます。
特に非言語の問題は、表面的なテクニックでは解けないことが多く、正確な思考プロセスの理解が欠かせません。解法を暗記するのではなく、なぜその方法で解けるのかを根本から理解する姿勢が必要です。
たとえば、速さや割合の問題は公式に当てはめるだけでは不十分で、状況を読み取って整理する力が求められます。理解を深めるには、解説を丁寧に読み、同じパターンの問題を何度も解き直してみましょう。
解法の定着には時間がかかるかもしれませんが、一つひとつ積み重ねることがスコアアップへの最短ルートです。焦らず、基礎から丁寧に固めていくことが大切です。
②時間配分を間違えている
SPI試験は、制限時間の中で多くの問題を効率よく解く必要があります。
それにもかかわらず、1問に固執してしまったり、苦手な問題に無理して取り組んだりして、全体のバランスを崩してしまうケースは少なくありません。
時間が足りなくなると、焦りが生じてケアレスミスも増えてしまいます。スムーズに問題を解くためには、「完璧を目指さない」という意識も必要です。
得点源になりそうな問題を素早く見極めて、優先順位をつけて処理していきましょう。
たとえば、文章題のように考えるのに時間がかかる問題は後回しにして、計算問題など短時間で解けるものから先に進むとよいでしょう。
時間配分の感覚を養うには、模擬試験や過去問を実際の制限時間で解くトレーニングが有効です。継続することで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
③試験形式に対応できていない
SPIには「ペーパーテスト」と「Webテスト」があり、それぞれの形式によって操作性や問題の出題順などに違いがあります。
また、Webテストは企業によって画面デザインや操作方法が微妙に異なる場合もあるため、想定と違って焦ってしまう原因にもなります。
事前に受験企業がどの形式を採用しているかを必ず確認し、それに合わせた準備をしておくことが重要です。
市販のSPI対策本やオンラインツールの中には、Web形式に特化した模擬テストを体験できるものもあるため、積極的に活用してみてください。
本番前に形式に慣れておくだけでも、気持ちの余裕が全く変わってくるはずです。
④問題演習が不足している
SPIのスコアを上げるためには、理解だけでなく「手を動かす」ことが欠かせません。
演習が不足していると、問題に慣れないうえ、スピード感も身につかないため、本番で時間が足りなくなる原因になりがちです。SPIの問題は独特の形式や制限時間があるため、ある程度の慣れが必要です。
演習を繰り返すことで、自分の得意・不得意な分野も明確になります。苦手な分野に集中的に取り組むことで、バランスよく得点できるようになりますし、自然と時間配分の感覚もつかめてくるでしょう。
特に、間違えた問題を放置せず、なぜ間違えたのかを確認しながら復習することが重要です。ノートなどに自分専用の「ミス集」を作っておくと、直前の見直しにも役立ちます。
演習は「量」も「質」も大切です。習慣として継続できるよう、毎日少しずつでも取り組むのが理想です。
⑤出題傾向を把握できていない
SPIには出題されやすいテーマや形式にある程度の傾向があります。しかし、それを把握しないままやみくもに対策しても、効率が悪くなってしまいます。
たとえば、グラフの読み取りや割合、損益算、資料解釈などは頻出分野として知られています。
こうした傾向を理解していないと、本番で初めて見る形式に戸惑い、得点につながらないまま終わってしまう可能性もあるでしょう。
出題傾向は、市販の対策書やインターネット上の受験体験談などから把握できます。傾向を知っていれば、自分が重点的に対策すべき分野を明確にできますし、学習の優先順位もつけやすくなります。
また、時間が限られる就活期間中に、無駄な勉強を避けるうえでも効果的です。効率よく得点力を伸ばすためには、まず情報を集めて全体像をつかむことから始めてください。
⑥本番で焦ってミスしている
SPIで点数が伸びない要因の1つに、本番の緊張によるミスがあります。
模試や自習では安定した結果を出せていたのに、本番では焦って読み間違いや入力ミスをしてしまう……そんな経験をした人も少なくないでしょう。
特に第一志望の企業だった場合、そのプレッシャーは一層強まります。焦りを軽減するには、事前に「本番を想定した練習」を重ねることが効果的です。
たとえば、自宅で実際の試験時間に合わせて模擬問題を解いてみたり、制限時間を設定して演習するだけでも本番に近い状況を再現できます。
また、直前に新しい問題集に手を出すのではなく、これまで解いた問題の復習に集中した方が精神的な安定にもつながるはずです。
本番で自分の実力をきちんと出し切るためには、慣れと準備が何よりの安心材料となります。
SPIを実施する目的
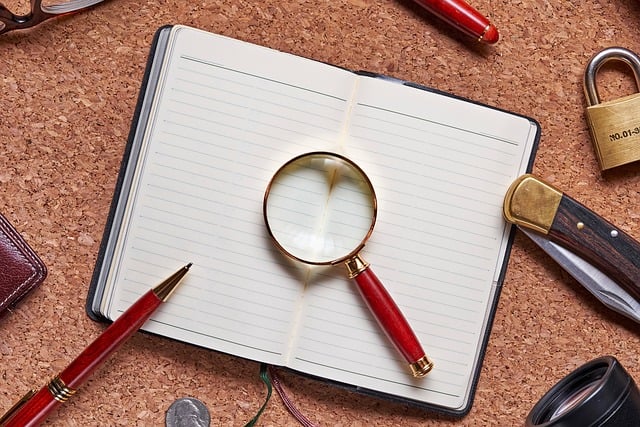
就職活動において避けて通れないSPIですが、その実施目的を正しく理解している学生は意外と少ないものです。
企業がSPIを活用する理由を知ることで、対策の方向性が明確になり、効率よく準備を進められるようになります。ここでは、企業がSPIを導入する背景にある6つの目的について詳しく解説します。
- 基礎学力を確認するため
- 足切りを実施するため
- 企業との適性を確認するため
- 応募者の論理的思考力を評価するため
- 短時間で多くの応募者を選別するため
- 入社後の業務適応力を見極めるため
① 基礎学力を確認するため
企業がSPIを通してまず確認したいのは、応募者が社会人として最低限必要な基礎学力を持っているかどうかです。
特に非言語分野では、計算能力や図表の読み取りといった数的処理力を、言語分野では読解力や語彙力、論理展開の理解などを評価しています。
これらは業務において指示を正確に理解し、適切に対応するために不可欠な力といえるでしょう。
早めの対策を心がけ、自分の得意・不得意を客観的に把握しながら取り組むことが、通過率を上げるコツといえるでしょう。
②足切りを実施するため
企業、とくに大手や人気業界では、SPIを「足切り」として活用するケースが少なくありません。
これは、応募者が多すぎて一人ひとりを面接で評価することが難しい場合に、一定水準に達しない人を早期にふるい落とすための手段として使われます。
いわば、SPIの点数は面接以前に「会ってもらえるかどうか」を左右する重要な判断材料なのです。
たとえばSPIの基準点を突破できなければ、学歴や自己PRがどれほど優れていても、そもそも評価のテーブルにすら乗れません。
SPI対策をおろそかにすると、その後の選考準備がすべて水の泡になる可能性もあるのです。つまりSPIは、面接やエントリーシートと並ぶ「最初の壁」として、避けて通れない試験といえるでしょう。
基準点を超えるためには、まず出題形式を理解し、苦手分野を徹底的に克服することが大切です。
③企業との適性を確認するため
SPIには性格検査のパートがあり、企業はこれを通じて応募者の人柄や価値観、行動特性などを確認しています。
これは単なる性格診断ではなく、応募者が自社のカルチャーや仕事のスタイルに適応できるかを見極めるための重要な情報源となっています。
たとえば、協調性が求められる企業では、個人主義が強すぎると不適合と判断される可能性があります。このような適性確認は、入社後の早期離職を防ぐ目的も含まれています。
企業としては、スキルがあっても価値観が合わなければ長期的に活躍してもらえないリスクがあるためです。そのため、性格検査では「どう見せるか」よりも「どれだけ自分らしく答えられるか」が問われます。
嘘や見栄をはって答えると、回答に一貫性がなくなり、かえって評価が下がってしまう場合もあるでしょう。
SPIを受ける前に、自分の強みや仕事観を整理しておくことが、適性検査でも良い結果につながります。
④応募者の論理的思考力を評価するため
SPIでは、数的処理や文章理解といった論理的思考力を問う問題が多数出題されます。これは、実際の業務で発生するさまざまな課題に対して、根拠をもって判断を下せるかを測るためです。
とくにコンサルティングやシステム開発、マーケティングなど、論理性が重視される職種ではこの能力が合否に直結することもあります。
論理的思考力は一朝一夕に身につくものではありませんが、SPIにおいては設問のパターンに慣れれば得点を伸ばしやすい領域でもあります。
重要なのは、ただ正解するのではなく、「なぜその答えになるのか」を筋道立てて考える訓練を積むことです。また、時間制限があるため、スピードと正確性の両方が求められます。
演習を重ねて処理能力を鍛えながら、ミスを減らす習慣を身につけていくとよいでしょう。日常生活でも論理的に物事を考えるクセをつけることで、SPIだけでなく社会人としての思考力向上にもつながります。
⑤短時間で多くの応募者を選別するため
企業にとって、採用活動は限られた時間とリソースの中で行う必要があります。とくに新卒採用では、数百人から数千人単位の応募が集まるため、面接や書類選考だけでは対応しきれません。
こうした状況で、SPIは短時間かつ効率的に応募者を選別する有効な手段として活用されています。
SPIを導入することで、採用担当者は事前にスクリーニングを行い、面接対象者をある程度絞り込むことができます。これは時間と労力の削減だけでなく、一定の公平性を保つうえでも有効です。
学生側から見ると、SPIは単なる筆記試験というより、選考への「第一関門」として捉えるべきでしょう。
また、試験時間が限られているため、問題に慣れておかないと焦って本来の力を出せないこともあります。
過去問や模擬問題を使って時間感覚を養い、本番で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう準備を進めてください。
⑥入社後の業務適応力を見極めるため
SPIでは、応募者の入社後の適応力や職場でのパフォーマンスを予測するための設問も組み込まれています。
たとえば、複数の情報を処理して結論を導く力や、ストレスのかかる状況でも冷静に判断できるかなど、現場で役立つ資質を評価しています。
このような観点から見ると、SPIは単なる選考試験ではなく、「社会人としての基礎力」を測る試験でもあります。
特に性格診断では、職場での協調性、リーダーシップ、柔軟性といったソフトスキルも判断材料となります。これらは面接だけでは判断が難しいため、SPIの役割がますます重要になってきているのです。
学生のうちから、状況に応じて行動や考え方を切り替える習慣を身につけておくと、SPIだけでなくその後のキャリアにも大きく活きてきます。
試験対策だけにとどまらず、日々の行動の中に応用を意識してみてください。
SPIができない人が押さえるべき言語分野の対策ポイント

SPIの言語分野は、表面的な読解力や語彙力だけでは十分とはいえません。とくに「何となく」で解いてしまう人は、点数が安定しづらい傾向にあります。
ここでは、SPIが苦手な就活生に向けて、重点的に取り組んでおくべき言語分野の対策ポイントをわかりやすく解説します。
- 語彙力と熟語知識の強化
- 語彙問題の処理スピード向上
- 長文読解の読み方の工夫
- 設問のパターンの把握
- 文法問題の解き方の工夫
- 選択肢の見極め方の強化
①語彙力と熟語知識の強化
SPIの言語問題において、語彙力と熟語の知識は安定した得点の土台となります。語彙が不足していると、選択肢の意味がとれずに時間を浪費しがちで、長文読解でも主旨をつかめなくなってしまいます。
まずは、SPI頻出の基本単語・四字熟語・慣用句を重点的に押さえることが重要です。
たとえば、「的を射る」「足をすくわれる」といった表現の意味と使い方を理解しておけば、意味判断や文中の理解に役立つ場面が増えるでしょう。
さらに、単語帳だけに頼るのではなく、実際の文脈で言葉を覚えることが定着につながります。
新聞の見出しや社説、Webニュースの要約などを日常的に読む習慣を持つと、語彙を自然に広げられるうえ、文脈理解力も高まります。
時間がない場合は、SPI対策アプリや単語学習ゲームを使って通学時間などのスキマ時間を活用するのもおすすめです。習慣化と反復が最大のコツといえるでしょう。
②語彙問題の処理スピード向上
語彙問題は、1問あたりにかけられる時間が限られているため、速く正確に処理する力が求められます。
とくに言葉の意味や使い方があいまいなままだと、ひとつの問題で何十秒も迷ってしまい、全体の時間配分に影響が出てしまいます。この対策には、まず語彙の「即応力」を鍛えることが必要です。
即応力とは、単語を見た瞬間に意味や使い方がすぐ浮かぶ力で、知識の深さと演習経験の両方がカギとなります。1日10問でも構いませんので、定期的に時間を計って語彙問題を解く練習をしましょう。
また、選択肢を比較する際には、消去法を徹底することが効果的です。明らかに不自然・不正確な語を除外することで、正解の可能性を高めるとともに、迷いも減ります。
さらに、問題に慣れることはスピードアップにも直結します。公式問題集や模擬試験で出題傾向を把握し、頻出テーマに集中して取り組んでいくと、効率よくレベルアップできるでしょう。
③長文読解の読み方の工夫
長文読解は「読む量が多いから苦手」と感じる人が多いですが、実際には読み方次第で負担を大きく軽減できます。
ポイントは、すべてを一字一句読むのではなく、設問の意図に合った情報にだけ注目する読み方を身につけることです。まず、本文に入る前に設問と選択肢を読み、「何を問われているか」を明確にします。
たとえば「筆者の主張は?」「この文章の要旨は?」といった問いに対しては、冒頭と末尾を重点的に読むことで効率よく答えに近づけます。次に、接続詞や指示語を手がかりに文脈をつかみましょう。
「しかし」「つまり」などの言葉は、文章構造の変化を知らせるサインです。そうした言葉の前後にヒントが含まれていることが多いため、意識的にチェックしてください。
また、段落ごとの内容を簡単に頭の中で整理しながら読む習慣を持つと、全体の論理展開が見えやすくなります。
読み終えたあとに「筆者は結局何を言いたかったのか」を一言でまとめてみるのも、理解度を高める効果があります。
④設問のパターンの把握
SPI言語では、設問の形式をあらかじめ知っておくことが、正確さとスピードの両立に役立ちます。
パターンがある程度決まっているため、各問題の狙いや答え方を知っているだけで、かなり有利に進められるのです。代表的なのは、空欄補充、要旨把握、指示語の内容判断、言い換え問題などです。
空欄補充では文脈から自然な流れを読み取る力が、要旨把握では全体の構成を俯瞰する力が求められます。
また、パターンを把握していると、問題文を読んだ瞬間に「これはこの解き方だな」と方針を決められるため、迷いが少なくなります。
反対に、パターンを知らないと、どう解くべきか分からずに手が止まってしまいがちです。過去問や問題集を通じて、「どんな設問がどんな力を試しているのか」を分析してみてください。
自分なりの分類表を作ると頭に残りやすく、復習にも便利です。
⑤文法問題の解き方の工夫
文法問題は「なんとなく選ぶ」スタイルでは正解率が安定しません。とくに助詞や言い回しの微妙な違いが問われることが多いため、文法の基本ルールを理解したうえで、論理的に解答する力が求められます。
対策の第一歩は、品詞や語順、助詞の用法などの基本事項をしっかり押さえることです。たとえば「に」「へ」「で」の使い分けや、敬語の使い方など、SPIでは常識的な文法知識がそのまま問われます。
また、選択肢をただ読むだけでなく、「どこがどう違うか」を明確に比較し、文章として自然かどうかを判断する目を養いましょう。
選択肢の中には、似ているようで細かい意味の違いや不自然な語順が隠れていることもあります。
演習を重ねれば、「このタイプの文法問題は自分がよく間違える」といった弱点が浮き彫りになってきます。その部分を集中的に復習することで、効率よく精度を高めることができます。
⑥選択肢の見極め方の強化
SPIの問題で高得点を狙うには、選択肢の見極め力が欠かせません。選択肢はすべて「正しそう」に作られており、本文の一部と少し似ていたり、印象が強い表現だったりすることで迷わせようとしてきます。
ここで大切なのは、正しい選択肢を探すと同時に、「なぜ他の選択肢が不正解なのか」を明確にできることです。
誤答を見抜くには、文脈とのズレ、不自然な言い回し、設問の意図と合っていない回答を見抜く視点が必要です。
また、「必ず」「絶対に」「すべて」など極端な断定表現が含まれる選択肢は、誤答である可能性が高いという傾向もあります。このような特徴に慣れておけば、迷う時間を減らすことができるでしょう。
選択肢の比較には時間がかかるため、普段から「選ばない理由」を意識して解く練習をしておくと、本番でも落ち着いて判断できます。精度の高い選択力は、日々の演習の中で少しずつ磨かれていくものです。
SPIができない人が取り組むべき非言語分野の対策ポイント

SPI試験の非言語分野は、計算や論理的思考が必要なため、多くの就活生が苦手意識を持ちがちです。しかし、出題パターンがある程度決まっているため、効率よく対策すれば十分に克服できます。
ここでは、SPI非言語でつまずきやすい人に向けて、重点的に取り組むべきポイントを紹介します。
- 頻出公式の暗記
- 図を使った推論問題の対処
- 解けない問題の見切り方
- 処理速度を意識した練習
- 出題パターンの把握
- 情報整理のためのメモの活用
- 計算ミスを防ぐための工夫
①頻出公式の暗記
SPI非言語で安定して点数を取るには、頻出する基本公式をしっかり覚えることが出発点です。特に、速さ、割合、損益計算、濃度などの分野では、公式を知っているかどうかで正解率が大きく変わります。
たとえば「速さ=距離÷時間」や「売価=原価×(1+利益率)」といった計算式は、問題の本質を理解していると素早く使いこなせるようになります。
ただ丸暗記するだけでなく、実際に問題を解く中で繰り返し使い、体で覚えていくのが効果的です。また、なぜその式が成り立つのかという背景まで理解することで、応用問題にも対応しやすくなります。
数値を変えたり条件を増やしたりして、自分でバリエーションを作って練習するのもおすすめです。
計算式が自然と頭に浮かぶようになれば、問題文にかける時間も短縮でき、全体の解答スピードも確実にアップします。
②図を使った推論問題の対処
推論問題では、複数の条件や要素を同時に扱う必要があり、頭の中だけで考えようとすると混乱しやすくなります。
特に人物や位置関係、時系列が関わる問題では、情報が入り組んでいて理解しにくいケースが少なくありません。そのため、図や表を使って視覚的に整理することがとても有効です。
さらに、図解をすること自体が「情報を構造化する訓練」になるため、論理的思考力の強化にもつながります。
最初は時間がかかっても、慣れてくると自然と頭の中でも図式化できるようになり、解答の正確性も大きく向上します。
視覚的に把握するクセを身につけることで、難解に見える問題も冷静に対応できるようになるでしょう。
③解けない問題の見切り方
SPI試験では、すべての問題に同じだけ時間をかけて取り組むことができません。限られた時間の中で高得点を狙うには、解ける問題に集中し、解けない問題は素早く見切る判断力が不可欠です。
特に、計算量が多く構造が複雑な非言語問題では、最初の1〜2行を読んだ時点で「時間がかかりそう」と感じることがあります。
そういった場合は潔く飛ばして、後ろの簡単な問題に時間を回す決断が必要です。試験は勝負の場であり、完璧を目指すよりも得点を確保することが最優先になります。
「この問題を捨てても大丈夫」と思える準備があると、精神的な余裕も生まれます。勇気を持って切り替える力が、結果的に合格へとつながるのです。
④処理速度を意識した練習
非言語問題では、正確性だけでなくスピードも求められます。どれだけ正しい答えを出せる力があっても、時間内にすべて解けなければ得点にはつながりません。
そのため、普段の学習から「時間を意識する」ことが重要です。まずは1問あたりの目安時間を設定し、ストップウォッチやタイマーを使いながら問題を解いてみましょう。
時間制限があると、自然と手を動かすスピードも上がり、頭の回転も早くなります。たとえば「1問60秒以内」と目標を決めて取り組むことで、実戦感覚を養うことができます。
また、過去問や模試を使って「制限時間内に何問正解できるか」という形式で練習を重ねると、本番での緊張感に慣れることができます。
最初は焦りやすいですが、繰り返すことでペース配分が身についてきます。正確さとスピードを両立させるには、時間内での判断力と集中力を磨く必要があります。
短時間で答えを導く感覚を、日々のトレーニングで身につけていきましょう。
⑤出題パターンの把握
SPI非言語の出題内容には、ある程度決まったパターンがあります。そのため、無計画に全範囲を網羅しようとするよりも、よく出る問題形式に絞って集中的に対策するほうが効果的です。
たとえば、「表の読み取り」「割合」「順列・組合せ」「損益計算」「仕事算」「集合問題」などは、毎年高確率で出題されているテーマです。
これらの問題に慣れておくだけで、試験全体の得点力が大きく上がります。出題パターンを分析するには、過去問や市販のSPI模試を活用するのが有効です。
問題を解くだけでなく、「どの形式が多いか」「どんな考え方が必要か」を自分なりにメモして整理しておくと、復習にも役立ちます。
さらに、似たパターンでも少しずつ条件が変化するため、単純な暗記に頼るのではなく「なぜこの解き方になるのか」を理解しながら取り組むことが重要です。
型を知ることで、自信を持って問題に取り組めるようになります。
⑥情報整理のためのメモの活用
非言語分野では、長文の問題や複雑な条件が登場することが多く、読み進めるうちに混乱するケースも珍しくありません。こうした混乱を防ぐには、メモを取りながら情報を整理する習慣が非常に効果的です。
たとえば、複数の条件や数値を一度に処理する必要があるときには、表や箇条書きを使って整理するだけで、思考の流れがスムーズになります。
人間の記憶には限界があるため、記憶に頼らず、手を動かして情報を「見える化」することがポイントです。さらに、解き終わった後にメモを見返すことで、見落としていた情報や条件の確認もできます。
特に論理パズル系の問題では、途中経過のメモがなければ検証が難しくなる場面もあるでしょう。
慣れてくると、どの情報を書き出せばいいかが自然に分かるようになります。メモを上手に使いこなせるかどうかが、正答率と解答スピードの両方に直結するといえるでしょう。
⑦計算ミスを防ぐための工夫
非言語問題では、解法が合っていても計算ミスをしてしまうと得点になりません。特に、数字が多く出てくる問題ではケアレスミスが起きやすく、注意が必要です。
対策としては、まず途中計算を省略せずに丁寧に書き出すことが基本です。暗算や頭の中の処理に頼ると、見落としや誤解が発生しやすくなります。
紙に数字を並べるだけでも、自分の考えを視覚的に確認できるため、ミスに気づきやすくなります。また、数字を書き間違えたり読み間違えたりしないよう、筆記の丁寧さにも気を配りましょう。
焦って急ぐほど、簡単な計算でつまずくリスクが高くなります。時間に余裕がある場合は、逆算や検算を取り入れて結果をチェックするのも有効です。
小さなミスを軽視せず、丁寧な処理を心がけることで、取りこぼしを防げます。確実に点数につながるよう、日頃から「ミスをしない工夫」を意識して取り組んでください。
SPIができない人でも合格を目指せる勉強法

SPIが苦手だと感じている人でも、正しい方法で取り組めば十分に合格を目指せます。大切なのは、原因を把握し、自分に合った学習法を選ぶことです。
ここでは、SPIに苦手意識を持つ就活生が取り組むべき具体的な対策法を紹介します。
- 苦手分野の問題を繰り返し解く
- 出題形式に合わせた練習
- 模擬試験の活用
- アプリやツールの活用
①苦手分野の問題を繰り返し解く
SPIで思うように得点が伸びない人の多くは、不得意な分野をそのまま放置してしまいがちです。しかし、得点力を高めるには苦手を避けず、徹底的に向き合う姿勢が必要です。
特に非言語分野では、計算問題や論理問題に苦手意識を持つ人が多く、解けないまま進めてしまうことで、さらに自信を失ってしまいます。
こうした場合は、まずは問題の種類を整理し、よく出題されるテーマを優先的に復習することが大切です。そして、同じような問題を繰り返し解いてパターンを体得しながら、少しずつ理解を深めていきましょう。
また、「正解できた問題」も軽視せず、なぜ合っていたのか、他の選択肢とどう違うのかを確認することで、より確実な理解へとつながります。苦手な分野こそ、丁寧に取り組むことが合格への一歩になります。
②出題形式に合わせた練習
SPIは学校の試験とは異なり、非常にスピードが求められるうえ、独特の出題形式が特徴です。
知識の深さよりも、素早く正確に判断する力が問われるため、形式を知らないまま本番を迎えると、実力を出しきれずに終わってしまう恐れがあります。
そのため、単に問題を解くのではなく、実際の出題傾向に近い演習を繰り返すことが不可欠です。
たとえば、制限時間を設けて過去問や模試形式の問題に挑戦することで、本番の緊張感や時間感覚にも慣れることができます。
繰り返すうちに、設問のパターンが見えてくるようになり、解き方の引き出しも自然と増えていくでしょう。また、よくあるミスやひっかけ問題にも事前に慣れておけば、本番で余計な焦りや混乱を避けられます。
こうした「形式慣れ」は、単なる知識以上に大きな武器となります。特に初見の問題に対応する柔軟性を鍛えるには、バリエーション豊富な演習が欠かせません。
③模擬試験の活用
SPI対策で見落とされがちなのが、実践的なトレーニングです。その中でも模擬試験は、自分の現状を客観的に知る絶好の機会となります。
模試では、実際の試験に近い時間設定や問題構成が再現されており、普段の学習では気づけない弱点や時間配分のクセなどを洗い出せます。
特に注意したいのは、本番さながらの緊張感の中でどれだけ集中を保てるかという点です。時間に追われる状況下でこそ、普段は見えない課題が浮き彫りになります。
模試のたびに結果を記録し、前回との比較をすることで、自分の成長度や対策の有効性も確認できるでしょう。また、模試を受けっぱなしにせず、復習に力を入れることが非常に重要です。
間違えた問題を放置せず、「なぜ間違えたか」「どうすれば防げたか」を具体的に考えることで、次の模試や本番でのミスを防ぐことにつながります。
試験本番の疑似体験として、模試を積極的に取り入れていきましょう。
④アプリやツールの活用
現代の就活生にとって、スキマ時間をいかに活用するかは大きな課題です。SPI対策においても、その時間を有効に使えるアプリやオンラインツールの存在は非常に大きな助けとなります。
スマートフォン1台あれば、通学時間や待ち時間に少しずつ学習を進められるのが魅力です。
特に最近では、問題演習だけでなく、解説付きやAIによる弱点分析機能がついたアプリも登場しており、自分のレベルや理解度に合わせて最適な学習ができます。
ゲーム感覚で進められる設計になっているものもあり、モチベーションの維持にも効果的でしょう。ただし、ツールに頼りすぎて内容を理解しないまま進めるのは避けるべきです。
間違えた問題には必ず解説を確認し、自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深めることが大切です。うまく使いこなせば、限られた時間でも質の高い対策が実現できます。
SPIができない人におすすめの対策本・参考書

SPIに苦手意識を持っている就活生は少なくありません。特に、言語・非言語どちらもバランスよく出題されるSPIでは、対策本の選び方が合否に直結します。
ここでは、SPI初心者から本格的に取り組みたい人まで、幅広く対応できるおすすめの参考書を紹介します。
- これが本当のSPI3だ!2027年度版 (SPIが初めてで基礎から学びたい人向け)
- SPI3突破テキスト&問題集 (苦手分野を克服しながら実力を伸ばしたい人向け)
- SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2027年度版 (短期間で要点だけを押さえたい人向け)
①これが本当のSPI3だ!2027年度版(SPIが初めてで基礎から学びたい人向け)
SPIが苦手だと感じているなら、「これが本当のSPI3だ!2027年度版」から取り組むのが効果的です。
この参考書は、全体の構成がとてもわかりやすく、SPIの基礎をきちんと理解したうえで実践へと進めるように作られています。
各分野の出題傾向や頻出問題が明確にまとめられており、「なぜそうなるのか」という背景まで丁寧に解説されています。
とくに非言語問題では、視覚的に理解できるよう図表を多く取り入れているため、数字が苦手な人でも取り組みやすいでしょう。
また、実際のテストセンターで出題される形式に近い問題も多数掲載されており、初学者でも本番に近い感覚で学習できます。初歩から始めて段階的に力をつけたい方にぴったりの一冊です。
②SPI3突破テキスト&問題集(苦手分野を克服しながら実力を伸ばしたい人向け)
時間を効率よく使ってSPI対策を進めたい方には、「SPI3突破テキスト&問題集」がおすすめです。
この本の最大の特徴は、基礎→演習→模試という三段階構成になっており、自分の理解度や進捗に合わせてステップアップできる点です。
特に章ごとにチェックポイントが設けられており、どこが苦手かを明確にしながら対策を進められます。問題ごとに丁寧な解説が付いているので、つまずいてもすぐに復習ができ、反復学習にも適しています。
さらに、模擬試験ページでは制限時間付きで解く形式もあり、実戦的な力を身につける練習に最適です。
学習に対する不安がある人や、どこから手をつけてよいか迷っている人にとって、この一冊が道しるべになるでしょう。
自習しやすい構成なので、塾や講座に頼らず独学でSPIを乗り越えたい人にも向いています。
③SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2027年度版(短期間で要点だけを押さえたい人向け)
とにかく時間がないけど結果は出したい、そんな就活生には「SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2027年度版」がぴったりです。
この本は、過去の出題データを分析して「本当に出る」ところだけを厳選してまとめています。そのため、広く浅く勉強するのではなく、限られた範囲を深く、確実に対策できるのが強みです。
とくに言語・非言語どちらも要点が明確に整理されており、苦手分野を効率よく克服することができます。また、テストセンター対策も充実しており、SPIだけでなくWebテスト全般の準備にも役立ちます。
さらに、ページ構成もシンプルで読み進めやすいため、短期間で集中して学習したい人に最適です。試験直前に重要ポイントだけを総復習する「おさらい用の一冊」としても使えるでしょう。
限られた時間の中で確実に点を取りたいなら、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。
SPIテスト当日に意識すべきポイント

SPIテスト当日は、ただ問題を解くだけでなく「どう解くか」を意識することが重要です。
本番では限られた時間内で実力を発揮しなければならないため、事前の対策だけでなく、当日の行動も合否を左右します。
ここでは、テスト当日でどのようなことを意識すべきかについて具体的に説明します。
- 得意な問題を優先して解く
- メモを活用して情報を整理する
- 難問に固執せず切り替える
- 制限時間を常に意識して解く
- 見直しの時間を確保しておく
- 試験直前に焦らず心を整える
①得意な問題を優先して解く
SPIは時間との勝負といえる試験です。問題ごとの配点が同じであることが多く、難しい問題に時間をかけて正解しても、簡単な問題を落としてしまえば結果的に得点は下がってしまいます。
だからこそ、自分の得意な問題を見極めて、そこから解き始めることが得策です。得意なジャンルから取り組めば、自信を持って試験に臨むことができ、心理的にも落ち着いた状態を維持しやすくなります。
また、テンポよく問題を処理できるため、試験全体のペースを作るうえでも効果的です。事前の模擬試験や問題集を通じて、自分がどの分野でスムーズに解けるかを明確にしておくとよいでしょう。
本番では、焦らず着実に点数を積み重ねる姿勢が求められます。
②メモを活用して情報を整理する
SPIの非言語分野では、複数の条件や数値をもとに論理的に答えを導く問題が多く出題されます。
こうした問題を頭の中だけで解こうとすると、情報の整理が追いつかず、途中で混乱してしまうことが少なくありません。このような場面で有効なのが、メモの活用です。
メモを取ることで、思考を一度外に出して整理し、情報を視覚的に把握できます。特に条件整理や計算式、選択肢の絞り込みなど、複数の要素を比較検討する際に非常に役立ちます。
また、ミスを防ぐうえでもメモは効果的です。計算過程を残しておくことで、自分の考えが正しいかを見直しやすくなり、途中で迷った場合も再検討がスムーズに行えます。
普段から練習問題でメモを取る癖をつけておくと、本番でも自然と使えるようになるでしょう。
③難問に固執せず切り替える
SPIの出題内容には難易度の差があり、すべての問題を完璧に解くのは現実的ではありません。特に非言語の中には、複雑な図形や条件の多い推論問題など、時間をかけても解きにくいものが含まれています。
そのため、難問に出くわしたときは、潔く飛ばす判断が求められます。1問にこだわってしまうと、他の簡単な問題に手が回らず、本来取れるはずの得点を落としてしまう可能性があります。
時間が限られている以上、解けそうな問題から優先的に処理していくことが大切です。ただし、難問を完全に無視するのではなく、時間に余裕ができたときに戻って再挑戦するというスタンスが理想的です。
問題番号に印をつけておくと、後で効率よく見直しに戻れます。冷静に取捨選択する判断力が、SPIでは得点力に直結するといえるでしょう。
④制限時間を常に意識して解く
SPIの最大の特徴の一つが「時間制限の厳しさ」です。限られた時間内で高得点を取るには、正確さだけでなくスピード感が不可欠です。
ゆっくり確実に解いていたのでは、すべての問題に目を通すことすら難しくなってしまいます。そのため、本番では常に時計を意識して、時間配分をコントロールすることが重要です。
目安として「1問〇秒以内で解く」といった基準を決めておけば、途中で焦ることなくペースを維持しやすくなります。また、解けない問題に時間を取られすぎないための指針にもなります。
時間感覚は練習の中で身につけるしかありません。模試や問題集でタイマーを使いながら解答することで、自分に合ったペースをつかめるようになるでしょう。
本番で焦らず対応できるよう、日頃から時間意識を持って練習してください。
⑤見直しの時間を確保しておく
SPIではケアレスミスが得点を大きく左右するため、見直しの時間を持つことが非常に重要です。ただし、見直す時間を作るには、前提として解答ペースをしっかり管理しなければなりません。
理想的には、全体の解答を試験終了の5分前までに終えるように設定し、その残り時間で見直しに充てられると安心です。
特に計算問題や読解問題では、わずかなミスが失点につながりやすく、見直しによって誤りに気づくことがよくあります。
また、選択肢のマークミスや転記ミスといった単純なミスも、見直しによって回避できます。こうした小さな見直しの積み重ねが、最終的な点数を押し上げる結果につながるでしょう。
模試などでも「見直しを前提とした時間配分」を意識して練習することで、本番でも自然と余裕が生まれます。時間内に解くだけでなく、見直す力もSPI対策の一部として取り組んでください。
⑥試験直前に焦らず心を整える
試験本番の数分前は、緊張と不安で思考がまとまらなくなることも珍しくありません。どんなに準備を重ねていても、気持ちが不安定なままだと実力を十分に発揮できない可能性があります。
そんなときは、深呼吸をする、ストレッチをする、目を閉じて静かに過ごすなど、自分に合った方法で心を整えることが大切です。
直前まで参考書を見続けるのではなく、むしろ何も見ずに頭を休めるほうが、精神的に落ち着きを取り戻しやすくなります。
また、「これまでしっかり対策してきた」という自信を持つことで、自然と余裕が生まれます。本番に向けての準備は、知識だけでなく、心の準備も含まれます。
焦りを感じたら、「今の自分で十分」と一度自分に言い聞かせてください。SPIは実力を出し切れば必ず結果が出ます。だからこそ、最後まで冷静に、自分を信じて試験に臨むことが最も重要です。
SPI対策は「できない理由」を知ることから始まる

SPIができないと感じる人には共通した原因があります。例えば、問題形式への理解不足や時間配分の失敗、演習不足などがあげられます。
これらの課題を放置したままでは、企業がSPIで確認する基礎学力や適性、論理的思考力を正しくアピールできません。
だからこそ、SPIが苦手な人ほど「できない理由」を明確にし、言語・非言語両分野の対策をバランスよく進めることが重要です。
語彙力や読解力、計算力を伸ばすためには、頻出パターンを把握し、繰り返し練習することが効果的です。さらに、模試やツールを活用し、実践形式での経験を積むことも欠かせません。
SPIができないという状況は、正しい方法での努力によって十分に克服可能です。自分の課題に向き合い、計画的に対策を進めることで、内定への大きな一歩となるでしょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









