公務員の退職金は、基本額に調整額がプラスされた金額が支給されます。しかし、具体的な計算方法やもらえる平均金額がわからず、困ってしまう人もいるでしょう。
本記事では、計算方法や制度の注意点について解説します。
国家公務員や地方公務員の退職金の平均金額も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
まず確認!公務員の退職金の意味

公務員の退職金は、定められた期間勤務した公務員が退職する際に支給されるものです。
勤続年数が長いほど多くの金額を受け取れるのが特徴で、退職手当と呼ばれることもあります。
退職後の生活を保障するための制度として用意されていて、後払い式で賃金を追加支給する以外に勤続に対する報酬として支払われる意味合いが大きいのが特色です。
また定年が65歳に引き上げとなった影響で、もともとは60歳の定年退職時に支給されていましたが、65歳に支給されるよう、タイミングを変更した企業もあります。
公務員の退職金の計算方法

公務員の退職金の基本額や調整額の計算方法は、以下の通りです。(出典:国家公務員退職手当法)
- 退職金=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給割合)+調整額
- 調整額:在職期間中の貢献度に応じた加算額
具体的な計算例として、39年勤続して2020年4月に5級に昇格し、2023年3月に定年退職した際、在職中の休職期間が7か月あった場合は387,400円 × 47.709 (支給割合)+(32,500円×36月+27,100円×24月)=20,302,866円 (1円未満の端数を切り捨てた金額)となります。
前述の例では、7か月の疾病休職期間が4月分の除算期間となり、38年8月の勤続期間が38年に切り捨てされているのが特徴です。
公務員の退職金制度のポイント4つ

公務員の退職金制度のポイントを押さえていれば、ルールを理解しやすくなります。把握しておくべき注意点は、以下の4つです。
- 法律で定められている
- 勤務1年目から支給される
- 退職した翌月に振り込まれる
- 税金が発生する
①法律で定められている
退職金の仕組みや計算方法は、法律で定められています(出典:国家公務員退職手当法)。
国家公務員は「国家公務員退職手当法」で、地方公務員は各地方の条例で定められているのが特徴です。
なお、法律は官民均衡などを図るために改正されることがあります。
平成29年には国家公務員退職手当法の一部が改正され、退職手当の支給水準が引き下がり、調整率が0.87から0.837に変更されました(出典:内閣人事局|国家公務員制度|給与・退職手当)。
②勤務1年目から支給される
退職金自体は、勤続1年目から支給されます(出典:人事院「国家公務員退職手当支給割合一覧」)。
例えば国家公務員が1年目に自己都合で退職した場合は、「退職時の棒給月額に大して支給割合の0.5022を掛けた金額」が支給されるのが特徴です。
在職期間は6か月未満の場合は切捨てで、6か月以上で切上げになります。そのため、6か月勤めれば勤続年数が1年となり、退職金が支給される対象者になるのがポイントです。
③退職した翌月に振り込まれる

退職手当は退職した次の月に振り込まれます(出典:国家公務員退職手当法)。
国家公務員の場合は「国家公務員退職手当法」に準じ、翌月中の振り込みが予定されますが、地方公務員は地方自治法に基づいて、1ヵ月以内の振り込みが決まっているのが特徴です。
そのため、3月31日が退職日となった場合は4月中に、遅くとも4月下旬頃には受け取りが見込めます。
④税金が発生する
退職手当の受け取りには税金が発生するため、注意が必要です(出典:人事院「1退職手当制度の概要」)。税金の計算式は、以下のようになっています。
- (退職手当額-退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切捨て)
- 退職控除額は勤続年数20年以下で「勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)」
- 20年より上の場合は「(勤続年数-20)×70万円+800万円」で計算
勤続年数が21年以上かどうかで控除金額が大きく変わってくるため、長く勤続している方が税金が少なくなります。
【国家公務員】退職金の平均
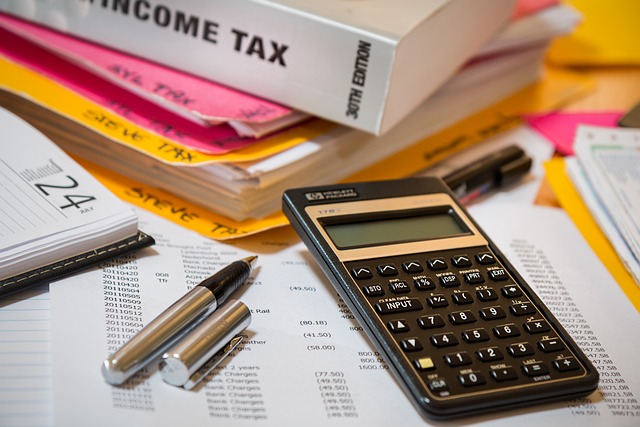
国家公務員の退職金の平均額は、以下のように退職理由によって大きく変動します。
| 退職理由 | 常勤職員平均支給額(千円) | うち行政職俸給表(一)適用者平均支給額(千円) |
| 計 | 11,043 | 13,910 |
| 定年 | 21,122 | 21,114 |
| 応募認定 | 25,247 | 22,500 |
| 自己都合 | 2,745 | 3,275 |
| その他 | 2,121 | 2,300 |
上記のうち、その他の退職理由には任期制自衛官の任期終了などが含まれるのがポイントです。
また、行政職俸給表(一)の適用者の具体例としては一般行政事務職員などが挙げられます。職務の難易度や経験年数に応じて金額を算定する表は「俸給表」と呼ばれるのも特徴です。
【地方公務員】退職金の平均

地方公務員の退職金の平均額は、以下のように職員区分や勤続年数によって変動します。
| 職員区分 | 平均支給額(千円) | 自己都合の退職等(千円) | 11年以上25年未満勤続後の定年退職等(千円) | 25年以上勤続後の定年退職等(千円) |
| 全職種 | 12,783 | 1,864 | 11,219 | 21,811 |
| 一般職員 | 12,036 | 2,210 | 11,367 | 21,123 |
| 教育公務員 | 13,298 | 1,253 | 10,955 | 22,593 |
| 警察官 | 16,704 | 2,869 | 11,282 | 22,300 |
地方自治体ごとに定められた「給料表」によって決定されるほか、職務の難易度が高いほど平均支給額が多くなっている傾向があるのが特徴です。
公務員の退職金を調べて就活を進めよう
公務員の退職金制度や計算するやり方を調べて、就活を進めましょう。退職手当には税金がかかり、21年以上勤続していることで控除額が大きく増加します。
勤続後に支給される制度について調べて、自身のキャリアプランを練りましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









