博士課程に進まず、就職することを決めた大学院生であれば、早めに就活の準備を整える必要があります。
しかし「どのように就活を始めれば良いのか」「研究との両立はできるのか」など、不安に感じることもありますよね。
そこで、本記事では理系院生の就活対策やポイントについて解説します。
ぜひ、これからの就活対策の参考にしてみてください。
理系院生の就活事情2つ

最初に、理系院生の就活事情について紹介します。
- シビアな研究と就活の両立
- 専門性が評価されやすい
就活を乗り越えるためには、自分がどのような現状にあるのか把握することが大切です。主な就活事情を確認し、就活の進め方について考えていきましょう。
①シビアな研究と就活の両立
理系院生が就活を始める場合、学会発表や研究と同時進行で準備をする必要があります。
研究には長い時間を割く必要があるので、就活だけに集中するのは困難。研究と就活を両立し、どちらも順調に進むようバランスを取らなければなりません。
多忙なスケジュールに追われないためには、徹底した計画管理が求められます。
管理ができていないと、エントリーの受付期限を忘れたり、面接準備が十分にできなかったりといった事態に陥る恐れがあるでしょう。
➁専門性が評価されやすい
大学院生は、学部生と比べて専門的な研究を行うため、就活で有利に扱われることがよくあります。
また、学会などの公の場に出る経験が豊富で、学部生より論理的思考力や説明能力に優れている場合が多いのも院生が高評価を受ける理由です。
企業によっては理系専用の採用枠を設けている場合もあり、理系人材は需要が高いと考えられるでしょう。
面接などで採用担当から好印象を持たれやすいので、自分のスキルをしっかり活かせればスムーズに就活が進められる可能性がありますよ。
理系院生の就活方法2つ

ここからは、理系院生の就活方法を紹介します。
- 自分で選考に応募する
- 推薦応募を利用する
選択する方法によって就活の進め方は変わります。自分に合う方法を選び、就活を行っていきましょう。
①自分で選考に応募する
自分で入社したい企業を探してエントリーし、選考を受けた後に内定をもらう方法です。一般的に自由応募と呼ばれています。
応募は、企業の公式サイトや就活情報サイトなどを経由して行うのが基本です。応募するのは1社のみに限らず、いくつかの企業に応募して複数の内定を得ても問題はありません。
ただし、自由応募では他の就活生と同じスタートラインに立つことになります。人気企業は競争率が高く、しっかりとした準備が必須です。
あらかじめ応募する企業を絞り込み、研究と就活準備を両立できる体制を整えておくようにしましょう。
➁推薦応募を利用する
推薦応募とは、大学院で公開された企業の入社枠に応募し、校内選考を経た後に入社試験を受けて内定を獲得する方法のことです。
事前に校内の選考を突破しているため、企業の選考が一部免除になるなど他の就活生より有利に進む場合がよくあります。
また、入社枠を出す企業は大学院の研究内容と類似した事業を手掛けているケースが多いため、入社後に「自分とマッチしない企業だった」と後悔する可能性が低い点もメリットです。
ただし、推薦を受けている以上、内定を辞退するのは難しいため慎重に企業を選ぶようにしましょう。
理系院生の就活はいつからすべきか

ここでは、就活を始めるタイミングについて解説します。
- 修士1年の夏までには始めよう
- 博士は2年夏から始めるのがおすすめ
就活を成功させるためには、始めるタイミングが重要です。適切な時期に始めて、内定獲得を目指しましょう。
修士1年の夏までには始めよう
毎年6月頃からインターンシップの選考が始まるため、修士1年の夏までには就活をスタートするようにしてください。
6月より前に自己分析や業界・企業研究を深めておけば、選考に応募する企業を選定しやすくなります。選考が始まった後も、事前に収集しておいた知識を活かすことで受かりやすくなるでしょう。
院生は、修士1年の後半に入ると学会発表の準備や研究で忙しくなっていきます。
就活に割く時間が少なくなるため、なるべく早めに就活を進めることが大切です。
博士は2年夏から始めるのがおすすめ
博士の場合は、2年の夏頃から就活を始めるのがおすすめです。
博士は、学部生や修士と異なり就活に関する明確なルールが決まっていません。そのため、できるだけ早めに準備を進めておくことが内定を獲得するためのキーポイントです。
博士採用に積極的な企業のなかには、10月頃から選考を始める場合もあります。夏にきちんと準備を整えておけば、早めの選考にも対応できるでしょう。
情報収集を徹底して、他の学生より早いスタートを切りましょう。
理系院生の就活のメリットとデメリット

理系院生が就活をする際のメリットとデメリットを紹介します。
- メリット①即戦力として活躍できる
- メリット②高い初任給
- デメリット|社会に出るのが遅くなる
どのようなメリット・デメリットがあるのか確認し、就活に役立てていきましょう。
メリット①即戦力として活躍できる
理系院生は、研究を通じて専門的な知識を得ているため、入社後も即戦力として働けるのがメリットです。
大学院で研究してきた分野とマッチする企業に入社すれば、すぐに自分の実力を発揮できるようになります。
若いうちから責任のあるプロジェクトを任されるようになれば、早めのキャリアアップにも繋げられるでしょう。
また、興味関心を持って研究してきた分野で働けるため、自分がやりたいと思っていることを仕事にしやすいのも大きな利点です。
メリット②高い初任給
一般的に、最終学歴が高くなればなるほど高い初任給を提示する企業が多いといわれています。
厚生労働省が発表した調査結果によると、大学院の修士課程を卒業した院生は、大学を卒業した学部生と比べて約3万円ほど初任給が上回っていることがわかりました。
1年で換算すると約36万円の差がでるため、院生は初任給の面で得する可能性が高いでしょう。専門知識を活かしてキャリアアップすれば、さらに高い給与をもらえるようになるはずです。
デメリット|社会に出るのが遅くなる
大学院に進学した後に就活をする場合、入社のタイミングは学部卒と比べて2年以上遅れることになります。
たとえ年齢が同じでも、社会人としてのスキルは学部生の方が上回っている場合が多く、ギャップを感じる可能性があるでしょう。
また、早く社会に出て働いている分、学部生と院生とでは生涯に得られる給与額に開きが出ることも。
しかし、院生は学部生より初任給が高くなる傾向があるのに加え、専門知識を活かしてキャリアアップしやすいため、努力次第では学部生との差を埋められる可能性は十分にありますよ。
就活に失敗してしまう理系院生の特徴3選
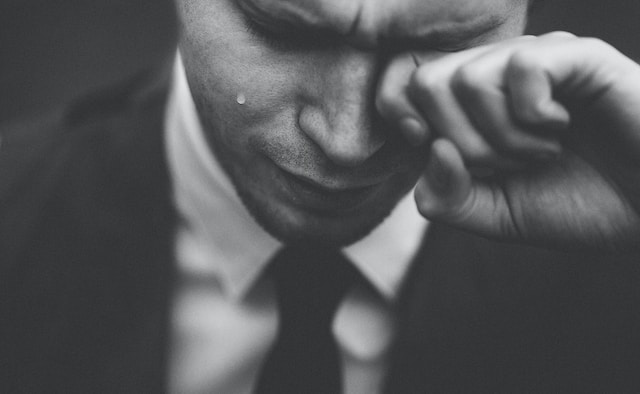
ここからは、就活に失敗する理系院生の特徴を紹介します。
- 「院生だから大丈夫」と楽観視している
- 就活の動き出しが遅い
- 大学院の研究と両立できていない
就活を成功させるためには、どのような点で失敗しがちなのか把握することが重要です。具体的な内容を確認し、気をつけていきましょう。
①「院生だから大丈夫」と楽観視している
「理系院生は学部生と比べて有利」と考え、就活を楽観的に捉えていると失敗の原因になります。
たとえ有利だとしても、何の対策もしないまま就活に臨んだ場合は、院生でも内定を得られない可能性が高いでしょう。
就活では、大学院で学んだ専門知識だけでなく、ビジネスマナーも求められます。また業界・企業研究を深め、しっかりとした志望動機を伝えられるようにすることも大切です。
特に競争率の高い企業は院生でも選考突破が難しいことがあるため、怠けずに就活準備を進めるようにしてください。
➁就活の動き出しが遅い
就活のスタートが遅いことも失敗の要因になります。
院生の場合、修士1年の夏までに就活を始める必要がありますが、大学院に入ったばかりの時期は新しい環境に慣れず、就活にまで考えが及ばない場合も少なくありません。
しかし、大学院卒業後に社会人になることを考えているのであれば、全く就活に触れないのはリスクがあります。
新しい環境に慣れながら、徐々にでも就活の準備を始めるようにしましょう。早めにスタートを切ることで、後々の就活と研究のバランスも取りやすくなりますよ。
③大学院の研究と両立できていない
就活と研究のバランスが取れていない人は、どちらも失敗してしまう恐れがあります。
研究ばかりを優先していると、就活に手を回せなくなるでしょう。一方で、就活に集中するあまり研究が疎かになっては大学院に進んだ意味がなくなります。
どちらも両立できるように、上手な時間の使い方を習得することが大切です。事前にスケジュールを組み、研究も就活も余裕を持って進められるようにしましょう。
どうしても研究との両立が難しいときは、担当教授や先輩などに相談し、対処法を考えてみてくださいね。
理系院生が就活を成功させるための3つのポイント

就活を成功させるためのポイントは、以下の通りです。
- 早めの就活準備
- 自己分析や業界・企業研究の徹底
- 研究内容を明確に伝えられるようにする
ポイントをきちんと押さえておけば、就活の失敗を防げます。詳細を確認し、今度の参考にしてみてください。
①早めの就活準備
就活で失敗しないためには、早めに準備をスタートするのがポイントです。
院生になってからしばらくすると研究が忙しくなり、就活に長い時間を割くのが難しくなる可能性があります。
忙しくなる前に就活のためにできることをやっておけば、余裕を持ってスケジュールを組めるようになるでしょう。
また、研究だけに必死にならないようにすることも重要です。博士課程に進まず、就職すると決めたのであれば、優先順位を意識して研究と就活の両立を目指しましょう。
➁自己分析や業界・企業研究の徹底
就活は情報戦になることが多いため、なるべくたくさんの情報を集めて研究しておくことが大切です。
まずは自己分析を行い、自分にはどのような職種や業界が合っているのか検討してみてください。
希望する業界や企業の分析を徹底的に行い、理解を深めておく必要もあります。自己分析や業界・企業分析をきちんと行っていれば、就活に欠かせない自分なりの軸を確立できるはずです。
しっかりとした軸があれば説得力のある志望動機を伝えられるようになり、選考で高い評価を得られる可能性が高まるでしょう。
③研究内容を明確に伝えられるようにする
採用担当者に対して研究内容をしっかりと伝えることも重要なポイントです。
院生の強みは、優れた専門性。大学院で研究したことや、研究で得た知識を入社後にどうやって活かせるか説明できるようにしましょう。
説明内容を考える時は「相手が理解しやすいか」ということを重要視する必要があります。たとえ優れたスキルを持っていても、相手にきちんと伝えられなければ意味がありません。
相手が分かりやすいように簡潔かつ明確に説明内容をまとめるようにしてください。
理系院生の就活はスケジュール管理と対策がカギ

研究と就活の両立が求められる理系院生は、しっかりとスケジュール管理をすることが大切です。
また、早めに就活をスタートし、自己分析や業界・企業分析を行って対策を徹底しておく必要もあります。
研究と就活のバランスを取りながら進められるように計画を立てていきましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









