入社した企業で長く働くためには、企業の「離職率」をあらかじめ調べておく必要があります。しかし「離職率はどのように調べればいいの?」と悩みますよね。
そこで本記事では、離職率の調べ方や見るポイントを解説します。離職率が高い・低い業界も紹介しているのでぜひ最後まで読んでみてくださいね!
離職率の4つの調べ方
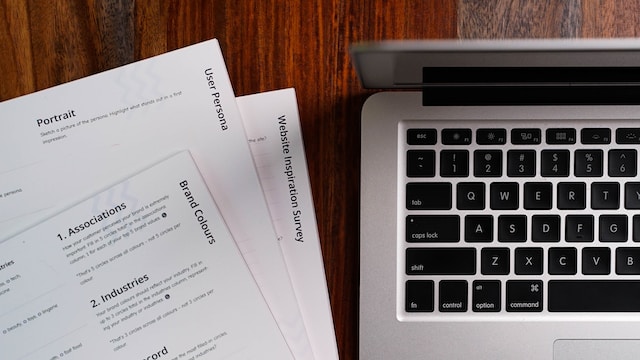
まず、離職率の主な調べ方を4つ紹介します。
- 会社四季報で調べる
- 有価証券報告書で調べる
- 口コミサイトで調べる
- 就活エージェントから聞き出す
①会社四季報で調べる
会社四季報は、国内市場全上場企業の業績や配当予想、財務・大株主情報、資本異動、株価推移などを掲載した季刊雑誌です。
企業の採用数・年収・離職率・残業など会社の待遇や働きがいがわかるため、就活では手離せません。
ただし、掲載されている情報が最新のものとは限りません。正確な情報を得るためには、企業の公式ウェブサイトなどと合わせて活用しましょう。
②有価証券報告書で調べる
有価証券報告書とは、株式などを発行している上場企業が、自社の企業概況や経営状況をまとめた書類です。
有価証券報告書には、「従業員の状況」として従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与が記載されています。
この中で離職率に大きく関連するのが、平均勤続年数です。平均勤続年数をチェックすることで、長く働ける企業はどこかを見定めやすくなるでしょう。
③口コミサイトで調べる
口コミサイトで確認することも、離職率を知る方法のひとつです。
口コミサイトには、実際にその企業で働いたことのある社員の生の声や感想が掲載されています。そのため、離職率だけでなく、離職の理由や労働環境に関する情報も得られます。
ただし、信ぴょう性が確保されていないことも多いため、情報を鵜呑みにしないことが重要です。信頼性が高い情報を知りたい場合は、複数の口コミサイトの参照や、他の方法との併用がおすすめです。
④就活エージェントから聞き出す
「リクルートエージェント」や「マイナビエージェント」などの転職エージェントは、離職率を調べる上で強い味方になってくれます。
転職エージェントは、企業の離職率を数値で把握しているわけではありませんが、「離職率・定着率に課題のある会社かどうか」については一定の知見・見解を有していることが多いのです。
ただし、就活エージェントに離職率を聞いたとしても、必ずしも情報を共有してくれるとは限らないため、注意しましょう。
離職率の見方で抑えるべき4つのポイント

次に、離職率の見方で抑えるべきポイントを4つ紹介します。
- 離職率の算出方法を確認する
- 業界の平均離職率と比較する
- 複数年の離職率をチェックする
- 離職率が低ければ良いわけではない
①離職率の算出方法を確認する
1つ目は、離職率の算出方法を確認することです。離職率は、企業が定める一定期間内の離職者数を起算日の在籍者数で割り、100(%)を掛けた値で算出します。
たとえば、2023年4月1日の社員数が100名いた会社で、在籍していた100名のうち20名が、2024年3月31日までに離職した場合、離職率は20名÷100名×100=約20%となります。
ただし、離職率の算出方法は法律などで定められているわけではありません。離職率が低くなるような算出方法を採用している場合もあるので注意しましょう。
②業界の平均離職率と比較する
2つ目は、業界の平均離職率と比較することです。なぜなら、離職率は業界によって大きく異なるからです。まずは離職率を知りたい企業が属する業界の離職率を調べましょう。
もし、企業の離職率が業界標準より高い場合、要因を明確に把握し、安定性や福利厚生などの複合的な指標と合わせて総合的な判断が必要です。
企業の過去の離職率傾向も考慮し、従業員の声や評価指標と組み合わせて判断材料とすることが重要です。
③複数年の離職率をチェックする
3つ目は、複数年の離職率をチェックすることです。なぜなら、年度によって離職率が大きく異なる可能性があるからです。
たとえば、事業が縮小したことによって、1年だけ離職率が高くなってしまうことも考えられます。逆に、企業の業績が好調であったり、景気が良い時期には、従業員の離職率は下がります。
大切なのは、複数年のデータを参照することです。企業の離職が継続的なものか、それとも一時的なものなのかを判断でき、より正確な評価が可能となります。
④離職率が低ければ良いわけではない
4つ目は「離職率が低ければ良いわけではない」と知っておくことです。
企業によっては従業員が定着し、新入社員が馴染みづらいケースがあります。また、独立することを推奨・サポートする企業も存在します。
そのため「離職率が高い=長く働けない」と安易に決めつけないようにするべきです。様々な観点から企業を研究するよう心がけましょう。
離職率の高い企業の特徴5選

次に、離職率の高い企業の特徴を5つ紹介します。
- サービス残業が多い
- 有給休暇が取得しにくい
- 産休や介護休暇を取りにくい
- 人間関係が悪い
- 給与が低い
①サービス残業が多い
離職率が高い企業は、サービス残業が多い傾向にあります。
サービス残業が頻繁に発生すると、従業員のワークライフバランスが損なわれ、仕事への不満やストレスが蓄積し、これが離職を招きやすくなるのです。
また、サービス残業が常態化する企業は、労働環境が改善されていない可能性があり、従業員のモチベーション低下や健康問題に繋がることがあります。
②有給休暇が取得しにくい
有給休暇が取得しにくいことも、離職率が高い企業の特徴です。従業員がバランスの取れたワークライフを求める中、有給休暇の取得が難しい状況は働きがい低下につながるからです。
この現象は、労働環境の悪化やストレス増大に繋がり、結果として離職率が上昇することがあります。
有給休暇が取得しにくい企業や業界は、過重な業務負担や働き方の柔軟性の不足が見られ、これらが離職を招く傾向があるのです。
③産休や介護休暇を取りにくい
離職率が高い企業では、産休や介護休暇が取りにくいことが一因となります。なぜなら、従業員が出産や育児、介護の時間を確保しにくく、仕事と家庭の両立が難しくなるからです。
特に、女性の場合は産休や育休などの制度が設けられているかで大きく離職率が変化します。
特に、産休や介護休暇を取りにくい企業や業界では、労働環境や制度が柔軟性に欠け、従業員が自分の生活事情に合わせて休暇を取りにくい状況が見られます。
④人間関係が悪い
人間関係が悪い企業は、離職率が高い傾向にあります。なぜなら、コミュニケーション不足や上下関係の風通しの悪さによって従業員が十分なサポートを受けられず、仕事への満足度が低下するからです。
また、人間関係が悪い企業では、情報がうまく共有されず、従業員のモチベーション低下やストレス増加が見られます。
働く上で人間関係の構築と柔軟なコミュニケーションはとても重要です。そこが欠けていれば、離職率は高くなる一方でしょう。
⑤給与が低い
給与が低い企業では、離職率が高まる傾向があります。なぜなら、給与が低いと従業員のモチベーションが下がり、優秀な人材が他の環境を求めるようになるからです。
また、給与が低いと、生活の不安定感やキャリアの発展が見込みにくいと感じるようになります。このように、給与の低さは「辞めたい」と考えることに直結しやすいのです。
そのため、離職率を見る際は給与に焦点を当ててみましょう。
離職率が比較的高い業界3つ

次に、離職率が比較的高い業界を紹介します。
- 教育業界
- 宿泊業・飲食業界
- 生活関連サービス・娯楽業界
①教育業界
教育業界は、学校や塾の講師が主な活動をする業界です。離職率が高い背景には、長時間労働、低給与、多忙な業務量、そして生活の不規則さが挙げられます。
また、生徒や親とのコミュニケーションや対応によるストレスや事務作業の増加なども要因となっています。
さらに、部活動指導など、授業外にも多くの時間を費やさなければならず、その割に報酬が見合わないことも課題です。これらが離職率を高める要因となっています。
②宿泊業・飲食業界
宿泊施設や飲食店を営む業界宿泊業・飲食業界も、離職率が高い傾向にあります。
なぜなら、これらの業界では土日祝日に休みが取りにくいことに加え、給与が低く、長時間の労働が一般的だからです。
また、労働条件の厳しさや経済的な不安定さが、従業員の離職を促進していると言えます。これらが、離職率を高める要因となっているのです。
③生活関連サービス・娯楽業界
生活関連サービス・娯楽業界も、離職率が高い傾向にあります。生活関連サービス業はクリーニングや美容業、娯楽業界はテーマパークやギャンブルなどを含みます。
これらの業界の離職率が高い理由は、顧客サービスやエンターテインメントが多く、従業員には肉体的な労働やクレーム対応などが求められるからです。
結果的に、労働条件の厳しさやストレスが生じやすい環境が影響し、離職率が比較的高くなっています。
離職率が比較的低い業界3つ

最後に、離職率が比較的低い業界を紹介します。
- 郵便・協同組合
- 金融・保険業
- 情報通信業
①郵便・協同組合
郵便・協同組合業界は郵便局や農業協同組合、信用事業、保険事業などを含みます。
この業界では、公共サービスの提供や地域社会の支援が中心です。そのため、離職率が比較的低い傾向があります。
特に、郵便・協同組合では従業員の労働時間が相対的に短く、ワークライフバランスが重視されています。この労働環境の整備が、従業員の満足度を向上させ、定着率を高めているのです。
②金融・保険業
金融・保険業は、資産運用や融資、保険商品の提供など、専門的な金融サービスを提供する産業です。
この業界では、高い給与水準や手厚い福利厚生が整備されていることが多いため、従業員は安定感を感じることができます。それが離職率の低さにつながっています。
また、健康保険、退職プラン、教育サポートなどの福利厚生が提供され、働きやすい環境が整っていることも要因のひとつです。
③情報通信業
情報通信業は、放送や音声・映像メディアとIT業界を含む業界です。近年、デジタル技術の進化に伴い急成長している注目の業界と言えるでしょう。
そんな情報通信業は、かつては給与の低さや人材不足から離職率が高い傾向にありました。しかし、近年では技術の進歩と需要増加により改善傾向にあります。
新たなビジネスモデルや働き方の変化が業界全体を活気づけ、従業員の満足度向上が見られている。絶えず進化する技術環境と成長機会が、従業員の定着に貢献しているのです。
離職率の正しい知識を持って、自分で調べてみよう
本記事では、離職率の調べ方や見るポイントを解説しました。
離職率は、企業での働きやすさを評価する重要なヒントです。会社四季報や有価証券などを活用し、調べておくと良いでしょう。
ただし、離職率が必ずしも正しいとは限らないことや、離職率が低ければ良いわけではないということに注意しましょう。離職率の正しい知識を持って、自分で調べることが重要です。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









