面接の後にお礼メールを送る方は多いかと思います。ただ、もっと気軽な雰囲気で開催される座談会の後は、お礼メールが必要かどうか迷ってしまうこともあるでしょう。
結論から言うと、たとえ選考に直接影響しない座談会でも、お礼のメールは送るべきです。本記事では、お礼メールの必要性、また書く内容やポイントを例文をまじえて詳しく解説します。
メールテンプレで自動作成!
- ★メールテンプレ|3分でメール作成
- 煩雑なメール作成を自動で効率よく
- ★志望動機テンプレシート|簡単作成
- 4つの質問に答えるだけで志望動機完成
- ★自己PR自動作成|テンプレシート
- 自己PRを3分で簡単作成
座談会のお礼メールは送るべき

座談会とは、会社説明会ほど堅苦しくなく、社員と学生が割とフランクな雰囲気で話ができる場です。あくまで学生が企業について質問する場であり、選考には直接影響しません。
また、インターンや面接などよりも、お礼メールの必要度は低く、決して必須ではありません。
とはいえ、企業が学生に時間や場所を割いてくれているのも事実です。就職活動においては、企業になにかしてもらった場合には、お礼メールは送るもの、と考えておくとよいでしょう。
自分の言葉で感謝の気持ちを伝えることで、企業はあなたの存在や名前を覚えてくれ、好印象を持ってくれることもあるでしょう。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
座談会のお礼メールで書くべき内容3つ

それでは実際、どのようなことを書けばいいのでしょうか? ここではお礼メールに書くべき内容を3つ紹介します。
- 感謝の言葉
- 感想・学んだこと
- 本選考への気持ち
①感謝の言葉
まずは座談会という貴重な機会を用意してもらったこと、それに参加させてもらったことに対して、お礼の気持ちを述べましょう。
「この度は貴社の座談会に参加させていただき、誠にありがとうございました。」など、長くなりすぎないよう簡潔なお礼の言葉から書き始めてみてください。
複数の場所や時間帯で座談会が開かれていた場合は「◯時から開催された◯◯部の座談会」など詳しく記載すると、企業側にも伝わりやすくなりますね。
②感想・学んだこと
続いて、その座談会で印象に残ったことを書きましょう。自分の質問に答えてくれた社員の方への印象や、座談会で聞くことができた興味深い回答、参加したからこそ感じることができた心情などを、なるべく具体的に書きます。
「〇〇様に伺った〇〇というお話が印象に残っています」「業務内容について質問した際に、◯◯様がしてくださったお話で、より具体的にイメージできるようになりました」など、直接話を聞けたからこそわかったことを伝えてみてください。
③本選考への気持ち
最後に、その企業の本選考に進みたいと考えている場合は、企業への意欲をアピールしましょう。本選考に進みたいという希望がない場合は書かなくてもOKですが、一文として加えておくのがおすすめですよ。
「今回の座談会を通じて、貴社への入社意欲がますます高まりました」「本日の座談会を通して、より一層貴社で働きたいという気持ちが強まりました」など、シンプルな言葉で大丈夫です。
メール自体が長くなってしまうと、先方にとって読む時間が長くなり迷惑にもなりかねません。面接でもエントリーシートでもないので、過度に自己アピールはしないように気をつけましょう。
座談会のお礼メールの例文

それでは、上記のポイントをふまえ、座談会のお礼メールの例文を紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。
| 件名:〇月〇日座談会のお礼 △△大学 田中太郎 〇〇株式会社 人事部人事課 〇〇様 お世話になっております。 △△大学〇〇学部〇〇学科の田中太郎と申します。 本日はお忙しい中、座談会という貴重な場を設けていただき、誠にありがとうございました。 実際にお仕事をされている社員の方々からたくさんのお話を伺うことができ、 業務内容について、より具体的にイメージできるようになりました。 特に◯◯様が話してくださった、◯◯の商品開発についてのエピソードが大変興味深く、 私も貴社でぜひ一緒に働きたいという気持ちがますます高まりました。 ぜひ貴社の選考を受けさせていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 略儀ながら、御礼を述べたくご連絡させて頂いた次第です。 今後とも宜しくお願いいたします。 ―――――――――――― 田中 太郎(たなか たろう) 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 Mail::xxxxx@mail.com ―――――――――――― |
件名は相手方がひと目でわかるよう、簡潔にしましょう。宛名は座談会の担当社員になります。名刺や資料をもらっておらず、担当者名がわからない場合は「座談会ご担当者」でも大丈夫です。
大学・学部・名前は略さず正式名称で名乗るようにしましょう。そのあと、感謝の気持ち→座談会で実際に感じることができた具体的なエピソード、を記載します。
最後に意欲と、この場合は選考に進みたいという意気込みを述べましょう。
座談会のお礼メールを送る時の注意点3つ
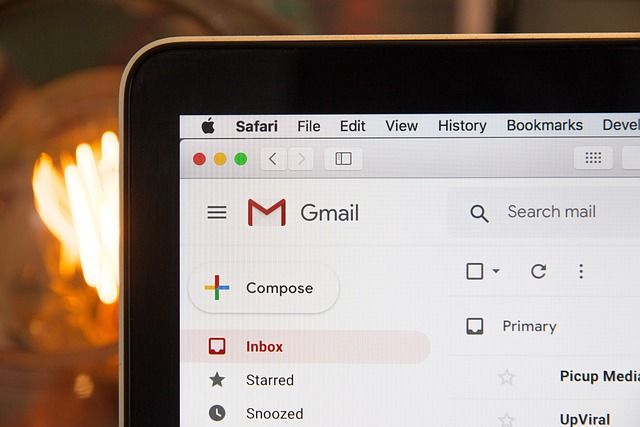
ここでは、座談会のお礼メールを作成する際に注意したいポイントについて解説します。主な注意点は下記の3点です。
- 宛名は間違えない
- 件名は簡潔にする
- 署名を忘れない
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
①宛名は間違えない
お礼メールだけではありませんが、就活においてメールを送る際は、宛名は絶対に間違えないようにしましょう。先方に失礼ですし、かえってネガティブな印象を持たれてしまいます。
宛名には座談会の担当者や社員の名前を書きますが、名前の漢字など間違いがないか、しっかりチェックしてから送信するように気をつけましょう。
書き方としては「会社名・部署名・役職名・氏名」です。担当者名がわからない場合や、この人で合っているのか不安な場合は「座談会ご担当者様」としましょう。
また、企業の会社名も(株)ではなく「〇〇株式会社」と正式名称で書いてください。
②件名は簡潔にする
件名(メールタイトル)は、先方の担当者がぱっと見てわかるように記載するのが重要です。
人事部には日々大量のメールが届きます。社員の方にも、仕事の流れ上、開封する優先順位があるはずです。「座談会のお礼」であると一目でわかるように書きましょう。
「◯月◯日の座談会のお礼(大学名・氏名)」がベストです。学部や学科まで入れると長くなってしまうので、それは本文に記載してください。
「本日はありがとうございました」や「◯◯大学 田中です」のような件名は、たとえ簡潔でもわかりにくく、お礼メールなのに逆に迷惑と思われてしまいます。
③署名を忘れない
就職活動も含め、ビジネスメールには署名がつきものです。ビジネスメールの常識をわかっていることをきちんと伝えるためにも、署名は忘れずに入れましょう。
具体的には、大学名・学部・学科・氏名・連絡先です。大学名や学部名などは、略さず正式名称で記載します。名前にはふりがなも合わせて記載しましょう。連絡先は基本はメールアドレスと携帯電話番号で問題ないです。
署名はメールソフトに事前に設定すると、自動入力されて便利ですよ。
座談会のお礼メールにまつわるQ&A

ここでは、座談会のお礼メールについてよくある質問や疑問点をまとめました。以下3つについて詳しく解説します。
- メールを送るタイミングはいつ?
- 相手からお礼メールの返信がきた場合はどうする?
- 例文のメールをそのまま送って良い?
①メールを送るタイミングはいつ?
メールはなるべく早く、できれば座談会の当日に送りましょう。
とはいえ、あまり遅い時間になってしまうと、先方の終業時間近くになるので、かえって迷惑になる可能性もあります。17時を過ぎるようであれば、翌日の午前中に送る方が好ましいでしょう。
担当者があなたのことを覚えているうちにお礼メールを送ることができれば、好印象となり、選考に有利となる可能性もあります。遅くても翌日の午後までには送信するように心がけてくださいね。
②相手からお礼メールの返信がきた場合はどうする?
お礼メールには、基本的に返信がないことがほとんどです。とはいえ企業の社風や規模によっては、返信が来るかもしれません。
もし企業からお返事メールが来たら、必ずなるべく早く返信をしましょう。メールの件名は新たに打ち込むのではなく、「Re:」を含めそのままの文章で返信します。本文も引用という形で残しましょう。
内容としては、下記のような簡潔なもので十分です。
| お忙しい中、ご丁寧にお返事をいただきまして、誠にありがとうございます。 またこのような機会がございましたら、ぜひ参加させていただきたいと存じます。 その際はどうぞよろしくお願い申し上げます。 |
お礼メール同様、署名を付けて返信しましょう。
③例文のメールをそのまま送って良い?
お礼メールのような短い文章なら、例文をそのまま使っても問題ないのでは、と思いがちですよね。ただ、あまりにも定型文そのままでは、担当者に流し読みされてしまう可能性が高いでしょう。
お礼メールは「感謝の気持ちと感想」が大切です。特に感想の部分は、絶対に人それぞれ違うはずです。誰から、どんな話を聞いて、どう感じたかを具体的に記載することで、あなた自身を企業に印象付けることができますよ。
例文はあくまで参考程度にして、伝えるべき内容は自分の言葉で書きましょう。
座談会のお礼メールは忘れないうちに送ろう
座談会に参加した際には、貴重な機会を頂いた感謝と、具体的にどのような話を聞きどう感じたかを、簡潔にまとめてお礼メールとして送りましょう。
座談会は直接選考に影響はしませんが、お礼メールで好印象を与えることで、面接などが有利に進む可能性もあります。ぜひ参考にしてみてくださいね。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









