公務員試験では適性試験が実施される場合があります。しかし、中にはどのような設問があるのかわからなかったり、事前準備の仕方に困惑してたりする人もいるでしょう。
本記事では、適性試験を受ける際の対策ポイントや、実際に出る内容について6つ解説します。公務員試験を控えている人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員の適性試験とは

公務員試験では、適性試験が実施される場合もあります。主な適性試験の内容としては、以下の3種類があります。
- 性格適性検査
- 職場適応性検査
- 事務適性検査
上記の中でも1番対策が必要なのが事務適性検査であり、計算問題や図形問題などのような試験問題が出題されます。
もちろん、事務適性検査以外についても事前にどのような検査なのか把握しておくことは大切です。本番で焦らないためにも事前準備は怠らないようにしましょう。
公務員の適性試験対策のポイント3つ

適性試験も面接などと同様に対策をする必要があります。事前準備や試験中では、以下の3つを忘れないようにしましょう。
①計算問題は解き方を予め把握しておく
適性試験は、内容が統一されているわけではなく、的を絞って対策するのが難しい傾向にあります。
そのため、試験対策をする際はできるだけ幅広く対応できるように準備しておくと良いでしょう。
対策としては、自分が受ける自治体にあった過去問を何度も繰り返し、解き方の理解やスピードを上げる努力をしましょう。
②常識問題は確実に回答する
適性試験の中には、文章問題や計算問題のように対策が必要な問題の他に、常識問題がいくつか出題される場合があります。
特別難しい問いが出るわけではありませんが、他の受験者も答えやすいところのため、できるだけ確実に解答することが大切です。
③とにかく落ち着いて受験する
適性試験は、学校の試験などとは違い、試験時は臨機応変に設問を進めていく必要があるため、落ち着いて受験することが求められます。
特に、常識問題などについては他の受験生も解答しやすい場所のため、取りこぼしがないようにしなければいけません。落ち着いて解答することを心がけましょう。
公務員の適性試験の主な出題内容6つ

公務員の適性試験では主に以下の6つの内容が出題されます。事前に内容を把握して対策しておくことで、問題に対応しやすくなるでしょう。
①計算
計算問題は適性試験の中でも定番の問題です。比較的簡単な問題が多い傾向にありますが、他の設問に使う時間のことを考えると、できるだけ正確に早く解く必要があります。
出題の仕方としては「3+2、3×2、12÷2」の中で大きいのはどれかといった問題や「12÷◯+3=9」のような穴埋め問題などが出ます。
正確性とスピードを上げるためにも、計算のルールの復習や計算に関する問題集などを数多くこなしておくと良いでしょう。
②分類
分類は、出題された数字などをあらかじめ問題で用意されている記号ごとに分ける問題です。イメージしにくい人もいると思いますので、具体例を確認しておきましょう。
例えば、1234という数字は「a(1101~1200)、b(1201~1300)、c(1301~1400)」の3つの選択肢の中でどれに当てはまるか解答する問題です。
特別な対策をしなくても解答できますが、本番では上記の例題よりも複雑な問題が出る可能性もあるので注意しましょう。
③置換
置換は、出された情報をもとに数字を漢字やカタカナなどに変換する問題です。
例えば、与えられた情報が「1(い)、2(か)、3(あ)、4(ろ)」だとして、3214の組み合わせとして正しいものを選択肢から選ぶとすると「あかいろ」が正解です。
問題が複雑になるにつれて、与えられた情報を理解して問題を解くまでの時間が長くなってしまいます。できるだけ多くのパターンに触れ、問題慣れしておきましょう。
④照合
照合と聞くと難しいイメージがある人も多いかもしれませんが、簡単に説明すると、間違い探しに似た問題です。
出題の仕方としては、ある数字や、数字と文字が混ざったデータと同じものを選択肢の中から選ばせるものが一般的です。
例えば「12345-ab」と同じものを「a(13456-ba)、b(54321-ab)、c(12345-ab)」の中から選ぶといったような問題が出題されます。
複雑になるほど、文字数が多くなって間違いやすくなるので注意が必要です。
⑤図形把握
図形把握では、出題された図形と同じものを選択肢の中から選ぶ問題です。
簡単な問題であれば同じ図形を選ぶだけで済みますが、難易度が上がるにつれて、図形を回転させないとわからないなど、一瞬で判断できない選択肢もあるでしょう。
一般的な計算問題と違い、図形把握では反復練習で慣れるのが難しいため、苦手意識を持つ人も多いです。
そのため、対策を始める時期を早めたり、他の分野で点数を稼げるようにしたりするなど工夫をしましょう。
⑥複合問題
複合問題は、これまで解説した5つの問題が合わさった状態で出題される形式のことです。例えば、計算と分類を組み合わせた問題が出題されることが考えられます。
どのような組み合わせが出題されるか予想するのは難しいですが、それぞれの出題形式に慣れておくことで、ある程度対応できるようになります。
基本的な問題に慣れてが整ってから、過去問や問題集などで複合問題の演習を重ねると良いでしょう。
公務員の適性試験におすすめな対策本3つ

公務員の適性試験の対策をするのであれば、自分に合った問題集を1冊用意しておくと良いでしょう。
もし、どの問題集が良いのかわからない場合は、以下の3冊がおすすめですので検討してみてください。
①高卒程度公務員 完全攻略問題集 2024年度版
高卒程度公務員 完全攻略問題集 2024年度版は、地方や市役所初級などの高卒程度の公務員試験を対策できる問題集です。
本記事で解説している適性試験の対策に加えて、教養試験や面接、作文試験の対策もできます。公務員試験を幅広く対策したい人におすすめの1冊と言えるでしょう。
試験対策の問題集を数多く持ちたくない人は、ぜひ検討してみてください。
②公務員試験 適性試験対策 やればやるほど伸びるトレーニング 第3版
公務員試験 適性試験対策 やればやるほど伸びるトレーニング 第3版は、国家一般職(高卒者)や地方初級などの適性試験の対策ができる問題集です。
全20回分のオリジナルの問題がついているため、適性試験をしっかり対策したい人におすすめの1冊です。教養試験や面接対策とは別で適性試験の対策ができる問題集を探している人は、ぜひ購入を検討してみてください。
③事務能力検査
事務能力検査は、事務職の仕事をする上で必要とされる応用能力と適性試験に対応できるように、26種類の検査と3種類の演習を備えています。
クレペリン検査(解答用紙にある1桁の数字を足していく試験)用紙も付属しているため、クレペリン検査を体験してみたい人はぜひ購入してみてくださいね。
公務員の適性試験では事前対策でコツを掴んでおこう!
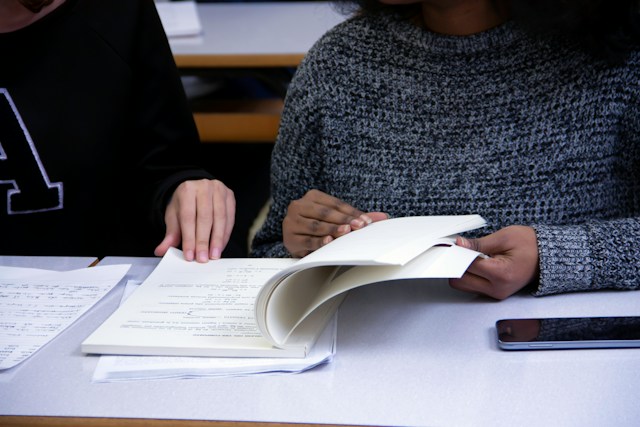
適性試験は、筆記試験や面接と違い暗記などで対応しにくいため苦手意識を持つ人が多いです。しかし、事前対策次第ではコツを掴んだ上で適性試験に臨むことが可能です。
早く正確に解く事が求められる適性試験ですが、過去問や問題集を何度も繰り返すことで、問題を解くスピードも上がります。しっかり事前準備をした上で試験に挑みましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









