公務員を目指している就活生も多いと思います。しかし、公務員就活は民間就活とスケジュールも違うため、どう進めていいか迷っている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、公務員就活のスケジュールと対策について解説します。
公務員の種類や試験についても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員には大きく2つの種類がある

一口に公務員と言っても、大きく分けて2種類あります。ここでは国家公務員と地方公務員について解説します。それぞれの特徴を理解することは、公務員を目指す上で非常に重要です。
- 国家公務員
- 地方公務員
①国家公務員
国家公務員は、日本国政府の直轄下にある公務員です。国家公務員の主な仕事は、国の政策を実行し、国民の生活を支えることにあります。
国家公務員には、総合職と一般職があり、総合職は政策立案や企画などの高度な知識や技術を要する業務を、一般職は事務処理などの定型業務を担当します。
国家公務員は、全国規模での転勤が多いことや、場合によっては海外勤務の可能性もあることが特徴です。また、国の運営に直接関わるため、高い専門性と責任感が求められます。
②地方公務員
地方公務員は、都道府県や市区町村などの地方自治体で働きます。地方公務員の主な役割は、地域住民に密着した行政サービスの提供です。
地方公務員には一般職、技術職、公安職、特別職などの職種があり、それぞれが地域の特性に合わせた業務を行います。
例えば、一般職は都道府県庁や公共機関での事務職、技術職は建設や土木などの専門的な技術を活かした職種です。地方公務員の魅力は、地域社会に直接貢献できる点にあります。
また、地方公務員はその勤務地域に根差した生活を送ることが多く、地元でのキャリアを築きたい人に適しています。
公務員として働く4つのメリット

公務員には様々な魅力があります。ここでは公務員として働く4つのメリットを紹介します。
- 解雇リスクが非常に低い
- ワークライフバランスを取りやすい
- 社会的な信用が厚い
- 国や地域に直接貢献する働き方が可能
①解雇リスクが非常に低い
公務員の最大の魅力の1つは、その雇用の安定性にあります。民間企業と比較して、公務員は解雇リスクが非常に低いとされています。
これは、公務員が国や地方自治体によって雇用されており、組織自体が倒産するリスクがほとんどないためです。また、公務員の職は、景気の変動に左右されにくい性質を持っています。
したがって、公務員は長期的なキャリアプランを立てやすく、生活も安定するのです。経済的な安心感は、プライベートな生活にも余裕をもたらし、精神的な安定にも寄与するでしょう。
②ワークライフバランスを取りやすい
公務員はワークライフバランスを保ちやすい職業です。多くの公務員職では、週休2日制が確立されており、有給休暇も比較的簡単に取得できます。
これにより、仕事とプライベートの時間を適切に分け、充実した生活を送ることが可能です。また、残業が少ない傾向にあるため、家族や趣味の時間を大切にできる点も魅力的です。
仕事とプライベートのバランスを重視する人にとって、公務員は理想的な職業と言えるでしょう。
③社会的な信用が厚い
公務員は社会的な信用が厚い職業です。公務員としての仕事は、国民の生活や社会の安定に直接関わるため、高い社会的責任と信頼が伴います。
このため、公務員は一般的に尊敬される職業とされています。また、金融機関からの信用も高く、住宅ローンの審査なども有利です。
社会的な地位や信頼を重視する人にとって、公務員は魅力的な選択肢と言えます。
④国や地域に直接貢献する働き方が可能
国や地域社会に直接貢献できることも魅力です。公務員は、国民の生活を支え、社会の安全と秩序を守る重要な役割を担っています。
公務員の仕事は、社会貢献度が高く、多くの人々の生活に影響を与えます。自分の仕事が社会にどのように貢献しているかを実感しやすいのも、公務員の大きな魅力です。
社会貢献を重視する人にとって、公務員は非常にやりがいのある職業と言えるでしょう。
公務員試験の2つの種類
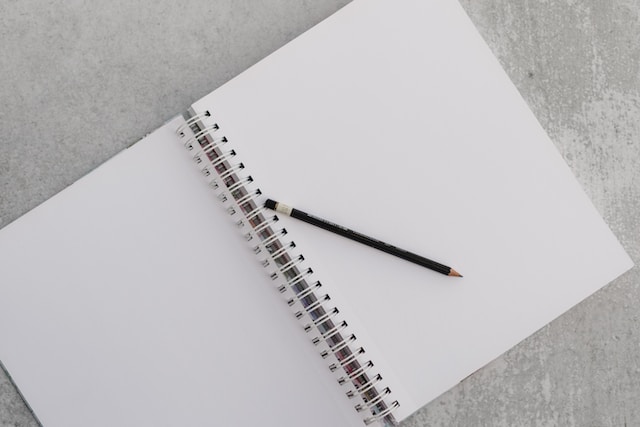
公務員試験は、国家公務員と地方公務員で内容が異なります。ここでは、国家公務員と地方公務員それぞれの試験の特徴を詳しく解説します。
- 国家公務員
- 地方公務員
①国家公務員
国家公務員試験は、大きく分けて「総合職」と「一般職」があり、それぞれの試験内容や対策方法が異なります。
総合職試験は、人事院が実施し、院卒者試験と大卒程度試験に分かれているのが特徴です。試験は第1次試験と第2次試験から構成され、公務員としての基礎能力や専門分野の知識が問われます。
一方、一般職試験は、大卒程度試験、高卒者試験、社会人試験に分かれ、地域ごとに受験します。試験内容は、基礎能力や専門分野に関する選択・記述問題が中心です。
試験に合格した後は官庁訪問があります。官庁訪問は、受験者が各官庁を訪れ、業務説明を受けたり、面接を行います。官庁訪問は採用に直結する重要な選考です。
②地方公務員
地方公務員試験は、一般職、技術職、公安職など、様々な職種に分かれています。試験内容は、一般教養や専門知識を問う筆記試験と面接が中心です。
特に一般職の場合、国語、数学、社会、理科などの一般教養を問う試験が多く、地方自治体によっては特定の専門知識を要求することもあります。
地方公務員試験は各自治体ごとに実施され、地域に根差したサービスを提供する職員を求めています。そのため、試験内容や形式は自治体によって異なり、地域の特性やニーズに合わせた準備が必要です。
公務員就活の一般的なスケジュール

公務員になるための道のりは決して簡単ではありません。特に、就活スケジュールの管理は非常に重要で、計画的に進める必要があります。
ここでは、公務員試験の一般的なスケジュールと、その進め方について詳しく見ていきましょう。
- 大学3年生、院1年生の4月~6月に試験勉強開始
- 大学3年生、院1年生の7月~9月に夏インターンシップ
- 大学3年生、院1年生の3月頃から出願開始
- 大学4年生、院2年生の5月~6月に一次試験
- 大学4年生、院2年生の6月~7月に二次試験
①大学3年生、院1年生の4月~6月に試験勉強開始
公務員試験の準備は早ければ早いほど良いです。特に大学3年生や院1年生は、4月から6月の期間に試験勉強を開始することが推奨されます。
この時期に始めることで、試験の内容をじっくりと理解し、十分な準備時間を確保できます。また、この時期には自己分析を行い、自分に合った公務員職種を見つけることも大切です。
②大学3年生、院1年生の7月~9月に夏インターンシップ
夏の期間は、インターンシップに参加する絶好の機会です。7月から9月にかけて、多くの自治体や官公庁ではインターンシップを実施しています。
夏インターンに参加することで、公務員の仕事内容や職場環境を実際に体験することができ、自分のキャリアプランについて考える良い機会となります。
③大学3年生、院1年生の3月頃から出願開始
公務員試験の出願は、大学3年生や院1年生の3月頃から始まります。この時期には、受験する自治体や官公庁の選定を行い、出願準備を進めることが重要です。
出願には、履歴書やエントリーシートの提出が必要な場合が多く、事前に準備を整えておくことが求められます。また、出願期間は自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
④大学4年生、院2年生の5月~6月に一次試験
一次試験は通常、大学4年生や院2年生の5月から6月にかけて実施されます。一次試験は、公務員に必要な基礎知識や能力を測るためのもので、多くの場合、筆記試験で行われます。
試験対策としては、過去問の解析や模擬試験の受験が有効です。
⑤大学4年生、院2年生の6月~7月に二次試験
一次試験に合格した後、6月から7月にかけて二次試験が行われます。
二次試験は、面接や論文、集団討論など、より実践的な形式で実施され、コミュニケーション能力や問題解決能力が重視されます。
面接対策としては、自己PRや志望動機の明確化、時事問題への対策などが必要です。
公務員就活と民間就活の2つの違い

公務員就活は民間就活と大きく異なります。民間就活との違いを理解することは、就活を効率的に進める上で非常に重要です。
ここでは、公務員就活と民間就活の2つの違いについて解説します。
- スケジュールの違い
- 対策の違い
①スケジュールの違い
まずスケジュールが違います。公務員就活は、一般的に民間企業の就職活動よりも遅れて始まります。
公務員試験のスケジュールが遅いため、民間企業の就職活動と比較して全体的なスケジュールが後ろ倒しになることが原因です。
このため、公務員就活と民間企業への就活を並行して行う場合は、スケジュール管理が重要になります。
②対策の違い
次に対策も異なります。公務員就活は、民間就活よりも試験の重要度が高いのが特徴です。
また、公務員試験の内容は、民間企業の選考試験より専門性が高く、難易度も高い傾向にあります。そのため、公務員では筆記試験対策が重要になります。
一方、民間企業の就職活動では、面接やグループディスカッションなど、コミュニケーション能力や総合的な人物評価が重視されることが多いのです。
公務員就活で押さえておきたい4つのポイント

公務員になるには入念な準備と対策が必要です。ここでは、公務員就活で押さえておくべき4つのポイントを解説します。
- 自分のやりたい仕事を明確にする
- 筆記試験の勉強を特に重点的に進める
- 面接対策も計画的に進める
- 世の中のニュースにについて関心を持っておく
①自分のやりたい仕事を明確にする
公務員として働くためには、まず自分がどのような仕事をしたいのかを明確にすることが重要です。公務員の職種は多岐にわたります。自分の強みや興味を活かせる分野を見つけることが大切です。
自己分析を行い、自分の適性や興味を深く理解することから始めましょう。また、公務員の仕事内容や職種に関する情報を収集し、自分に合った職種を選ぶことが大切です。
自己分析を徹底することで、自分のキャリアビジョンを明確にし、目指すべき目標を設定できます。
②筆記試験の勉強を特に重点的に進める
公務員試験を突破するには、筆記試験の準備が不可欠です。筆記試験は、公務員試験の中でも特に重要な部分であり、多くの受験生がこの段階で脱落しています。
試験の内容は幅広く、法律、経済、一般常識など多岐にわたるため、計画的かつ効率的な学習方法を見つけることが重要です。
また、過去問題を解くことで試験の傾向と対策を理解し、効果的に学習を進められます。早めに学習計画を立て、コンスタントに勉強を進めることが合格への近道です。
③面接対策も計画的に進める
筆記試験に合格した後は、面接試験が待っています。面接対策も計画的に進めましょう。面接では、自己PRや志望動機、時事問題に関する意見などが問われることが一般的です。
面接官に自分をしっかりとアピールするためには、自己分析を深め、自分の強みや経験を明確に伝えることが重要です。
また、公務員としての適性や社会に対する意識を示すことも求められます。面接対策としては、模擬面接を行う、フィードバックを受けて改善するなど、実践的な練習を重ねることが効果的です。
④世の中のニュースにについて関心を持っておく
社会の動向を理解し、時事問題に精通していることも重要です。面接では時事問題に関する質問がよく出されるため、日頃から新聞やニュースサイトを読み、世の中の出来事に関心を持ちましょう。
また、公務員としての業務においても、社会の変化を理解し、それに応じた対応を取る能力が必要です。
そのため、就職活動中だけでなく、公務員としてのキャリアを通じて、常に社会に関心を持ち続けることが大切です。
公務員就活は戦略的かつ計画的に進めることが重要
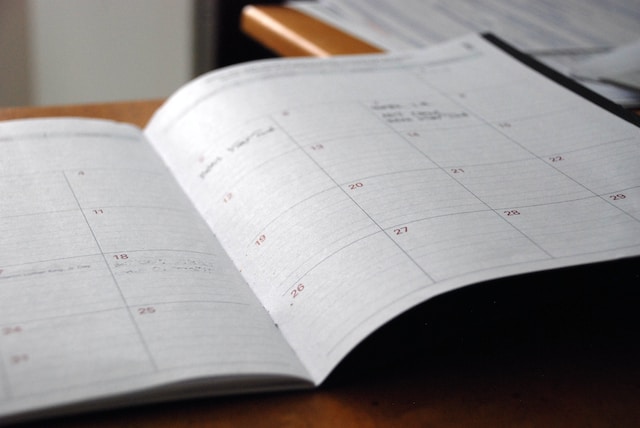
公務員就活の成功には、戦略的かつ計画的なアプローチが不可欠です。公務員試験は、単なる知識の詰め込みではなく、時間管理、情報収集、そして自己分析を要求します。
まず、自分が目指す公務員の種類を明確にし、それに適した勉強計画を立てることが重要です。また、公務員試験のスケジュールは民間企業の就職活動より遅いため、注意が必要です。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









