就活中の記録を残すために、日記をつけている方は少なくありません。「私も日記をつけてみようかな」と思っても、何を書けば良いのかわからない方もいるでしょう。
そこで本記事では、就活日記をつけるメリットや何を書くべきかを解説します。日記を続けるコツを紹介するため、3日坊主になりそうな方は参考にしてください。
就活日記をつける5つのメリット

日記のつけ方によっては、就活に有利に働く可能性があります。就活中に日記を書く主なメリットは以下の5つです。
- 振り返りをする習慣がつく
- 不安や悩みを可視化できる
- 自己分析に役立つ
- 就活中の意思判断に役立つ
- 自分の成長に気づくことができる
①振り返りをする習慣がつく
日記を書くことで振り返りをする習慣がつくメリットがあります。
就活日記には、その日のできごとを「記録」としてつけていきます。特に面接をした日は、聞かれた質問や答えを記録しておくと良いでしょう。
日記を書く過程で自然とその日の振り返りができるため、次回への反省点が見えてくるはずです。
振り返りをせずに就活を進めるよりも、毎回振り返って反省点を見つけたほうが自身の成長につながるでしょう。
②不安や悩みを可視化できる
日記を書くことで就活中の不安や悩みを可視化できます。就活日記にはその日のできごとのみでなく、その時にどう感じたかを書くとよいでしょう。
不安や悩みを感じていても、自分自身で気づけていないケースは少なくありません。「何が起きた時にどう感じたのか」を日記に書くことで、自分自身の深層心理が見えてきます。
また、人にはぶつけられないものでも日記ではぶつけることができるため、感情の整理がつきやすくなる点も大きなメリットです。
③自己分析に役立つ
日記は自己分析にも役立ちます。日記を書くことで、自分の感情や思考を言語化できるからです。
就活においては自己分析が欠かせません。しかし、自分のことを冷静に分析できる方は意外と少ないものです。
日記を書くことで、自分の感情はもちろん、行動パターンも見えてくるでしょう。就活で長所や短所、自己PRを考える際に役立つはずです。
④就活中の意思判断に役立つ
日記は就活中の意思判断に役立つ可能性もあります。複数社から内定をもらい、1社に絞り込まなくてはいけない時に自身が書いた日記が活躍してくれるかもしれません。
日記に会社説明会や面接の際に良いと思った点などを書き出しておくと、1社に絞り込む際の参考になります。
「ここが本命」とはっきりと決まっている企業から内定をもらえた場合、迷う余地もないでしょう。しかし、そうではない場合は迷う可能性があるため日記が役立ちます。
⑤自分の成長に気づくことができる
日記を書くことで、自分の成長に気が付きやすくなります。以前の価値観と比較することができるため、就活をよりスムーズに進められるでしょう。
就活を進める中で、価値観や志望が変化することは決して珍しいことではありません。中には、就活開始時に思い描いていたキャリアプランとまったく違う道を目指す学生もいます。
なぜ自分の価値観が変わったのか、どのタイミングで変わったのかを分析するために日記が役立ちます。
就活日記を書く際の4つのポイント

ただ何となく日記をつけていても、あまり意味がありません。日記を書く際のポイントは以下の4つです。
- 振り返った時に理解できる文章を書く
- その日のことはその日のうちに書く
- 面接で聞かれたことをメモしておく
- その日の出来事+それに対しての感情や考えを書く
①振り返った時に理解できる文章を書く
1つ目のポイントは、振り返った時に理解できる文章を書くです。就活中は忙しく、日記を書く時間を確保しにくい方もいるでしょう。
手書きの場合、忙しさからつい汚い文字になってしまうこともあるでしょう。文章にするのが面倒で、メモのような記録になってしまう方もいるかもしれません。
振り返った時に意味がわかれば問題ありませんが、自分自身でも何を書いてあるのかわからないと困ります。
②その日のことはその日のうちに書く
2つ目のポイントは、その日のことはその日のうちに書くです。その時のリアルな感情やできごとの詳細を残すためには、当日中に書くほうが望ましいでしょう。
就活中は忙しく、「明日思い出して書こう」と思う日もあるはずです。確かに翌日になってから書いても大まかな記録は残せます。
しかし、人間の記憶はだんだん薄れていくものです。翌日になってからでは詳細を思い出せない可能性もあります。
また、一晩経ったことで冷静になり、本音が見えにくい文章になるのもデメリットです。
③面接で聞かれたことをメモしておく
3つ目のポイントは、面接で聞かれたことをメモしておくです。面接で聞かれたことをメモしておくと、今後の就活に活かせるでしょう。
就活の面接で聞かれることは、大体のテンプレートが決まっています。複数社の面接を受けるうちにその業界の質問傾向が分ってくるため、次回の面接に向けて回答の準備ができますよ。
日記を書く際には、質問内容のみでなく自分の回答もメモしておくことが重要です。あとで振り返り、次回の面接ではさらに良い回答ができるように対策できます。
④その日の出来事+それに対しての感情や考えを書く
その日のできごとのみでなく、起こったことに対しての感情や考えを書くことも重要なポイントです。
その日のできごとをただ羅列しても「記録」となってしまい、自己分析にはあまり役立ちません。何かのできごとが起こった際に、自分はその場で何を感じたのかを書いておきましょう。
また、日記を書いている時点では少し冷静になっているはずです。そのできごとを振り返って改めてどう感じているのか、次回はどうしたいのかも書いておくと良いでしょう。
【三日坊主必見】就活日記を継続するための5つのコツ

日記をつけても三日坊主になってしまう方は少なくありません。日記を継続するためのコツは以下の5つです。
- 毎日書くことにこだわりすぎない
- 書く時間を固定する
- 就活の内容に限定しない
- 書くことがない日もとりあえず書いてみる
- 定期的に読み返す
①毎日書くことにこだわりすぎない
1つ目のポイントは、毎日書くことにこだわりすぎないことです。毎日書くことを目標とすると、日記を書くこと自体が苦痛になるかもしれません。
日記は義務ではなく、あくまでも自分のために書くものです。誰かに見せるわけでも評価されるわけでもないため、肩の力を抜いて取り組みましょう。
就活以外のことで忙しかった日や体調が悪い日などは、日記は休んでも問題ありません。
②書く時間を固定する
2つ目のポイントは、書く時間を固定することです。1日の中で日記を書く時間を決めたほうが習慣化しやすいでしょう。
日記は夜寝る前に書くイメージがあるかもしれませんが、1日の終わりにこだわる必要はありません。
「夕食前に書く」「入浴後に書く」など、自分が書きやすいタイミングを決めましょう。日記を毎日のルーティンに組み込むことで継続しやすくなります。
③就活の内容に限定しない
三日坊主が心配な方は、就活の内容に限定せずに好きなことを書きましょう。就活日記だからといって、就活に関する内容しか書いはいけない決まりはありません。
就活の内容のみにこだわると、就活に関するできごとがなかった日に書くことがなくて困ります。無理にネタを探すのは大変ですし、日記を書くこと自体が苦痛になるかもしれません。
就活に関するイベントがなかった日は、大学やアルバイトでのできごとなどを自由に書いてみましょう。
④書くことがない日もとりあえず書いてみる
これといって書くことがない日も、何かしら書いてみることをおすすめします。日記は一言でも書くことで習慣化しやすいためです。
内容は就活に関することではなくても問題ありません。とりあえず一行のみでも良いので、何かしら書いてみましょう。
今日の天気でも、今思っていることでも何でもOKです。1行のみを毎日続けるうちに、「今日は長く書けそう」という日も出てくるでしょう。
⑤定期的に読み返す
日記は書きっぱなしではなく、定期的に読み返すことを徹底しましょう。日記は読み返すことが一番重要だからです。
就活日記は、就活に関するできごとやその時の感情を記録に残すために書きます。日記を読み返すことで、次の面接に活かせることもあるでしょう。
就活のモチベーションアップにもつながるため、ぜひ日記を上手に活用してみてください。
アプリよりも手書きの就活日記がおすすめな理由
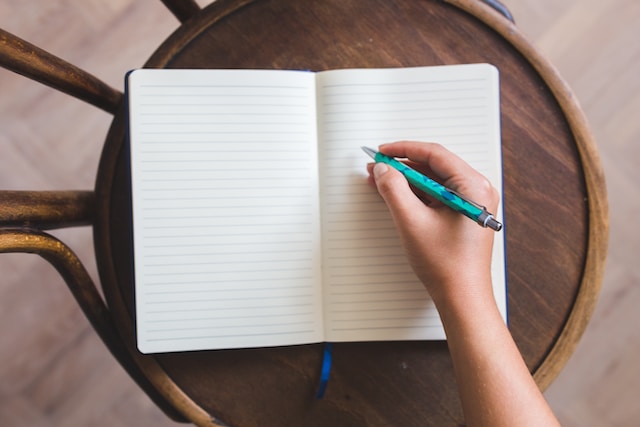
当サイトでは、手書きの日記を推奨します。アプリよりも手書きの日記が良い理由は、手を動かすことが刺激となって記憶に定着しやすくなるためです。
手を動かして日記を書いている間は、脳が刺激され続けます。すばやく入力できるパソコンやスマートフォンと比較すると情報に触れている時間も長いため、記憶に残りやすいといわれていますよ。
また、手書きの日記ならデータが消える心配もありません。自宅に保管しておけば外部に流出するリスクもほぼないため、安全性は高いでしょう。
就活日記はメリットだらけ!明日からでもやってみよう
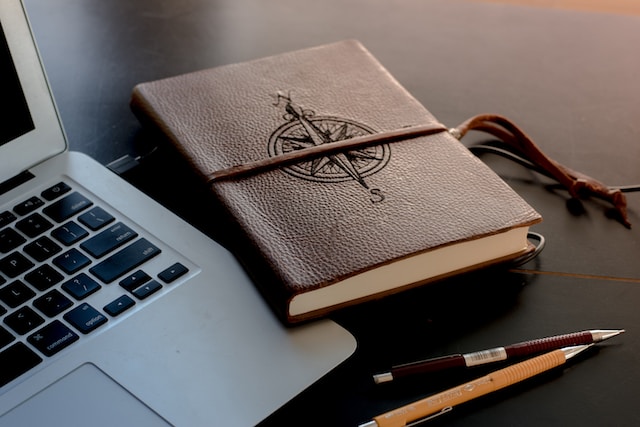
就活中に日記を書くことで、振り返りの習慣がついたり、自己分析ができたりと多くのメリットを得られます。記憶に定着させるために、日記アプリではなく手書きが望ましいでしょう。
日記をつけるのは就活中盤からでも遅くはありません。就活日記を上手に活用し、内定を勝ち取りましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









