就活で作成する履歴書には「研究課題」の記載欄が設けられていて、大学での研究内容を魅力的に記載することで企業への強いアピールとなります。
しかし「何を書けばいいのかわからない。書くことがない場合はどうすればいいの?」と悩みますよね。
そこで本記事では、履歴書における研究課題の書き方をわかりやすく解説します。書くことがない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
履歴書はこれで完璧!お助けツール集
- 1AIで自動作成|作成を丸投げ
- スマホで記入項目をすぐに作成できる
- 2志望動機テンプレシート|簡単作成
- 受かる志望動機が5STEPで完成!
- 3自己PR作成ツール|受かる自己PRに
- 3分で好印象な自己PRが作成できる
履歴書の研究課題に書く内容は「卒業研究」を書くのが基本
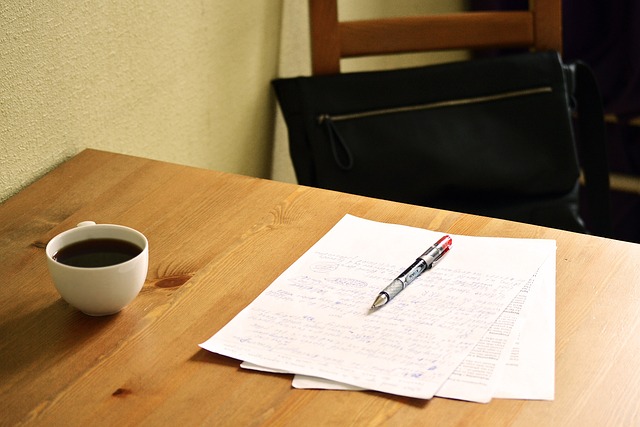
前提として、履歴書の研究課題には「卒業研究」を書くことが基本です。その理由や方法について、詳しく解説します。
- 卒業論文・修士論文について
- ゼミ・研究室で学んでいるテーマ
①卒業論文・修士論文について
履歴書の研究課題には、卒業論文や修士論文について書くとよいでしょう。なぜなら、卒業論文・修士論文はほとんどの人にとって学生時代もっとも力を入れた研究だからです。
そのため、研究の内容を詳細に説明でき、そこからの学びも効果的にアピールできる可能性が高くなります。
もちろん、それら以外に力を入れた研究があればそちらを記載するべきですが、基本的には卒業論文・修士論文の内容がおすすめです。
②ゼミ・研究室で学んでいるテーマ
ゼミや研究室で学んでいるテーマの記載もおすすめです。もし卒論の内容が未定であったり、研究をしない場合は、ゼミの課題や専攻で力を入れた科目について書くとよいでしょう。
ゼミや研究室の活動や課題へ積極的に参加したことや、学び取った知識やスキルの習得について具体的に触れると、志望動機がより具体的になります。
また、専攻で力を入れた科目や興味を持っている分野に焦点を当て、その分野におけるあなたの成長や将来の展望について熱意を込めて表現すると、面接官に強い印象を与えられます。
【ケース別】研究課題が書けない時の対処法3選

みなさんの中には、研究課題が書けないと悩む人もいるでしょう。ここでは、その対処法をケース別に紹介します。
- 研究課題が未定の場合
- ゼミに入っていない場合
- 研究内容が明確に設定されていない場合
①研究課題が未定の場合
研究課題が未定の場合は、まずは研究したいテーマを具体的に記述します。自分の興味や関心がある分野や未解決の問題に焦点を当て、それに対する疑問や仮説を述べましょう。
同時に、これからの研究での展開をアピールします。研究方針や動機を端的に伝えることで、課題が未定でも前向きな姿勢を表現できます。
②ゼミに入っていない場合
ゼミに入っていない場合は、興味のある講義に焦点を当てましょう。
自分が選んだ講義や授業から得た知識やインスピレーションについて書き、それが研究テーマにどのように関連しているかを考察します。
また、ゼミに入らなかったポジティブな理由も明記します。たとえば、「他の専門分野で学びを深めたい」や「資格取得に専念したかった」などが挙げられます。
③研究内容が明確に設定されていない場合
内容が不透明な場合は、あなたが過去に取り組んだ研究や経験から興味を持ったテーマを挙げましょう。それに基づいて、関連する文献や先行研究を調査し、新たな研究の可能性を見つけます。
過去の経験や興味がもたらすヒントは、新たなアプローチや独自の視点を見つける手助けとなります。このプロセスで研究内容が明確になり、研究課題の構築に繋がるのです。
履歴書の研究課題で書くべき4つの内容

次に、履歴書に書くべき内容をわかりやすく紹介します。
- どのような研究に取り組んだか
- 研究の結果・わかったこと
- 研究を通して学んだこと
- 学んだことを仕事にどう活かすか
①どのような研究に取り組んだか
まず、どのような研究に取り組んだかを記載します。なぜなら、専門性や問題解決能力をアピールできるからです。
取り組んだ研究を記述する際は、その研究が自己成長や専門知識の向上に繋がり、企業の課題解決に貢献できることを強調します。
研究のポイントは具体的な課題や目的、使用した手法・ツール、結果や得られた洞察を明確かつ要約して提示することです。専門用語を避けつつ、わかりやすく伝えましょう。
②研究の結果・わかったこと
専門知識や問題解決能力をアピールし、企業にあなたの価値を伝えるために、研究の結果・わかったことを書きます。
ポイントは、結果を具体的かつ明確に表現し、それがどのように課題解決に貢献したかを強調することです。難しい内容でも読みやすく伝え、自らの成果を引き立てる工夫が求められます。
③研究を通して学んだこと
次に、研究を通して学んだことを強調します。これは、専門的なスキルや知識をアピールし、自己成長を訴える重要な手段です。
たとえば、研究を通じて問題解決能力や分析力を向上させ、協力やコミュニケーションの重要性も理解し他ことを伝えることが有効です。
このように、研究内容とセットで学びを伝えることで、学びや仕事にも積極的に取り組めることをアピールできます。
④学んだことを仕事にどう活かすか
最後に、学んだことを仕事にどう活かすかを記載します。これは、履歴書で自己アピールを強化する重要なポイントです。
学びを仕事に結びつけることで、新しい視点や解決能力を提供し、職務遂行において独自の付加価値を生むことが期待されます。
履歴書では、学んだスキルや知識を実務でどう活かし、組織や仕事にどのような貢献ができるかを具体的かつ魅力的に伝えることが重要です。
研究課題を面接官に上手にアピールする3つのコツ

研究課題について丁寧に書いても、それが面接官にアピールできなければ、評価は下がるでしょう。そこで、ここでは面接官に上手にアピールするコツを紹介します。
- 誰にでもわかる表現を使う
- 専門的な用語を使わない
- 自己PRを盛り込む
①誰にでもわかる表現を使う
研究課題をアピールする際、誰にでもわかる表現を使うことが重要です。なぜなら、わかりやすい表現を使うことで、研究内容が理解されやすくなるからです。
専門的な用語や複雑な概念をできるだけ避け、身近な例や具体的な事例を交えることで、相手にとっても興味深く感じやすくなります。
研究の意義や目的を端的に伝え、その成果がどのように社会や学問に活かせるかを分かりやすく説明することも重要です。
②専門的な用語を使わない
研究課題をアピールする際、専門的な用語は避けましょう。面接官は専門知識を持っていない可能性があり、難解な言葉は伝わりにくくなります。
面接官は専門知識がなくても理解できるように、専門用語をできるだけ避け、具体的かつイメージしやすい言葉を選びましょう。
「自分にとっては知っていて当然の言葉でも、世間一般では使われていない用語だった。」ということも考えられるため、表現には気を付けて下さいね。
③自己PRを盛り込む
最後に、自己PRも盛り込みましょう。なぜなら、独自性をアピールする絶好の機会だからです。
企業は、あなたの研究課題そのものよりも、そこから何を学び取り、今後どう活かすかを知りたいと考えています。
自己PRとしては、あなたの研究が将来的な社会貢献や業績にどう繋がるかもアピールが重要です。誠実で自信を持って話すことで、研究への理解を深め、印象を強化できます。
【パターン別】研究課題の例文4選

次に、研究課題の例文を4種類紹介します。
- 文系の場合
- 理系の場合
- 卒業研究が決まっていない場合
- ゼミに所属していない場合
①文系の場合
| 私は大学時代の課題研究として、「言語の表現力と社会的影響に関する研究」に取り組みました。具体的には、特定の社会的出来事が言語表現に及ぼす影響の調査です。 その結果、メディアの報道が言語の選択や表現に与える影響が明らかになりました。特に、社会的な議論が活発な時期において、言語は感情や意見の形成に大きく関与していることが示されました。 この研究を通じて、言語は単なるコミュニケーション手段に留まらず、社会的な文脈において強力な影響を持つことを理解しました。また、言葉が与える影響を分析するスキルも磨けたと感じています。 今後は、この研究で得た知見を活かし、コミュニケーションや広報の仕事において、適切な言語選択が与える影響を予測し、効果的なコミュニケーション戦略を構築していきたいと考えています。 |
この例文では、文系学問での研究経験を紹介しています。特に社会的出来事が言語表現に与える影響を報告し、メディア報道が言語に及ぼす影響を強調していることがポイントです。
②理系の場合
| 私は大学時代の課題研究として、「新素材の開発とその物性評価に関する研究」に取り組みました。具体的には、特定の材料の組成変更が物性に及ぼす影響に焦点を当て、実験を通じてその特性を解明しました。 その結果、材料の微細な変化が、強度や伝導性などの物理的特性に与える影響が判明しました。具体的には、新たな合金組成の発見や製造プロセスの最適化により、予想外の物性向上が確認されました。 この研究を通して、素材の微細な変化が持つ重要性に気づき、材料工学や物性評価の基本的な理解を深めることができました。また、実験やデータ解析のスキルを向上させました。 今後は、この研究で得た知見をもとに、新しい素材の開発や既存素材の改良に貢献したいと考えています。 |
この例文は、理系の学問における研究実績を示すものです。新素材の開発と物性評価に焦点を当てた研究内容が具体的に紹介されています。
③卒業研究が決まっていない場合
| 現在、私は卒業研究のテーマが未定ですが、、新たな研究領域に挑戦したいと考えています。具体的には、素材工学や物性評価、あるいはデータ科学領域などの研究に興味があります。 これまでの学びを踏まえ、研究の幅を広げつつも、未知の領域に挑戦することで新しい発見を目指したいです。具体的なテーマは模索中であり、適切な課題に出会えるよう情報収集や先行研究の理解に努めています。 未定の研究テーマに対する興味と好奇心から、新たな知識や手法を習得する過程で成長したいです。柔軟性と創造性を活かし、問題解決能力を向上させる経験を積む予定です。 卒業研究を通して得たスキルと知見を将来の研究や産業応用に生かし、社会に新たな価値を提供できるよう努めたいと考えています。 |
この文章は、卒業研究が決まっていない場合の例文です。このように、学問への興味と探求心を強調しつつ、未定の卒業研究テーマに対する意欲や方針を述べるとよいでしょう。
④ゼミに所属していない場合
| 私は、大学でゼミに所属していませんでした。代わりに、専門的な知識を身につけるため、興味を持っていた「材料力学」や「実験工学」などの講義に重点的に参加しました。 また、ゼミ外での活動として、インターンシップの経験が豊富です。学んだ理論的な知識を実践に結びつけ、講義で学んだ材料工学や実験手法がどのように現場で活かされているかを見聞きしました。 特に、「実践と理論の連携」に焦点を当て、講義の内容を実際のプロジェクトにどう応用できるかを模索しました。 これらの経験を通じて、実践的な経験を通して学んだことを講義の枠を超えて有機的に結びつけ、より実践的な専門知識を身につけることができました。 将来的には、この経験や学びを活かし、新しい分野での研究やプロジェクトに貢献したいと考えています。 |
例文のように、ゼミに所属していない場合は、興味のある講義や力を入れて受けた講義について述べることが重要です。また、ゼミ以外で取り組んだ内容(インターンなど)を講義に関連づけてみましょう。
履歴書の研究課題に関する2つの注意点

最後に、履歴書の研究課題に関する注意点を紹介します。
- 空欄や「なし」はNG
- 研究内容と志望業界は関係なくてもOK
①空欄や「なし」はNG
履歴書の研究課題欄は、空欄や「なし」と記載することを避けましょう。
先ほど紹介した通り、研究課題やそこから学んだことをアピールすることは、選考において重要です。そのため、何も書かないことはアピールする機会を自ら逃していることを意味します。
そのため、仮に研究の経験が不足していても、具体的なプロジェクトや課題、取り組んだ内容、学び得たスキルなどを記載しましょう。
②研究内容と志望業界は関係なくてもOK
履歴書の研究課題では、研究内容と志望業界が一致しなくても構いません。なぜなら、異なる分野で培ったスキルや知見が新たな視点をもたらし、他業界に価値を提供できる可能性があるからです。
たとえば、生態学の研究がきっかけで環境問題に対する独自の視点を得たとします。これらの知見は、エネルギー業界での研究職に応募する際に生かされる可能性があるのです。
「関係ないからアピール材料にならない」と諦めず、積極的にアピールすることを心がけましょう。
履歴書の研究課題の欄は自己PRに有効活用しよう!
本記事では、履歴書における研究課題の書き方を解説しました。
履歴書の研究課題は、基本的に卒業論文や修士論文について書きましょう。その際、研究したことだけを伝えるのではなく、そこから何を学び、今後どう活かすかを伝えることが重要です。
もしゼミに所属していない場合は、興味を持った講義について記載するなど、記載欄を空欄にしないようにしましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









