ケーススタディとは、コンサルなどの選考などで用いられやすい手法です。しかし、どんな問題が出題され、どう対応すればよいのかがわからず、困ってしまう方もいるでしょう。
本記事では、ケーススタディ面接の概要・面接の流れ・評価されるポイント・対策法について解説します。
出題されやすい問題の具体例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
【コンサルティングファーム頻出】ケーススタディ面接とは?

ケーススタディ面接とは、状況を分析して解決策を考え、問題のバックグラウンドにあるルールなどを探る手法を取り入れた面接形式です。
主に論理的な課題解決力が問われ、問題の形式を理解しておき、与えられた課題に適したアプローチを取る必要があります。
コンサルティングの場面で向き合う課題を、自身の知識だけでなく推定も用いながら論理的思考によって解決する力を問うために取り入れられているのが特徴です。
ケーススタディ面接の流れ

ケーススタディ面接の流れは、以下の4段階に分類可能です。
- 課題提示
- 回答作成(15分)
- 回答をプレゼン(5分)
- ディスカッション(10分)
合計30分ほどで終わるため、時間配分を適切にすることを意識しましょう。しかし、課題の説明とディスカッション部分の時間は自身では節約できません。
回答作成時間に多めの時間を割いて、プレゼンをスムーズに済ませられるように準備することがおすすめです。
ケーススタディ面接で評価される3つのポイント

ケーススタディ面接で評価されるポイントを把握していれば、好印象を与える答え方を心がけやすくなります。高評価をもらうためのポイントは、以下の3つです。
- 論理的思考力
- ロジカルコミュニケーション
- プレッシャー耐性
①論理的思考力
面接では、課題に対して論理的思考力を発揮し、適した解決策を提示できるかどうかが重視されます。
最適な提案をプレゼンするには、課題を解決するスキルや分析力も問われるのが特徴です。
ケーススタディ形式の問題を事前に練習しておき、テーマ別の対処法を身につけておけば、論理的にも正しいアプローチで面接を進められます。
課題の背景を把握して、時間内に解決案を順序だてて説明できるように準備をしておきましょう。
②ロジカルコミュニケーション
ロジカルコミュニケーションが上手にできているかどうかも、評価のポイントになります。
考えをまとめる際に論理的な筋道をもとにしているかや、話し方がわかりやすいかどうかが見られるのが特徴です。
提案内容が正しかったとしても、伝え方がわかりづらい場合は評価が下がってしまうため注意しなければいけません。
難しい言葉は簡単な表現に変更したり、結論を最初に話す構成に変更したりなど、工夫が必要です。
③プレッシャー耐性
採用者は、プレッシャー耐性がどれほどあるかを見て、候補者を評価する場合もあります。
実際の業務でも冷静さを保ち、期限までに適した提案を生み出して、顧客にわかりやすく説明するスキルが必要になるためです。
与えられた時間の中で適切な回答を導き出すのはプレッシャーがかかりますが、コンサルティング業務などでも責任感のある仕事を遂行しなければいけません。
冷静な判断力を発揮して、仕事への適性があることを強調しましょう。
ケーススタディ面接の対策方法3選

特殊な形式の面接が実施される場合は、専用の対策をしておく必要があります。おすすめの対策法は、以下の3つです。
- 多くの問題に触れる
- 対策に活かせる本を読む
- 問題で出会ったテーマについて詳しく調べる
①多くの問題に触れる
実際に出題されたテーマの具体例の多くに触れておくことで、問題の傾向や対処法を掴みやすくなります。
企業の面接で過去に出題された問題がわかっている場合は、チェックしておくと本番での緊張を和らげやすくなるでしょう。
書店によっては問題集も販売されているため、事前に目を通して問題を解いておき、解き方も頭に入れてください。
実際に紙とペンを用いて情報を整理しながら解けば、本番の面接でも実践しやすくなります。
②対策に活かせる本を読む
対策に活かせる本を読んでおけば、高評価を受けるために必要な対応を取りやすくなります。
具体的には、フェルミ推定系の問題集や、論理的思考法のコツについて書かれた本を読むと面接に活かせますよ。
面接のテーマによっては明確な指標がないものを概算して提案の説得力を高める必要もあるため、フェルミ推定のやり方や流れ、問題例などをチェックしておきましょう。
一夜漬けで対策をするのではなく、毎日コツコツと知識を蓄え、練習することが重要です。
③問題で出会ったテーマについて詳しく調べる
問題集を見て、取り上げられているテーマについて知識を深めておくことも大切です。
ケーススタディの課題では、日本や世界の人口・カーボンニュートラル・業界で取り扱う製品などが取り上げられます。
企業研究を進めながら、企業が将来的に意識している課題などにも目を向けて、知識が不足している分野があれば適宜調べるようにしましょう。
企業で進行しているプロジェクト内容などを調べておくと、課題のヒントが見つかる場合もあります。
ケーススタディ面接の代表的な5つのパターン

面接で出やすいパターンを把握していれば、解き方の流れを確認しつつ対策しやすくなります。よく出題される問題のパターンは、以下の5つです。
- 「売上」を増加させる施策を考えるケース
- 「利益」を増加させる施策を考えるケース
- 「二者択一」をさせるケース
- 「公共の問題」を解決させるケース
- 「新規事業」を考案するケース
①「売上」を増加させる施策を考えるケース
売上増加のための施策を考えることが求められるケースでは、該当店舗の立地や客層、営業時間などの条件を推定して売上にアプローチする必要があります。
クリーニングなど生活に根差したサービスの場合は、店舗周辺の住民数と来店頻度をもとに考えましょう。
カフェなどのさまざまな人が利用する店舗では時間帯ごとの来客数と売上を構成するサービスの割合を基準に考えるのがおすすめです。
顧客の視点に立って考えると、実用的な施策が思い浮かべやすくなります。
②「利益」を増加させる施策を考えるケース
利益増加のための施策を考えるケースでは売上を計算した上で、費用を推定して差し引くことで、現状のおおよその利益を計算する必要があります。
提供している商品やサービスの原価が売上の何割か、店舗の維持費や人件費は売上の何%かを考えて、利益が売上の何%になるのかを概算しましょう。
課題の内容によっては、売上を向上させる施策だけでなく、売上のうち多くを占めている費用を抑えるアイディアなども考えることが求められるのがポイントです。
③「二者択一」をさせるケース

二者択一の問題形式では、問題文の中で2つの選択肢が提示されているのが特徴で、それぞれの強みと弱みをリストアップして考えることが求められます。
他のケースと比べて問題文がシンプルな分、前提条件を丁寧に確認して、認識の相違が出ないように注意しましょう。
テーマに挙げられている事柄に対して賛成する場合と、反対する場合に考えられる利益とリスクを紙に書き、論理的に考えていることをアピールするのも重要です。
④「公共の問題」を解決させるケース
公共の問題の解決策を考えさせるケースでは、満員電車などの社会的な問題が出題されます。
普段の生活の中から社会問題を見つけ、対処法を考える習慣をつけておくと、実体験に基づいた論理展開をしやすくなるのが特徴です。
満員電車の場合は、利用者数や通勤者と通学者の割合、混雑率などを推定して考えると、混雑率を低下させるための施策に結びつけやすくなります。
運行本数を増やすなどの施策でどのように混雑率が低下するか、筋道立てて説明することかが大切です。
⑤「新規事業」を考案するケース
新規事業の立案と理由の説明が求められるケースでは、まず実現したい目標を設定してから商品やサービスを用いたアプローチ方法を考える必要があります。
具体的な計画を検討する際には、製品・販売促進方法・価格・流通手段の4つの観点から考えると、説得力のある回答を作成しやすくなるのがポイントです。
ターゲットとなる業界で現在展開されている事業内容を把握しておくと、競合になる事業を参考にして、対策を練られます。
ケーススタディ面接での思考の流れ3ステップ
ケーススタディ面接では、論理的な思考プロセスを踏むことが重要です。
ここでは、ケーススタディ面接を成功に導くための3つの重要なステップを見ていきましょう。
- 前提・与件の整理
- 現状分析・課題特定
- 戦略策定
①前提・与件の整理
前提・与件の整理は、ケース面接の最初のステップとして極めて重要です。
このフェーズでは、与えられた問題の語句の定義、想定クライアント、目標を明確にします。
例えば、「売上を2倍にせよ」という課題の場合、売上の定義や、対象期間、対象エリアなどの条件を確認する必要があるでしょう。
また、店舗の立地や客層、営業時間などの基本情報も整理してください。
②現状分析・課題特定
「現状分析」では、問題の全体像を把握し、課題の構造を明確にすることが重要です。
市場環境、競合状況、顧客ニーズ、内部リソースなどの観点から、現状を多角的に分析していきます。
また、問題の構造を明確にするために、フレームワークを活用することも効果的。ただし、フレームワークに固執しすぎず、状況に応じて柔軟に思考を展開することが大切です。
課題特定では、解決策立案につながる重要な洞察を得ることを意識し、論理的な思考プロセスを展開していきましょう。
③戦略策定
戦略策定は、課題解決のための具体的なアプローチを組み立てる最後の重要なステップです。
例えば、売上拡大のケースでは、顧客層や立地条件を考慮した上で、価格戦略や商品展開の見直しなど、実行可能な施策を提案します。
戦略の優先順位付けも重要で、実現可能性、投資対効果、実施時期などの観点から総合的に判断します。
ケーススタディ面接でよくある2つのミス
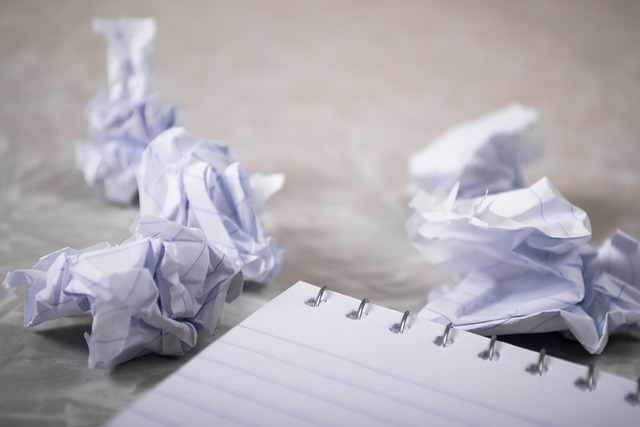
ケーススタディ面接で発生しやすいミスをチェックしていれば、面接で失敗しないように対策が可能です。気を付けるべきミスには、以下の2つがあります。
- 練習で得た知識にこだわってしまうケース
- 一部の情報だけに言及してしまう
①練習で得た知識にこだわってしまうケース
実際の面接では、練習や本で得た知識にこだわりすぎないように注意が必要です。
学習した思考法を参考にして、適切なアプローチに役立てることは大切ですが、覚えた知識に固執してしまうと、柔軟な思考の妨げになります。
課題の内容によって、概算方法を適宜変更できるようにするには、さまざまなジャンルの問題を解く練習をしておくことが重要です。
②一部の情報だけに言及してしまう
問題文で提示されている内容のうち、一部の情報だけに焦点をあてて言及しないよう注意する必要もあります。
理解が難しい情報の分析に時間がかかるからとスルーしてしまうと、回答に粗が目立ちやすくなるのが懸念点です。
ディスカッションで質問された時にスムーズに回答できなくなるため、気を付けなければいけません。
問題文に書かれている情報は、まんべんなく分析を行うことを意識して、盲点がない回答を目指しましょう。
ケーススタディ面接で使えるフレームワーク4選
ケーススタディ面接を成功させるためには、効果的なフレームワークの活用が欠かせません。
本章では、コンサルタントに求められる分析力を高め、さまざまな問題を迅速に捉えるための4つの信頼できるフレームワークを厳選して紹介します。
- 3C分析
- 4P分析
- ファイブフォース分析
- SWOT分析
①3C分析
3C分析は、Customer(顧客・市場)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素を分析することで、事業環境を体系的に理解するためのフレームワークです。
ケース面接では、与えられた課題に対して論理的な解決策を導き出す必要がありますが、3C分析を活用することで、市場における自社の競争力を高めるための成功要因を特定しやすくなります。
具体的には、まず市場・顧客のニーズや規模を分析し、次に競合他社の状況を把握します。そして自社の強みと弱みを明確にすることで、差別化戦略を立案することができるでしょう。
このフレームワークは特に売上増加や利益拡大のケースで有効で、ビジネスの方向性を明確化する際に役立ちます。
②4P分析
4P分析は、マーケティング戦略を立案する際に活用される代表的なフレームワークです。
Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促活動)の4つの要素から分析を行います。
例えば、「コンビニエンスストアの売上を上げる施策を考えよ」というケースでは、以下のように分析できます。
- Product:品揃えの見直しや、PB商品の開発
- Price:時間帯による価格変動の導入
- Place:立地条件の最適化や、デリバリーサービスの展開
- Promotion:SNS活用やポイント施策の強化
ケーススタディ面接では、この4つの要素を漏れなく検討することで、論理的な解答を組み立てることが可能になるでしょう。
③ファイブフォース分析
ファイブフォース分析は、業界の競争状態と収益性を分析する際に活用できる強力なフレームワークです。
マイケル・ポーターが提唱したこの手法では、「業界内の競合の脅威」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」という5つの要因から業界構造を体系的に分析します。
たとえば、新規事業への参入を検討するケース問題では、これら5つの視点から市場の魅力度を評価できるでしょう。
各要因の力関係が弱ければその業界の収益性は高く、強ければ収益性は低いと判断することができます。
④SWOT分析
SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を体系的に分析できる強力なフレームワークです。
Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素から、与えられた課題を多角的に分析でき、特に売上拡大や新規事業立案のケースで活用できます。
例えば、ある企業の売上拡大策を考える際、その企業の強みである技術力や顧客ネットワークを活かしつつ、弱みを克服する具体的な施策を導き出せます。
また、市場機会や競合からの脅威を整理することで、より説得力のある解決策を提示することが可能でしょう。
ケーススタディ面接を対策して他の志願者に差をつけよう!
ケーススタディ面接を対策して、他の志願者と差をつけましょう。
ケーススタディ面接では、売上や利益に関する施策や社会問題、新規事業に関する施策について考えることが求められます。
事前に問題集やフェルミ推定についての本を活用して練習し、本番に備えましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









