公務員の事務職を志望している就活生はたくさんいると思います。しかし、事務職の具体的な仕事内容や、採用試験の内容についてはあまりよく知らない人もいるのではないでしょうか。
本記事では、公務員事務職の仕事内容や試験内容について解説します。事務職のメリットや向いている人の特徴も解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員の事務職について紹介!

公務員事務職は、主に一般行政事務、学校事務、警察事務の3つの業務に分けられます。さらに、地方公務員と国家公務員で採用区分や職種が異なり、事務職といっても様々な職種が存在しているのです。
例えば、地方公務員の事務職は都道府県などの地方自治体に勤務をし、地域住民のための行政サービスの他に、国公立大学や警察署での事務作業などを行っています。
国家公務員の事務職は、国家公務員一般職や裁判所事務官、衆議院事務局一般職などが存在し、特定の分野の専門知識を用いて業務を行う職種です。
事務職の3つの種類と仕事内容
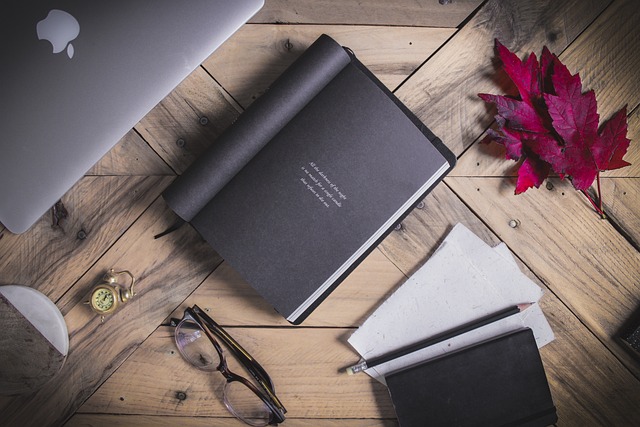
公務員の事務職にはさまざまな種類が存在します。ここでは、公務員事務職の中でも主要な3つの種類とその仕事内容について解説します。
- 行政事務
- 学校事務
- 警察事務
①行政事務
行政事務は、都道府県や市町村などの地方自治体での業務を担当する公務員です。行政事務の主な業務は、地域住民への行政サービスの提供や税金の徴収、財務・経理・庶務など多岐にわたります。
近年では、観光立国としての政策推進や国際交流、福祉サービスの充実、防災対策、環境保全、文化やスポーツの推進など、地域の特性やニーズに応じた業務も増えてきました。
行政事務の特徴として、様々な業務を経験できる分、人事異動が多いことが挙げられます。しかし、その範囲は主に自治体内に限られるため、大きな地域移動はほとんどありません。
②学校事務
学校事務は、国立や公立の学校での業務を担当する公務員です。学校事務は教師とは異なる職種で、学校の運営をサポートする役割を果たします。
主な業務は、電話・来客対応、教職員のサポート、総務・人事・経理関係の業務、備品管理、学校行事の準備、生徒や保護者との対応などです。
特に、総務・人事・経理関係の業務は学校事務の中心となる業務で、経費精算や給与計算、事務用品の管理などを担当します。
学校事務の特徴として、業務をこなす中で保護者や生徒とのコミュニケーションが求められることが挙げられます。
③警察事務
警察事務は、警察署やその関連組織での業務を担当する公務員です。警察事務は警察官とは異なり、犯罪捜査や交通指導などの現場業務は行いません。
主な業務は、遺失・拾得物の管理、免許更新、道路使用許可の窓口業務、警察職員の給与・勤務管理、情報セキュリティの管理、経費精算などです。
また、犯罪統計の作成や鑑識課での資料鑑定など、警察組織特有の業務も担当します。
警察事務の特徴として、警察官とは異なり、身体基準や体力測定などの採用基準が緩やかであり、武器の使用や現場業務に関与しない点が挙げられます。
公務員事務職のメリット3つ

公務員の事務職の、福利厚生がや安定性の理由から人気がある職種です。ここでは、公務員事務職の主なメリットを3つ紹介します。
- 休日・休暇制度が充実している
- 収入が安定している
- 長く働くことができる
①休日・休暇制度が充実している
公務員の事務職の最大のメリットは、労働環境が整っていることです。特に、休日や休暇制度が充実している点は、多くの人々にとって大きな魅力となっています。
安定した待遇のもと、デスクワークを中心に業務を進める中で、休みも取得しやすい環境は、長期的に働く上で非常にありがたい条件と言えるでしょう。
②収入が安定している
安定した収入が得られる点も大きなメリットです。ほぼ確実に昇給するシステムがあり、経済的な安定感を得られます。
また、公務員としての地位は、一定の社会的信用も伴うため、生活の質を維持しながら働くことが可能です。安定した収入は、将来的なライフプランを立てる上でも大きなメリットとなります。
③長く働くことができる
公務員の事務職は、長期的に働ける環境が整っています。特に、育児休暇や各種の制度が充実しており、人生の様々なフェーズに合わせて働き方を変えられます。
例えば、家庭を持った後も、職場復帰の際のポストが用意されているため、キャリアを途切れることなく続けられるのです。
柔軟な働き方が可能な環境は、多くの人々にとって大きな魅力となっています。
公務員事務職に向いている人の3つの特徴

公務員事務職は、多岐にわたる業務を担当し、日々の行政サービスの提供を支える重要な役割を果たしています。ここでは、公務員事務職に向いている人の特徴を3つ紹介します。
- 様々な分野の仕事に携わりたい人
- 人とのコミュニケーションが得意な人
- 仕事のやりがいを大事にしたい人
①様々な分野の仕事に携わりたい人
公務員事務職は、様々な業務を担当します。そのため、1つのことを極めるのではなく、多種多様なの業務に携わりたい人が向いています。
例えば、一般行政事務では、税金の徴収、財務・経理、庶務、観光推進、国際交流、福祉サービスの充実、防災対策、環境保全、文化やスポーツの推進など、幅広い分野の事業に携わります。
様々な業務の経験から広く知識やスキルを身につけられるので、多様な業務にチャレンジしたいと考える人にとって、公務員事務職は非常に魅力的な職種と言えるでしょう。
②人とのコミュニケーションが得意な人
公務員事務職は、窓口業務や外部との調整、部署間の連携など人と話す機会が多く、コミュニケーション能力が高い人に向いています。
特に学校事務では、総務・人事・経理関係の業務や学校行事の準備、生徒や保護者との対応など、高いコミュニケーション能力が求められます。
また、時にはクレーム対応も求められることがありますが、そのような状況でも冷静に対応できる人が向いています。
コミュニケーションを通じて地域住民や関係者との信頼関係を築く力が、公務員事務職をしていく上でとても重要です。
③仕事のやりがいを大事にしたい人
公務員事務職での業務を通じて、住民の役に立ったと感じる瞬間が多くあります。そのため、仕事のやりがいを重視している人は向いていると言えるでしょう。
例えば、行政サービスの提供や公共サービスの向上など、日々の業務を通じて地域社会に貢献できます。やりがいを感じられるのは、公務員事務職の大きな特徴の1つです。
やりがいを感じることで、仕事のモチベーションも高まり、日々の業務に取り組む姿勢も向上します。
地方公務員試験の種類を2つにわけて説明!
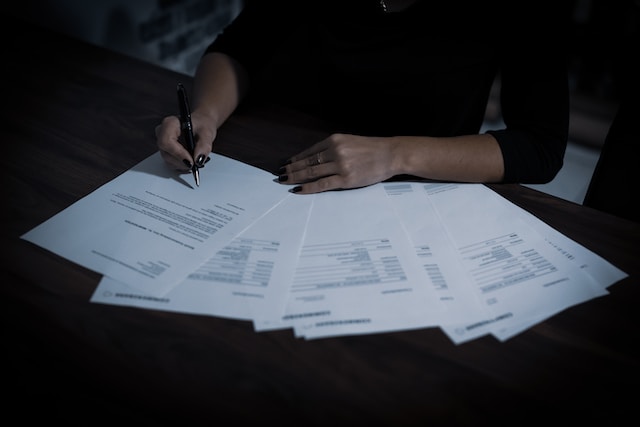
地方公務員試験にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を理解することで、より効果的な対策が可能です。ここでは、地方上級と地方中級・初級に分けて、特徴を解説します。
- 地方上級の試験内容
- 地方中級・初級
①地方上級の試験内容
地方上級の公務員は、学力レベルとして大学卒業を前提としています。このため、試験内容も大学卒業レベルに合わせられており、難易度は高めです。
具体的には、法律や政治学、経済学などの専門的な知識を問う専門科目と、一般的な教養を問う教養科目の2つが主な出題範囲となります。
専門科目は暗記中心での対応が求められることが多く、合格者の平均得点率は80%程度です。地方上級の公務員試験は、高度な知識とスキルが求められる試験となっています。
②地方中級・初級の試験内容
地方中級の公務員試験は、短大卒業レベルを前提としています。しかし、試験の難易度は大卒レベルとほぼ変わらない内容が出題されるため、受験者にとっては厳しい戦いとなることが多いのです。
一方、地方初級の公務員試験は、高校卒業レベルを前提としています。しかし、高校卒業レベルとはいえ、難易度は決して低くなく、しっかりとした準備が必要です。
特に、地方初級の試験は専門科目がなく、教養科目のみでの受験となるため、幅広い知識が求められます。
国家公務員試験の種類を3つに分けて説明!
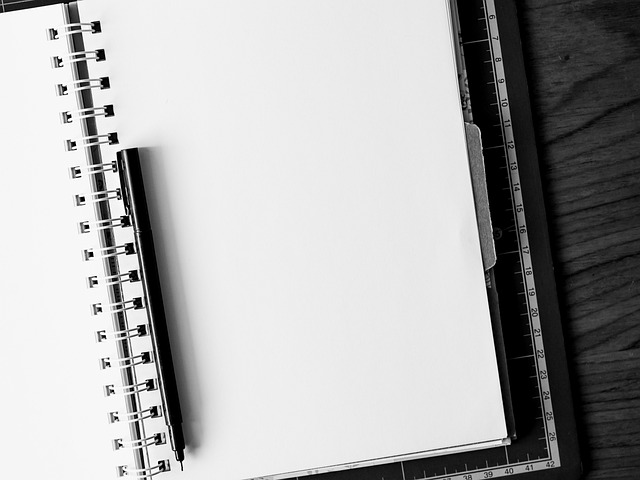
国家公務員試験にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴や内容を知ることで、より効果的な対策ができます。国家公務員試験の種類を3つに分けて解説します。
- 総合職の試験内容
- 一般職の試験内容
- 宮内庁訪問
総合職の試験内容
総合職は、国家公務員の中でも最も高い職階を目指す方々が受験する試験です。総合職の試験は、幅広い知識と高度な判断力が求められるため、難易度が高いとされています。
具体的には、専門職としての能力を試す「専門試験」や、一般的な教養を問う「一般試験」が実施されます。
また、面接やグループディスカッションなど、実際の業務に近い形式での評価も行われることがあるため、総合職を目指す方は、多岐にわたる知識とスキルの習得が必要です。
一般職の試験内容
一般職は、総合職に比べて専門的な知識を持つ職種です。試験内容は、応募する職種によって異なりますが、基本的には筆記試験と面接試験の2段階で実施されます。
筆記試験では、専門知識を問う問題や、中学高校レベルの基礎的な算数・数学、国語の問題が出題されることが多いです。
面接試験では、応募者の適性やモチベーションが評価されるため、自分の強みや経験をアピールすることが大切です。
宮内庁訪問
宮内庁は、天皇陛下や皇族の公務をサポートするための組織です。国家公務員試験の一環として、宮内庁を訪問することがあります。
宮内庁訪問は、宮内庁の業務内容や役割を深く理解するためのもので、受験者にとっては貴重な経験となるでしょう。
宮内庁の職員や関係者からの説明を受けることで、実際の業務の様子や、公務員としての役割についての理解を深められます。
試験対策をして公務員事務職を目指そう!

公務員事務職になるには公務員試験に合格する必要があります。公務員試験は難易度が高く、競争率も高いため、十分な対策が必要です。
特に上級の試験は、高度な内容が問われるため、独学だけでは難しいことも。また、筆記試験だけでなく、面接や論文試験にも対策が必要です。
予備校や通信講座を積極的に利用して、効率的に対策しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









