公務員試験を受けようと考えている就活生は多くいますよね。しかし、公務員試験で提出しなければいけない面接カードの書き方が分からなくて悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、面接カードの入手・提出方法と、書き方のコツを詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてくださいね!
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
面接カードは公務員試験で提出が必要になる
公務員試験を受験する際、筆記試験だけでなく、面接も重要なステップです。その際、面接官が受験生の情報を把握するための資料として、面接カードの提出が求められます。
ここでは、面接カードの入手方法と提出方法を解説します。
入手方法
面接カードの入手方法は、受験する公務員試験の種類や自治体によって異なりますが、一般的には公務員試験の公式サイトや自治体のホームページからダウンロードできます。
また、一部の自治体や官庁では、試験の申し込み時に面接カードのテンプレートを郵送してくれる場合もあります。
ダウンロードした面接カードは、指定されたフォーマットに従って、必要な情報を記入しましょう。記入する内容は、基本的な個人情報や学歴、職歴、志望動機、自己PRなどが一般的です。
提出方法
面接カードの提出方法も、受験する公務員試験の種類や自治体によって異なります。
一般的には、筆記試験の合格者に対して、面接の日程とともに面接カードの提出を求める通知が送られるので、その通知に従い、指定された期日までに面接カードを提出する必要があります。
国家公務員の場合、一次試験合格後に面接カードをダウンロードし、面接試験当日に持参するのが一般的です。
一方地方公務員の場合は、願書提出時や一次試験当日、または面接試験当日に持参するケースなど、様々な提出方法があります。
面接官が面接カードで見る評価ポイント3つ
ここでは、面接官が特に注目する3つの評価ポイントを紹介します。
これらを押さえることで、より効果的な面接カードを作成できるでしょう。
①公務員の仕事への熱意がありそうか
面接官は、あなたが公務員としてやりがいを感じ、国民のために尽くしたいという熱意を持っているかを見ています。
志望動機の欄では、なぜ公務員を目指すのか、あなたの価値観と公務員の仕事がどう結びついているのかを具体的に書きましょう。
また、これまでの経験から得た学びを公務員の仕事にどう活かせるかを示すことで、仕事への熱意をアピールできます。
単に「安定しているから」ではなく、あなたの情熱が伝わるような志望理由を書くことが重要です。
②この人と一緒に働きたいと思えるか
面接官は、あなたが職場の雰囲気に馴染めるか、チームワークを大切にできるかを見極めようとします。
そのため、面接カードには、協調性やコミュニケーション能力を示す経験を記入しましょう。
例えば、学生時代のサークル活動やアルバイトでの協力体制、プロジェクトでの役割などが有効です。
面接官があなたと一緒に働きたいと思えるよう、誠実さと熱意を込めて記入することが大切です。
③応募先の仕事に向いている行動特性がありそうか
面接官は、面接カードを通じて応募者の行動特性が応募先の仕事に適しているかを判断します。
具体的には、チームワーク力、問題解決能力、コミュニケーション能力などが重視されます。そのため、これらを示すエピソードを自己PRや学生時代の経験などの項目に盛り込むことが重要です。
ただし、単なる経験の羅列ではなく、学びや成長も記述することで、応募先の仕事に活かせる特性を具体的にアピールできますよ。
面接カードの4項目を紹介
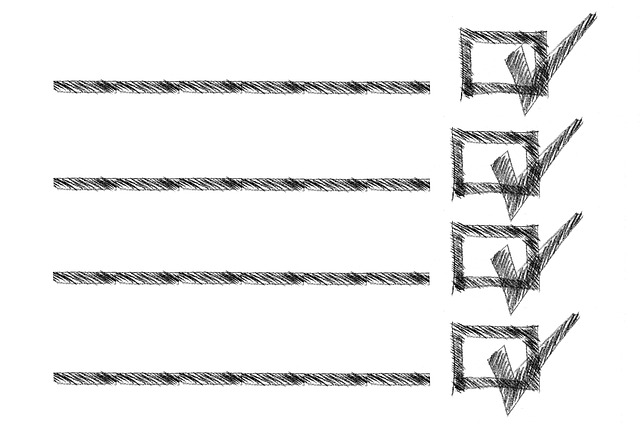
面接カードは、民間企業の採用で言うES(エントリーシート)と同じようなものです。ここでは、面接カードに書く4項目を紹介します。
- 志望動機
- 自己PR
- 趣味や特技
- 最終学歴
①志望動機
1つ目は志望動機です。公務員としての仕事に対する熱意や、その自治体や官庁のどこに魅力を感じているのか明確に伝えることが大切です。
具体的な経験やエピソードを交えて、なぜその職種や部署を選んだのか、どのような貢献をしたいのかを述べると、面接官に自分の意欲やビジョンを伝えられます。
また、受験先の特色や取り組みを研究し、それに対する自分の考えや期待を述べることで、真剣にその職を志していることが伝わります。
②自己PR
2つ目は自己PRです。自己PRでは、自分の強みやこれまでの経験を通じて培ったスキル、特性をアピールします。
具体的なエピソードや実績を元に、どのような場面でどのような行動を取ったのか、その結果どのような成果が得られたのかを明確に伝えることが重要です。
また、その経験が公務員としての仕事にどのように役立つのかを結びつけて説明することで、自分の適性やポテンシャルをアピールできます。
③趣味や特技
3つ目は趣味や特技です。趣味や特技は、自分の人間性や多様な経験を伝えるための項目です。
単に「読書が好き」と書くだけではなく、どのようなジャンルの本を読むのか、それが自分の人生や価値観にどのように影響しているのかを具体的に述べると良いでしょう。
特技がある場合は、それを磨くための努力や、その特技を活かした経験などを紹介することで、自分の熱意や取り組みをアピールできます。
④最終学歴
4つ目は最終学歴です。最終学歴は、自分の学びの背景や専門知識を伝えるための項目です。
単に学校名や専攻を列挙するだけではなく、学生時代にどのような研究や活動に取り組んだのか、その経験が今後の公務員の仕事にどのように役立つのかを考え、具体的に述べることが求められます。
面接カードの書き方の3つのポイント

面接カードはあなたの能力や人柄を伝える大切な書類です。ここでは、面接カードの書き方の3つのポイントを解説します。
- 最初に結論を書く
- 文章を見やすく書く
- 簡潔にまとめる
①最初に結論を書く
面接カードの最も重要なポイントは、自分の強みや志望動機を明確に伝えること。そのため、最初に結論を明確に書くことで、読み手の印象に残りやすくなります。
具体的には、自己PRや志望動機の冒頭部分で、自分の特徴やその組織での貢献方法を、簡潔に述べると良いでしょう。
結論を書いたあとで、具体的なエピソードや経験を交えて書くことで、説得力を持たせられますよ。
②文章を見やすく書く
面接カードでは、限られたスペースの中で情報を伝える必要があります。そのため、文章の流れをスムーズにすることが大切です。
1つの情報から次の情報へと自然に移行するように心掛けましょう。不自然な区切りや、情報が飛び飛びになると、読む側にとって理解しにくくなります。
例えば、学歴を書く際には、高校→大学→大学院というように時系列に沿って書くことで、読み手が自然に情報を追っていけます。
③簡潔にまとめる
面接カードは、短時間であなたの情報を把握するためのツールです。冗長な表現や不要な情報は避け、ポイントを絞って情報を伝えることが求められます。
例えば、志望動機を述べる際には、自分がその職種や企業を選んだ具体的な理由を簡潔にまとめることが大切です。
また、過去の経験やスキルを述べる際も、その経験がどのように今後の仕事に役立つのか、どのようなスキルを活かして業務に取り組むのかを明確にしてください。
余計な情報は削除することで、面接官が必要な情報だけを迅速に把握できるようにしましょう。
面接を見据えた面接カード作成のコツ
ここでは、面接を見据えて面接カードを作成する上で押さえておきたいコツを解説します。
面接で好印象を与えるための秘訣を知ることで、自分の強みを効果的に伝えましょう。
①求められる人物像をしっかり理解する
求められる人物像をしっかり理解することは、面接カード作成の重要な第一歩です。
まず、応募する企業の公式サイトやパンフレットを熟読し、企業理念や求める人材像を把握しましょう。また、業界研究を通じて、その企業が必要としている能力や資質を推測することも大切です。
自分の強みや経験を、企業が求める人物像に合わせて表現することで、面接官の印象に残りやすくなります。
また、求められる人物像を理解し、それに沿った自己アピールを行うことで、「活躍してくれそうだ」と好印象を与えられますよ。
②アピールする強みを1-2個に絞って強調する
面接カードでは、自分の強みを効果的にアピールすることが重要ですが、多くの強みを列挙すると焦点がぼやけてしまいます。
そこで、最も面接官の印象に残る1-2個の強みに絞って強調することをおすすめします。
応募する職種や企業の求める人材像を考慮して強みを選んだあとは、その強みを裏付ける具体的なエピソードや実績を用意しましょう。
例えば、「リーダーシップ」を強みとする場合、学生時代のプロジェクトでチームをまとめた経験を挙げるといった具合です。
強みを絞ることで、面接官に明確なメッセージを伝えられるほか、限られた面接時間内で自分をアピールできますよ。
③他の回答との一貫性をもたせる
面接カードを作成する際、最も重要なポイントの1つが一貫性です。
自己PRや志望動機などの回答が、他の質問への回答と矛盾しないよう注意しましょう。
事前に自分の経験を整理し、具体的なエピソードを交えながら、一貫した主張を貫くことで信頼性が高まります。
面接カードの内容が食い違っていると、面接官に不誠実な印象を与えかねないため、提出前に全体を通して矛盾がないかしっかりと確認することをおすすめします。
④深堀りの余地を残した回答をする
面接カードの回答は、面接官の興味を引き、さらなる質問を促すようなものが理想的です。
あまりに詳しく書きすぎると、面接での話題が尽きてしまう恐れがある一方で、回答が短すぎたり抽象的すぎたりすると、面接官は追加の質問をしづらくなります。
そのため、面接カードには、自分の経験やスキルの概要を簡潔に記載し、具体的なエピソードや成果の詳細は面接で直接語れるように準備しておくことが大切です。
例えば、「リーダーとして、チームのコミュニケーションを円滑にし、納期通りに完了させました」であれば、「どんなコミュニケーションを取ったのか」「課題にどう対応したのか」と、深堀りしたくなるはずです。
面接カードのNGな書き方3つ

面接カードのNGな書き方を3つ紹介します。以下の書き方をしてしまうと、印象が悪くなるので注意してください。
- 誤字脱字がある
- 一文が長く読みにくい
- 嘘の内容が書かれている
①誤字脱字がある
面接カードは、あなたの第一印象を形成する大切な書類です。誤字や脱字があると、面接官に不注意や不真面目な印象を与えてしまう恐れがあります。
特に公務員の仕事では、文書作成能力が求められる場面が多いため、面接カードに誤字脱字があるとその能力を疑われることも。
提出前には、何度も自分でチェックするだけでなく、他の人にも読んでもらい、誤字脱字のチェックをお願いすることで、ミスを未然に防ぎましょう。
②一文が長く読みにくい
一文が長くなりすぎると、その内容が伝わりにくくなります。また、視認性が低下し、面接官が読むのにストレスを感じる可能性があります。
面接官は、多くの面接カードを読む必要があり、読みやすさは非常に重要です。
大切なのは、簡潔に要点を伝えることです。情報を整理し、短い文でポイントを明確にすることで、面接官にあなたの思いや経験を効果的に伝えられます。
③嘘の内容が書かれている
面接では面接カードの情報をもとに面接することもあります。嘘を書くと面接時にバレてしまうため、面接カードには嘘を書かないようにしましょう。
嘘や誇張をすることで、一時的に良い印象を与えられるかもしれませんが、後で真実が発覚した際の信用失墜は計り知れません。
公務員としての職務においても、誠実さや信頼性は非常に重要な要素です。面接カードに書く内容は、自分の真実の経験や考えを基にして、誠実に伝えることが大切です。
面接カードに書く内容を予め決めておこう
面接カードは、公務員試験のエントリーシートです。面接官の第一印象を左右する大事な書類なので、真剣に書きましょう。
最初に結論を書いてから、具体的な経験を書き、自分の強みをアピールしてください。誤字脱字がないのはもちろんのこと、読みやすくて分かりやすい文章を心がけましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。











