研究職は、大学や企業の研究所で研究を行う職種です。
理系学部の就活生が目指すことが多い職業ですが、自分に向いているかどうかわからず悩んでいる方もいるでしょう。
本記事では、研究職に向いている人の特徴・向いていない人の特徴・研究職の種類・やりがい・注意点について解説します。
研究職を目指すかどうか検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
研究職に向いている人の4つの特徴

研究職に向いている人の特徴を押さえていれば、自分との共通点があるかチェックできます。研究職に適性がある人の特徴は、以下の4つです。
- 集中力が長けている
- 探求心がある人
- 忍耐強く粘り強い人
- コミュニケーション能力がある人
①集中力が長けている
集中力に長けていて、正確に作業を進められる人は研究職に向いています。
研究職の業務では繊細な作業に取り組む機会が多いため、集中して丁寧に作業を継続できる能力が必要です。
目の前の実験に打ち込んで、実験結果やデータを的確に分析するためには、長時間集中できる力を備えていることが重要になります。
集中力を発揮できるだけでなく、長丁場においても継続できるスキルを持っていれば、研究職で活躍しやすいです。
②探求心がある人
探求心があり、分析結果をもとに改良するためにはどうすれば良いか考え抜ける人は、研究職に適性があります。
研究職の業務には、目標に近づくためにさまざまな観点から考え、新しい可能性を求めて挑戦をいとわない姿勢が必要です。
またさまざまな物事に関心を強く持ち、柔軟な発想も取り入れられる性格を備えていれば、より多様な研究分野に対してモチベーションを高められます。
新しく発表された論文なども自発的にしっかりとチェックし、知識を貪欲に増やしていく姿勢も大切です。
③忍耐強く粘り強い人
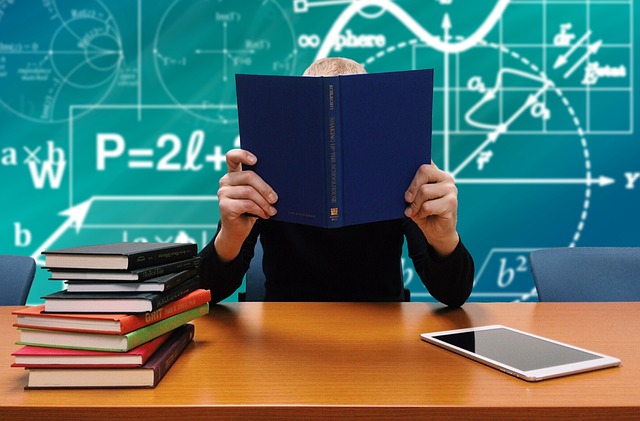
粘り強く物事に取り組むことが得意で、忍耐強い人も研究職として適しています。
研究職の業務は、結果が出るまで長い時間がかかるものが多いのが特徴です。
年単位で取り組む必要がある業務でも、最後まで諦めずに遂行する姿勢を備えていることが重要になります。
また、業務では期待していた結果が得られず、実験方法を検討し直すケースも多いのがポイントです。
数回の試行で失敗が重なっても、投げ出さずに取り組める忍耐力が必要になります。
④コミュニケーション能力がある人
コミュニケーション能力を備えている人も、研究職に必要とされる人材です。研究職の業務は、個人ではなく複数人のチームで進めることが多くあります。
チームのメンバーとデータを正確に共有するため、定期的に連携することが苦ではない人が向いているといえます。
また異なる部署や会社の人と連絡を取り、研究結果を商品に活用する方法を考えたり、実験結果をデータとして示したりしなければいけない場面も。
相手の視点に立って考える力や、明るく接するスキルも問われる仕事です。
研究職に向いていない人の2つの特徴
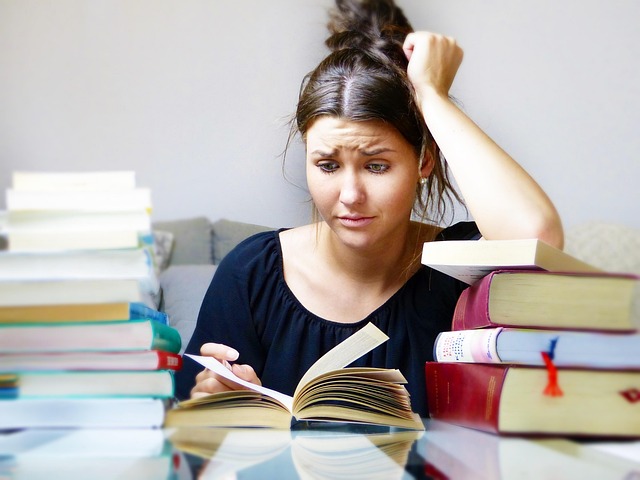
研究職に向いていない人の特徴もあわせて確認すれば、自分が長続きできるか判断可能です。
ここでは、研究職に合わない人の2つの傾向について紹介します。
- 継続力がない人
- 行動力がない人
①継続力がない人
継続力がない人は、研究職には不向きとなります。研究職の業務は結果が出ない状態が続くこともあるため、継続力がない人は苦痛を感じやすいです。
コツコツと実験や研究を積み重ねなければいけない業務も、問題なくこなせる忍耐力が必要になります。
また、集中力が途切れやすい人も研究職にはあまり向いていません。
研究職の仕事では、長いスパンでの作業も最後まで責任感を持ってこなせるスキルの有無が重要となります。
②行動力がない人
行動力がなく、受け身の姿勢になりやすい人も研究職としては適していません。
研究職では、日々進化する技術や理論を積極的に学びながら実践していく姿勢が必要になります。
自分から新しい発想を取り入れ、好奇心を持って分析できる人でなければ、多様な分野への対応力を伸ばせません。
また、研究職では他人とコミュニケーションを取りながら行動することも求められます。
チームの状況に応じて連携できるスキルがないと、成果を生み出しにくくなってしまう点に注意が必要です。
研究職の種類を2種類紹介
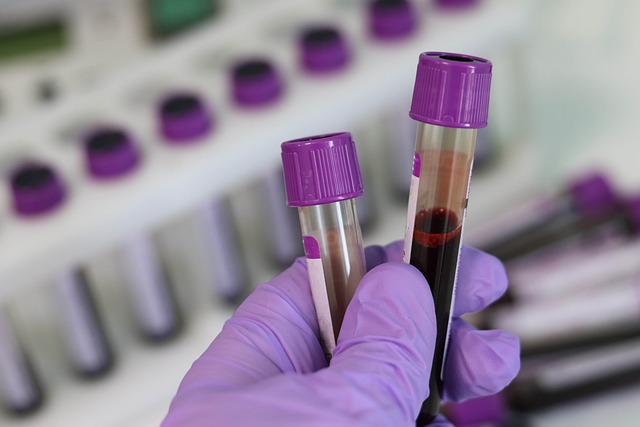
研究職の種類について把握していれば、どのような業務があるのか確認可能です。ここでは、業務を2種類に分けて紹介します。
- 基礎研究
- 応用研究
①基礎研究
基礎研究は、まだ世の中で判明していないものを研究して開発する仕事です。
プロセスが明らかになっていない現象やなぜ発生するかわからない法則を研究することで、社会で発生している問題を解決するための手がかりを探せます。
人間の体の中で起こっている働きに関して研究したり、植物や動物の生態について研究したりと、さまざまな分析が行われるのが特徴です。
生物だけでなく、天候や物質を構成する元素などを対象とする場合もあります。
②応用研究
応用研究は、基礎研究の結果をもとに、製品やサービスへの実用化を進める方法を探す仕事を指します。
基礎研究は大学や研究施設などで行われますが、応用研究はメーカーなどの民間企業で行われることが多いのが特徴です。
現在判明している法則や現象を活用して、顧客が求めている機能を付与する方法を考えたり、問題の新しい解決策を提供したりすることも業務に含まれます。
有効なデータを集めるために実験を重ねることもあるのがポイントです。
研究職の3つのやりがい

続いて、研究職にはどんなやりがいがあるかを確認していきましょう。ここでは、3つのやりがいを紹介します。
- 新しいことを見出せる
- 好きなことを追求できる
- 達成感を得られる
①新しいことを見出せる
研究職には、業務を通して明らかになっていなかった新しい法則や現象を見つけ出せる、といったやりがいがあります。
研究で物事のプロセスを明確にすれば、応用性を広げて社会問題の解消に貢献できるのが魅力です。
新しい可能性を生み出す最前線で働ける、といった強みもあります。
結果が出ず苦労することがあっても、自分が所属するチームで生み出した成果が、人々の暮らしに有効活用されるやりがいを感じられるのがメリットです。
②好きなことを追求できる
研究職のやりがいとしては、好きなことを追求する業務に携われることも挙げられます。
研究職では、興味深い物事の法則を明らかにするために打ち込んだり、目標や課題に対してどのような理論を活用すればよいか考えたりできるのが魅力です。
研究分野に興味を持っていれば、自分の知的探求心を満たしながら業務を進められます。じっくりと考え、理系分野の知識を掘り下げたい方におすすめです。
③達成感を得られる
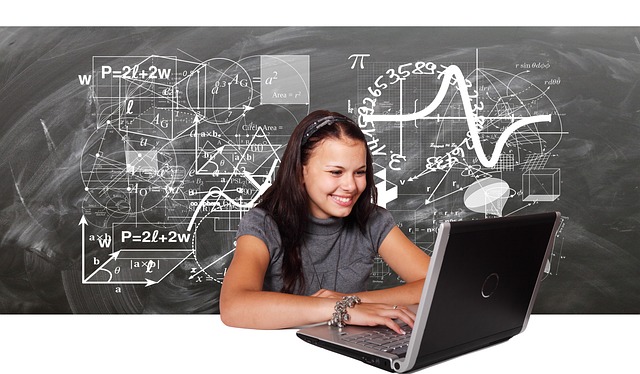
研究職は、成果を得られた時の達成感が大きいのが魅力です。
多くの実験を繰り返して製品への実用化が決まった時や、プロセスが不明の現象を解き明かした時には、特別な達成感が得られます。
自身が携わった業務が製品として形になって生活を便利にしたり、社会で生まれている課題を解決する糸口になったりするため、やりがいを実感しやすいのが強みです。
研究職を目指すときの3つの注意点

研究職を目指す際の注意点をチェックすれば、自分が納得して取り組める仕事かどうか判断可能です。ここでは、3つの注意点を説明します。
- 研究の成果が求められる
- 転職先が絞られる
- コミュ力が求められることを理解する
①研究の成果が求められる
研究職では、ただ研究をするだけでなく、一定の成果を出すことが求められます。
特にメーカーで働く場合、特許の取得に結びつかない、結果が現れない状態が続いてしまうと営業職への転向を進められることがあるのがポイントです。
また大学で研究を行う場合でも、研究成果を出して実績を積み上げていかないと助教授から昇格しづらくなってしまいます。
成果を出せない研究は打ち切られる可能性もあるため、定期的に成果が求められる環境で働くことを了承しなければいけません。
②転職先が絞られる
研究職は転職先が限られている職業なので、就職先はしっかりと吟味する必要があります。
もともと研究職に就職するのはハードルが高く退職率も低いため、転職をしたくなっても募集が出ていない、といった状況に陥りやすいです。
また、募集があった場合も期間が限られていることがあり、長く勤められないリスクがあります。
研究職の経験を活かして新たな職種に転職する場合は、品質管理やコンサルティング・エンジニア・営業などが選択肢となるのが特徴です。
③コミュ力が求められることを理解する

コミュニケーション能力が求められることを理解した上で、研究職を志望することも大切です。
研究職に対し個人で好きなことを突き詰めて研究するイメージを持つ人もいますが、実際は基本的にチームで作業にあたります。
成果や分析結果をわかりやすく説明するスキルも問われるため、人と接することが苦ではない性格でないと向いていません。
一定の成果を生み出すためには、チームの中で話し合い、連携して動くことが求められます。
研究職に向いている人の特徴に合っているか確認しよう
研究職を目指す際は、研究職に向いている人の特徴と、自分の性格が当てはまっているか確認しましょう。
本記事で紹介した情報を参考に、就職後のミスマッチを防いでくださいね。研究職のやりがいや注意点を把握して、就活へのモチベーションを高めましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









