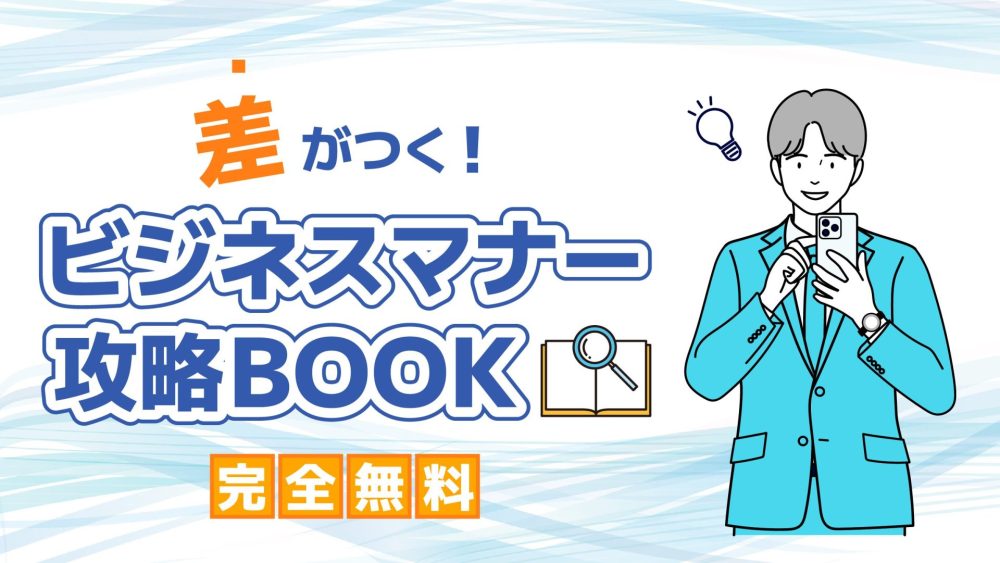内定者懇親会とは、内定が出た就活生と社員が交流するために設けられる会のことです。
しかし、内定者懇親会で社員に対してどのような質問をすればよいのかわからず、入社前に必要な情報を聞き逃がしてしまう方もいるでしょう。
本記事では、内定者懇親会で質問を用意する重要性・質問をする利点・おすすめな質問例・質問のNG例について解説します。
社員だからこそ知っている情報を引き出して企業への理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。
内定後もカリクルがサポート!
- 1AI強み診断|強み再発見
- 入社後も活かせる強みを見つけよう
- 2ビジネスマナーBOOK|マナー確認
- 社会人にも通じるマナーを収録!
内定者懇親会は質問を用意して臨もう!
内定者懇親会は、内定者と社員が交流を深めるために開催される会で、質問内容をあらかじめリストアップしておくと有意義に過ごせます。
オンラインや食事会などさまざまな形式で実施され、内定者懇親会の特徴は、以下の2つです。
- 企業側から質問を求める場合も多い
- 雑談の中でも積極的に質問すると吉
①企業側から質問を求める場合も多い
会によっては、あらかじめ企業が質疑応答用に時間を設けていて、質問を求められる場合も多いのが特徴です。
企業が用意した質問時間では、選考の際には聞けずにいたことや、事務的な手続きについて主に質問しましょう。
企業側が質問時間を設けるのには、内定者が入社前に感じている不安や疑問を解消し、好感を持ってもらう意図があります。
また、懇親会には複数の企業から内定が出ている就活生も参加しているのも特徴です。回答を聞いて、企業に入社するかどうかを判断している就活生もいます。
②雑談の中でも積極的に質問すると吉
雑談の中でも積極的に社員に話しかけ、質問をするのがおすすめです。質問タイムはやや改まった雰囲気になるため、形式的な回答が多くなることもあります。
先輩社員と雑談する中で質問を取り入れることで、実際の現場の声を聞きやすくなるのがメリットです。
また、どのような流れで働いているのか、どんなプロジェクトが進んでいるのか、具体的な内容を聞き出す質問をするのも適します。
自分が会社で働いている姿をイメージしやすくなるのが利点です。
内定者懇親会で質問するメリット3つ

内定者懇親会で質問するメリットを確認すれば、質問を用意する際のモチベーションにつながります。メリットは、以下の3つです。
- 企業とのマッチ度を判断できる
- 入社のための準備をしやすくなる
- 自分を売り込める
①企業とのマッチ度を判断できる
自分から質問をしてコミュニケーションを取ることで、企業とのマッチ度が判断できるのがメリットです。
質問の回答内容と自身の考え方に共通点があれば、会社のやり方に馴染んで働けることがわかります。
また、回答の伝え方が丁寧かどうかや、企業が強く推している事柄をチェックすることも大切です。
新卒社員を大切にしている会社かどうか、自分がいきいきと働ける社風かどうかを判断する際の基準になります。
②入社のための準備をしやすくなる
質問をして疑問点を解消しておけば、入社に向けて準備がしやすくなる、といった利点もあります。
手続きでわかりづらい部分を自分から聞くことで、用意するべき書類や記載するべき情報を正しく把握できるのがメリットです。
また、わからない所を自分から聞いて答えてもらう練習にもなります。
自分から行動する姿勢を見につければ、仕事上でもスムーズに疑問点を聞いて効率よく作業を進めやすくなるでしょう。
③自分を売り込める
質問をして社員と話す機会を増やせば、自分を売り込めるのもメリットです。
今後関わっていくことを考慮して和やかに会話をすれば、先輩と良好な関係を築いて仕事を進めやすくなります。
また、会社の雰囲気に慣れれば、のびのびと自分らしさを活かして働きやすくなるでしょう。
自身が志望する部署に所属している先輩社員を見かけたら、雑談や質問をして自分の顔を覚えてもらえるように行動してみてくださいね。
内定者懇親会でおすすめな質問例5つ

内定者懇親会に適した質問の具体例を知っていれば、質問時間を有意義にするために準備できるのが利点です。ここでは、5つの具体例を紹介します。
- 一日の仕事の流れ
- 仕事で苦労すること、やりがい
- 入社までにしておいた方が良い事
- 企業の福利厚生の実態
- 企業としての展望
①一日の仕事の流れ
一日の仕事の流れについて聞けば、自分がこれから携わる業務内容を把握しやすくなります。
志望部署に所属していない社員に聞く場合も、何時に昼食や休憩があり、何時まで働くことが多いのか聞けば、ある程度働くイメージが湧くでしょう。
また、質問前に会社の定時時間について情報を把握しておくと、回答内容をもとに残業が多いのかどうかを判断できます。
業務内容についてもある程度聞けると、何のスキルが必要になるか予想でき、対策ができますよ。
②仕事で苦労すること、やりがい
仕事で苦労することや、やりがいを感じる部分について聞けば、どのような達成感を得られる仕事なのか想像しやすくなります。
仕事内容への理解を深めつつ、入社後自分はどのように仕事に向き合っていくかイメージできるのが特徴です。
また、質問相手が持っている個人の目標や、仕事で大切にしている考えなどを聞くのも良いでしょう。
どんな社員がどのような心構えで仕事に携わっているのか聞けば、仕事へのモチベーションを高められるのが利点です。
③入社までにしておいた方が良い事
入社までにしておいた方が良い事を質問すれば、仕事に有用なスキルや取得すべき資格は何か探れます。
自分が現在持っている強みをどのように活かせばよいのか、取得して昇格につながる資格はあるのかどうか把握できるのがメリットです。
また、入社までにどんなスキルを磨けば仕事に活かせるのか聞くと、意欲があることをアピールできますよ。
④企業の福利厚生の実態
企業の福利厚生の実態を聞けば、労働環境について探りを入れられます。入社を考えている就活生は、しっかりと聞いておくべき質問です。
実際はどれくらい残業しているか、繁忙期はどのように仕事に取り組むのか聞いておくことで、残業管理はしっかりと行われているか入社前に判断できます。
また会社で取り入れられている福利厚生制度の特徴について質問するのもおすすめです。
法律で定められた制度以外にも、どのようなケアを社員に施しているのか聞くと良いでしょう。
⑤企業としての展望
企業としての展望について質問すれば、自身がこれから入社する企業の将来像を把握しやすくなります。
展望については曖昧な質問をするのではなく、現在動いているプロジェクトの内容や、これからの経営戦略について具体的に聞きましょう。
実際にプロジェクトや経営に関わっている社員がいれば、会社の最前線を作っている現場の声が聞けるチャンスになります。
内定者懇親会ならではの貴重な回答を得るためにも、進行しているプロジェクトは何か、積極的に質問しましょう。
内定者懇親会でNGな質問例4つ

内定者懇親会でNGな質問例もあわせて確認すれば、失礼な印象を与えないよう対策が可能です。ここでは、質問のNG例を4つ紹介します。
- 調べれば分かること
- 社外秘の情報に関すること
- 相手の給与について
- 抽象的なこと
①調べれば分かること
自分で調べればすぐにデータが出ることは、わざわざ質問しないことが大切です。
貴重な質問の時間を無駄に使ってしまい、他に聞くべきことを質問できなくなってしまいかねません。
事前に質問したい内容をリストアップし、調べれば回答が出てくるものがないか再確認しましょう。
また自分で調べられることを社員に聞いてしまうと、データ調査力がないのではないか、仕事に対して受け身なのではないか、と捉えられるリスクもあります。
②社外秘の情報に関すること
社外秘の情報に関することを質問するのは避けるようにしましょう。
内定をもらった就活生は、懇親会の時点ではまだ入社していないため、厳密には社外の人間となります。
そのため、社外秘とされる財務・取引・事業の根幹となる、研究情報について聞くのはNGです。
質問相手が話の流れの中で教えてくれる分には問題ありませんが、自ら社外秘になりうる情報を聞き出そうとするのはマナー違反となります。
聞いておきたい質問リストの中で、社外の人間には答えにくいものがないか確認しましょう。
③相手の給与について
相手の給与について聞くのは、失礼な印象になってしまうため避けなければいけません。
給与だけでなく、貯蓄はどのくらいあるかなどの質問を面と向かって行うのもやめましょう。
また給与やボーナス制度の質問ばかりしてしまうと、金銭面のみを気にしていて働く意欲が感じられない、と捉えられるリスクがあります。ほかの質問の中に1つだけ混ぜたり、濁した形で聞くようにしましょう。
④抽象的なこと
抽象的な質問は、回答内容も曖昧になりやすいため避けることを心がけましょう。
企業の展望について聞きたい時は、進行中のプロジェクト名を述べた上で、どのような戦略があるのか聞くようにすると具体性のある回答を得られます。
質問したいことをまとめたリストを見直して、もっとわかりやすい言い方に変更できるものはないか、具体的に聞けるものはないかチェックしましょう。
内定懇親会でたくさん質問して社会人生活に活かそう!
内定懇親会ではたくさん質問して、得られた情報を社会人生活に活かしましょう。
一日の流れややりがい、入社までにどんなことをするべきか、などについて質問するのがおすすめです。
積極的に質問や会話をして、入社後に自分らしく働けるように行動しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。