作文は、就職試験の設問として出題されやすい問題形式です。しかし、どのように回答すればよいのか悩んでしまう方もいるでしょう。
本記事では、作文が課される意図から、うまくまとめる書き方の流れ、回答するコツなどを解説します。
初めに作文例から確認したい方は、こちらをご覧ください。
企業が就職試験で作文を課す2つの意図

企業が就職試験でなぜ作文を課すのか知っていれば、意図に合わせた回答を作成しやすくなるのがメリットです。ここでは、2つの意図について解説します。
- 就活生の価値観を知りたい
- 自社の求める人物像と合うか知りたい
①就活生の価値観を知りたい
企業側が作文を課すのは、作文を通して就活生の価値観を知りたいと考えているためです。
提示されたテーマに作文形式で回答させる問題を用意すれば、文章の構成や取り入れられている意見から物事に対する考え方を把握できます。
回答内容からは、どんな信念を大切にしているのか、問題に対してどのように解決策を導き出すのか、考え方の傾向を読み取れるのもポイントです。
仕事に関わる価値観を知る手がかりにもなります。
②自社の求める人物像と合うか知りたい
企業側は作文を通して、自社が求めている人物像と合致しているかを見ているのも特徴です。
文章からわかる就活生の価値観と、会社の雰囲気やポリシーに共通点があれば、採用後のミスマッチを減らせます。
そのため、作文テーマに対して回答する際には、会社が掲げている社員に求める人物像と回答内容がかけ離れないよう注意しなければいけません。
あらかじめ志望している会社がどんな人材を求めているのか確認して、自分の考え方と似ている部分を押し出して説明しましょう。
就職試験の作文頻出テーマ10個
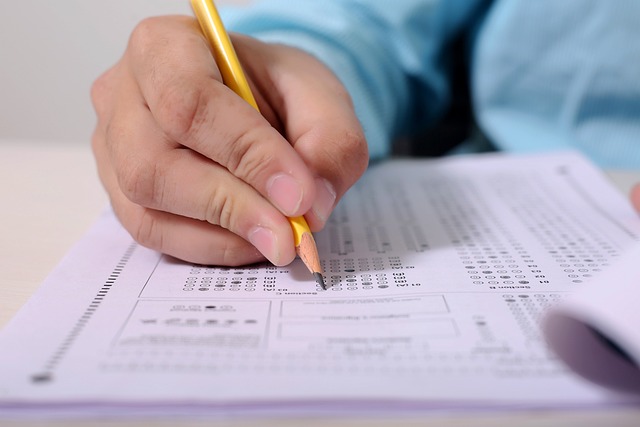
就職試験の作文問題には、頻出するテーマがあるため、あらかじめ対策しておくのがおすすめです。テーマの具体例は、以下のようになっています。
| ・学生時代に頑張ったこと ・将来の自分はどうなっているか ・仕事で成し遂げたいこと ・最近身近で起きた興味深いこと ・苦労した出来事 ・興味を惹かれたニュースや新聞記事 ・人と会話する上で心がけていること ・部活動で取り組んだこと ・大切にしている言葉や教え |
これまでの経験について聞く設問や、将来のビジョンを聞く設問もあり、自己分析ができているかどうかが問われやすくなります。
また、最近興味を持ったことや、時事問題への関心を問われる場合もありますよ。
【3ステップ】就職試験の作文テーマを書くポイント

就職試験の作文テーマを上手にまとめて回答するためには、書き方の流れを知っておくことが大切です。
ここでは、書き方の流れを3ステップに分けて説明します。
- 序論で結論を述べる
- 本論で序論の根拠を述べる
- 結論で自分の考えを述べる
①序論で結論を述べる
まず、序論で結論をはっきりと述べるようにしましょう。初めに作文で述べたいことを大まかに書けば、文章の内容が伝わりやすくなります。
提示されたテーマに対して簡潔に回答を述べることで、しっかりとレスポンスができる印象を与えられるのがポイントです。
また、最初の一文で読み手の心を掴むことも大切。流し読みされてしまわないよう、相手が読みたくなるような一文を考えましょう。
自分の信念が表れている文章を心がければ、一文目から個性を主張できますよ。
②本論で序論の根拠を述べる
次に、序論の根拠になる具体的なエピソードや、自分の考えについて書きましょう。
本論は結論に向けて書くことが重要なため、主題からずれたエピソードを選ばないようにしてください。一貫性のある内容を心がけ、自然な流れで読める文章に仕上げましょう。
また、エピソードは最初の状況・自身が取り組んだこと・努力した結果得られたこと、の3段階で説明するのもコツです。
経験した出来事の概要と成果をわかりやすく伝えましょう。
③結論で自分の考えを述べる
結論では、出されたテーマに対して自分なりに考えた答えを述べましょう。序論と結論を読めば内容が伝わるような文章に仕上げることが大切です。
最後の文で文章全体の結論をまとめることで、自身が言いたいことを強調しやすくなります。
志望動機などを回答する場合、将来自分がどのように活躍できるのか書くなど、過去の出来事だけでなく自身の将来像も含めて文章でまとめるのがおすすめです。
就職試験で作文テーマが難しいときのコツ3つ

就職試験で作文テーマが難しいと感じた場合に備えて、作成時のコツをチェックしておきましょう。覚えておくべきコツは、以下の3つです。
- 5W1Hを意識して書く
- 設問の意図を考える
- あらかじめ書きたい内容を箇条書きにする
①5W1Hを意識して書く
文章を上手く作成できないと感じたら、5W1Hを意識して、いつどこで、誰が何を行い、なぜ、どのように取り組んだのか書きましょう。
本論で意識して使うようにすれば、エピソードをわかりやすく説明しやすくなります。
5W1Hを取り入れて文章を作成すれば、自身の経験を活かした具体性のある内容になるのもメリットです。
文章にオリジナリティを出せるため、採用者の印象に残る回答に近づけられます。
②設問の意図を考える
回答が浮かばない時には、設問の意図に視点を切り替えて考えてみましょう。
その企業が「なぜこの設問を用意したのか」を意識して、背景を考えてみると適した回答内容をイメージしやすくなります。
設問の意図を考える際には、企業理念・企業の文化・社員に求めている人物像・活躍している社員の具体例などをヒントにするのがおすすめです。
企業研究からわかったことを踏まえて、自分なりに「どんな人材を求めているか」を企業目線で想定してみましょう。
③あらかじめ書きたい内容を箇条書きにする
何を書けばよいか詰まってしまわないよう、あらかじめ書きたい内容を箇条書きでリストアップしておくこともおすすめです。
箇条書きで作文に含めたい意見や考え方を書いておくと、アピールしたい内容を書き忘れないように対策できます。
また、書きながら何を書けばよいか迷ってしまう時間を減らすことにもつながるのが利点です。
箇条書きした項目は、序論と本論、結論のどの部分に使えるのか考えた上で並び変えれば、作文に取り入れやすくなります。
就職試験で作文テーマの内容を書くときの注意点3つ

作文テーマの回答をする際の注意点を確認していれば、悪印象を与えないよう対策ができます。知っておくべき注意点は、以下の3つです。
- 指定文字数の8割以上を埋める
- 段落分けする
- 文体を揃える
①指定文字数の8割以上を埋める
作文問題に回答する際には、指定文字数の8割以上の文字を使った文章を意識しましょう。
企業は設問に対して文字数を指定することで、「文字数のボリュームで伝えられる要素を知りたい」と考えています。
そのため、指定された量をしっかりと書く意識を持つことが大切です。
文字数が8割を満たしていないと、「指定文字数を守っていない」と捉えられるリスクがあるため、注意が必要。
また、冗長な印象を与えないためには、指定文字数を超えすぎないことも重要ですよ。
②段落分けする
段落分けを取り入れて文章を作成することも大切です。場面や話の内容が変わるタイミングでは、新しい段落にするとスムーズに読みやすくなります。
また、段落を分ける際には、文頭を1文字空けることを忘れないようにしましょう。
段落分けを行わずに書かれた文章は、どこからどこまでが結論なのか判断しづらくなってしまいます。
採用者に主張したいことをストレートに伝えられるよう、全体の流れを確認した上で段落分けをしましょう。
③文体を揃える
作文問題では、文体を揃えることを心がけましょう。問題文で文体を指定されていなければ、「です・ます調」でも「である・だ調」でも問題はありません。
しかし、文章内では必ずどちらかに統一することが大切です。文体が揃っていないと、ただ書き連ねたような乱暴な印象の回答になってしまいます。
また、主語に対して述語の活用形が合っているかどうかもチェックするのがおすすめです。
作文中に箇条書きを取り入れる場合には、語尾の品詞を揃えるようにしましょう。
【テーマ別】就職試験の作文例3つ

就職試験の作文例を参照すれば、具体的にどんな文章を作成すればよいのかイメージしやすくなるのが利点です。ここでは、3つの作文例を紹介します。
- 設問例①「学生時代に頑張ったことについて書いてください」
- 設問例②「仕事で成し遂げたいことについて書いてください」
- 設問例③「最近身近でおきた興味深いことについて書いてください」
設問例①「学生時代に頑張ったことについて書いてください」
| 私が学生時代に頑張ったことは、個別指導塾のアルバイトに新しい指導法を取り入れたことです。 個別指導塾で私が担当した生徒達は、カリキュラムへの理解度が異なっていました。そこで私は、生徒全員が同じレベルの教材を使っていることに問題があると考え、それぞれのレベルに合った教材を取り入れました。 指導法の見直しを行った結果、担当生徒が苦手としている部分を集中的に強化でき、成績が20点から40点上昇しました。 私はこの経験から、一人ひとりにフォーカスを当てて最適な提案を考え抜くことで、ポテンシャルを引き出し、より良い成果を生み出せることを学びました。仕事においても、自分から課題を見つけて解決に取り組み、顧客に最適なサービスを提供できるよう尽力したいです。 |
上記の例文では、まず簡潔に結論を述べてから、個別指導塾のエピソードで結論を補強しています。
自身が経験したことから、将来頑張りたいことにつなげて文章をまとめているのも特徴ですよ。
設問例②「仕事で成し遂げたいことについて書いてください」
| 私が仕事で成し遂げたいことは、企業や人の根幹を支えて、成長に貢献することです。 私はアルバイトで人手が足りず、業務が回りづらく困った経験があります。問題を解決するには業務効率を上げるべきだと考え、人手不足を補うためにマニュアルの見直しを行いました。 アルバイト先の先輩や後輩に、マニュアルでわかりづらい部分や変更したい部分を聞き、店長に根気よく掛け合ったことで、業務の効率を上げて売上を5%上昇させられました。 私はこの経験から、粘り強く解決策を探ることの大切さや、業務の見直しで従業員がいきいきと働きやすくなることを学びました。さまざまな経営資産を活かして企業のDX化に働きかけている貴社で、根気よく取り組む力を活かし、企業や従業員がのびのびと成長できる環境作りに貢献したいです。 |
上記の例文では、設問に対して一文で回答を述べた後で、回答を考えたきっかけとなった経験を紹介しています。
会社の強みにも触れた上で、どのように業務に取り組んでいくのか説明しているのがポイントです。
設問例③「最近身近でおきた興味深いことについて書いてください」
| 私の身近で最近起きた興味深いことは、太陽光発電を取り入れている家庭が増えていることです。 私が住んでいる住宅地は戸建が多く並んでいますが、今年から太陽光パネルを設置している住宅が3軒増加しました。 そして、太陽光パネルについて改めて調べてみると、コンパクト化や長耐久化が進んでいることを知り、利便性の向上が普及率につながっているとわかりました。 また、家庭で使う電力の一部を太陽光で賄うなど、自然エネルギーを家庭にも手軽に取り入れやすくしている貴社の取り組みは、今後の環境問題を改善していく上でなくてはならないものだと実感しました。 私は自然エネルギーを住宅に取り入れる事業を展開している貴社で、環境にも人にもやさしい暮らしへの変化を促せるよう、尽力したいです。 |
上記の例文では、太陽光パネルを設置している住宅が身の回りで増えたことを述べ、会社の事業内容につなげています。
身の回りで起きたことから新たに気付いたことや学んだことを詳しく説明しているのも特徴です。
就職試験の作文テーマの内容で自分の魅力をアピールしよう
就職試験の作文テーマに対して適した回答を行い、自身の魅力をしっかりと伝えましょう。
作文問題はあらかじめ頻出するテーマを把握しておき、上手な書き方を取り入れることで、アピール力の高い回答を作成できます。
難しい作文問題への対策も行って、採用者に自身の強みが伝わる文章を作成しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









