「就活の面接練習って……1人でできるかな、どんな風にすればいいのだろう」と悩んでいませんか?そこで、本命企業の面接の前にやるべき「面接の練習方法」を10通り紹介します。
また、面接で必ず聞かれる頻出質問も10パターン用意し、どのように答えたらいいのか回答も解説。自分に合った練習方法を試して、リラックスした気持ちで面接に臨みましょう!
全て無料!面接対策お助けツール
- 1面接質問集100選|400社の質問を分析
- LINE登録で面接前に質問を確認!
- 2ビジネスマナーBOOK|ルール確認
- 面接のマナーはこの1冊で大丈夫!
- 3企業・業界分析シート|企業研究
- 企業研究で回答を差別化!
面接練習なしはあり?面接練習をした方がいい理由

面接練習はしないよりもした方がいいです。
面接練習をしなければ、一番伝えたいことがうまく伝えられなかったり、想定外の質問に対応できなかったり、本来の力を発揮できない可能性もあるでしょう。
ここでは、面接練習をした方がいい理由を詳しく説明していきます。
①面接後に後悔している人が多い
就職試験の面接を受けた後は、比較的後悔している人が多い傾向にあります。
その後悔の内容は、予想外の質問に対応できなかったことや質問の意図から外れてしまったこと、自己PRや志望動機がうまく伝えられなかったことなどです。
これらは面接の頻出質問であり、練習をしっかり行っておけば、後悔せずに済んだ可能性が高いでしょう。
面接で後悔しないためにも、よく聞かれる質問の回答は事前に用意しておき、練習しておいて下さいね。
②第三者の意見が聞け早期改善できる
面接練習をすれば、第三者の意見を聞けるため、改善点も早く見つかります。また、自分では気にならなくても、第三者が見れば気になる点があることに気付けるでしょう。
声の大きさや表情、姿勢や言葉遣い、入退出のマナーなどの印象に関わる部分は、自分では詳細にわからないので特にアドバイスをしてもらって下さい。
自分にとって不都合な評価は聞きたくないかもしれませんが、早めに気づき改善することで内定獲得への確率がグッとUPしますよ。
③リラックスして本番に臨める
面接は何度も練習することで、本番の面接で慌てずリラックスした気持ちで臨めるでしょう。入退出時のマナーや面接の質問内容、流れがある程度決まっていますので、慣れることが大事です。
頭の中でシュミレーションをするよりも、実践練習を重ねることで面接への免疫がつき緊張感も軽減されるでしょう。
面接練習はいつから始める?
面接練習は、自己分析や企業研究など事前準備が必要なので、できるだけ早くから始めましょう。
面接では、お決まりの自己PRや志望動機、学チカ(学生時代力を入れていたことの略)以外にも「自分をお酒に例えたら?」などと変化球も飛んできます。
しかし、面接練習の際に実施する自己分析をしていれば、事前に準備してない質問でも近しい答えを見つけ出せる可能性が高まるでしょう。
面接練習は、就活スケジュールが埋まる前のできるだけ早い段階から始めるようにして下さい。
面接練習の3つのポイント

どのような面接練習をすればいいかわからないという方のために、面接練習のポイントを3つ紹介します。
①頻出質問の受け答えの練習をする
1つ目の面接練習のポイントは、頻出質問の受け答えの練習をすることです。あらかじめ予想できる頻出質問に関しては事前に対策できるはずなのに、対策せずに答えられなければ準備不足とみなされ採用には至らないでしょう。
業界や企業によって出題される質問は異なりますので、全てを網羅することはできませんが、最低限の頻出質問は押さえておいて下さい。
※頻出質問は、後述の「企業からの10の質問&回答のコツ」で紹介していますので目を通しておきましょう。
②姿勢・表情・話し方の練習をする
2つ目の面接練習のポイントは、姿勢・表情・話し方の練習です。アメリカの心理学者が提唱したメラビアンの法則によると、人の印象は話の内容が7%、声の大きさやトーンに関するものが38%、見た目が55%を言われています。
この法則に基づけば、面接においても見た目や話し方の印象をよくする必要があることが分かるでしょう。
「猫背になっていないか」、「口角を上げ明るい表情か」、「結論から話しているか」、「ゆっくり抑揚をつけながら語尾まで聞こえるか」などに注意した練習を心がけて下さい。
③本番を想定した練習をする
3つ目の面接練習のポイントは、本番さながらの本気モードで練習をすることです。「練習だからきっちりしなくてもいいや…」と思わずに、入室のノックから退室の扉を閉めるところまでしっかり練習しましょう。
おそらく本番は緊張しますし、他の就活生の緊張感も伝染しいつも通りの実力が発揮できないことが予想されますので、練習時から本番を想定して取り組んで下さい。
1人で完結!面接練習方法3選

面接の練習相手がいなくても、1人でできる面接練習方法があります。ここでは、1人でも完結する手軽にできる練習方法を3つ紹介しましょう。
①ESシートに沿った質問を深堀する
1人で面接練習する効果的な方法は、ESシートに沿った質問を深堀することです。
面接官は、ESシートの信憑性の確認や志望動機の本気度を知るために質問を深堀し、その深堀パターンは、次の5つで特技が柔道だった場合を例に挙げて解説します。
| 特技が「柔道」だった場合の深堀質問 |
| 【何故】「なぜ、柔道をしようと思ったのですか?」 【何が】「柔道をしてきて、何が一番大変でしたか?」 【どんな】「強くなるためにどのような工夫をしましたか?」 【学んだこと】「柔道から学んだことは何ですか?」 【活かしたいこと】「学んだことを仕事にどう生かしたいですか?」 |
深堀質問に対する答えは、まず「結論」を話し、次に「具体的な例(エピソード)」の順に話すと魅力的な回答になるでしょう。
②面接している姿を録音・録画する
1人で面接練習する効果的な方法は、面接している自分の姿を録画・録音することです。
面接練習は、自分の面接を主観的ではなく客観的に見ることで効果を発揮するので、録画や録音して次のことを確認しましょう。
- 背筋は伸びているか
- 胸を張っているか
- 自信をもって話せているか
- 語尾を伸ばしていないか
- 目を見て話せているか
- 表情は朗らかか
上記の点を意識するだけで「自信を持った優秀な人材」に見えるので、面接官になった気持ちで、録画・録音した自分の映像を見て、ダメな部分は早期改善していきましょう。
③面接練習アプリを使う
1人で面接練習するのに効果的な方法は、面接練習アプリの活用があります。
面接練習アプリとは、就職や転職活動における面接試験への対策をサポートするために開発されたウェブアプリケーションのことです。代表的な機能を3つ紹介します。
- 利用者が実際の面接に似た環境で練習できる「模擬面接機能」
- 利用者の回答や振る舞いを分析し、アドバイスしてくれる機能
- 面接の頻出質問や回答例を提供する「学習コンテンツ機能」
面接アプリもたくさんありどれがいいのか迷いますが、模擬面接機能やフィードバック機能など実践に近い面接練習ができるアプリがおすすめです。
複数人でできる!面接練習方法7選

複数人でできる面接練習方法を7つ紹介していきます。
- 第一志望以外の企業の面接を受ける
- 家族と面接練習をする
- 大学の就職課で模擬面接を受ける
- 本命企業のOB・OGに助言を乞う
- 就職エージェントを利用する
- 就活生同士で面接練習をしあう
- 就活イベントで面接練習する
①第一志望以外の企業の面接を受ける
第一志望以外にも、たくさんの企業を受験し、面接の場数を踏む必要があります。面接は、20社受けても内定がもらえるのはそのうちの1~2社程度なので、必ずしも第一志望が受かるとは限りません。
企業によって面接スタイルも質問も違って、その度に次の面接に活かせる学びや反省につながります。第一志望以外の企業の面接を受けることで、実践的な面接練習をすることができるでしょう。
②家族と面接練習をする
一番身近な社会人経験も面接経験もあるとっておきの面接官役と言えば、家族です。家族なら、率直なアドバイスをもらえ、本当に悪いところに気づける利点があります。
ただし、身近な存在すぎるがゆえに練習に気が緩みがちになるので、本番さながらに厳しくしてもらえるようお願いしましょう。
③大学の就職課で模擬面接を受ける
大学の就職課では、キャリアカウンセラーによる模擬面接が受けられます。
キャリアカウンセラーは、いわば就活のプロなので知識や経験も豊富です。あらゆる業界に精通し、面接の傾向や専門的なこともアドバイスしてくれます。
模擬面接も本番さながらに、入室から退室まで緊張感をもって対応してくれるのでおすすめです。
④本命企業のOB・OGに助言を乞う
本命の企業に入社した大学のOGやOBを訪問し、アドバイスをもらうことも刺激になるでしょう。
企業によって求める人材が違うので、実際に就職できたOGやOBに合格した秘訣を聞いてみて下さい。
その上で、実際に練習相手になってもらい的確なフィードバックをもらうことで、他の就活生よりも一歩リードできます。
⑤就職エージェントを利用する
就職エージェントとは、新卒の人材紹介を行っている就職の仲介人です。就職エージェントに登録すれば、履歴書やESシート、面接のアドバイスも行ってくれます。
就活状況や人柄を把握した上で、希望すれば面接練習にも付き合ってくれるのでプロの目線から貴重なアドバイスを受けられるでしょう。
⑥就活生同士で面接練習をしあう
大学の友人など、就活生同士で面接官役と就活生役を交代しながら面接練習しましょう。
特に、面接官役を務めることで客観的に面接全体を見渡すことができ、友人の受け答えを見て自分と重ね合わせることができ学ぶ点もあります。
就活生役では気づけなかったポイントを改善できるので効果的です。
⑦就活イベントで面接練習する
就活イベントとは就活情報を得られるイベントのことで、模擬面接などの面接練習をすることもできます。
また複数の業界や企業が集まって開催されるので、今まで知らなかった企業に出会えたり、周りの就活生から刺激をもらったりできるのでより就活に力が入るでしょう。
実際のリアル企業がたくさん参加することで、会社の雰囲気をつかめ、面接練習にも気合が入ります。
企業からの10の質問&回答のコツ
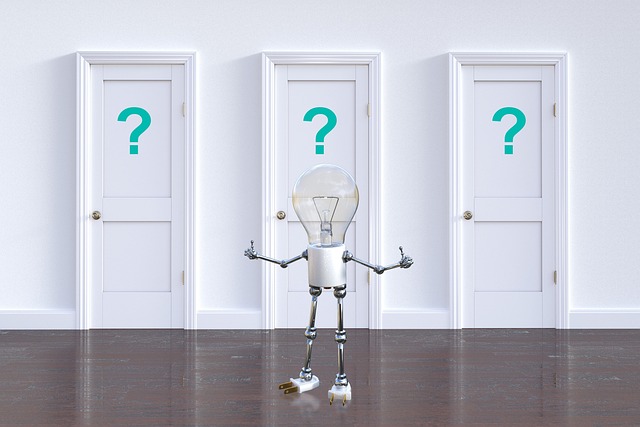
企業の面接でよく聞かれる頻出質問のうち10の質問を厳選しました。回答のコツも紹介しますので、是非参考になさって下さい。
①自己紹介
自己紹介は、初対面の面接官に、自分が何者かを伝える構成にして下さい。
盛り込むべき内容は、「氏名」・「学校情報」・「ガクチカ」・「意気込み」などで、250文字~300文字程度で1分以内で話せる長さが適当です。
しかし、企業によって時間も様々なので30秒~2分バージョンまで作っておくと咄嗟の対応も可能になりますよ。
Q:自己紹介してください
A:〇〇〇〇(氏名)と申します。〇〇大学△△学部に通っております。
大学では主に国際経済学について学んでおり、先進諸国間の国際経済政策の研究を行ってきました。学業以外では、フットサルサークルの活動に力を注いでおります。
本日は貴重な時間を作って下さりありがとうございます。宜しくお願いいたします。
②自己PR
自己PRは、自己紹介とは違い「就活生の強み」を知るために質問されます。面接官はその強みが自社でどう活躍できるかを見極めているのです。
また自己PRは、伝えたいことを1つに絞ることで、面接官の印象に残りアピールしたいことが伝わりやすくなります。
Q:自己PRをして下さい。
A:私の強みは、行動力があることです。
私の実家は、観光地が近いこともあり観光客のゴミの忘れ物が多く、景観を損ねると以前から問題になっていました。そこで、実際にごみがよく捨てられている所へ行ってみると、ごみを捨てる場所はあるものの分かりづらい場所にあったのです。
私は、大学のロボット研究会とタッグを組み、「ゴミ箱はここだよ!」としゃべるゴミ箱を作る作戦を決行しました。町の観光課に相談したところ、支援していただけることになり、ごみ箱の近くを通ったらセンサーで「ここだよ!」としゃべるゴミ箱の制作に成功しました。ゴミ箱の設置以来、ごみは半減し、地元の人にも喜んでもらえた経験があります。
貴社に入社した際には、この行動力を活かし、何か問題に直面した際には解決方法を自ら考え周りと協力しながら少しでもお役に立ちたいと考えております。
例文を見ても、急にクオリティの高い自己PRは思いつかない……と悩む人も多いですよね。そんな人は、カリクルのチャットGPTツールを使ってみましょう!いくつかの質問に答えるだけで、5分程度で自己PRが作れますよ。
③志望動機
面接官は、「志望動機」からあなたの熱意や覚悟を知りたがっており、なぜ自社を選んだのかをしっかり答えられなければ、どこでもよかったのではないかと思われてしまうでしょう。
面接官は、「志望動機」を知ることで入社後すぐに辞めずに長く働いてくれるかどうかも短い面接時間の中で判断しています。
志望動機作成のポイントは、まず働く目標やモチベーションを明確化し、応募企業ならではの強みや特徴を知り、応募企業で働くべき理由を言語化することです。
Q:志望動機は何ですか?
A:私は、日常生活を快適で効率的に変えてくれるインターネットサービスを支えているIT技術者に魅力を感じ貴社を志望しました。
私は、小さい頃から、わからないことがあればWebサイトですぐに調べる習慣がありましたが、大人になるにつれ、そのシステムが気になって仕方なかったのです。
そこで、ITの知識を身に付けたくて、大学時代に以前から興味のあったプログラミングのスクールに通い始めました。スクールの課題で、「アプリを作る」という授業があり、私も、自分がどこの国に行ったら一番モテるのかを検索できるアプリを作成しました。すると、先生や友人からも「おもしろい」と評価をいただき嬉しかったです。
入社後は、多くの方に喜んでもらえるような機能やサービスを開発できるようなIT技術者になりたいと考えております。
志望動機は大抵の面接で聞かれるぶん、きちんと質の高いものを作りたい人も多いでしょう。しかし時間をかけたくない!というのも本音のはず。そんなときは、カリクルのテンプレシートを使うのがおすすめです。
簡単なアンケートに答えるだけで、志望動機を簡単に作れるテンプレシートが無料でゲットできますよ。気になる人は利用してみてくださいね。
④会社選びの基準
会社選びの基準とは、企業を選ぶ時の自分なりの基準を意味し、企業は、会社選びの基準を知ることで、「自社の価値観と合うか」、「意欲をもって長く働いてくれるか」を確かめています。
そのような企業意図に応えるため、具体的なエピソードを交えながら分かりやすく伝える必要があるでしょう。
ただ何となく応募したというのではなく、応募企業のどのような点に惹かれたのかを明確にアピールし、入社後のやりたいことやどのような貢献ができるかも盛り込んで下さい。
Q:あなたの会社選びの基準は何ですか?
A:私の会社選びの基準は、社会に貢献できるかどうかです。
私は、小さなころから社会に役立つ職業に就きたいと考えておりました。母が看護師として働いているのですが、ケガや病気で苦しんでいる人のサポートをしている姿がとても誇らしかったです。いつしか私も母のような優しくて献身的な看護師になりたいと思うようになりました。
地域に根差し、患者様に寄り添う医療を理念とされている貴院で、笑顔でコミュニケーションの取れる看護師になりたいと考えております。
⑤学生時代に力を入れたこと
「学生時代に力を入れたこと」は、ガクチカとも呼ばれ、よく聞かれる質問の1つですが、業界を問わず質問される理由は、社会人としての素養を見極めているからと言われています。
文章作成のポイントは3つで、「どのように頑張ったか」、「なぜ頑張ったか」「何を学んで次にどう生かすか」です。
頑張った過程を掘り下げて伝えることで、入社後にも成功の再現性があることをアピールできます。代表的なエピソードは、部活、ボランティア活動、サークル活動やアルバイトなどです。
Q:学生時代に力を入れたことは何ですか?
A:学生時代に力を入れていたことは、小学2年生の頃から14年間続けている水泳です。
初めは週に1度スイミングスクールに通っていただけだったのですが、学校行事などでリレーの選手に選ばれていたので水泳が私の特技になりました。中学生の頃から、毎日1時間の練習を欠かしたことはありません。その甲斐あり、県の強化選手に選ばれ、全国大会8位に入賞したこともあります。私は、大会へ応援に駆けつけてくれる母の笑顔が見たくて頑張ってきました。
入社後も誰かを笑顔にする仕事に一生懸命取り組んでいく所存です。
ガクチカはエピソードをどうアピールしたらいいのかが最も難しいところです。そこで、カリクルではいくつかの質問に答えるだけでガクチカを簡単に作れる、便利なツールを配布しています!
気になる人は、下のボタンから無料でダウンロードしてみてくださいね。
⑥長所・短所
企業は「長所・短所」の質問で、応募者の人となりや社風にマッチしているかを推し量っています。
長所を理解できていれば、自分の能力を活かして活躍の幅を広げることができ、短所を知っていれば、克服する努力をし、他の人とカバーしあう対策を立てることができるでしょう。
「長所・短所」の作成のコツは、自己PRの内容とズレない様にすることと、短所はポジティブ変換できる内容にすることです。
Q:あなたの長所と短所を教えてください。
A:私の長所は、何事も一生懸命に取り組むことです。
人の嫌がるような作業も率先して手を抜かず全力でやり遂げられます。コンビニのアルバイトをしていたのですが、とても美味しいのになかなか売れない商品がありました。そこで、この商品のおいしさをたくさんの人に知ってもらうことと、売り上げアップのために販促用のポップを作成いたしました。
すると、先月の10倍の売り上げになり店長から感謝状をいただき嬉しかったです。
短所は、おせっかいなところです。
私は、自分がやらなくてもいいことでも相手が喜ぶと思うと、ついついしてしまうことです。私は、大学時代に授業を休みがちだった友人のためにノートを貸してあげていました。しかし、私がいつも貸してあげるので、友人は用事や病気でなくても休んでも大丈夫だと思っていたそうです。私は、その友人を甘やかし、よくない方向に導いてしまったと思いました。
今後は、何か行動する前に、本当にその人のためになることなのかをよく考えて行動できるよう改善していきたいと思っております。
⑦挫折した経験
面接官は、「挫折した経験」を聞くことで、応募者のストレス耐性やどんな困難に直面しても逃げないかどうかを判断しています。
企業は、挫折を味わっても、そこからどのようにして這い上がり会社に利益をもたらしてくれるのかを知りたがっているのです。
入社後の困難に対し逃げずに仕事に取り組める人材であることを証明するためには、何かしらの挫折を経験し、乗り越えたエピソードが必要になります。
Q:今までに挫折した経験はありますか?
A:私の挫折した経験は、部活の練習試合で靱帯を損傷し、大好きだったバスケ部をやめたことです。
小学生の頃から始め、中学まで大きなケガをしたことがなかったため、ケガへの意識に欠けていました。
このケガにより、レギュラーからはずれ活躍の場を失ったことから無気力になり部活動をやめてしまいました。
しかし、どうしてもバスケットが好きという気持ちはあったので、リハビリをし、高校では再びプレーに復帰することができました。
この挫折を経て、徹底したケガの予防や油断しない注意力を養うことができました。
御社へ入社した際にも、失敗しても、失敗から学んで自分を成長させるきっかけにできるよう努力したいと考えております。
⑧人生で一番頑張ったこと
「人生で一番頑張ったこと」の質問は、応募者の人柄を知り、入社後の活躍をイメージするためによく聞かれる質問なので、インパクトのあるエピソードを示し面接官の印象に残す必要があります。
「人生で一番頑張ったこと」の題材としてよく選ばれているのが、部活動やアルバイト、サークル活動や学業についてです。
「人生で一番頑張ったこと」の書き方で、選考の評価は180度変わると言っても過言ではないくらい重要な質問なのでよく考えておきましょう。
Q:あなたが人生で一番頑張ったことは何ですか?
A:私が人生で一番頑張ったことは、〇〇大学への受験勉強です。
私の成績は〇〇大学へ受かるには程遠い成績で周囲も諦めていました。
しかし、どうしても〇〇を学びたかったので〇〇が学べる〇〇大学へ進学したかった私は努力しました。
毎朝の2時間の勉強に加え、学校の授業が終わったら2時間図書館で勉強し、わからないところがあれば先生に質問して難問も克服しました。
往復2時間かかる通学の電車の中でも、単語帳を見たり、お風呂と寝る以外は勉強に明け暮れた結果高校3年生の時は学年でトップになり念願の〇〇大学に合格できました。
私は、目標に向かって努力する大切さを知り、達成した時の喜びを知ることができ涙が出るくらい嬉しかったです。
貴社に入社しても、目標に向かって努力し、成果を追求するため全力で取り組んでいきたいと考えております。
⑨5(10)年後のビジョン
面接で5(10)年後のビジョンを聞くのは、志望度の高さを見るためです。面接官は、応募者が入社後の未来をイメージできているかどうかを知りたがっています。
きちんと答えられれば志望度が高いと評価され、逆に答えられなければ志望度が低いと見なされてしまうでしょう。応募企業の理解を深め、企業が求める人物像をイメージした回答が好ましいといえます。
Q:5(10)年後はどうなっていると思いますか?
A:5年後には、1つのプロジェクトを任せてもらえるようなリーダー的存在になりたいと思っています。
そのためにも、技術者としてたくさんの経験を積み、様々なプロジェクトに携わりスキルを積み重ねていきたいです。
⑩最後の逆質問
面接の最後に、面接官から「何か質問はありますか?」と聞かれることがあります。この逆質問の意図は、応募者の疑問点を払しょくするためと、応募者の入社意欲を知るためです。
また、応募者の最後のアピールの場を提供する意図もありますので、アピールし損ねた方は、この時が最後のチャンスだと思い質問に答えましょう。
逆質問に対し、「特にありません」と答えてしまうと、志望度が低いと判断されかねませんので必ず答えを準備しておいて下さい。
Q:最後に何か質問はありますか?
A:社内のコミュニケーションを活発にするための取り組みはどのようにされていますか?
面接練習の注意点

面接練習の注意点を2つ紹介します。
①回答を準備しても暗記はNG
就活生の中には、面接の質問の回答を丸暗記しようとする方がいますが止めて下さい。回答を丸暗記してしまうと、棒読みしているかのように聞こえてしまい意欲や熱意が伝わってきません。
面接練習をする際には、質問に対する要点をまとめ、自分の言葉で臨機応変に組み立てられるように外せないキーワードを覚えておくことが大事になります。
②面接練習をゴールにしない
面接練習はあくまで練習に過ぎないので、練習したからと言って満足してはいけません。
面接練習のゴールは、練習することではなく「本命企業に合格すること」です。すなわち、本番で120%のパフォーマンスができるように面接練習する必要があります。
「今日は5回練習したから上出来!」ではなく、「前回の練習で表情が堅かったから今回は口角を上げてみよう」など実のある練習にしましょう。
面接練習をしっかりして内定を勝ち取ろう!

面接練習はできるだけ早くから始めましょう。面接練習をすることで、第三者から的確なアドバイスをもらえ早期改善し、本番の面接に役立てることができます。
面接練習のポイントは、「頻出問題の受け答えの練習」、「姿勢・表情・話し方」などの身だしなみを本番さながらに本気で行うことです。
練習相手のいる方もいない方も練習方法は10通りあります。面接で後悔しないためには、100%の準備をすること、すなわち面接練習を怠らないことです。
面接練習をしっかりして内定を勝ち取りましょう!

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









