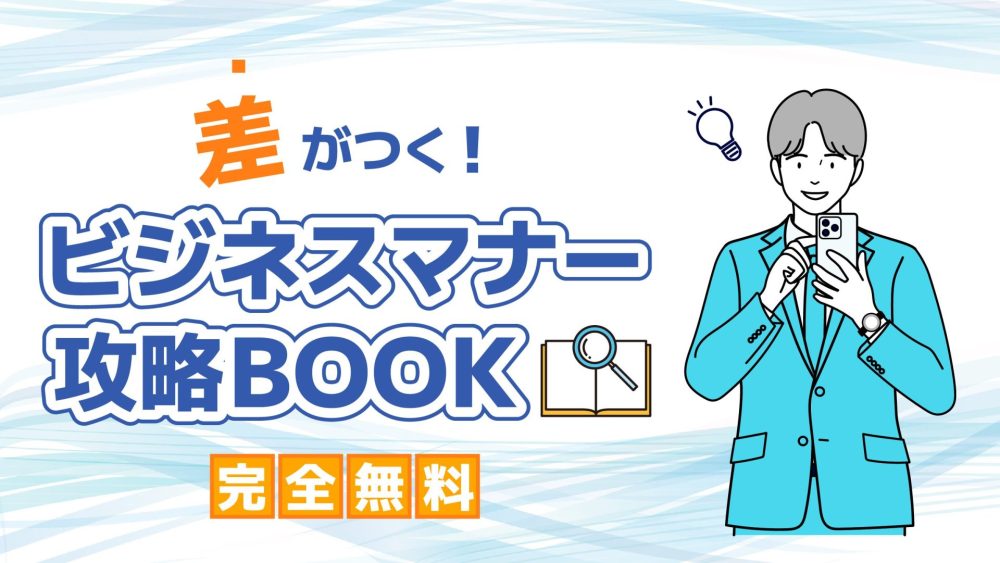就活生のみなさん、返信メールの書き方で悩んだことはありませんか?
採用担当者への返信は、自分自身をアピールし、好印象を与える貴重な機会です。しかし、どのような言葉遣いやフォーマットを選べば良いのか迷うこともあるでしょう。
本記事では、就活における返信メールの書き方と具体的な例文をご紹介します。正しいメールのマナーや書き方を学び、就活時の参考にしてくださいね。
メールテンプレで自動作成!
- ★メールテンプレ|3分でメール作成
- 煩雑なメール作成を自動で効率よく
- ★志望動機テンプレシート|簡単作成
- 4つの質問に答えるだけで志望動機完成
- ★自己PR自動作成|テンプレシート
- 自己PRを3分で簡単作成
就活の返信メールは自分で終わらせるのが基本
就活の過程では、企業からのメールが一斉送信であったり、返信不要と明記されている場合があります。また、送信専用のアドレスからのメールも返信の必要はありません。
しかし、これらは例外であり、基本的には企業からのメールには返信を行うべきです。返信を行うことで、自分がメールを確認し、内容を理解したことが企業に伝わります。これは、就活生としての基本的なマナーになります。
企業からのメールを受け取ったら、相手に対する敬意と、自分がメールを確認したことを示すために、その旨を伝えましょう。相手に対する感謝の意を示すとともに、自分がメールを受け取ったことを明確に伝えられます。
メールの内容を確認したことを伝えるためには、「○○を確認いたしました。」という表現が適切です。
就活の返信メールは届いたその日に送る

就活メールには、なるべく早く返信しましょう。遅くとも届いたその日のうちに返信するのがマナーです。
これはビジネスマナーの一部であり、迅速な対応は相手に対する敬意を示すとともに、自身の意欲や誠実さを伝えられます。逆に返信が遅いと印象も悪くなる可能性もあるため注意が必要です。
メールの内容が複雑で、すぐに返信できない場合も、一旦「メールを受け取ったこと」や「返信に時間がかかる旨」を伝えることで、相手に対する配慮を示しましょう。
遅れた場合はお詫びを添えてすぐ返信
万が一、返信が遅れてしまった場合は、まずはその事実を認め、お詫びの言葉を添えて返信しましょう。遅れた理由を具体的に説明し、同様の事態が再発しないように注意する旨を伝えてくださいね。
例えば、「大変申し訳ありません。メールの確認が遅れてしまいました。これからは定期的にメールの確認を行うように心掛けます」といった表現が考えられます。
早朝・深夜のメール送信は避ける
メールの返信は早いに越したことはありませんが、ビジネスシーンにおいて、早朝や深夜のメール送信は基本的に避けるべきです。これは、相手のプライベートな時間を尊重するという観点から重要なマナーとなります。
一般的に、ビジネスメールの送信時間は、午前9時から午後6時までが適切です。これは一般的な企業の業務時間に合わせたもので、この時間帯にメールを送ることで、相手が業務中に確認できます。
深夜にメールを確認した場合でも、返信は翌日の適切な時間帯に送るようにしましょう。
就活の返信メールの書き方を6つのステップで紹介

就活の返信メールに限らず、ビジネスメールは以下の6つの構成が基本です。この機会に覚えてしまいましょう。
①件名
メールの件名は、相手が一目で内容を把握できるように、簡潔かつ明確に書くことが重要です。用件、大学名(所属)、名前の順番で書きましょう。
用件は、「面接日程調整のお願い」や「選考辞退のご連絡」など、具体的な内容が伝わるような表現を心掛けましょう。
ただし、返信メールの場合は、相手から送られてきた件名をそのまま使用して「Re」で返すことが基本です。
②宛名
宛名は、「株式会社〇〇 人事部長 △△様」のように、正式な社名、部署名、役職、個人名の順に記述します。会社名・部署名などは省略せずに正確に書きましょう。
て下さいね個人名が不明な場合は、「人事部 御中」や「新卒採用ご担当者様」などと記載して下さいね。
③自分が名乗る
メールの本文を始める前に、自分が誰であるかを明示します。例えば、「お世話になっております。〇〇大学の◇◇と申します。」といった形で、自己紹介を簡潔に行いましょう。これにより、相手に自分が誰であるかを明確に伝えられます。
④用件
用件は、結論から簡潔に伝えましょう。長文になりがちな内容も、要点を押さえて短くまとめることで、相手にとって読みやすいメールになります。
⑤締めの挨拶
メールの最後には、締めの挨拶を必ず入れましょう。これは、相手への敬意を示すとともに、メールの終わりを明示する役割も果たします。「何卒よろしくお願いいたします。」など、簡潔に丁寧な表現を用いることが一般的です。
⑥署名
最後に、自己の所属と名前、連絡先を明記します。具体的には、所属、名前、電話番号、メールアドレスの順に記述しましょう。また、本文と署名部分を明確に区別するために、点線などを用いて署名だけを区切ると見やすくなります。
【6つのシーン別】就活の返信メールの例文

面接の日程調整などで、企業に質問された場合の返し方が分からない人も多いでしょう。そこで、シーン別に返信メールの例文を紹介します。ぜひ活用してください。
①面接日程の調整メール(企業が候補日を指定した場合)
面接日程の調整メール①
件名:面接日程について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
先日は面接日程の候補をご連絡いただき、ありがとうございます。ご提案いただいた日程の中から、7月15日(水) 14:00~を選ばせていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
ポイント解説
このメールでは、企業から提案された面接日程の中から選択し、その旨を伝えています。メールの冒頭では、自己紹介を行い、その後に日程の選択を伝える構成です。メールの最後には連絡先を明記し、企業からの連絡を待つ形にしています。
このように、自己紹介、日程の選択、連絡先の明記という順序で書くことで、企業側も理解しやすいメールになります。
②面接日程の調整メール(自分で候補日を指定する場合)
面接日程の調整メール②
件名:面接日程の提案について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
面接日程について、私の方から提案させていただきます。以下のいずれかの日程で面接を実施いただけますと幸いです。
①7月18日(土) 10:00~
②7月19日(日) 14:00~
③7月20日(月) 16:00~
ご都合をお伺いできますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
ポイント解説
このメールでは、自分から面接日程の候補を提案しています。自己紹介の後、候補日を列挙し、企業側の都合を尋ねる形になっています。ポイントは、なるべく時間に幅を持たせて提示することです。
また、連絡先を明記して企業からの返信を待つ形にしています。自己紹介、日程の提案、連絡先の明記という順序で書くことで、企業側も理解しやすいメールになります。
③面接後の日程変更・再調整の依頼メール
面接日程の変更依頼メール
件名:面接日程の変更依頼について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
先日は面接の機会をいただき、ありがとうございました。しかしながら、私事で恐縮ですが、予定していた面接日の変更をお願いしたく存じます。
新たに以下の日程を提案させていただきます。
①7月25日(土) 10:00~
②7月26日(日) 14:00~
③7月27日(月) 16:00~
ご都合をお伺いできますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
ポイント解説
このメールでは、面接後に日程変更の依頼を行っています。自己紹介の後、日程変更の理由を述べ、新たな日程を提案しています。ポイントは、日程が都合悪くなった理由を詳しく書かないことです。
また、連絡先を明記して企業からの返信を待つ形にしています。自己紹介、日程変更の理由と提案、連絡先の明記という順序で書くことで、企業側も理解しやすいメールになります。
④面接後のお礼メール
面接後のお礼メール
件名:本日の面接について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
本日は面接の機会を頂き、誠にありがとうございました。貴重なお時間を割いていただき、感謝申し上げます。
面接を通じて、貴社の強い組織力と社員一人ひとりの熱意を感じることができました。私の志望度は更に高まり、貴社で働くことへの意欲が増しました。
引き続き、最善を尽くして選考に臨みます。何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
ポイント解説
面接後のお礼メールは、面接官に感謝の意を示すとともに、自分の意欲を再度アピールする機会です。メールの内容は、面接のお礼を述べ、面接を通じて感じた企業の魅力や自身の意欲を具体的に伝えることが重要です。また、敬意を示すために、敬語を正しく使い、丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。
⑤内定の承諾メール
内定承諾メール
件名:内定の承諾について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
この度は貴社から内定を頂き、心から感謝申し上げます。貴社のビジョンに深く共感し、自身の力を発揮できると確信しております。
喜んで内定を承諾させていただきます。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
ポイント解説
内定の喜びを全面的に表明する
内定の承諾メールは、自分の意志を明確に伝える重要な一手紙です。内定を承諾する意志をはっきりと伝え、企業からの内定に対する感謝の気持ちを示すことが大切です。
また、自分が企業のビジョンに共感し、自分の力を発揮できるという意欲を伝えることで、企業側にも安心感を与えます。敬語の使い方や丁寧な言葉遣いを心掛け、プロフェッショナルな印象を与えましょう。
⑥内定の辞退メール
内定辞退メール
件名:内定の辞退について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
この度は貴社から内定を頂き、深く感謝しております。しかし、慎重に考えた結果、残念ながら内定を辞退させていただくことにいたしました。
貴社での経験は私にとって大変貴重で、多くを学ばせていただきました。この経験を生かして、今後の人生を歩んで参ります。
誠に申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
・ポイント解説
内定の辞退メールは、非常にデリケートな内容を伝えるため、慎重な表現が求められます。まず、内定を辞退する理由を具体的に述べる必要はありませんが、自分の決断を尊重してくれるようにお願いすることが大切です。
また、企業からの内定に対する感謝の気持ちを忘れずに伝え、選考過程で得た経験や学びについて触れると良いでしょう。これにより、企業側に対する敬意を示すことができます。
注意点は、企業の発展を祈らないことです。上から目線にとられる可能性があります。
就活の返信メールで注意したい3つのポイント

就活の返信メールは、上記のフォーマットで送れば基本的に問題ありません。しかし、他にも注意すべきポイントが3つあります。これは就職後も役立つビジネスマナーです。この機会にぜひ覚えてください。
①了解という表現は使わない
ビジネスメールでは、「了解しました」という表現は避けるべきです。なぜなら、「了解」は相手の意図や要求を理解したという意味であり、ビジネスの場では「承知しました」や「了承しました」の方が適切です。
「了解」は口語表現であり、目上の人に対しては使いません。ビジネスメールでは敬語を用いるべきです。したがって、「了解しました」ではなく、「承知しました」や「了承しました」を使いましょう。
②プライベートのメールアドレスを使わない
就活においては、プライベートのメールアドレスを使用するのは適切ではありません。
プライベートのメールアドレスは、その名前やドメインから個人的な趣味や好みが伺えることがあり、それが企業に対する印象を悪くする可能性があります。
そのため、就活用のメールアドレスを新たに作成し、そのアドレスを使用することをおすすめします。就活用のメールアドレスは、自分の名前や大学名を含めると良いでしょう。
③企業から返信が来ない時は自分のミスを確認後問い合わせ
土日をはさむ場合など以外の状況で3日以上企業から返信がない場合、まずは自分のミスがないか確認しましょう。
メールアドレスの打ち間違いや、送信先の間違い、返信が迷惑メールフォルダに入っていないかなど、自分で確認できる範囲でチェックします。
それでも返信がない場合は、再度メールを送り企業に問い合わせてみてください。ただし、問い合わせる際は、丁寧な言葉遣いを心掛け、自分の名前や問い合わせの理由を明確に伝えましょう。
メールでの問い合わせ例文
面接日程の問い合わせメール
件名:面接日程について(〇〇大学〇〇太郎)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇課 〇〇様
お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇〇学科の〇〇太郎と申します。
先日にお送りした面接日程調整のメールについて、まだ返信がないため、再度ご確認いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
——————————
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇太郎
携帯番号:000-0000-0000
メール:xxx@xxx.com
——————————
就活の返信メールでやってはいけないNG例3選
内定が獲得できたかどうかにかかわらず、就活生が企業に送る返信メールは重要なビジネス文書で、気を付けるべき点は多くあります。もちろん、やってはいけないNG例も。
ビジネスマナーに欠けていると思われると就活に悪影響なので、十分な注意が必要です。
ここでは特に注意したいNG例として、以下の3点を解説します。
①誤字脱字がある
誤字脱字があるメールは、社会人としてふさわしくありません。
誤字や脱字があると文章が読みづらいのはもちろん企業に対して失礼で、特に応募先の企業や担当者の名前を間違えるのは印象を大きく下げてしまいます。
誤字脱字がないかをチェックするには、音読がおすすめです。
眼だけで文字を追うよりも間違いを見つけやすいので、返信前に声に出してメールを読み上げてミスを徹底して排除しましょう。
②絵文字や顔文字が使われている
就活の返信メールでは、絵文字や顔文字の使用は厳禁です。
メールはビジネスシーンでの正式なコミュニケーション手段でのため、カジュアルな印象が強い絵文字や顔文字はふさわしくありません。
特に就活でのメールに絵文字を使用すると、学生気分が抜けてないと思われたり、社会人になる心構えができていないと思われます。
入社後は社員間のやり取りに絵文字や顔文字が使用されるケースもまれにありますが、就活中は使用せずに真剣に臨みましょう。
③相手に手間取らせる内容になっている
忙しい相手に手間を取らせる内容になっているのも避けるべきNG例です。
たとえば必要な情報を記載せずに「詳細は電話でお伝えします」といった曖昧な表現を使うのは適切ではありません。
また、添付ファイルの開き方を聞いたり一度通達された内容を聞き返したりと、調べればわかることを尋ねるのも厳禁です。
相手の負担を軽減する配慮は社会人に求められるスキルなので、余計な手間をかけさせない内容に仕上げてください。
就活の返信メールを読みやすくするポイント3選
就活の返信メールは、単に必要な情報を網羅しているだけでは不十分です。
企業に良い印象を与えるには、読みやすさにも目を向けてください。
ここでは就活の返信メールの読みやすさをアップさせる方法として、以下の3点を解説します。
①適切に改行や段落分けをする
返信メールの文章は適切に改行や段落分けするよう意識すると、読みやすさに差が生まれます。
一文が長くダラダラと続く文章は読む気を削いでしまううえ、段落分けがされていないとどこで文章が区切られているのかわかりません。
人事担当者は日々数多くの応募者からのメールに目を通しているため、パッと見て内容が理解できる読みやすい文章で返信しましょう。
②文字に装飾を加えない
就活の返信メールは、文字に装飾を加えずに作成しましょう。
特に太字や斜体、アンダーラインを多用するとかえって重要な部分が分かりにくくなるうえ、相手のデバイスによっては文字化けする懸念もあります。
就活の返信メールは文字の装飾よりも、内容そのものの方が大切なので不要な装飾は避けるべきです。
メールの目的を明確にし、装飾なしの文字だけで的確に伝える意識が就活の返信メールにおいて重要と言えます。
③過剰な挨拶をしない
過剰な挨拶は、就活の返信メールを読みづらくする一因です。
丁寧さを示そうとして長々とした挨拶文を加えるとかえって読み手に負担をかけるので、冒頭では簡潔な挨拶に留めましょう。
たとえば「お世話になっております」や「ご連絡ありがとうございます」と簡単に挨拶をした後にすぐに本題に移れば、要点を明確に伝えられます。
また過剰な礼儀表現は、ビジネスの場においては逆効果になってしまうため、端的でストレートな表現を心がけてください。
就活の返信メールのマナーを守って内定に繋げよう
就活における返信メールは、あなたのプロフェッショナリズムとコミュニケーション能力を示し、企業との良好な関係を築く重要な手段です。
まずは、迅速かつ丁寧に返信しましょう。メールのフォーマットや言葉遣いにも気を配り、ビジネスライクなスタイルを保ちましょう。また、相手への感謝の気持ちを忘れずに表現し、丁寧な敬語を使用することも大切です。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。