就活の選考時にSPIを活用する企業は多いですが、選考通過のボーダーラインはどのくらいなのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
希望する企業のボーダーラインを知っておけば目標も立てやすく、勉強もスムーズに進みます。SPI対策にどれくらい時間をかけるかの判断基準にもなるため、ぜひチェックしておきましょう。
この記事では、SPIの形式別のボーダーラインについて詳しく解説します。効率的な勉強法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
SPIにもボーダーラインが実在する

一定レベル以上の就活生を効率的に絞り込むために、多くの企業はSPIにボーダーライン(合格基準)を設定しています。基本的に大手企業ほどボーダーラインが高く、足切りされやすいでしょう。
一般には正答率が7割以上であれば選考を通過できると言われていますが、企業によっては8~9割がボーダーラインの場合もあります。
希望している企業のボーダーラインを見極め、早いうちにSPI対策を始めましょう。
[形式別]SPIテスト3つのボーダーライン

SPIテストにはWebテスト・テストセンター・ペーパーテストの3つの受検形式があり、出題傾向がそれぞれ少し違います。ここでは各形式ごとのボーダーラインを詳しく解説するので、ぜひ対策に役立ててください。
- Webテストのボーダーライン
- テストセンターで受けるSPIのボーダーライン
- ペーパーテストのボーダーライン
①Webテストのボーダーライン
WEBテストは自宅や学校のパソコンで受検できるSPIで、比較的難易度が高いのが特徴です。1問ずつに解答時間が設定されており、制限時間を過ぎると強制的に次の問題に進みます。
Webテストのボーダーラインは6~7割です。無事に選考を通過するには、7割の正答率を目標にするとよいでしょう。
テスト内容は言語・非言語・性格に関するもので、中学~高校レベルの難しい問題も出題されます。解答は選択式ではなく入力式であることが多く、十分な対策が必要です。
②テストセンターで受けるSPIのボーダーライン
テストセンターは専用の会場で、試験監督者の監督のもと受検するのが特徴です。今はオンラインでも受験できますが、専用システムに接続し、Webカメラを通して本人確認などを行います。
テストセンターで受けるSPIのボーダーラインは7割です。8割の正答率を目指して受検すると、選考通過の可能性が高くなるでしょう。
受検者の正答率に合わせてコンピュータが問題レベルを調整するなど、一般的なテストとは違う点も多いので要注意。必ず対策を徹底してから受検しましょう。
③ペーパーテストのボーダーライン
ペーパーテストは応募先の企業で受検する形式で、一般的にはマークシート方式で行われます。
ペーパーテストのボーダーラインは7割前後です。企業によっては8割の正答率が求められるので、事前に十分な対策をして高得点を目指しましょう。
試験会場は企業の会議室などを使用するため、訪問時の態度に失礼がないよう気を配る必要があります。消しゴムのカスやゴミなどを放置して、印象を下げないように注意しましょう。
SPIテストの勉強法3つ
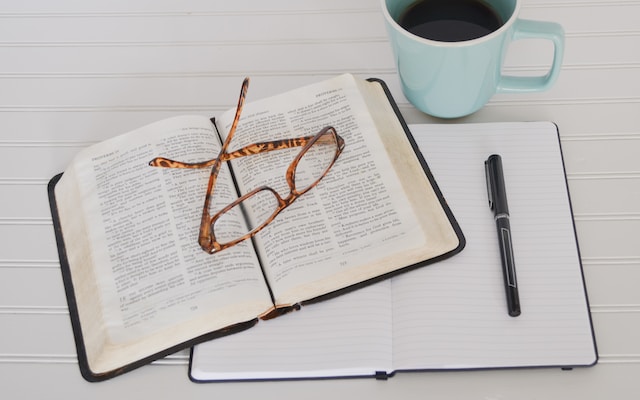
SPIのスコアがなかなか上がらないという人は、一度勉強方法を見直してみましょう。ここでは、効率的なSPIテストの勉強法を3つご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 問題集を何周も解く
- 悩んだらすぐ解説を見る
- 本番同様に時間を測ってみる
①問題集を何周も解く
SPIの出題傾向をつかむためには、1冊の問題集をくり返し何周も解くのがおすすめです。いろいろな問題集を何冊も使うよりも、効率的にSPIの問題に慣れることができます。
同じ問題をくり返し解いて、問題のパターンと解き方をセットで覚えてしまいましょう。
また、問題集は自分に合ったものを選ぶのもポイント。例えば、図書館やカフェで勉強したい人はコンパクトな問題集を選ぶと持ち運びに便利です。
テストまで時間がない人は短期集中型の問題集を選ぶなど、自分の状況や好みに合ったものを選びましょう。
②悩んだらすぐ解説を見る
勉強を始めたばかりの頃は、解答がなかなか出せない問題も多いでしょう。もし解き方がわからない時は、すぐに解説を見る癖をつけましょう。
わからない問題に悩み続けていると時間を浪費してしまい、効率が良くありません。まずは解説を見ながら解いてみて、正しい解き方を覚えましょう。
自信のない問題が多い人は、解説が詳しい問題集を選ぶのがおすすめです。
③本番同様に時間を測ってみる
問題を解く時は、本番と同じように時間を測りましょう。どの問題にどれくらい時間がかかるのか把握しておけば、制限時間内に終わらないといった失敗も避けられます。
例えばペーパーテストの場合、制限時間は70分で出題数は70問です。単純計算すると1問1分の時間配分ですが、苦手な問題だと1分以上かかることも。
普段から時間を測って問題を解くことで、本番でも上手に時間配分ができるでしょう。
SPIのボーダーが高い・低い企業の特徴
SPIのボーダーが高い・低い企業にはどんなものがあるのか、あらかじめ把握しておくのも大切です。
ここでは、SPIのボーダーラインが高い企業と低い企業の特徴を解説します。具体的な企業名もいくつかご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
①ボーダーが高い企業
SPIのボーダーラインが高い企業では、人柄よりも能力の高さを重視する傾向にあります。例えば、ボーダーラインが高い企業は次の通りです。
<90%>
- 日本銀行
- 外資系戦略コンサル
<89%>
- 外資系金融機関
- 三菱総研
- 野村(IB)
- 政策投資銀
<88%>
- みずほ(GCF)
- 電通
- 博報堂
<87%>
- 三井物産
- 三菱商事
とくに金融系や大手総合商社は、ボーダーラインが80~90%と高めです。また、人気企業も書類選考でできるだけ応募者を絞り込む必要があるため、SPIのボーダーラインが高く設定されます。
ボーダーラインが高い企業を目指す人は、SPIのスコアで足切りされないように十分な対策が必要です。
②ボーダーが低い企業
SPIのボーダーラインが低い企業は、面接時の評価や人柄を重視しているのが特徴です。例えば、次の企業はSPIのボーダーラインが7割前後に設定されています。
- 住友生命
- 損保ジャパン
- 明治安田生命
- 森永製菓
- ハウス食品
- ユニチャーム
- りそな
これらの企業は、学力の高さよりもどれだけ自社にマッチした人材かを重視している傾向があります。SPI対策とともに、面接やグループワークなどの対策も入念に行うようにしましょう。
ボーダーを超えるためにSPIの対策は怠らないようにしよう

SPIのボーダーラインは企業によって違うため、応募先のボーダーラインがどれくらいなのか事前にきちんと把握しておくことが大切です。
いくら高学歴でも、企業が設定したボーダーラインを超えないと選考を通過できない可能性があるので要注意。
また、SPIの形式によって出題傾向や解答方法が大きく違うので、自分が受検するテスト形式を確認してしっかり対策をしましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









