ほとんどの大企業は学生たちに対し、事前に筆記試験や適性検査を受けさせます。筆記試験で高得点が獲れるだろうかとそわそわした経験、皆さんもありませんか?
企業側が試験会場を用意するケースがある中、テストセンターで受験するパターンもあります。
本記事ではテストセンターで受験を行う際の流れから、受験の注意点、概要を解説していきますね。
テストセンターとは適性検査「SPI」を受ける手段のひとつ
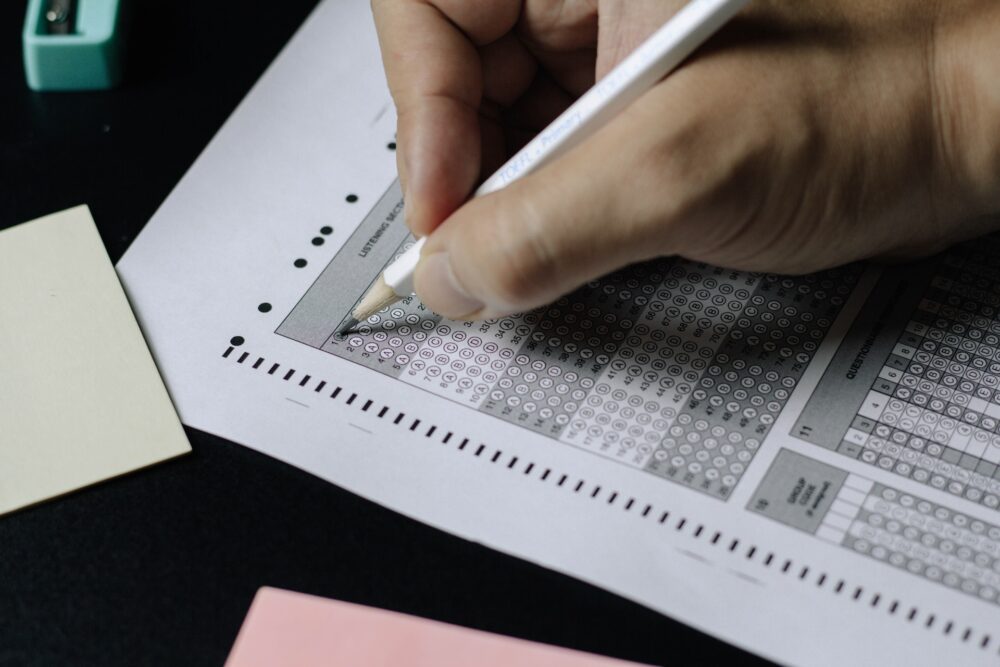
テストセンターとは、「SPI」と呼ばれる適性検査を受ける専用の受験会場のことです。SPIの受検は、基本的に志望先の企業から受験案内メールが届いていた場合に行うことになります。
テストセンターで一度受けた試験の点数は、複数の企業に使い回すことも可能なのが特徴です。
また、企業によっては、テストセンターではなく自社の会議室などでの受検となることもあり、その場合はテストセンターの出番はありません。
SPIは性格検査と基礎能力検査の二段階に分かれており、このうちテストセンターで受検を行うのは基礎能力検査のみとなっています。
後ほど詳しく解説しますが、性格検査は自宅で事前に完了させる必要があります。
SPIが受けられるテストセンターの場所は?

テストセンターには、大きく分けてリアル会場とオンライン会場の2種類があります。
受検の期間は企業によって指定されますが、受検会場は自身の都合に合わせて選択可能です。自宅と試験会場、どちらがより集中できるかで選ぶのもよいでしょう。
以下で、それぞれの会場について詳しく解説します。
リアル会場
リアル会場は、全国7都市(東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡)に常設されています。
会場まで足を運ぶ必要がありますが、オンライン会場と違いパソコン等の受検環境を自分で整える手間がありません。
また、新卒採用のピーク時期には臨時のリアル会場が設置されます。
リアル会場の場所は公式ページで確認できるので、アクセスしやすい会場を選んで受検しましょう。
オンライン会場
オンライン会場では、自宅などから自身が用意したパソコンで受検することになります。
交通費を節約できたり、スケジュールに柔軟に対応できるのがオンライン会場のメリットです。
リアル会場では監督者が試験の様子を直接確認しますが、オンライン会場ではWEBカメラを通じて監督が行われます。
そのため、インターネット環境はもちろん、ウェブカメラ付きパソコンや受検に適した環境を自身で整えなくてはならない点には注意しましょう。
テストセンターで受験するときの流れ
ここからはテストセンターで実際に受験する流れについてご紹介しています。
- 企業から届いた受験案内メールを確認
- 会場と日時をネットで予約
- 事前に性格検査を受ける
- 能力検査をテストセンターで受験する
それではテストセンターを利用する際の、一連の流れを解説していきますね。
①企業から届いたメールを確認
まず最初は、企業から送付された、テストセンターでの受験案内メールを確認しましょう。
そもそも、SPI試験を受ける方法はさまざまあり、必ずしもテストセンターで受けるとは限りません。志望企業から「テストセンターで試験を受けてください」というメールが来るはずです。
メールには「〇日までにテストセンターで試験を受けること」という旨の記載があります。それに合わせて就活のスケジュールを調整し、何日までに受けるべきかを決めましょう。
また、過去にテストセンターで適性検査を受けていて、点数に不満がなければ、指定された日までに結果を送信すれば問題ありません。
②会場と日時をネットで予約
次は、テストセンターの会場や日時をネットで予約することです。
テストセンターの会場は通年で設置されている会場と期間限定で設置されている会場、そして、オンライン会場があります。
会場や時期によって予約が取りにくいケースがあるため、就活のスケジュールに合わせてネットで予約を行っていく流れです。
一方で、この段階での予約はあくまでも「仮予約」なので、性格検査を受けることで正式な予約となります。
③事前に性格検査を受ける
次に行うのは、前もって性格検査を受けておくことです。
事前に性格検査を受ける理由は先ほどもご紹介した通り、仮予約から本予約にするため。
性格検査に関してはパソコンやスマホからでも受験ができるため、テストセンターでの受験前に済ませておきましょう。
スマホの場合は最新のOSにアップデートをしておいて、正しく表示されるようにしておくことをおすすめします。
④能力検査をテストセンターで受験する
いよいよ、能力検査をテストセンターで受験していく段階です。
事前に予約を行った会場・日時を確認し、テストセンター会場に行って受験を行います。
会場によってはビルの中にあり、会場までの経路がわかりにくいこともあるため、受付で聞きましょう。
慌てることなく、予約した時間の15分ほど前までに到着するぐらいの余裕が必要です。
テストセンターで受験する際の注意点4つ

ここからは、実際にテストセンターで受験する場合の注意点を4つご紹介していきます。
- 受験案内が届いたら素早く予約
- 持ち物を確認
- 腕時計は持ち込み禁止
- 性格検査を先に受けること
初めて受験をする時は緊張をすることもあるので、事前に確認しておきましょう。
①受験案内が届いたら素早く予約
1つ目は、テストセンターの受験案内が届いたらなるべく早く予約を済ませることです。ギリギリになってから動いても大丈夫だろうと考えるのはやめましょう。
就活シーズンは企業も学生も一気に動くため、採用活動が集中する時期は予約が取りにくくなります。
テストセンターの受験案内が届き、提出期限が決まっていた場合、1日でも早く予約を行い、もう1度受け直す余裕があるぐらいがちょうどいいでしょう。
テストセンターで試験を受けるメリットは、やはり何度でも受験が可能なところです。受験費用もかからないため、早めに一度受けてみて、手ごたえがなければ再度試験を受けましょう。
②持ち物を確認
2つ目は、テストセンターに持っていく持ち物を確認しておくことです。
持ち物に関しては後ほどご紹介しますが、リアル会場では筆記用具やメモ用紙は会場で用意されているので、本人確認書類と受験票さえあれば問題ありません。
ただ会場までの道すがらでSPIの勉強をしたい場合は参考書を持参し、ロッカーがある会場であれば参考書などを前もって預けた上で適性検査に挑みましょう。
③腕時計は持ち込み禁止
3つ目は、腕時計の持ち込みは禁止ということです。
多くの試験で持ち込みが可能なため勘違いされがちですが、SPIでは不正防止のため持ち込み不可となっています。
SPIは1問にかけられる時間が決まっており、回答時間を過ぎると強制的に次の問題に切り替わる仕組みです。時間の目安は画面右上のインジケーターで確認でき、時計を見る必要がない設計になっています。
試験会場まで腕時計を着用していくのは構いませんが、試験が始まる前に外してしまっておきましょう。
④性格検査を先に受けること
3つ目は、適性検査を受ける前に性格検査を受けておくことです。
性格検査を受けないと適性検査の正式な予約が取れないため、必ず性格検査を受けなければなりません。
性格検査で注意したいのは、仮予約が決まった日から翌日の午前3時までが受験のタイミングである点です。
受験忘れは単に予約がキャンセルされるだけですが、予約が埋まりやすいタイミングだったらもう1度取り直さなければならないので、こちらも素早く受けておきましょう。
SPIテストセンターで必要な持ち物と準備

ここでは、SPI試験をテストセンターで受ける際に忘れたくない持ち物について解説します。
リアル会場とオンライン会場で必要な準備が異なるので注意してください。
リアル会場の場合
リアル会場で必ず持っていくべきなのは、受験票と身分証明書です。筆記用具等は会場で貸し出されるため、持ち込む必要はありません。
| 持参するもの | 印刷した受験票・顔写真付き身分証明書 |
| 貸し出されるもの | 筆記用具・メモ用紙・ヘッドホン |
受験票は、スマートフォンの画面等ではなく印刷したものが必要になります。
ただし、印刷できない場合は、テストセンターID・氏名(カナ)・検査名・会場名・日程・タームをA4サイズの白紙にメモして持参すれば問題ありません。
オンライン会場の場合
オンライン会場で受検する場合、受験票は必要ありません。用意が必要なものは以下の通りです。
| 用意するもの | ・顔写真付き身分証明書 ・ウェブカメラ付きパソコン ・筆記用具(ボールペン不可) ・メモ用紙(A4用紙2枚まで) |
本人確認書類はコピー不可、顔写真付きで有効期限の切れていないものを用意してください。
また、受検にはウェブカメラ付きのパソコンを使用します。スマートフォンなどのタブレット端末は私用できないため注意が必要です。
対応している動作環境について、詳しくは公式であるリクルートが提示している、テストセンターに関するよくある質問を参照してください。
SPIを受ける前に知っておきたいこと2つ

ここでは、テストセンターや準備物のほかに知っておきたいSPIの特徴について解説します。
- 受験科目は企業によって異なる
- 受検結果は他企業にも使いまわせる
受験科目は企業によって異なる
テストセンターで受けるSPIの受験科目は、志望する企業によって異なります。
「性格検査」「基礎能力検査(言語/非言語)」「英語能力検査」「構造的把握力検査」のうち、主には性格検査と基礎能力検査が実施されることが多いようです。
しかし、一部企業では性格検査のみを実施することもありますし、外資系企業では英語検査が加わったりします。
志望する企業がどの科目の検査を行うかを事前に確認して、それに合わせた対策を進めておきましょう。
受検結果は他企業にも使いまわせる
企業によっては再受験を求められることもありますが、テストセンターで受けたSPIの受検結果は受検後1年間使いまわすことができます。
ただし、WEBテスティングの結果は使いまわせませんので注意してください。
使いまわすことで受検の手間を省き、選考を効率的に進めることができますので、テストセンターで納得のいく結果が出せた人はそれを提出してもよいでしょう。
しかし、「SPIの受検結果は知らされない」ということには注意が必要です。
受検結果は知らされない!点数はどうやって確認する?
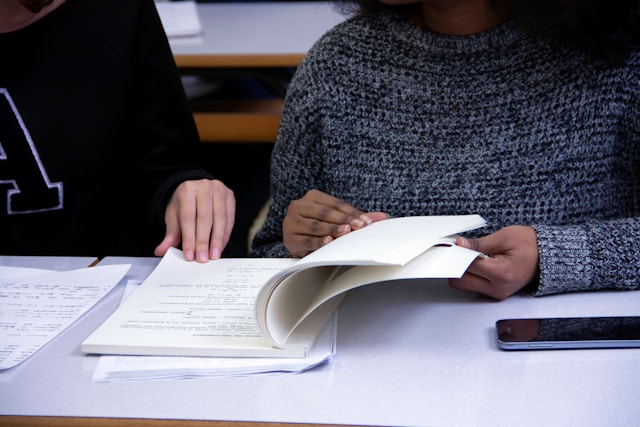
先述の通り、SPIの受検結果は教えてもらえません。そこでこの章では、点数や合否の手ごたえを確認する方法を3つ紹介します。
- 自己採点する
- 出題の難易度から推測する
- 企業ごとの足切りラインを把握しておく
A社の足切りラインには届いていても、B社の足切りラインには届いていない可能性もありますので、使いまわしを検討している場合は以下を参考にしてください。
①自己採点する
1つは内容を覚えておく、またはメモを取っておいて、受検後に自己採点をするという方法です。
受験中はメモ用紙を利用できますが、テストセンターで利用したメモ用紙は持ち帰れません。
WEBテスティングで受検した際はメモが手元に残りますが、テストセンターで受検する場合は覚えておくしかないでしょう。
②出題の難易度から推測する
2つ目は、出題の難易度から正答率を推測する方法です。
SPIは、正解すれば次はより難しい問題、不正解ならば同等の難易度か少し簡単な問題が出される仕組みになっています。
そのため、「一定の正答率を越えなければ出題されない問題」というのがいくつかあります。
例えば言語分野では「長文問題が出る」、非言語分野では「複数タブ問題が続く・推論にチェックボックスが出る」などが高得点の目安です。
③企業ごとの足切りラインを把握しておく
企業ごとの足切りラインを把握しておくのも、自分の得点を知る手掛かりになります。
まずは自身が志望する企業の足切りライン、そしてそのワンランク上に足切りラインが設定されている企業を調べてください。
そのワンランク上の企業でSPIを受検し合格したものは、志望する企業に安心して提出することができます。
多くの場合、8割の正答率が求められる企業を通過したSPIの結果は、多数の企業で使いまわすことができるでしょう。
不正受検(カンニングや替え玉受検)はその場で受検中止

万が一SPIで不正が発覚した場合、その場で受検中止となります。
SPIで落ちてばかりだと、カンニングや替え玉受検を考える人もいるかもしれません。
しかし、SPIは就活生が公平に受検できるよう、本人確認や持ち物の取り締まりを徹底しています。
テストセンターでは監督員が巡回しますし、WEBテスティングでも常に監視の目が向けられています。不正と受け取られる行為は、絶対にしないようにしましょう。
テストセンターで受験する人は早めに予約を済ませよう

テストセンターを初めて利用する場合、素早く仮予約を済ませて性格検査を受けることを心がけましょう。仮予約だけだと性格検査を受け忘れてキャンセルになってしまうからです。
また、できればリアル会場で受け、緊張感のある中で受験することをおすすめします。
不正をすれば、企業側に連絡が入るため、不正は絶対にやめましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









