【就活生必見】適性検査10種類を紹介|行う目的や実施方式も解説
就活対策として書類選考や面接と共に考えなくてならないのが、「適性検査」の存在ですよね。
しかし実際に対策をするとなっても、「適性検査ってそもそも何?」「どんな種類があるの?」と分からないことも多くあるのが実情でしょう。
そこで本記事では、適性検査とは何か、実施方式や種類などについて幅広く解説します。
適性検査について気になっている方は、ぜひとも対策にお役立てください。
全て無料!ES作成に役立つツール
★ES自動作成ツール
AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
★志望動機テンプレシート
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機をカンタンに作成できる
★自己PR作成ツール
最短3分で、受かる自己PRを作成できる
適性検査とは|意味を確認

適性検査とは、人材がその職務に対してどれだけ適性を持っているのか判断するための検査です。
新卒採用はもちろん、中途採用や配属先の検討など幅広い場面で使用されますよ。
学力テストのような印象を持っている方もいるかもしれませんが、適正検査で見るのはあくまでも「適性」です。
学力や知能だけではなく意欲や価値観などさまざまな側面から、1つの職業や行動に対する適正を判断するために行います。
多くの企業が利用しているSPIをはじめとして、玉手箱やGAB・CABなど適性試験の種類は多種多様ですよ。
適性検査を行う目的3つ

ここでは、適性検査を行う目的について解説します。適性検査の主な目的は、以下の3つです。
①企業とのミスマッチを防ぐため
適性検査を行う目的としてはまず、企業とのミスマッチを防ぐことが挙げられます。
ミスマッチを防ぐことは、就活生側にとってはもちろん、早期離職を避けたい企業側にとっても重要なポイントだと考えられます。
検査結果を受けて自社の社風にマッチした人材かどうか判断することで、入社後にミスマッチが発生するケースを回避できるでしょう。
②人物特性を可視化するため
その人材の特性を可視化することも、適性検査を実施する大きな目的の1つです。
その人材の考え方や価値観は書類選考や面接でも一定は把握できますが、的確な言語化やデータ化までは難しいでしょう。
適性検査であれば、人材の特性を客観的に評価・把握可能です。
適性検査によって書類審査や面接では判断しにくい就活生の資質を見極めることで、自社で活躍できる人材の選定に役立ちます。
③基礎能力を数値化するため
適性検査を実施する目的としては、基礎能力の数値化も挙げられます。能力を数値化できれば、採用の判断材料にしやすいと考えられるでしょう。
就活生同士の比較も、数値であれば行いやすいと言えます。自社の応募者だけでなく、同じ検査を受けている応募者すべてとの比較も可能です。
また、同じ検査を繰り返し取り入れ続けることで、過去のデータを次回以降の採用活動に活かせるでしょう。
適性検査の実施状況

適性検査について調べる中で、「現在の実施状況はどの程度なのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
訂正検査対策を考えるにあたっては、現在の実施状況を把握することも大切です。
株式会社リクルートのデータによると、就職活動プロセスとして「適性検査・筆記試験を受ける」と答えた2023年卒就活生は59.0%でした。
(引用元:株式会社リクルート『就職白書2023』)
つまり、全体の約6割の学生が適性検査を受ける予定を立てていたことが分かります。就活においては、適性検査を受ける機会は多いと考えておくべきでしょう。
適性検査の種類2つ
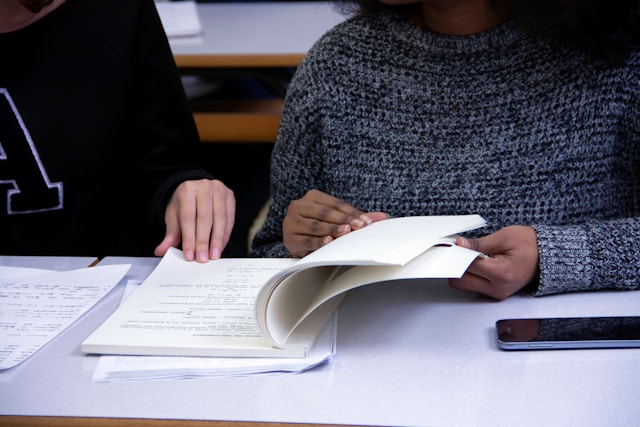
ここでは、適性検査の種類について以下の通り解説します。
①能力検査
能力検査とは、業務を遂行する上で求められる広い意味での学力(知的能力や思考力、そして一般常識)に関する検査です。
能力検査は、以下の3つに分けられます。
- 言語分野:文章や言葉の意味・趣旨の理解力を測る
- 非言語分野:数的処理や論理性に関する能力を測る
- 英語能力:英語能力を測る
上記の内「言語分野」と「非言語分野」の2つが中心になるケースが多く、英語能力に関する検査は実施されないこともあります。
②性格検査
性格検査は、人材の考え方や価値観などを可視化する検査です。ただしあくまでも特徴の分析が目的であり、性格の「良し・悪し」を見るものではありせん。
考え方の特徴や人間性を把握し、自社の風土や業務内容との相性を確認するために行います。
設問内容は比較的シンプルであることが多く、「はい・いいえ」の二択で答えるような問題が中心です。
自分を良く見せようと回答で嘘をつくケースも散見されますが、企業とのマッチングを把握するものであるため素直に応えるのが最適でしょう。
適性検査の実施方式4選
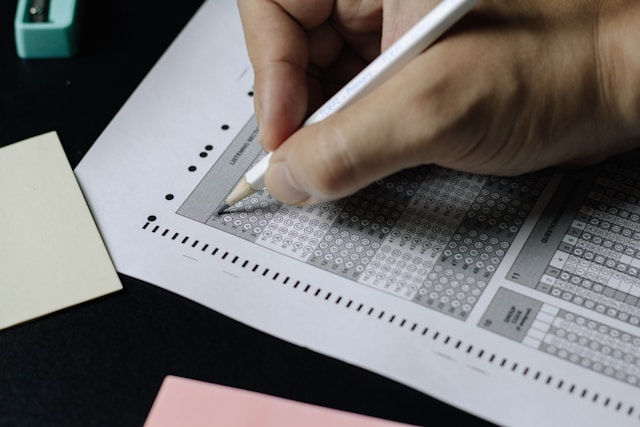
ここでは、適性検査の実施方式として以下の4つを紹介します。
①ペーパーテスト
ペーパーテストとは、企業が指定する会場で受検する方式です。企業が用意した会場や、企業自体の中で受検を受けるケースが考えられます。
ペーパーテストには記入式もありますが、集計のしやすさからマークシート式を選択するケースが多数です。
試験官による監督があることから、不正リスクが低い方式だと言えます。しかし会場の準備や運営が必要であり、企業の負担は大きくなると言えるでしょう。
②自宅受験型Webテスト
自宅受験型Webテストは、自宅やその他任意の場所にてパソコンからオンラインで受験するテストです。
企業側にとっては、会場を用意・運営する必要がないためコストや時間の削減につながる点が大きなメリットですよ。
受験者にとっても、時間や場所を問わず都合の良いタイミングで受けられる点は魅力的でしょう。
ただし任意の場所で受けられることから不正リスクが高く、身代わり受験には注意が必要です。
③インハウスWebテスト
インハウスWebテストとは、企業が用意した会場で用意されたパソコンを使って受けるテスト方式です。
同じように会場で試験を受けるペーパーテスト方式と比較すると比較的コストが低く、不正リスクも抑えられる点が特徴的だと言えます。
デジタルにテスト結果を集計できることから、集計・分析にかかる時間を押さえられる点も魅力的でしょう。
ただし会場の準備や設営、日程調整、パソコンの準備などに手間やコストがかかる点は、インハウスWebテストの注意点だと考えられます。
④テストセンター
テストセンターとは、全国に設置されている「テストセンター」と呼ばれる会場で受検する方式のことです。
テストセンターで用意されているパソコンを使って受験することから、企業側は会場を用意する必要がありません。
適性検査実施にかかる手間や時間を削減したいのであれば、テストセンターの利用は合理的だと考えられます。
ただしテストセンターに適性検査を委託する必要があることから、コストがかかる点は注意点です。
主な適性検査10選

ここでは、主な適性検査の種類を紹介します。現在行われている適性検査は、主に以下の10種類です。
| 出題範囲 | 試験時間 | 実施方式 | |
|---|---|---|---|
| SPI3 | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | テストセンター WEBテスト65分 ペーパーテスト110分 | ペーパーテスト Webテスト テストセンター |
| 玉手箱 | 能力検査(言語・非言語・英語) 性格検査 | 45分 | ペーパーテスト Webテスト |
| GAB | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 90分 | ペーパーテスト Webテスト |
| CAB | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | WEBテスト72分 ペーパーテスト95分 | ペーパーテスト Webテスト |
| Compass | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 20分 | ペーパーテスト Webテスト |
| 内田クレペリン | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 50分 | ペーパーテスト Webテスト |
| tanΘ | 能力検査(言語・非言語・英語) 性格検査 | 能力検査各15分 性格検査15分 | ペーパーテスト Webテスト |
| DATA-OA | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 能力検査各45分 性格検査20分 | Webテスト |
| CUBIC | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 20分〜 | ペーパーテスト Webテスト |
| DII | 能力検査(言語・非言語) 性格検査 | 50分 | ペーパーテスト |
上記の中でも特にSPIを採用している企業が多く、中小企業から大企業まで幅広い就活の場面において受験する機会があると想定されます。
ただしどの適性検査を利用するのかは、あくまでも各企業が選択するものです。
そのため就活生は、自分の志望企業がどの適性検査なのか事前にチェックしましょう。
またそのほかでは、玉手箱やGAB、CABなども比較的採用されるケースが多いと言えますよ。
適性検査を行うタイミング4つ

ここでは、適性検査を行う主なタイミングとして以下の4つについて解説します。
①書類選考後
適性検査を行うタイミングにはまず、書類選考実施後が挙げられます。書類選考でふるいにかけた候補者を、適性検査によってさらに絞り込むことが可能です。
また、面接を実施する前に適性検査を行っておくことで、応募者の情報をより多く得た状態で面接を実施できますよね。
面接を適性検査の結果をフィードバックするような形式で進めていくことで、応募者の情報をより深く集められるでしょう。
ただし応募から面接の実施までに一定の時間が必要となることから、応募者が他企業に流れてしまうリスクはあります。
②面接時
適性検査の実施時期には、面接実施と同時のタイミングも考えられます。
面接と適性検査を同日に行うことで日程を短縮でき、会場説明・調整のコストや手間を押さえられる点がメリットです。
書類選考と面接の間に適性検査をはさむ必要がないことから、応募者の流出を抑えることも考えられるでしょう。
ただし書類選考後に応募者を絞る効果は期待できず、その分面接対象の候補者が多くなる可能性は考えられます。
③一次面接後
一次面接実施後に、適性検査を行うパターンも考えられます。
一次面接を通過した候補者に対して実施することから、対象者のモチベーションを保ったまま実施できる点が特徴的です。
既に候補者の人数を一定程度減らした状態で実施することから、実施にかかるコストを抑えられる点はメリットだと言えるでしょう。
また、就活生の目線ではこの時点で適性試験を理由として足切りされる可能性は低いと考えられます。
④最終面接後
適性検査を実施するタイミングとしては、最終面接後も候補に挙げられます。
最終判断の材料にする目的だけでなく、内定後のフォローや入社後の人事情報としての活用なども考えられる点が特徴的です。
また、受験者が必然的に限定的になることから、実施にかかるコストは大きく抑えられるでしょう。
ただし採用の最終局面においての実施になることから、候補者の削減効果は期待できないと考えなくてはいけません。
適性検査は種類ごとに対策を立てて受けよう

適性検査とは、人材の知的能力や考え方、価値観などを把握できる検査です。
適性検査には実施方式やテストの種類などにおいてさまざまなパターンがあることから、応募先企業が何を選択しているのか確認して対策を立てるべきでしょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









