公務員試験には、マークシート方式の試験以外にも論文試験が課せられるケースがあります。しかし、なにを書いたらいいかわからず困る人も多いでしょう。
本記事では、公務員試験の論文を書く方法や対策法を解説します。
どのような対策をしておけばいいか確認し、安心して公務員試験に臨みましょう。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員試験の論文とは?
公務員試験の論文とは、主に公務員として必要な考察力や表現力、課題解決能力を評価するための試験の一部です。
受験者は与えられたテーマに対し、自身の考えを論理的に整理し、分かりやすく伝えることが求められます。
論文の内容には時事問題や行政課題、社会問題等が含まれることが多く、受験者の視野の広さや公務員としての適性も見られます。
まず確認!公務員試験の論文がある理由
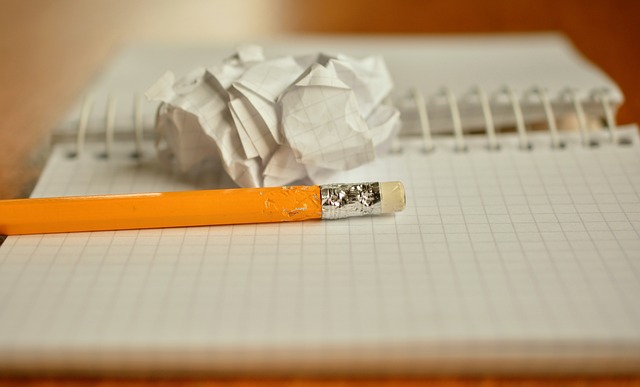
はじめに、公務員試験に論文がある理由を解説します。公務員試験に論文がある理由は、学生に行政課題への知識、問題意識があるかどうかを知りたいからです。持っている意見を、文章で伝える能力も問われています。
論文問題を出現することで、時間制限がある中で問題文が聞きたいポイントを整理して、答えを文章に表現する力を持っているがわかります。
公務員として働くには、トラブルや自治体が抱える問題を明確にし、問題への解決能力が必要です。問題解決へ向けて、他者を説得する能力も欠かせません。
純粋な文章力を求めているわけではないため、その点を理解して回答しましょう。
公務員試験の論文の概要2つ

公務員試験の論文は、形式が2つに分かれます。概要を理解していないと、求められている内容がわからず良い評価が得られません。
それぞれ求められている内容や書き方が変わってくるため、しっかりと対策しましょう。
- 2種類に分けられる
- 制限時間・字数がある
①2種類に分けられる
公務員試験の論文は、「小論文」と「作文」に分かれます。
「作文」で書く内容は、「目指す公務員像」や「いままでの人生で感じた挫折」といった自分の考えや想いを文章にすることを求められます。
「小論文」は、福祉や教育、社会問題への解決策やどのような意見を持っているか見られています。小論文が多くの公務員試験で出題されるだけでなく、自治体によっては配点が高いケースも多いです。
どちらが出ても対応できるよう、しっかり対策しておきましょう。
②制限時間・字数がある
公務員試験で出題される論文は、制限時間である60〜90分の間に800〜1,000文字書く必要があります。原稿用紙でいうと2〜3枚程度の量になるため、時間配分をしながら素早く書かないと間に合いません。
文章を書くのに慣れていないと、1時間で800文字はなかなか筆が進まないでしょう。対策するときは実際に時間をはかり、自分が文章を書くときはどの程度のペースで書いているのか理解すると安心です。
文章に書き慣れておくと、だんだんと早く書く力が身に付きますよ。
公務員試験の論文対策と解答例
公務員試験の論文試験で高評価を得るためには、明確な構成と具体例を盛り込んだ論理的な文章作成が求められます。
ここでは、公務員試験の論文の効果的な書き方を解説するとともに、各パートの回答例を紹介し、実践的なアプローチをお伝えします。
①導入部分
論文の導入部分では、テーマの重要性や現状の問題点に触れ、読者の関心を引きつけることが大切です。
| 回答例 近年、少子高齢化が加速し、地域社会における介護サービスや医療体制の充実が急務となっています。 特に地方自治体では、限られた資源を有効活用し、高齢者が安心して生活できる環境を整えることが求められています。 本論文では、少子高齢化に対する具体的な取り組みと、その効果について考察します。 |
具体的には、テーマに関する背景情報や現代社会の課題を示し、自身の意見の立場を明確にするとスムーズな論文展開の土台が築けます。
導入部分が論理的で簡潔なものであれば、採点者にとっても読みやすく、好印象を与えられるでしょう。
②取り組み
取り組み部分では、テーマに沿った課題解決策や具体的な方策について詳述します。
| 回答例 まず、少子高齢化に対応するためには、地域に密着した福祉サービスの充実が必要です。 具体的には、自治体が地域包括ケアシステムを構築し、住民が身近な場所で医療や介護を受けられる体制を整えることが求められます。 たとえば、行政が医療機関や介護施設と連携し、必要な支援を一元的に提供することで、住民の満足度を向上させることが可能です。 |
この段階で、具体例やデータを示しながら自分の考えを裏付けることで、論文の説得力が増します。
公務員試験では、この取り組み部分が論文の核となるため、根拠のある内容を意識的に盛り込むことが大切です。
③まとめ
まとめ部分では、論文全体の内容を簡潔に振り返り、結論として自身の考えや今後の展望を示します。
| 回答例 以上のように、少子高齢化への対策として、地域包括ケアシステムの構築が重要であると考えます。 自治体が中心となり、地域社会全体で支え合う仕組みを確立することで、高齢者の生活の質を向上させることができます。 今後も、各地域が独自の工夫を凝らし、持続可能な社会を実現するための取り組みが期待されます。 |
論文の締めくくりとして、要点を再確認し、明るい未来への希望や社会に対する貢献を強調すると前向きで一貫した印象を与えられます。
公務員試験の論文のポイント3選

公務員試験の論文を書くときは、3つのポイントがあります。練習時はポイントを意識して、実際の試験で焦らずに済むようにしましょう。
- 文章構成を考える
- 書き終えたら一読する
- 公務員の立場で考える
①文章構成を考える
論文を書くときは、いきなり書き始めるのではなく、全体の構成を考えてから書きましょう。
文章構成を先に考えることで、自分の意見をわかりやすく読み手に伝える効果があります。主な構成は以下の3つです。
- 現状の分析
- 現状に伴う課題・影響
- 課題の解決方法
現状の分析
問題文を読みはじめたら、はじめに問題文のテーマを把握しましょう。問題文が言いたい内容がわからなければ、ゴールまでの道筋が変わってきます。正しい内容を記載できるよう、最初の理解が重要です。
そのうえで、問題文のテーマとして行政課題の現状を示すとわかりやすくなります。客観的な目線で見た根拠を提示し、行政の立場から文章を書きましょう。
現状に伴う課題・影響
現状の分析ができたら、課題が発生することで予想される影響を書きます。考える順番自体は、対策から考えても問題ありません。
なぜ現状を解決する必要があるのかを考えると、課題と対策がつながった内容を記載できます。内容に違和感がなくなり、採用担当者が読んだときに理解を得やすくなるでしょう。
課題の解決方法
最後に、課題解決に必要な対策を示します。不必要な部分をなるべく減らし、自分の考えを簡潔に書きましょう。不要な部分が多いと、読みづらい文章になるため注意が必要です。
具体的な解決策は複数あげ、それぞれがどのように課題解決につながるか書くのがおすすめです。課題と対策の関係性がしっかりしていると、納得されやすい文章になります。
②書き終えたら一読する
文章を書き終えたら、必ず読み返しましょう。提出した論文に誤字脱字があると、良い内容であっても減点されます。
書くのに慣れていないと思うように筆が進まず、思ったより時間がかかっているケースも少なくありません。必ず見直す時間を作り、減点されるポイントを減らしましょう。
見直す時間を作るには、最初から完璧な文章を書こうとせず、とりあえず執筆を進め残った時間で調整するのがおすすめです。はじめから完璧な文章を作るよりも、時間に余裕を持って論文が作成できます。
③公務員の立場で考える
文章を書くときは、自分が公務員だったらという目線で考えて書きましょう。一個人やマスコミ目線からの意見では、公務員になったときの自分が想像できていないと考えられる可能性があります。
公務員の目線で論文を書くには、志望する自治体の政策を調べておくと書きやすくなります。実際に自治体がおこなっている政策を知っておけば、文章内に参考として組み込めますよ。
オリジナルの政策でなくても、行政に対して調べており知見がある点をアピールできるでしょう。
併せて確認!公務員試験の論文の注意点3選

公務員試験の論文を書く前に、記載するときの注意点も理解しておきましょう。注意点を理解しないと、せっかく文章を書き終えても減点される可能性があります。
- 必ず自分の考えを書く
- 字数制限・書き方のルールを守る
- 問いに対する答えを書く
書いた文章を採用担当者にしっかり評価されるよう、注意点を意識して書きましょう。
①必ず自分の考えを書く
論文を書くときは、必ず自分の考えを書きましょう。
事前に調べておいた知識を活かせる内容であっても、知識や用語の羅列ばかりでは評価されません。持っている知識を活かし、どのような政策を立てていくかが重要になります。
文章を書くうえで知識は欠かせないものですが、重要な点を勘違いしていると論文の点数はとれません。あくまで持っている知識を活かし、行政に役立てる方法を考えましょう。
現状や問題点を分析し、持っている知識から解決策を導き出してくださいね。
②字数制限・書き方のルールを守る
公務員試験の論文を書くときは、字数制限や書き方にルールがあります。決められたルールを守らず執筆すると、内容が良い論文でも減点を受ける可能性が高まるでしょう。
文章を読みやすくするには、ただ書き続けるだけでなく適切なタイミングで改行するのも重要です。読み手が疲れないように、読みやすい文章を心がけてください。
また、決められた字数を守るのも重要です。話を広げすぎると文字数をオーバーしやすいため、説明不足にならないよう注意しましょう。
③問いに対する答えを書く
はじめに決められたテーマに対して、しっかり回答できているかも確認します。
文章を書いていると、気付かないうちに論点がずれ方向性が変わっているケースも多くあります。自分が書きやすい内容に、無意識に寄せていく可能性もあるため注意が必要です。
公務員試験の論文では、テーマに対してどのような対策を考えるかが重要なため、論点がずれていては評価が下がります。読み返すときに伝えたい内容が変わっていないか確認し、ずれていたら修正しましょう。
公務員試験の論文でよく出るテーマ3つ

公務員試験の論文では、よく出るテーマが決まっています。
事前に対策しておくと、当日テーマを見たときスムーズに内容が考えられるでしょう。ここで紹介する頻出テーマを理解しておき、論文作りに役立ててください。
- 社会問題
- 環境問題
- 地域に関するテーマ
①社会問題
社会問題は、少子高齢化や人口減少、貧困問題や女性の社会進出といった地域に限らず日本全国で重要とされる問題をテーマとしています。日本全体のテーマであっても、自治体ごとの対策は欠かせません。
社会問題は、実際に公務員になった後も、トラブルや課題として仕事に関係してくるテーマです。常にニュースをチェックしておくと、客観的な視点で問題を見ることが可能です。
日々の生活からどうすればいいか考えておくと、スムーズに文章が書けるでしょう。
②環境問題
環境問題は、地震や地球温暖化、海洋汚染プラスチックごみなどの未来を考えるうえで重要な課題です。日本だけでなく世界規模で重要としている問題ですが、対策は一個人から自治体単位でも可能です。
論文に書くときは、公務員としてどのような対策ができるか考えましょう。イベントとしての対策だけでなく、普段からできる対策も重要です。
小さな事柄でも、環境に対して意識を向ければ解決すべき部分が見えてくるでしょう。
③地域に関するテーマ
地域に関するテーマは、観光振興や地方創生、農林水産業の活性化といった自治体ごとのテーマです。斬新なアイディアがもとめられているわけではないため、現実的かつ成功の見込みがある対策を書きましょう。
地域に関するテーマへの対策は、実際に自治体がおこなっている政策へ目を向けるのが重要です。目指す自治体がどのような対策をおこなっているか理解すると、関連する内容や被らない内容が考えられます。
地域を活性化させるためにできる案を、普段から考えておきましょう。
公務員試験の論文の対策法2つ

公務員試験の論文には、効果的な対策が2つあります。対策を知っておけば、文章を書く以外の方法から論文を身近にできます。
- 上手な論文を読む
- 時事問題に触れておく
試験前に対策をしっかりおこない、当日に焦らないよう注意しましょう。
①上手な論文を読む
論文を身近にするには、上手な論文を普段から読んでおきましょう。上手な論文を読めば、書き方のコツを掴めます。話の展開方法やまとめ方がわかりやすく、自分が文章を書くときにも落とし込みやすいのがメリットです。
公務員試験に関する論文を読むと、テーマへの知識を深めることが可能です。知識が増えれば、実際に論文を書くときにも役立ちますよ。
論文の対策をしつつ、より多くの知識を身に付けられる効果的な方法といえるでしょう。
②時事問題に触れておく
普段の生活でも、公務員試験の論文に役立つ対策はあります。ニュースに目を通し、時事問題への理解を深めましょう。
公務員試験の論文は、予備知識がないと書けない問題が多くなっています。新聞やニュースを見ずに過ごしていると、テーマを見ても理解できず論文作成が困難になってしまうでしょう。
日々の生活でもテレビや新聞から時事問題の知識を取り入れておき、解決策を考えておくとスムーズに書けるようになります。最新の話題にも対応できるよう、意識的にニュースと見ておきましょう。
試験種別ごとのポイントと注意点
公務員試験には、受験する職種によって異なる特徴や求められるスキルが存在します。
ここでは、各試験種別のポイントと注意点を解説し、それぞれの試験で高評価を得るための準備方法を詳しくご紹介します。
①国家総合職
国家総合職では、課題に対する多角的な視点が重視されるため、日頃から時事問題や政策に関する情報を収集し、自分の意見を論理的に整理する練習が効果的です。
また、政策提案の際には具体的なデータや根拠を示し、実現性を考慮した内容にすると、説得力のある論文が作成できます。
バランスの取れた論理展開を心がけ、政策立案の基礎知識をしっかりと身につけましょう。
②外務専門職
外務専門職を目指す場合、英語力の向上や主要な国際ニュースを日々チェックしておくことが不可欠です。
また、国際機関や多国間の協力の事例を理解し、自分の意見をまとめる練習が有効です。
論文では問題に対する自国の役割を具体的に示しつつ、他国の立場も考慮した柔軟な発想を盛り込む工夫を凝らしましょう。
③地方上級・国家一般職
地方上級試験では、地域の特色や現状を踏まえた課題解決策が求められるため、受験先の自治体の現状や政策について調査しておくことが重要です。
また、国家一般職の場合も国全体の政策や地域間の課題に関する知識を持っていると有利です。
論文では、具体的な事例や住民目線での視点を交えながら現実的な解決策を示すと、実務に役立つ提案ができると高評価に繋がります。
公務員試験の論文は対策を立てて取り組もう
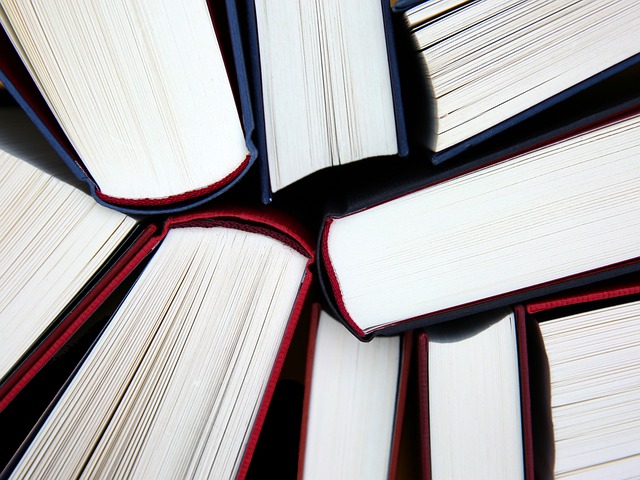
公務員試験の論文は、事前に対策が可能です。どのような問題が出るか理解しておき、練習を重ねておくと試験当日も焦らずに対応できます。
日々の生活でも、ニュースを見て時事問題に精通しておくと、問題への解決策がスムーズに浮かんできます。できることを続けておき、実際の試験に備えておくのがおすすめです。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









