公務員試験では、作文(論文)が実施されるケースがあります。公務員試験の作文について、「何か対策すべき?」「書き方が分からない」などと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、公務員試験の作文の書き方や対策方法を解説します。公務員試験を受ける予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員試験の作文とは

公務員試験の作文とは、受ける職種や区分によって出題内容が異なります。テーマが課され、600文字〜1000文字程度の作文を書くのが一般的です。
公務員試験の作文は、大きく「政策系」と「自己PR系」の2種類に分類されます。政策系はいわゆる小論文で、自己PR系は作文にあたります。
- 政策系:行政課題について自分の考えを述べる
- 自己PR系:自身の適性をアピールするもの
時間制限は、50〜90分程度に設定されているケースが大半です。試験内容の詳細は試験案内に記載されているため、必ず確認しておきましょう。
公務員試験の作文基本ルール4つ
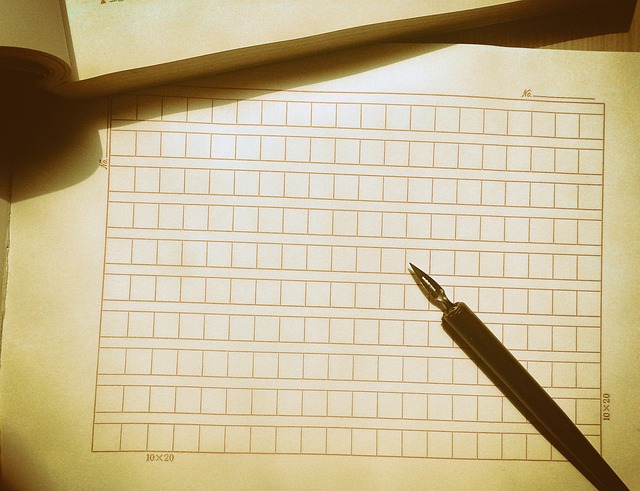
公務員試験の作文には、いくつかのルールが存在します。覚えておきたい基本ルールは以下の4つです。
- 題名は3マス空ける
- 文末を一致させる
- 本文は8割以上記入する
- 句読点を行頭に置かない
①題名は3マス空ける
作文に共通するルールとして、題名は最初の行に3マス空けて書く必要があります。
題名が長くて3マス空けると2行になってしまう場合は、2マスもしくは1マス空けでも問題ありません。ただし、1マスも空けないのはNGです。
また、段落を変えるときは改行して1マス空けるようにしましょう。これら2点は作文の基本的なルールなので覚えておいてください。
②文末を一致させる
作文では文末を一致させる必要があります。「ですます」「である」調が混ざってしまわないように注意しましょう。
「ですます」調は話し言葉が元になっているため、書き手が話しかけてきているような印象を与えます。一方の「である」調は、文末の表現が簡潔になるため論文に適しています。
「ですます」と「である」のどちらを使うかはケースバイケースですが、1つの作文の中で混在しないように注意してください。
③本文は8割以上記入する
本文は制限字数の8割以上記入することも重要なポイントです。公務員試験の作文では、「〇○字以内」と制限字数が指定されているケースがあります。
制限字数をオーバーするのはNGですが、少なすぎるものマイナス要素となります。可能であれば制限字数の9割以上、最低でも8割以上記入することを徹底しましょう。
④句読点を行頭に置かない
公務員試験の作文では、句読点(、。)を行頭に置かないようにします。こちらも小学校で習った作文の基本的なルールです。
句読点の直前の文字が行の最後にきてしまったときは、句読点を最後のマスに一緒に書くようにします。もしくは欄外に書いても問題ありません。
公務員試験の作文を書く際のコツ4つ
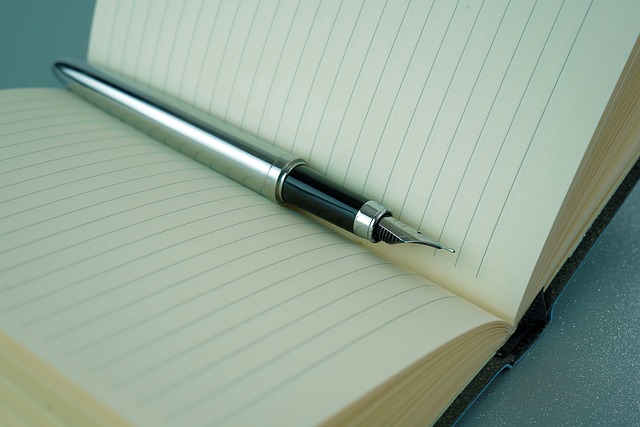
作文に苦手意識を持ってる方は多いはず。そこで、公務員試験の作文を書くコツをここで紹介します。コツは以下の4つです。
- テーマと本文がずれないようにする
- 意見に根拠をつける
- 本文の論理展開を丁寧に
- 誤字脱字がなく丁寧に
①テーマと本文がずれないようにする
1つ目のコツは、テーマと本文がずれないようにすることです。テーマを正しく理解し、本文内容とテーマがずれないようにすると高評価をもらえます。
公務員試験の作文では、第一に読解力や理解力をチェックされます。「何を問われているのか」を理解し、それに合った内容について論じなくてはいけません。
テーマをただしく理解する力がないと、ちぐはぐな作文に仕上がってしまいます。
②意見に根拠をつける
2つ目のコツは、意見に根拠をつけることです。公務員試験の作文には信憑性が求められます。
作文では自分の意見を述べることも重要ですが、あきらかに事実と異なる内容だとマイナス評価となります。
具体的なデータを挙げるなど、根拠をつけることで説得力を上げることが可能です。
③本文の論理展開を丁寧に
3つ目のコツは、本文の論理展開を丁寧にするです。序論→本論→結論の展開にすると、読み手に伝わりやすい作文に仕上がるでしょう。
まず序論では、テーマについて最も伝えたいことを書きます。本論では、序論で書いた事柄に対する根拠や具体例を挙げます。
結論では、序論で述べたことをもう一度書き、今後のビジョンがある場合は合わせて書きましょう。
④誤字脱字がなく丁寧に
作文に限らず、誤字脱字がないことは文書作成の基本です。
公務員試験では、誤字脱字がないかを細かくチェックされます。作文が仕上がったら全体を読み直し、誤字脱字がないかを確認しましょう。
また、公務員試験の作文は丁寧に書くことも重要です。丁寧に書くことで誤字脱字を防げるだけでなく、読み手に好印象を与えられます。
公務員試験の作文はどう対策すればいい?

公務員試験では筆記試験の対策に時間を取られ、作文対策が不十分の方も少なくありません。最低限行っておくべき作文対策は以下の3つです。
- 作文を書く練習を重ねる
- 読み直しを毎回行う
- 添削してもらう
①作文を書く練習を重ねる
作文を上達させるためには、くり返し練習することが重要です。普段から書き慣れておかないと、本番で実力を発揮するのは難しいでしょう。
解説したように、作文には基本的なルールが存在します。頭の中でルールを理解していても、実際に書いてみないと身に付きません。
また、公務員試験の作文では、制限時間内に制限字数の8割以上記入する必要があります。こちらをクリアするためにも日頃の練習は必須です。
②読み直しを毎回行う
作文が仕上がったら、読み直しを毎回行うことをおすすめします。自分でチェックし、論理展開の違和感や誤字脱字に気づけるようにしておくとよいでしょう。
誤字脱字はマイナス評価につながるため、絶対に避けたいものです。よって、読み直しを行う習慣をつけておきましょう。
書き進めながらこまめに読み直す方法もありますが、一度最後まで書くことをおすすめします。こまめに読み直していると、制限時間オーバーで最後まで書ききれない可能性があるためです。
③添削してもらう
もし可能なら、誰かに頼んで添削してもらうことをおすすめします。自分以外の人に読んでもらうことで、客観的な意見をもらえるためです。
自分1人で対策すると、視野が狭くなり正解がわからなくなる可能性があります。添削してもらうことで、視野が広くなり、よりよい作文を書けるようになるでしょう。
ただし、添削してもらう相手は誰でも良いわけではありません。教授や就職課のスタッフなど、作文や公務員試験に関して最低限の知識がある方にお願いしましょう。
公務員の作文対策をして試験突破を目指そう

公務員試験では、筆記試験の突破が第一関門です。筆記試験対策に気を取られ、作文対策が疎かになっている方もいるでしょう。
しかし、公務員試験の作文対策は必須です。ポイントを抑えて練習を重ねれば、試験突破は大幅に近づくでしょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









