公務員試験は難易度が高いことで知られています。そのため、どう勉強すれば合格を目指せるのかがわからず、困ってしまう人もいるでしょう。
本記事では、公務員試験の種類ごとの難易度や合格率・試験合格が難しい理由について解説します。
適した勉強法も説明するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
公務員試験は種類によって難易度が異なる

公務員試験にはさまざまな種類があり、国家公務員か、地方公務員かによっても難易度が異なるのが特徴でしょう。ここでは、試験の種類を難易度が高い順に紹介します。
- 国家公務員総合職
- 外務省専門職員・国会職員など
- 東京都庁・大都市圏県庁・政令都市職員など
- 国家公務員一般職・裁判所事務官一般職など
- 国家公務員専門職・地方上級職員など
①国家公務員総合職
国家公務員総合職は官庁で働く総合職を指していて、高度なスキルが問われるほか、ゼネラリストやキャリア官僚を目指す人が受ける試験としても知られています。
中央省庁で政策を立案する・予算を編成する・法案を作るなど、国の将来に働きかけて国政を動かしていく役割を担当するため、試験の難易度が最も高いです。
また、2次試験合格後に官庁訪問を行う必要があり、官庁訪問の結果によって採用が決まります。
➁外務省専門職員・国会職員など
外務省専門職員や国会職員の試験は、総合職の次に難易度が高くなっています。
外務省の総合職とは業務内容が異なり、より専門的な知識が問われる試験に重点が置かれやすいのが特徴です。
1年間の本省勤務後、在外研修や在外公館で経験を積んで本省に戻る流れになるなど、長期間の研修があります。
また、国会職員は筆記試験の難易度が高めです。人数の枠も少ないことが、テストの突破率に影響しています。
③東京都庁・大都市圏県庁・政令都市職員など

東京や大都市圏の県庁、政令都市の職員は、大規模な事業を取り扱う傾向があるため、出願者が多く倍率が高まる傾向があります。
国家の仕事と比べると規模感は減少しますが、県レベルの予算で業務を進めていくため、憧れを持つ人が多いのが特色です。
学力やスキルがある受験生が多く集まる傾向もあり、より実力がある候補者が採用されるのが競争の激しさにつながっています。
④国家公務員一般職・裁判所事務官一般職など
国家公務員や裁判所事務官の一般職は、国家公務員の試験の中では難易度は中程度です。総合職と比べると、一般職は募集人数が多いといった特色があります。
業務内容も転勤がほとんど発生せず、安定して働ける環境となっているため人気が高めです。
総合職を希望する人が滑り止めとして一般職を受けるケースも多くなっています。
裁判所事務官の一般職は業務で事務を担当しますが、法律分野の知識を深める必要があるのが特徴です。
⑤国家公務員専門職・地方上級職員など
国家公務員専門職は所属によって難易度に差があり、地方上級職員は地方公務員の中ではハイレベルな試験となっています。
どちらも過去問をしっかり分析して、希望する職種に合った対策を行うことが重要です。
また、地方公務員試験においては面接を複数回実施して、人間性を重視して採用する傾向もあります。
筆記テストをパスするための勉強を重ねるだけでなく、人物試験に対しても十分な対策が必要です。
【試験別】公務員試験の合格率・倍率の推移
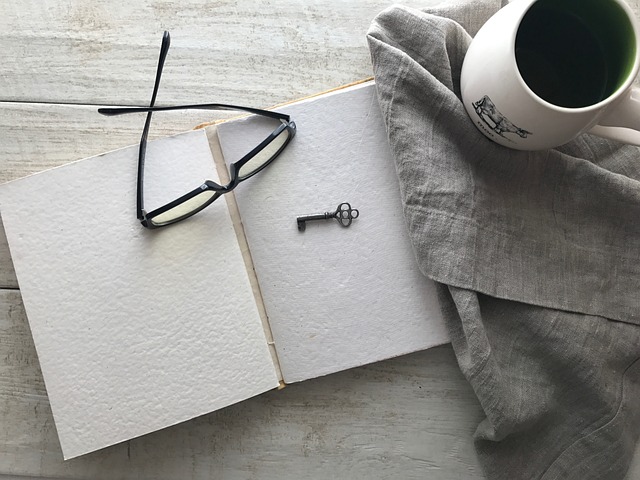
公務員試験の倍率や合格率の推移をチェックすれば、年度ごとの難易度の変化を把握しやすくなるのでぜひ確認しておきましょう。
ここでは、国家公務員や地方公務員の合格率、倍率の推移を紹介します。
- 国家公務員
- 地方公務員
国家公務員
国家公務員の年度別の倍率は、以下の通りです。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 国家総合職(院卒・大卒) | 8.46倍 | 8.56倍 | 7.5倍 |
| 国家一般職(大卒・高卒) | 3.77倍 | 3.43倍 | 3.1倍 |
| 国税専門官 | 3.13倍 | 3.62倍 | 4.3倍 |
| 法務省専門職員 | 4倍 | 4.28倍 | 4.21倍 |
申込者数を見ると、大卒程度を対象とした国家公務員一般職試験が26,319人と最も多く、次いで国税専門官採用試験が多くなっています。
地方公務員
地方公務員の年度別の競争率は、以下の通りです。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
| 受験者数 | 469,000人 | 465,000人 | 439,000人 |
| 合格者数 | 79,000人 | 80,000人 | 85,000人 |
| 競争率 | 5.9倍 | 5.8倍 | 5.2倍 |
受験者数は2年連続で減少しているものの、合格者数は増加しています。そのため、競争率はゆるやかに低下してきています。
公務員試験合格が難しい3つのワケ
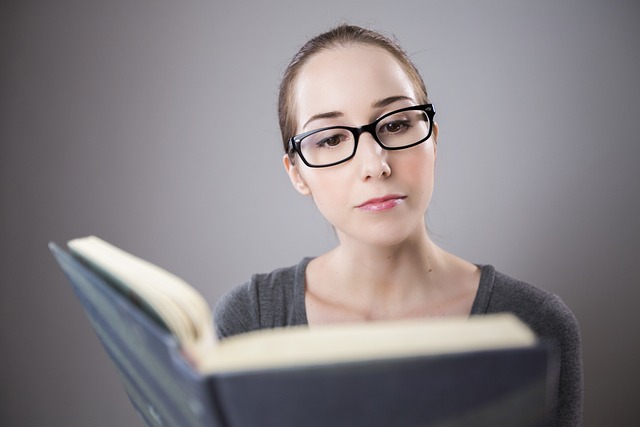
公務員試験のパスがなぜ難しいのか理由をチェックすれば、対策を探す糸口になるのでおすすめです。ここでは、3つの理由を説明します。
- 採用試験のため人物試験が課されるから
- 採用人数が決められているから
- 試験範囲が広いから
①採用試験のため人物試験が課されるから
採用試験のため、人物試験もクリアしなければいけないことが、難易度の高さにつながっています。
公務員試験は資格試験とは異なり、さまざまな形式のテストをパスしなければいけません。
職員として採用するかどうかを決めるため、筆記試験以外にも面接などの人物試験が課されます。
筆記試験に合格しても、面接で失敗してしまうと公務員として採用されないため、面接の対策もしっかりと行っておくことが重要です。
➁採用人数が決められているから
採用人数があらかじめ決まっていることも、難易度に影響しています。人数の枠は増えないため、希望者が多ければ多いほど倍率が高まり、難易度も高くなるのが特徴です。
さらに、近年は官公庁や自治体が経費を削減するため、採用予定人数を減らす傾向があります。
人数の枠が減少している分、試験を通過するためには、ほかの候補者よりもしっかりと対策を練り、長期間十分に勉強をしなければいけません。
③試験範囲が広いから
試験範囲が広い分、直前に勉強を始めても対応できない点にも注意が必要です。出題される分野は大きく教養試験と専門試験にわけられます。
それぞれのテストの出題範囲は、以下の通りです。
- 教養科目:現代文・判断推理・英文・資料解釈・古文・数的推理・法律・政治・時事・経済・化学・数学・物理・地学・生物・日本史・文学・思想・世界史・地理
- 専門科目:社会政策・政治学・国際関係・行政学・民法・刑法・労働法・憲法・行政法・マクロ経済学・財政学・ミクロ経済学
それぞれ対策をする必要があるため、多くの勉強時間を要します。
公務員試験を突破するためのポイント3つ
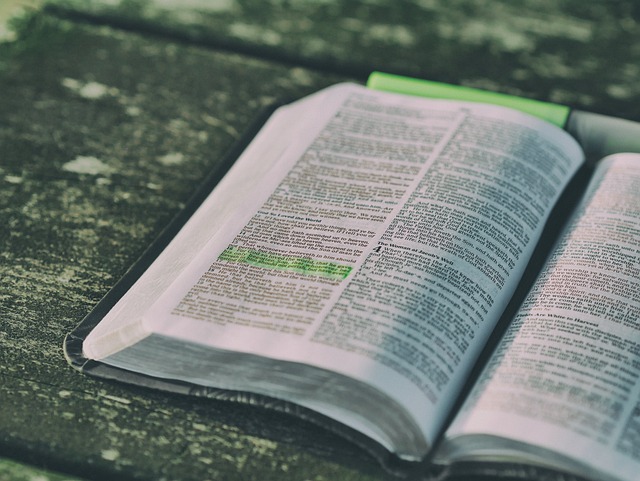
試験を突破するコツを把握すれば、効率よく対策を進めやすくなり、合格率を高められるでしょう。ここでは、勉強法のポイントを3つ解説します。
- 勉強の計画を立てる
- 過去問を何度も解く
- 出題割合が高い科目を優先的に勉強する
①勉強の計画を立てる
ます、無理のない勉強計画を立ててから実践していくことが大切です。具体的かつ実現可能な勉強計画を立てて、スケジュールの見通しを明確にすることが重要になります。
勉強を始める時期は、試験の一年前の春頃が一般的です。ただ、対策を始める時期は早ければ早いほど綿密な対策を練られます。
また勉強をする時期が遅れたり、勉強と両立しなければいけないことがあったりする場合は、スキマ時間を有効活用するのも手です。
➁過去問を何度も解く
過去問を繰り返し解いて対策することも重要です。勉強をする際には参考書から取り組みがちですが、まず過去問から解いた方が効率よく対策できます。
過去問を解けば、問題の出題傾向や苦手な部分は何かを掴みやすくなるのがメリットです。その後に参考書を使うことで、苦手分野を重点的に勉強して克服できます。
また、過去問を何度も解き直せば解法が身につき、スムーズに解き進めやすくなって得点率が高まるのがポイントです。
③出題割合が高い科目を優先的に勉強する
出題割合が高い科目を優先的に勉強すれば、高得点を目指しやすくなるのがポイントです。公務員試験の筆記試験においては、7割程度の合格率を目指す必要があります。
問題の中には公務員試験全般に共通して出題割合が高いものがあるため、優先して対策すると効率的です。
教養科目で出題割合が高いのは、文章理解・数的処理・社会科学で、専門科目では憲法・民法・経済系科目が出題されやすくなっています。
公務員試験は難易度が高いため十分な対策が必須
公務員試験は難易度が高いため、十分な対策が必須です。試験ごとの難易度を把握して、効率よく対策を行うことが重要になります。
計画を立てて実行し、試験対策を万全にして、希望した職種への就職を目指しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









