適性検査とは採用の判断基準|対策方法や問題・乗り切るコツを紹介!
就職活動における「適性検査」をご存じでしょうか。適性検査の存在は知っていても、どのような対策を取ればよいのか悩んでいる方もいるでしょう。
そこで本記事では、適正検査で出題される問題や対策方法、乗り切るコツなどをくわしく紹介します。これから就職活動を開始する方は必見です。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
適性検査とは|就活の採用基準として用いられる
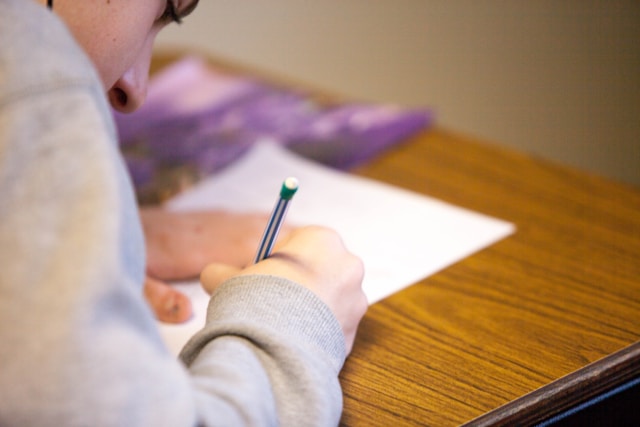
適性検査とは、新卒採用にあたり企業側が人材を判断するために使用する基準です。応募者の能力や性格などを測定し、企業が求める職務要件を満たしているのかを判断します。
適性検査では基礎学力や一般常識が問われるほか、性格の特徴を把握する問題が出題されるケースもあります。
適性検査は、新卒採用を行うすべての企業で実施されるわけではありません。しかし、実施する企業では採用基準として用いられるため、就活生にとっては重要な検査といえるでしょう。
企業が適性検査を行う理由2つ

就活中は履歴書や面接の準備に忙しく、「なぜ適性検査まで必要なのか」と不満に感じる方もいるかもしれません。企業が適性検査を行う理由は以下の2つです。
- 能力や性格を把握するため
- 企業とのミスマッチを防ぐため
①能力や性格を把握するため
適性検査を行う1つ目の理由は、能力や性格を把握するためです。適性検査は選考の序盤で行われることが多く、応募者を絞り込むために実施されます。
履歴書や面接のみから、応募者の基礎能力や性格を見極めることは難しいでしょう。また、面接官の主観が入りやすく、客観的な判断がされない可能性もあります。
適性検査は、応募者の能力や性格を客観的に測定する手段として有効です。
②企業とのミスマッチを防ぐため
適性検査を行う2つ目の理由は、企業とのミスマッチを防ぐためです。適性検査における性格検査から、応募者が社風に合っているか、周囲との調和を保てるかなどをチェックします。
企業側が重視するのは、応募者の能力や適性のみではありません。社風から大きく外れていたり、すぐに辞めてしまったりする人物は採用したくないものです。
採用後のミスマッチを防ぐために、適性検査を行うメリットは大きいといえるでしょう。
就活の適性検査に出る2つの問題

就活の適性検査にどのような問題が出るのか気になっている方は多いでしょう。就活の適性検査に出る問題は以下の2つです。
- 能力・学力検査
- 性格検査
①能力・学力検査
能力・学力検査とは、応募者の知的能力や一般常識、倫理的思考力を問う検査です。
能力・学力検査は、大きく分けて「基礎能力検査」「英語検査」「構造的把握力検査」の3つに分類されます。
さらに、基礎能力検査は「言語分野」と「非言語分野」の2つに分類されます。
- 言語分野:言葉の意味や話の要旨を理解できるか
- 非言語分野:数的な処理ができるか、論理的思考力があるか
構造的把握力検査では、物事の背後にある共通性や関係性を読み解き、構造的に把握できるかを問われます。
②性格検査
性格検査とは、応募者の価値観や性格の特徴を把握する検査です。履歴書や面接からは分からない、応募者の内面を明らかにする目的があります。
性格検査は性格の良し悪しというよりは、その人物が持つ特性や価値観、ストレス耐性などをチェックされると考えましょう。
性格検査の回答は、応募者が偏った考えを持っていないか、社風に合っているか、組織になじみやすいタイプかなどの判断材料となります。
企業側は性格検査を行うことで、採用後のミスマッチを防げるメリットがありますよ。
適性検査の種類5つを紹介

就活の適性検査は企業オリジナルのものではなく、専門会社が制作したものを使用します。適性検査の主な種類は以下の5つです。
- SPI
- 玉手箱
- CUBIC
- CAB・GAB
- クレペリン検査
①SPI
SPIとは「Synthetic Personality Inventory」の略で、リクルートマネジメントソリューションズ社が開発した適性検査です。
SPIは最も有名な適性検査で、大手企業の6割ほどが採用しています。よって、大手企業を何社かを受けるとSPIに当たる確率は高いでしょう。
SPIは、「性格検査」と「能力検査」の2つに大別されます。また、能力検査は「言語検査」「非言語検査」「英語能力検査」「構造的把握力検査」の4つで構成されています。
②玉手箱
SPIに次いで利用率が高いのは、日本エス・エイチ・エル(SHL社)が開発した玉手箱です。
玉手箱はWebで受験できるため、Web形式でのテストというと大半は玉手箱が採用されています。中小企業でも多く採用されているため遭遇率が高いでしょう。
玉手箱は、「能力テスト」と「性格テスト」の2つに大別されます。また、能力テストは「言語問題」「計数問題」「英語問題」の3つで構成されています。
➂CUBIC
CUBICは、株式会社AGPが開発した適性検査です。SPIや玉手箱と比較すると知名度は低いものの、年々導入する企業が増えています。
CUBICが、「基礎能力検査」と「性格検査」の2つに大別されます。時間は30分程度ありますが、問題数が多いためテンポ良く解いていかないと間に合わない可能性もあるでしょう。
一部企業では時間制限なしに設定されていますが、時間制限がある場合は要注意です。
④CAB・GAB
CAB・GABは、日本エス・エイチ・エル社が開発した適性検査です。CABは主にIT企業、GABは総合商社や専門商社などの選考で用いられます。
CAB・GABともに問題数が多いため、問題を解くスピードが求められます。また、SPIや玉手箱と比較すると難易度は高めです。
CAB・GABの受験方法は「企業での受験」「テストセンターでの受験」「自宅でのWeb受験」の3パターンで、それぞれ出題内容が異なるケースがあります。
⑤クレペリン検査
クレペリン検査は、株式会社日本・精神技術研究所が提供する適性検査です。内田勇三郎氏が1920年~1930年代にかけて開発した日本で最も歴史のある適性検査として知られています。
クレペリン検査は、一桁の足し算を1分ごとに行を変えながら行う簡単な検査です。途中で休憩を挟み、前半と後半で各15分間ずつ計30分間行います。
一見簡単な検査ですが、結果から受験者の「能力面の特徴」と「性格・行動面の特徴」が分かります。
就活の適性検査の対策方法4つ

就活の適性検査は選考の判断基準となるため、しっかりと対策を取ることをおすすめします。対策方法は以下の4つです。
- 対策本を買う
- 読解力を付ける
- 時間を測って練習をする
- 出題パターンを把握する
①対策本を買う
1つ目の対策方法は、対策本を買うことです。志望企業がどの適性検査を実施するのかが判明したら、該当する適性検査の解説本や問題集を購入しましょう。
1つの適性検査のみではなく、複数の適性検査に対応している対策本も存在します。複数社を受ける場合におすすめですよ。
対策本を購入したら、慣れるまで演習を繰り返すことが重要です。1回で完璧に解けなくても問題ありません。
②読解力を付ける
2つ目の対策方法は、読解力を付けることです。問題を正確に読み取る「読解力」がないと、正解を導き出すことができません。
読解力を付けることで、よく読まないと理解しにくい問題や国語の文章問題を落としにくくなりますよ。
普段から落ち着いてゆっくりと文章を読み、長くて分かりにくい文章は要約する癖を付けることをおすすめします。
➂時間を測って練習をする
3つ目の対策方法は、時間を測って練習をすることです。適性検査は制限時間が設けられているケースが多いため、練習の時から時間の感覚を身に着けておく必要があります。
特に問題数の多い適性検査では、テンポ良く問題を解きましょう。スピード感を意識しないと、時間内に間に合わない可能性があるためです。
問題集を解く際は、タイマーを設定して制限時間内に解くことを意識しましょう。
④出題パターンを把握する
4つ目の対策方法は、出題パターンを把握することです。適性検査は決まったパターンが多いため、出題パターンを把握することで、より正確かつスピーディーに解けるようになります。
出題パターンを把握するためには、最初に紹介したように対策本を購入する必要があります。出題パターンを考慮して対策本を作っているため、解いていくだけで大体の出題パターンは掴めるでしょう。
時間や金銭的に余裕のある方は、対策本を何冊か購入して解いてみるのもおすすめですよ。
就活の適性検査を乗り切るコツ2つ

就活生の中には、「適性検査を受けたけれど、上手くいかなかった」と落ち込んでいる人もいるでしょう。最後に、就活の適性検査を乗り切るコツを2つ紹介します。
- 消去法を使う
- 時間配分に気を付ける
①消去法を使う
正解が分からない時は、消去法を使うことをおすすめします。消去法を用いることで、正解を導き出せる可能性があるためです。
問題の選択肢には、明らかに誤っていると分かるものが含まれているケースがあります。まずは明らかに違うものを選択肢から外し、残りの中から正解を探しましょう。
明らかに誤っているものを最初に選択肢から外すことで、正解率が上がるだけでなく回答スピードも上がるはずですよ。
②時間配分に気を付ける
くり返しになりますが、多くの適性検査では時間制限が設けられています。よって、時間配分に注意する必要がありますよ。
学生時代の学力テストにもいえることですが、「得点を取れる所でいかに取るか」が重要です。分からない問題をいつまでも解いていると、他の箇所を解く時間がなくなってしまいます。
得点を取れる所でしっかりと正確に取れるように、問題の取捨選択を意識しましょう。
適性検査の目的を理解してしっかり対策しよう

企業が適性検査を行う目的は、応募者の能力や性格を把握し、企業とのミスマッチを防ぐためです。適性検査は採用の判断基準となるため、しっかりと対策することをおすすめします。
具体的な対策方法としては、書店などで対策本を購入し、慣れるまで演習をくり返すことが重要です。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









