就職活動用に作成する履歴書には、略歴を記載する欄が設けられていることがほとんどです。しかし「略歴には何を書けばいいの?」と悩む人も多いでしょう。
そこで本記事では、略歴について詳しく解説します。略歴の正しい書き方や見本も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
略歴とは何かを解説

略歴とは経歴の概要のことで、学歴や前職までの仕事の経歴を短くまとめたものです。経歴とは異なり、入退社日などの細かい日付や学歴、職歴は省略することが一般的となっています。
履歴書では、基本的に中学校卒業からの学歴と職歴の記載が求められますが、職歴が多い場合は、最終学歴の一つ前からの記載で基本的には問題ありません。
略歴は、時系列で入学・卒業・入社・退社の情報を全て記載しなければなりません。学校名や会社名は、「○○県立○○高等学校」「○○株式会社」など、正式名称を使いましょう。
略歴を履歴書に書く際のポイント6つ

ここでは、略歴を履歴書に書く際のポイントを6つ紹介します。
- 全て正式名称で書く
- 数字を算用数字に統一する
- 暦を統一する
- 嘘の情報は書かない
- 時系列順に記入する
- 「在学中」ではなく「卒業見込み」と書く
- 略歴の最後は「以上」と記入する
①全て正式名称で書く
1つ目は、略歴では学校名や会社名などは全て正式名称で書くことです。なぜなら、省略してしまうと異なる企業と混同されてしまったり、誤解が生じたりする可能性があるからです。
具体的には、大学名は「〇〇大学〇〇学部〇〇学科」といったように正確に記載することが重要です。また、高校は「高等学校」と記載することに注意しましょう。
②数字を算用数字に統一する
2つ目は、数字を算用数字に統一することです。日付や年月、実績や人数など、応募書類に記載する数字は「一、二、三…」などの漢数字ではなく「1、2、3…」のように算用数字で統一して記載しましょう。
たとえば、「三年間の経験」ではなく、「3年間の経験」といった具体的な数字を使用します。
このように、数字を統一することで文書の統一感を高め、読み手が理解しやすいものになるのです。
③暦を統一する
3つ目は、履歴書の年月は和暦・西暦のどちらかで統一することです。履歴書では、西暦・和暦のどちらを使っても問題ありませんが、履歴書全体で統一する必要があります。
「令和6年」「2024年」のように、同じ履歴書の中で和暦・西暦が混合することは避けましょう。途中で混同しないためには、最初に和暦か西暦のどちらを用いるかを決めておくことが重要です。
なお、履歴書に最初から日付が印字されている場合は、印字に従いましょう。
④嘘の情報は書かない
4つ目は、嘘の情報を書かないことです。「短期間での転職を何度も繰り返している」「ブランク期間がある」などの理由で、事実とは異なる業務内容や実績などを記載するケースがあるかもしれません。
これは経歴詐称を疑われる恐れがあるため避けましょう。他にも、嘘が明らかになった場合に内定を取り消される可能性があります。
虚偽が明らかにならなかったとしても、後ろめたさやいつバレるか怯えながら選考を受けることになることが考えられます。履歴書などの応募書類には、事実ではない情報を書かないようにしましょう。
⑤時系列順に記入する
5つ目は、履歴書の学歴を時系列順に記入することです。
学歴は、基本的に高校入学から書き始めるのが一般的なため、学歴・職歴欄の一番上には高校を書きます。高校の下には大学や短大、専門学校の順番で記載しましょう。
職歴がある場合は、新卒で入った会社から順番に記載します。下に行くほど直近の仕事に近づいていくと覚えておきましょう。
⑥「在学中」ではなく「卒業見込み」と書く
6つ目は、履歴書の略歴には「在学中」ではなく「卒業見込み」と書くことです。これは、企業が学歴を通じて応募者の将来の成長を把握するためです。
「卒業見込み」を記載する際のポイントは、予定された卒業年月を具体的に記載し、卒業に確実性があることを示すことです。
これにより、企業は新卒として入社する資格のある人材として学生を評価できます。
⑦略歴の最後は「以上」と記入する
7つ目は、略歴の最後は「以上」と記入することです。「以上」と記入することで、どこで略歴が終わるか一目でわかります。
逆に、書き忘れると「まだ続きがある可能性がある」と思われるかもしれません。意外と忘れがちなポイントであるため、提出前に必ずチェックしておきましょう。
略歴の正しい書き方の見本を紹介
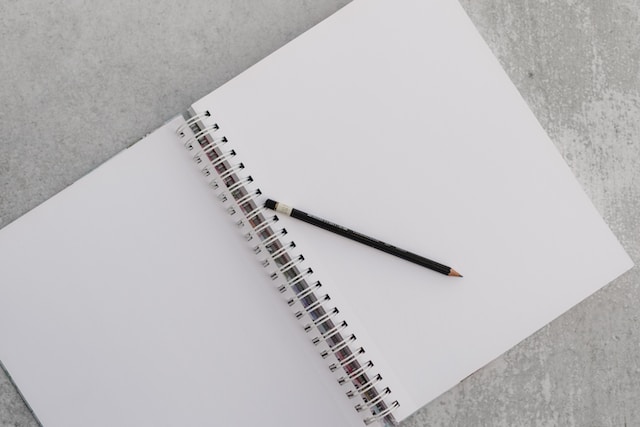
次に、略歴の正しい書き方の見本を紹介します。参考にしつつ、ご自身の状況に合わせて書き換えてみましょう。
- 新卒の場合
- 転職の場合
①新卒の場合
新卒の場合は、下記のように略歴を記載するのが一般的です。
| ーーーーーーー学歴ーーーーーーー 令和○○年 4 東京都立○○高等学校 普通科 入学 令和○○年 3 東京都立○○高等学校 普通科 卒業 令和○○年 4 ○○大学○○学部○○学科 入学 令和○○年 3 ○○大学○○学部○○学科 卒業見込み ーーーーーー職歴ーーーーーー なし 以上 |
新卒の場合、職歴欄に「なし」と記載することを忘れないようにしましょう。また、高校や大学名は名称を省略せず、正確に記載します。
②転職の場合
転職の場合は、下記のように記載しましょう。
| 令和○○年 ○○株式会社に入社 食品を扱う製造部門で新規開拓に従事 令和○○年 XX株式会社に入社 医療機器メーカーの販促部でリーダーに従事 |
複数社経験している人の場合は、その旨を丁寧に記載することがポイントです。なお、どのような仕事に従事していたかを記載すると伝わりやすくなるためおすすめです。
略歴に関するよくある質問3つ

最後に、略歴に関するよくある質問に回答します。
- 中退や退職の場合も記入する?
- 職歴が多すぎる場合は?
- 新卒で職歴が無い場合は?
①中退や退職の場合も記入する?
中退や退職の場合も、その旨を記載するようにしましょう。その際、理由を一言添えて書くことで内容が伝わりやすくなります。
たとえば、大学を中退した場合は、
- 令和○○年 ○○大学○○学部○○学科 入学
- 令和○○年 ○○大学○○学部○○学科 家庭の事情により中退
企業を退職した場合は、
- 令和○○年 株式会社○○ 入社
- 令和○○年 株式会社○○ 一身上の都合により退職
のように記載しましょう。また、面接で理由を深掘りされる可能性もあるため、回答を準備しておくことも重要です。
②職歴が多すぎる場合は?
たとえ職歴が多くても、基本的には全て記載しましょう。
なぜなら、これまでの職務経験が、新しい職場で有利に働くこともあるからです。また、職歴が多いことが後から発覚した場合、企業が不信感を覚えるかもしれません。
あまりにも職歴が多い場合は、略歴欄が多い履歴書を選んで対応するか、書き方を工夫して書くことが重要です。
③新卒で職歴が無い場合は?
新卒で職歴が無い場合は「なし」と書けば問題ありません。新卒で就職活動する場合、ほとんどの人が職歴がない状態からスタートします。そのため、職歴がなくても不利になることはないのです。
逆に、何も記載していないと、担当者から書き忘れたのかと思われることがあるため、必ず記載するようにしましょう。
略歴とは何かを知って就活に活かそう!
本記事では、履歴書に記載する「略歴」について解説しました。
略歴は、あなたの情報を正確に伝えるための重要な項目です。略さず書くなどのポイントを守って記載しましょう。
また、職歴を書く際は、具体的な職務内容を記載することで伝わりやすくなりますよ。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









