就活では、卒論について聞かれることもあります。しかし、どう回答すればよいかがわからず、悩んでしまう人もいるでしょう。
本記事では、企業が卒論について聞く意図・回答時のコツ・卒論が決まっていない場合の対処法・就活と卒論を両立させる方法について解説します。
まず回答例から確認したい方は、こちらをご覧ください。
就活で企業が卒論について聞く理由3つ

卒論について企業が聞く理由を把握すれば、どんな回答を用意するべきかイメージしやすくなります。卒論に関する質問をする意図は、以下の3つです。
- 就活生の興味・関心を把握するため
- 研究内容と企業との関連性を知るため
- 論理的な説明能力があるかを図るため
①就活生の興味・関心を把握するため
就活生の興味や関心がどの分野に向いているのか、把握するために質問をしている場合があります。
卒論には自身が希望するテーマが反映されるため、どんな学問や時事問題を取り上げているか見ることで、考え方や価値観を把握しやすくなるのがポイントです。
社会問題に目を向けてしっかりと考えているか、将来の課題に対してどう考えているのか探ることで、社員として採用した際の将来性を探りやすくなります。
②研究内容と企業との関連性を知るため
研究内容と企業の事業とに関連性があるかどうかを知るために、質問をするパターンもあります。
特に理系の知識が問われる研究職などでは、仕事に活かせる知識をどれほど持っているかどうかが重要視されやすいです。
業務とこれまで学んできた事柄に関連性があれば、仕事に対する熱意が本物であることを証明しやすくなります。
そのため、回答を作成する際には得られた学びにもフォーカスを当てることが大切です。
③論理的な説明能力があるかを図るため
論理的に説明できる能力があるかどうかを知るために、質問をするケースもあります。
卒論でどんな事柄を取り上げたのか、どう考えてテーマを選んだのか説明する際には、わかりやすく順序立てて紹介するスキルが問われるのがポイントです。
難しいテーマを相手に伝わるように言い替えて説明できれば、相手の立場で物事を考えてコミュニケーションが取れることを強調できます。
文章の構成も意識して解答を作成するのがおすすめです。
就活で卒論について聞かれた時の回答のコツ3つ
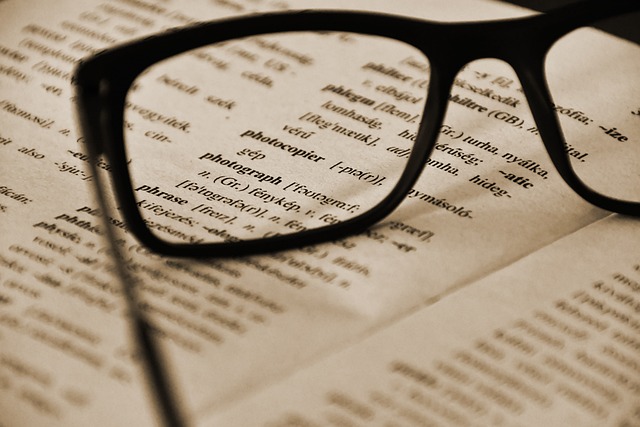
卒論について回答するコツを掴んでいれば、面接でスマートに対応しやすくなります。意識しておくとよいコツは、以下の3つです。
- 専門用語は極力避ける
- テーマ選定の理由を伝える
- 卒論で得た学びを伝える
①専門用語は極力避ける
専門用語を使うのはなるべく避けることが大切です。
取り上げた内容について説明する際には専門的な用語に頼ってしまいがちですが、そのまま採用者に伝えても、何が言いたいのかわかりづらくなってしまいます。
用語はより簡単な表現に言い直して、該当分野について詳しくない人にも伝わるように工夫しましょう。
自分では専門用語ではないと感じていても、人によって受け取り方が異なるため、わかりやすい言い回しかどうか見直すことが大切です。
②テーマ選定の理由を伝える
テーマを選んだ理由をはっきりと伝えることも重要です。
ただ好きだから、興味があったからといった単純な理由では印象に残りづらくなってしまうため、具体的な理由を説明する必要があります。
問題の背景について探ることで、理解を深めて解決策を見つけ出したいと感じたから、といった自身の考え方が現れた理由を伝えましょう。
理由は長々と書きすぎずに、一文でまとめることを意識するのも大切なポイントです。
③卒論で得た学びを伝える
卒論を通してどのような学びが得られたのかを伝えれば、自身がどのように成長できたのかを強調しやすくなります。
ただ内容について説明するだけでは終わらせずに、今の自分にどう活かされているのか、今後にどう活かそうと考えているのかを伝えてまとめるようにしましょう。
自分から学んで成長していく姿勢があることも伝えられます。仕事にあたる際の考え方などに結び付けると、アピール力を高めやすいです。
就活で卒論について聞かれたときの回答例
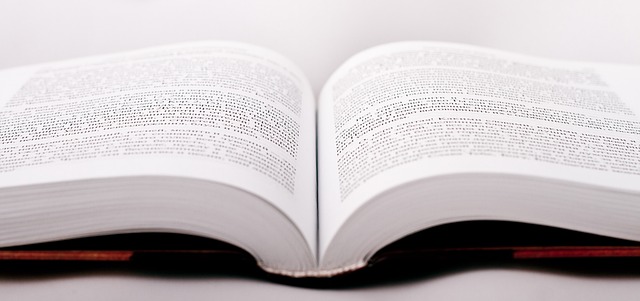
例文を確認すれば、具体的にどう答えるべきかイメージしやすくなるのが利点です。ここでは、文理別に例文を紹介します。
- 文系の場合
- 理系の場合
①文系の場合
| 私は卒論のテーマとして、ECサイトの効果を高めるための方法を取り上げています。 インターンでEC会社のサイト作りに携わらせていただいた経験から、消費者に選ばれるサイトの条件について理解を深めたいと感じたことがきっかけです。また卒論を進めるうちに、内容の説得力を高めるためには調査が必要であると考えました。 そしてECサイトの運営会社様にお声掛けをして、利用者がどのようなルートを辿って購入している傾向があるのかデータを集めました。データをもとに条件を分析して、実際に複数のサイトを作成してみたところ、条件を満たしたサイトの方が反響がもらえることがわかりました。 私は今後も自分から積極的に情報収集を行い、顧客に合ったアプローチを取れるように努めてまいります。 |
上記の例文では、消費者心理について学ぶためにテーマを決めたことや、卒論の中で自分から工夫したポイントを紹介しています。
今後も自分から情報を集め、業務に活かしていくことを伝えているのも特徴です。
②理系の場合
| 私は卒論のテーマに、ロボットによる溶接部検査の精度強化を取り上げました。 近年電子部品の小型化が進んでいることから、目視では接合部の検査がしづらくなっていると感じたことが、テーマを決めた理由です。 不良品を見分けやすくすることを目標として、ロボットに適切なデータを読み込ませて、識別能力を高めました。また、不良品を正確に見つけやすくする工夫はないか検討し、取り込んだ画像に加工を施すことを考え実践したところ、検査の精度をさらに高められました。 私は卒論でシステム構築方法と、ロボットの可能性について学びを深めた経験を、利便性を高めるシステム作りに活かしてまいります。 |
上記の例文では、専門的な表現を最小限に留めて、内容を紹介しています。
工夫したことや得られた学び、今後への活かし方もわかりやすくまとめているのがポイントです。
就活で卒論が無い・未定の場合の対処法2つ

卒論がなかったり決まっていなかったりした場合の対処法も確認すれば、自分の状況に合った対応ができます。場合別の対処法は、以下の2つです。
- 卒論が無い場合
- 卒論テーマが未定の場合
①卒論が無い場合
卒論が無い場合は、正直に話すようにしましょう。しかし、事実だけを述べても高評価にはつながらないため、代わりにゼミや授業でどんな事柄に力を入れたのか話すことが大切です。
自身が学んだ分野や関心を持って取り組んだ物事について紹介できれば、質問者の知りたい情報を伝えやすくなります。
卒論のテーマをでっち上げるのは信頼性を損なってしまうため、避けるようにしましょう。
②卒論テーマが未定の場合
卒論テーマが決まっていない場合は、正直に未定であることを述べた上で、今後の計画を話しましょう。
どんな問題に関心を持って、テーマに取り上げようと考えているのか紹介するのが適します。
また、卒論を進める際はどのような手段で解決策にアプローチしようと計画しているのか説明するのがおすすめです。
具体的に計画を伝えれば、質問の意図に沿った回答を行いながら、自分の考え方や取り組む姿勢を伝えやすくなります。
就活と卒論を両立する方法2つ
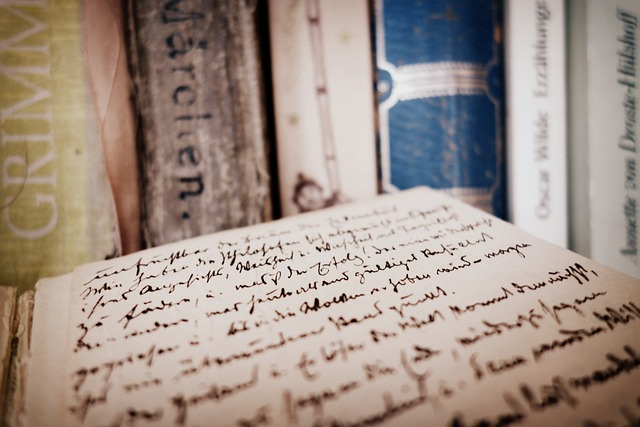
就活と卒論を両立させる方法をチェックすれば、卒論を進めながら就活にも集中しやすくなります。おすすめの方法は、以下の2つです。
- 綿密に計画を立てる
- 早めに就活対策をする
①綿密に計画を立てる
綿密に計画を立てて実行することを意識すれば、毎日着実に卒論を進めながら、就活に本腰を入れやすくなります。
卒論は論争が起こっている事柄を題材にして文献を集め、序章から書き始めて執筆を進め、引用文献の最終チェックを行う、といった流れで進むのが特徴です。
そのため、それぞれの段階を何月何日に終わらせるのか決めておくことが大切になります。
期日までに何の作業をするのか明確に決めていれば、今自分が何をするべきかがわかるのが利点です。
②早めに就活対策をする
早めに就活対策をしておけば、卒論制作に余裕を持たせやすくなります。
企業分析や自己分析だけでなく、面接練習も前もってしっかりと行っておくことで、空き時間に卒論を進めやすいです。
また周りよりも先に対策を始めていれば、精神面でも余裕ができ、就活本番までに練習時間を多く取りやすくなるといった利点もあります。
就活対策においても計画を立てておけば、毎日の時間の使い方を工夫しやすくなるのがポイントです。
就活で卒論について聞かれた時のコツをおさえよう!
就活で卒論の質問をされた時のコツを知っていれば、ベストな回答を目指せます。
専門的な言葉は避けて、企業と関連性がある学問を修めていることや、得られた学びなどを伝えるのが重要です。
例文もチェックして、わかりやすく説明できるように練習しておきましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









