就活のテストにはいくつか種類があり、それぞれ出題される問題や難易度が異なります。
しかし、自分が受ける予定があるテストにはどんな対策が必要なのかがわからず、悩んでしまう人もいるでしょう。
本記事では、テストが行われる目的や種類、種類ごとの対策方法について解説します。
事前に対策を練っておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
就活のテストとは
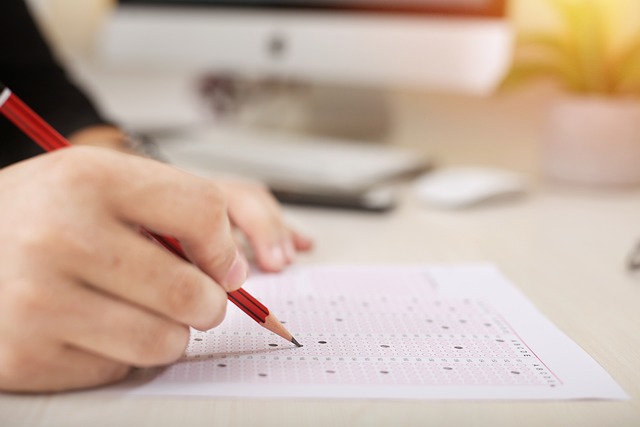
就職活動で必ず直面する採用試験について解説します。近年は対面式の筆記試験からオンライン形式へと変化が進んでいます。
2つの観点から詳しく説明していきましょう。
①就活のテストはWebテストが主流
就職活動で実施される採用試験の主流は、インターネット上で受験する「Webテスト」となりました。
従来の会場集合型の筆記試験と比べて、時間や場所を選ばず受験できる利点があります。企業側も、応募者の基礎能力や適性を効率的に判定できるため、導入が進んでいます。
テストの内容は、言語処理や数的処理などの能力を測る「適性検査」と、性格や価値観を把握する「性格診断」に大別されます。
多くの場合、エントリーシート通過後の早い段階で実施される重要な関門となっています。
②Webテストの合格ラインはどれくらい?
合格ラインは企業によって異なりますが、一般的な目安は総合得点で6割以上となります。
ただし、業界特性によって基準は変動します。例えば、数学的思考力を重視する総合商社や金融業界では、数的処理で7割以上の得点が求められる傾向にあります。
性格診断には明確な合否基準はありませんが、企業が求める人物像との一致度で判断されます。回答の一貫性も重要な評価ポイントとなるため、ありのままの回答を心がけましょう。
時間配分も合否を左右する要素です。全問正解よりも、制限時間内での処理力や正確性が評価されます。特に能力検査では、スピードと質のバランスが合否の分かれ目となるでしょう。
企業がWebテストを実施する3つの理由
就職活動で避けて通れないWebテストについて、企業側がなぜ実施するのか理解を深めましょう。
実は単なる選考ツールではなく、採用活動における重要な役割を担っています。
それぞれの理由について詳しく説明していきましょう。
①応募者の学力や性格を見極めるため
Webテストは、応募者の基礎学力と性格特性を客観的に評価する重要な指標となります。
言語処理問題では、ビジネス文書の読解力や論理的な文章構成力を測定します。数的処理問題では、データ分析力や問題解決能力を評価します。
性格診断では、コミュニケーション能力やストレス耐性など、実務で必要な資質を判定する狙いがあります。
学歴や専攻が異なる応募者を公平に評価できる点も特徴的です。例えば、文系理系を問わず必要とされる基礎的な計算力や、業務で不可欠な読解力を統一基準で判断できます。
さらに、テスト結果は入社後の育成計画にも活用されます。応募者一人一人の強みや課題を早期に把握し、効果的な研修プログラムを構築する材料にもなっているのです。
②応募者をより絞りやすくするため
多数の応募者から、基準を満たす人材を効率的に選抜する手段としても活用されています。
特に大手企業では、数千人規模の応募者から面接対象者を選定する必要があります。Webテストを活用することで、一定の基準に満たない応募者を初期段階で振り分けることが可能となりました。
選考の初期段階で実施されることが多いのも、採用活動の効率化を図る狙いがあります。基礎能力や適性を早期に見極めることで、その後の面接選考をスムーズに進められる利点もあるでしょう。
ただし、テストの点数だけで判断されることは少なく、エントリーシートや面接など、他の選考要素と組み合わせて総合的に評価されます。
業界や職種によって求められる得点も異なるため、柔軟な選考基準が設けられているのです。
③応募者の適性を確認するため
Webテストの結果は、応募者の職種適性や配属先を検討する際の重要な判断材料となります。
例えば、数的処理が得意な応募者は経理や企画系の部署に、言語処理が得意な応募者は営業や広報系の部署に配属されやすい傾向にあります。
性格診断は、リーダーシップの素質や専門性の追求に向いているかなど、将来のキャリアパスを見据えた判断材料としても活用されるのです。
また、ストレス耐性や協調性、問題解決能力など、実務で必要とされる要素を多角的に分析し、企業が求める人物像との適合度を測ります。
さらに、入社後の指導方針や配属先の決定にも影響を与えます。応募者の特性や潜在能力を把握することで、個々の強みを活かせる部署への配属や効果的な育成計画の立案が可能となるのです。
就活のテストの種類を5つ紹介
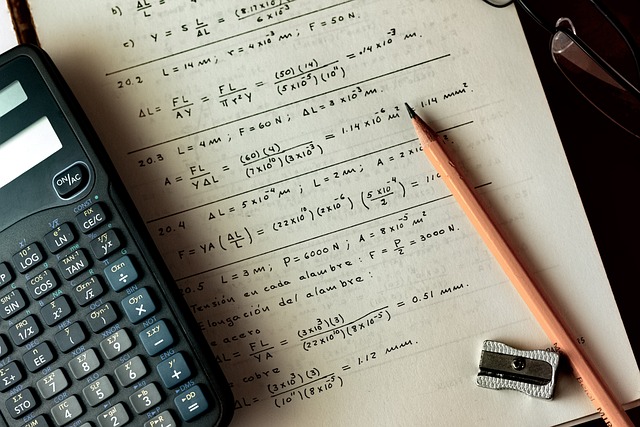
テストの種類を把握していれば、それぞれの特徴を掴んで対策しやすくなります。
就活で用いられるテストは以下の5種類に分類が可能です。
- SPI
- 玉手箱
- GAB
- CAB
- TG-WEB
では、それぞれのテストについて詳しくみていきましょう。
①SPI
SPIは、就活で最も一般的な形式であり、多くの企業が導入している傾向があるのが特徴です。
受験方法は、テストセンター・webテスト・インハウス・ペーパーテストなどがあるため、自分が希望している企業ではどんな方法で実施されるのか確認する必要があります。
出題内容は言語系・非言語系・性格検査に分かれていて、問題の難易度は中学・高校レベルですが、問題数が多いのが難点です。
頻出する業界としては、銀行・商社・大手企業などが挙げられます。
②玉手箱
玉手箱はwebテストで有名な形式で、SPIと比較すると難易度が高めになっています。受験方法はwebテストのほかテストセンターもあるため、必ずしも自宅で受験するわけではありません。
出題内容は計算理解・言語理解・英語理解・性格テストの4種類に分けられ、四則逆算・図表の読み取り問題・長文読解問題などが出るケースもあるのが特徴です。
頻出する業界には、証券・銀行・商社・総研などが挙げられます。
③GAB

GABは、玉手箱と同じ会社が提供している形式で、玉手箱のように基礎能力や性格を判断するよりは、新卒総合職の能力を測定する側面が強い傾向にあります。
受験方法はテストセンターのほか、自宅や企業の指定会場で受験するパターンがあるため、事前に試験会場を確認しておきましょう。
出題内容には計数・言語・性格テストがあり、長文の問題などが多いのが特徴です。
頻出業界としては、総合商社・専門商社・証券・銀行が挙げられます。
④CAB
CABは、SEやプログラマーといったコンピューター職を対象としたテストとなっています。
受験方法は指定会場での筆記試験のほか、webテストもあり、暗算・法則性・命令表・暗号・性格検査の問題が出題されるのが特徴です。
主に理系の学生が受ける機会が多く、論理的思考力を持っているかどうか知るための指標としても用いられています。
頻出業界としては情報処理やシステム関連の企業、ゲーム業界などが挙げられます。
⑤TG-WEB
TG-WEBは紹介しているテスト形式の中で導入率が低めですが、近年は導入する企業が増えてきています。
受験方法はテストセンターとWEBテストの2種類があり、問題形式によって従来型と新型に分けられるのも特徴です。
出題される問題は言語系・非言語系・性格診断・英語と共通していますが、新型は難易度が低い分時間設定がかなり短いといった違いがあります。
主に、IT業界などで実施され始めているいる形式となっています。
5つの就活のテストの対策方法
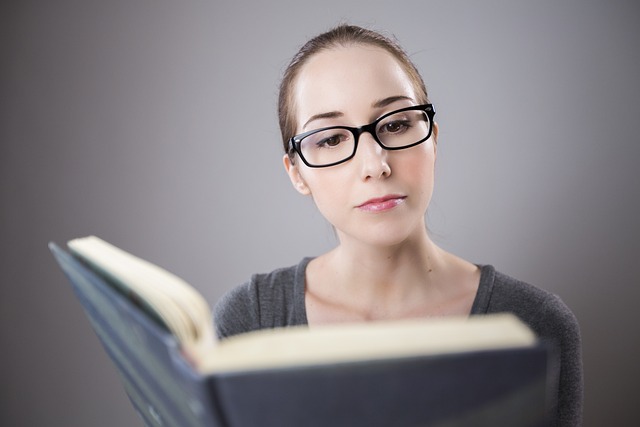
それぞれの形式の対策方法を確認すれば、自分がこれから受ける試験に向けて適した勉強法を実践しやすくなるのがメリットでしょう。
ここでは、5つの形式に合った対策方法を説明していきますよ。
- SPI
- 玉手箱
- GAB
- CAB
- TG-WEB
①SPI
SPIは時間が短く問題数が多いため、時間配分を意識しながら解く練習を積む必要があります。
受験者の回答状況によって出題問題が変化していくため、最初の問題に正解し続けていれば難易度が上がっていき、いい結果が出やすいのがポイントです。
SPI専用の対策本が出版されているため、言語分野と非言語分野で11ポイント以上取得し、60以上の偏差値が安定して出るように練習しましょう。
高めの得点を出す練習ができていれば、実際に解く場面でも実力を発揮しやすくなりますよ。
②玉手箱
玉手箱の問題では電卓が必須となるため、電卓を取り入れながら解く練習をしておくことが重要になります。
一問にかけられる時間が30秒ほどしかない問題が多いのも特徴で、高得点を目指すには事前に出題される問題の具体例と解き方を知っておき、対応力を高めなければいけません。
素早く解答していくためには、どの問題を取捨選択するか、見極める力を鍛えておく必要もあります。自分が得意な分野を把握して、実際の問題に目を通して練習しましょう。
③GAB

GABは他の試験と傾向が異なるため、対策本を使ってしっかりと練習を積むことが大切になります。
長文問題では、設問の内容と長文の内容が合致しているかどうか、どちらともいえないかの3択から選んで解答していくパターンがあるのが特徴です。
文章をより早く読解するために、情報をまとめる練習をするのが有効な対策になります。
計数問題では電卓を使用するため、練習時も電卓を用いて解いていく習慣を付けましょう。
④CAB
CABは制限時間が短く難易度が高いため、時間を意識しながら問題を繰り返し解いて対策していく必要があります。
目標得点は6割ですが、実際に解く場面で緊張してしまうリスクを考慮して、より高い得点を取れるように問題の解き方をしっかりと頭に入れておくようにしましょう。
また、解ける問題と解けない問題の見極めをスピーディに行えるように練習しておくのも有効な対策方法です。
⑤TG-WEB
TG-WEBは、言語問題がセンター試験の国語の問題と似ているため、センター試験の参考書を活用することで対策可能です。
また、webサイトの模擬受験を活用すれば、実践的な練習ができるといった特色もあります。従来型と新型で解き方が変わってくるため、両方の対策を済ませておくことも重要です。
ほかの形式と比べると、問題の出題数はやや少なめなので、1問1問の正答率を上げる必要があります。TG-WEBに特化した問題集を用いて、対応力を高めましょう。
就活のテストの種類を把握して対策しよう
就活のテストの種類や特徴をしっかりと把握して、適した対策を行いましょう。
業界によって取り入れられる種類は異なり、出題内容も変わるため、志望している企業で行われるテストに合わせて対策する必要があります。
専用の対策本なども活用して、スムーズに問題を解けるようにしましょう!

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









