どこでもいいからとにかく内定が欲しいと考えている就活生は多いと思います。しかし、その考えは危険です。
本記事では、どこでもいいと考えると就活が失敗する原因と、内定が欲しい時の対処法を解説します。ぜひ参考にしてください。
どこでもいいと考えると就活が失敗する!理由3つを紹介
就職活動は、自分の将来を左右する重要なステップです。しかし、「どこでもいい」と考えてしまうと、失敗する可能性があります。
ここでは、どこでもいいと考えると就活が失敗する3つの理由を解説します。
- 志望度が伝わらないため
- 回答に説得力がない
- 自分とマッチしない企業を選ぶため
①志望度が伝わらないため
就活において「どこでもいい」と考える人は、志望度が上手く伝わりません。企業は熱意ある応募者を求めており、志望度が高いことが重要な選考基準の1つです。
志望度が伝わらない場合、採用担当者は応募者のモチベーションや企業への理解度に疑問を抱き、選考過程で不利になるでしょう。
特に、自己PRや志望動機の部分で、具体性や熱意が感じられないと、採用担当者は応募者の真剣さを疑うことになります。
②回答に説得力がない
「どこでもいい」と考えている学生は、志望動機や面接の回答に説得力がありません。説得力のない回答は、採用担当者に不安を与え、結果として選考で不利になる可能性が高くなります。
「どこでもいい」と考えている学生は自己分析が不十分であることが多く、自分の強みや経験を効果的にアピールできません。
また、企業研究も不十分であるため、企業の特徴や業界の動向について具体的かつ深い理解を示せないのです。
③自分とマッチしない企業を選ぶため
「どこでもいい」と考えることは、自分に合った企業を見極める機会を逃す原因にもなります。
自分のキャリアビジョンや価値観に合った企業を選ぶことは、長期的なキャリア形成において非常に重要です。
しかし、志望度が低いと、自分の適性や興味に合った企業を見つける努力を怠りがちになります。その結果、自分に合わない企業に就職し、仕事に対する満足度が低くなるリスクがあるのです。
自分に合った企業を見つけるためには、志望度を高め、自己分析と企業研究に努めることが重要です。
どこでもいいと考えて就職した場合のリスク3つ

「どこでもいい」と考えて就活することは3つのリスクを伴います。適切な企業選びが将来のキャリアに大きな影響を与えるため、注意が必要です。
- 長く勤めることが難しい
- モチベーションが下がる
- 労働環境が厳しい企業を選ぶ可能性もある
①長く勤めることが難しい
就職先を選ぶ際、「どこでもいい」と考えると、自身の強みや適性が活かせない企業に就職してしまい、長く勤めることが難しくなるリスクがあります。
例えば、コミュニケーション能力が高い人が、個人作業が中心の職場に就職した場合、その能力を活かせずにストレスを感じることがあるでしょう。
また、スキルや経験が不足していると、仕事の質や効率が低下し、結果として職場での立場が不安定になりがちです。
長期的に見て、自分の強みやキャリアプランに合った職場を選ぶことが、安定した職業生活を送る上で重要です。
②モチベーションが下がる
また、適当に就職してしまうと、モチベーションが上がらず仕事にやりがいが感じられないリスクがあります。仕事に対する情熱や目標が不明確な状態では、日々の業務に対して意欲を持てません。
特に、自分の興味や価値観と合わない業務を長期間続けることは、精神的な負担となり得ます。モチベーションが低いと、仕事の質が低下し、キャリアアップの機会も減少します。
③労働環境が厳しい企業を選ぶ可能性もある
適当な就職先選びは、労働環境が劣悪なブラック企業に入社するリスクを高めます。
ブラック企業は従業員の健康や福祉を軽視し、過度な残業や不適切な人事管理が問題となることが多いのが特徴です。劣悪な労働環境では、精神的、身体的な健康を害する恐れがあります。
また、キャリア形成においてもブラック企業での経験は有益とは限らず、転職市場での評価が低くなる可能性も。企業の評判や労働環境を事前に調査し、自分に合った職場を選びましょう。
企業の選び方がよくわからない人は、以下の記事も確認してみてくださいね。
就活でどこでもいい思考から抜け出す方法3つ

「どこでもいい」と考えて就活をすると、自分自身の可能性を狭めてしまいます。ここでは、どこでもいい思考から抜け出して就活を成功させるための3つの方法を紹介します。
- 周囲と比べず焦らない
- 企業研究を徹底する
- 選考対策を徹底する
①周囲と比べず焦らない
就活において、他人と自分を比較し焦ることは避けるべきです。周囲が内定を得ていても、自分のペースを守ることが大切です。
焦りは不安を生み、最終的には適切な判断を妨げる原因になります。自分自身の価値観やキャリアプランに基づいて行動することで、納得のいく就職活動ができるでしょう。
また、自己分析を深めることで、自分に合った企業を見つけやすくなります。
②企業研究を徹底する
企業研究は就活成功の鍵です。ただ情報を集めるだけでなく、その企業がどのような価値観を持ち、どのような人材を求めているのかを理解することが重要です。
企業のウェブサイト、SNS、業界ニュースなど多角的に情報を収集し、企業の現状や将来性を把握しましょう。
また、企業訪問やインターンシップを通じて、実際の職場環境や社員の雰囲気を感じ取ることも有効です。徹底した企業研究は、面接での自己PRや志望動機の深化にもつながります。
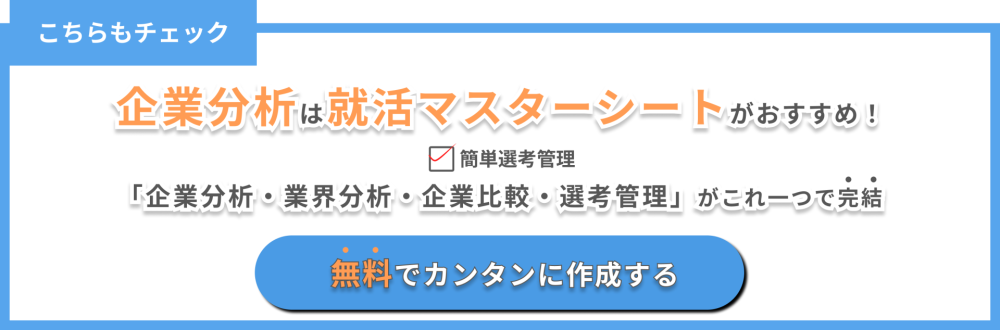
③選考対策を徹底する
選考対策の徹底も、就活成功のためには欠かせません。面接やグループディスカッション、筆記試験など、各種選考に対して事前に準備をしておくことが重要です。
特に面接では、自己PRや志望動機を明確に伝えることが求められます。事前に模擬面接を行い、フィードバックを受けるのもおすすめ。自分の弱点を改善し、自信を持って本番に臨めますよ。
「せっかくなら質の高いフィードバックがもらいたい……」と思う人は、カリクルのキャリアアドバイザーに相談するのも1つの方法です!
カリクルでは平均7~8回の面談の中で、自己分析から面接練習までじっくり選考対策ができます。模擬面接では、年間5000人の就活生と面談をしているキャリアアドバイザーから、的確なアドバイスがもらえますよ。
\ 気になる人はこちらから! /
就職先がどこでもいい場合の企業の探し方3つ

しかし、どうしても「どこでもいい」と考えてしまう人もいると思います。そこで、どこでもいいから内定が欲しい場合の企業の探し方を3つ紹介します。
- 中小企業に焦点を当てる
- 大学の推薦枠を確認する
- 採用人数が多い企業を選ぶ
①中小企業に焦点を当てる
まず、中小企業に焦点を絞りましょう。中小企業は大企業に比べて応募者数が少ないため、採用のチャンスが高まります。
また、中小企業では多様な業務に携わる機会が多く、スキルアップにもつながります。さらに、組織が小さいため、社内のコミュニケーションが密で、個々の意見が反映されやすいのも利点です。
中小企業は、自分の能力を発揮しやすい環境を求める就活生にとって魅力的です。
②大学の推薦枠を確認する
また、大学の推薦枠を確認することも重要です。多くの大学には、特定の企業との推薦枠が設けられています。推薦枠を利用することで、就職活動の負担を軽減できます。
推薦枠を通じて応募する場合、選考プロセスが簡略化されることが多く、採用される可能性が高まるのです。ただし、推薦枠で内定をもらった場合は辞退が難しいため注意しましょう。
③採用人数が多い企業を選ぶ
採用人数が多い企業を選ぶのもおすすめです。採用人数が多い企業は、多くのポジションを提供しているため、自分の専門分野や興味に合った職種を見つけやすくなります。
また、大規模な採用を行う企業は、研修プログラムが充実していることが多く、未経験者でも安心してスタートできる環境が整っています。
大企業の場合、福利厚生やキャリアアップの機会も豊富で、長期的なキャリア形成にも有利です。
「どこでもいい」は危険!焦らず就活を進めよう
就職活動は、自分のキャリアを左右する重要な選択です。焦る気持ちは分かりますが、どこでもいいと考えず、将来を見据えた慎重な職場選びが肝心です。
自分の強みや興味、価値観に合った職場を見つけることで、長期的なキャリア形成と充実した人生を送れます。焦らず、じっくりと就職活動を進めましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。










