
就活生のみなさんが不安に感じているのが、性格適性検査に含まれているライスケールの存在ではないでしょうか。
実際、就活生からは「嘘をついたらバレるの?」「上手く答える方法はあるの?」という声をよく聞きます。
そこでここでは、ライスケールとは何かを徹底解説して、嘘がバレる理由や対策についても紹介していきますので、参考にしてくださいね。
全て無料!ES作成に役立つツール
★ES自動作成ツール
AIが「志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所」を自動で作成
★志望動機テンプレシート
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機をカンタンに作成できる
★自己PR作成ツール
最短3分で、受かる自己PRを作成できる
ライスケールとは性格適性検査の判断基準の1つ!
「ライスケールって何の検査?」と疑問に思うかもしれませんが、これは性格適性検査に含まれている判断基準となるものです。
性格適性検査は簡単にいうと、検査を受けた人の性格や人柄、仕事に適しているかを判断するものですが、一方のライスケールは検査を受けた人の嘘を見抜いていくものです。
ライスケール(Lie Scale)は直訳の通り「嘘の尺度」で、質問を繰り返しすることで嘘を見抜いていきます。
これらの質問に引っかかってしまうと評価が下がってしまうため、注意が必要です。スコアを下げないためにも、しっかり対策していきましょう。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方は強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自身を持って臨めるようになりますよ。
性格適性検査を実施する企業の目的4つ

どうして企業は就活生に性格適性検査をするのか、その目的4つについて解説していきます。
企業側の目線で解説していきますので、対策の参考にしてくださいね。
- 就活生と企業との相性を確認するため
- 次の選考に進む就活生を絞り込むため
- 面接で参考にするため
- 自社で教育や配属の参考に使うため
①就活生と企業との相性を確認するため
採用する側は、就活生と企業との相性を確認するために、性格適性検査を行っています。
検査のスコアからは就活生の特徴や人柄が数値として現れるので、自社との相性を判断する手段としているのです。
企業は自社の社風や働き方、目指す方向性に合う人を採用したいと考えています。
このようなことから、スコアを上げるためには企業が求めているのはどういう人材なのかを、しっかり企業研究して知っておく必要があります。
②次の選考に進む就活生を絞り込むため
2つ目の目的として、次の選考に進む就活生を絞り込むためということが考えられます。
特に志望者が多くいる場合、検査結果をもとに就活生をふるいにかけ、自社と適合性のある人材を囲い込みたいと考えています。
性格適性検査が直接的に合否には影響しないといわれていますが、結果が選考過程で参考にされることはあるようです。
こういったことからも、選考で進んでいくためには良いスコアを狙うことが重要となります。
③面接で参考にするため
意外に感じるかもしれませんが、検査で出た結果を面接の際に参考にするためともいわれています。
採用担当者が就活生の性格や適性に関する質問を、事前に準備するために活用しているのです。
また検査結果から就活生の人柄を判断し、面接でのアピール内容と検査結果との整合性をチェックしています。
このように性格適性検査は、面接を進める上での参考材料としても貴重なデータであるといえるでしょう。
④自社で教育や配属の参考に使うため
この性格適性検査の結果は、自社教育や配属の際に参考として使うためにも利用されています。
前もって就活生の性格や適性を検査結果を参考に把握することで、入社後にどのように教育していくかを検討しているのです。
また適性を考慮することで、その就活生にとって適切なポジションに配置するためにも、検査結果は大切な役割を担っています。
このように入社後の配属先を決める際など、適性を判断するためのツールとしても活用されているのです。
ライスケールの結果だけで落ちることは少ない
就活生は不安に感じているかもしれませんが、ライスケールの結果だけで落ちるケースは少ないといわれています。
しかし直接的には合否に影響はしないといわれていても、実際には選考を進めていく上で就活生を選別する際の参考材料になっているのです。
このことからもスコアが低すぎると、印象が悪くなり低評価されてしまう可能性があります。
スコアを上げるにはコツもありますので、ライスケールがどういうものなのかを理解して対策しておくことが重要です。
【例文付き】ライスケールの主な質問内容2つ
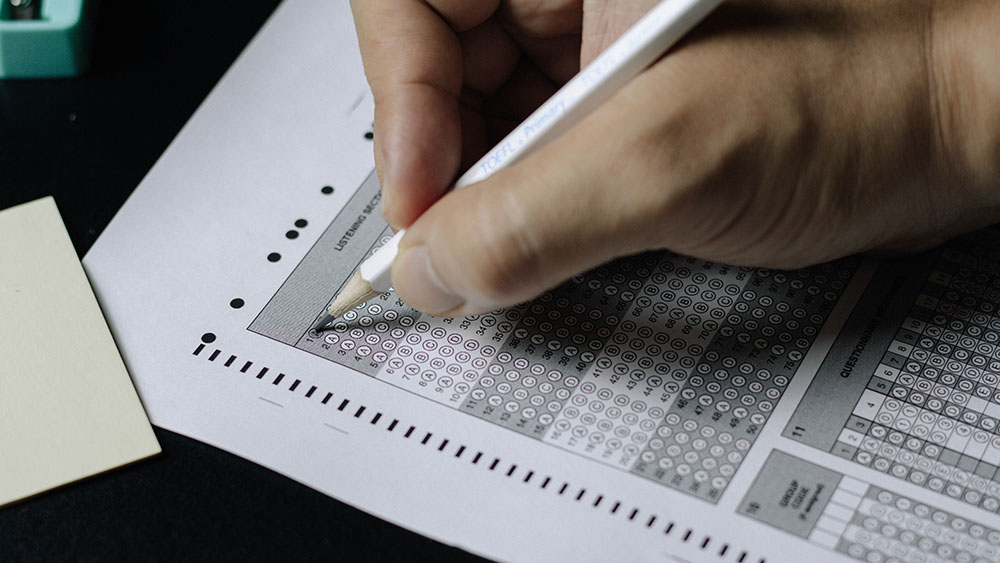
ここからは、就活生が惑わされやすいライスケールの主な質問形式2つを、例文つきで紹介していきます。
ここで紹介する2つの質問はライスケールでは典型的なものですので、一緒に確認していきましょう。
- 普通に生きていればYESとはならない質問
- 同じ内容を違う聞き方で問う質問
①普通に生きていればYESとはならない質問
要注意とされる質問は、普通に生きていればYESとはならない質問です。
例をあげると、「生まれてから一度も嘘をついたことがない」といった質問で、おそらく嘘をついたことがない人は、限りなくゼロに近いはずです。
しかしここで自分をよく見せたいという気持ちから、ついYESとしてしまうと「嘘」と判断されてスコアが下がってしまいます。
このように「一度も〜ない」といった極端な否定系の質問は要注意です。こういった質問には、好印象を残そうと考えずに、正直に回答するのがコツといえるでしょう。
②同じ内容を違う聞き方で問う質問
就活生が惑わされてしまうものに、同じような内容を違う聞き方で質問する形式があります。
これは、「事情があれば遅刻してもかまわない」「自分は時間を守るほうだ」といった質問です。
一見すると趣旨の異なる質問に見えますが、両方ともYESと回答してしまうと、時間を守る人なのか違うのか一貫性がなくなり、嘘をついていると判断されます。
ライスケールでは、あらゆる方面・角度から時には遠回しに質問され、他の質問の答えも総合して分析されるので、注意しましょう。
ライスケールで嘘がバレる理由2つ

ここからは、どうしてライスケールで嘘がバレるのかその理由2つについて解説していきます。
嘘がバレる仕組みをよく理解して、矛盾点の少ない回答ができるように対策しましょう。
- 履歴書やESでの意見と相違がある
- 適性検査での回答に一貫性がない
①履歴書やESでの意見と相違がある
嘘がバレる理由として、ライスケールから出た結果と履歴書やESで述べた意見と違いや矛盾点があることが考えられます。
例えば、ESでは「強みはコミュニケーション能力が高いことです」とアピールしているのに、性格適性検査の「少し引っ込み思案なところがある」でYESとしてしまうような回答例です。
この回答だとESでのアピール内容と、性格適性検査で答えた内容に矛盾点が生じてしまい、結果としてライスケールで「嘘をついている」と判定されてしまうでしょう。
このように嘘をついているという判定を避けるために、質問に対しての答えと履歴書やESで述べた内容に整合性を保つことが重要です。
②適性検査での回答に一貫性がない
2つ目の理由として、適性検査で一貫性のない回答を出してしまうことがあげられます。
例として、「人と話すのが好きだ」「団体競技より個人競技が好きだ」「人見知りなところがある」の問い全てにYESでは、一貫性のない答えとみなされて「嘘をついている」と判断されます。
このように一貫性のない回答を出してしまうと、ライスケールのスコアが下がってしまうため注意しましょう。
出された質問対して、「これは何を聞きたいのか?」という質問の裏にある本質を見抜くスキルを養うことが大切です。
ライスケールへの対策3つ

少しでも高いスコアを取るために、3つのライスケール対策法を紹介していきます。
ライスケールに苦手意識がある人もしっかり対策して、回答のコツをつかんでしまいましょう。
- ライスケールについて理解する
- 社風にあった一貫性のある回答を意識する
- 頻出の質問を解いて練習する
①ライスケールについて理解する
高スコアを目指すためには、まずライスケールとは何かをしっかりと理解することが重要になります。
「どんなテストなのか」「企業が何を知ろうとしているのか」を理解しないことには、対策することができないからです。
このライスケールは嘘を見抜いていくもので、すなわち就活生が虚偽のない誠実で信頼できる人材かを見極めています。
様々な角度から変化球で出される質問の意図を把握し、ブレることなく回答していくことがライスケールを攻略するポイントです。
②社風に合った一貫性のある回答を意識する
志望する企業の社風に合った一貫性のある回答を意識することが大切です。
企業は自社と就活生の相性を判断するために、スコアの数値を選考の際に参考にしています。
ですから企業との相性を考慮して回答するのが重要であるため、企業の求める人物像を理解し、質問の回答に整合性を図ることが求められます。
全て正直に答えるのではなく、社風や求める人物像に寄せて回答することがコツといえるでしょう。
③頻出の質問を解いて練習する
勉強と同じでスコアを上げるためには、頻出の質問を解いて練習することが効果的だと考えられます。
やはりライスケールも、質問と回答に慣れることでコツをつかめるようになるのです。
そのためには、SPI対策問題集などを買って、何度も質問を解くことでスコアアップにつながります。
ライスケールに難しい知識は必要ありませんが、慣れとコツが必要ですので練習することをおすすめします。
ライスケールへの理解を深めて就活に活かそう!
ライスケールを攻略するには、質問の裏にある意図を読めるようになることが重要です。
ライスケールへの理解を深めて、就活に活かしましょう。
きっと問題集などで何度か練習すれば、すぐに慣れて答え方も自ずとわかるようになりますよ。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









